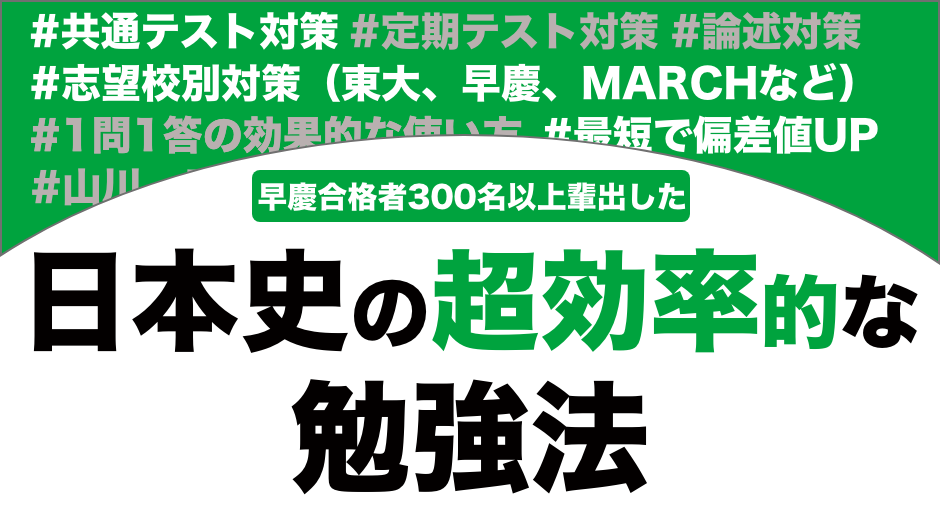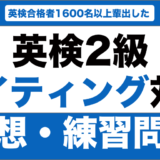本サイトの表記には、一部プロモーションを含みます
日本史の大学受験の勉強法を共通テスト対策の勉強法から志望校別に東大志望、早稲田志望、慶應志望、MARCH志望など志望校ごとの日本史の勉強法から高校生の定期テスト対策におすすめの勉強法も解説します。
また、これまで個別指導塾で講師として早慶に日本史選択の受験生を100名以上合格させてきた中でおすすめの勉強法から使ってよかった日本史の参考書とその使い方も併せて解説したいと思います。
ゼロからでも短期間で日本史の偏差値を伸ばせる大学受験の勉強法をこれから解説していくので、ぜひ参考にしてみてください。

【この記事の監修者:逆転合格特化塾塾長「竹本明弘」
これまで個別指導塾の塾長として早慶に現役生および浪人生を含めて合計で300人以上の合格者を輩出してきました。その中で共通テストの日本史で9割以上を取った生徒もたくさんおり、実際に指導する中でゼロからでも日本史の偏差値70まで到達した大学受験対策の日本史の勉強法や使ってよかった参考書およびおすすめの日本史の勉強の順番を解説したいと思います。
この記事でわかること
- ゼロからでも共通テストの日本史で9割取れる勉強法と使うべき参考書一覧
- 実際にどういう勉強のスケジュールをこなせば日本史の偏差値が70になるのか
6ヶ月で大学受験の日本史の偏差値を40から70にする勉強法
結論として、日本史の偏差値を6ヶ月で40から70にする勉強法としては以下のようになります。(目安:1日2時間の勉強時間)
これまで早慶合格者を300名以上輩出してきて、その中でも日本史選択の受験生は3割程度いましたが、受験勉強ができる期間を問わず王道は「一問一答(東進)、実況中継もしくは山川、日本史年代サーキットトレーニング」の3つを徹底的にやりこむことです。

高校から東大が10名以上出ていたり、早慶に30人以上合格者が出るような学校にいるのであれば、上記の王道をやり切ることをおすすめします。なぜなら学校のプリントや学校の先生の教え方に従った方が合格したり成績が上がる可能性が高いからです。
ただ自分も含めて、超進学校出身ではなく、これから頑張って日本史を伸ばしたいと思っている受験生の方はぜひこれから紹介する勉強法で独学でも日本史の偏差値をぐんぐん伸ばせるのでぜひ参考にしてみてください。
→金谷の日本史なぜと流れがわかる本と時代と流れで覚える!と一問一答の3冊を往復し続ける。(時間配分:1日30分講義本※金谷→30分問題集※なぜと流れがわかる→60分1問1答※東進→30分講義本で復習)
- 日本史の偏差値を一気に上げるための土台作りとしては、年号と人物の2つを軸に日本史全体を覚える土台作りが最重要になってきます。そのためには年号を最優先に覚えつつ、人物は他の用語ともあわせて暗記していくことが重要です。
- 金谷の日本史なぜと流れがわかる本で30分で読める範囲の大枠を掴みつつ、時代と流れで覚えるで年号とタテの流れと因果関係を意識して覚えて、最後に一問一答を使って用語を星2、星3を確実に覚えていきましょう。日本史の1問1答を使う時間は、金谷を読みながらタテの因果関係を理解しながら使うことが重要です。
→年号と人物を特に注意しながら、タテの流れを重点的に覚えていく。特に日本史年代サーキットトレーニングを徹底暗記(時間配分:1日45分講義本※金谷→45分日本史年代サーキットトレーニング→30分1問1答※東進→30分日本史の講義本)
- 3ヶ月目のメインテーマは「年号」を一気に覚えていくことです。日本史の論述でも共通テスト対策でも基礎力となるのは、年号を軸にタテの流れをしっかりと把握できていることだからこそ、元祖日本史年代暗記法をフル活用して、年号を覚えていきましょう。時間が取れる人は1日60分以上元祖日本史年代暗記法に使えると良いです。
- またただタテの流れをざっくり覚えてしまっても、もったいないので、同時に必ず元祖日本史年代暗記法で年号を覚えつつ、金谷の日本史なぜと流れがわかる本で因果関係を理解しつつ、その時代の用語を一問一答で星2以上は何度も復習して覚えていけるようにしましょう。
→志望校に応じて難関大志望は基礎問題精講を解きながら間違えた部分を復習、共通テストレベルの大学を志望する人は共通テストへの道日本史を解く。(時間配分:1日45分講義本※金谷→30分問題集→30分1問1答※東進→15分復習)
- 日本史はもう完璧に覚えたと思っていても実際には覚えていなかったことがどんどん見つかりやすい科目です。だからこそ、4ヶ月目からは難関大志望は基礎問題精講でアウトプットしながら、自分のまだ覚えきれていない分野を1つ1つ洗い出していきましょう。そして、その分野を金谷の日本史で間違えた部分を復習しつつ、一問一答でも用語を暗記して、文化史も金谷の日本となぜと流れがわかる本の文化史編を使ってその該当する範囲を覚えていきましょう。
- 早慶以下の大学を志望する受験生は共通テストへの道日本史を解いて、どの年代が苦手なのかを見つけて、講義本で復習→元祖日本史の年代暗記法で用語を暗記→日本史の一問一答で用語確認を繰り返して苦手を1つ1つ埋めていきましょう。早慶以下の大学受験においては元祖日本史の年代暗記ほうと星2以上の暗記がかなり重要です。
→難関大志望は特に文化史、史料問題対策は差がつきやすいので、このタイミングで重点的に取り組む。また志望校に関係なく、一気にタテの流れを完璧にするための用語(特に人物関連)と年号の徹底総復習を行う。(時間配分:1日30分講義本※金谷→30分1問1答※東進→30分日本史史料一門ー答→攻略日本史テーマ・文化史の文化史をやりつつ、金谷の文化史で確認※早慶以下は金谷の文化史のみでOK)
- 早慶以上の難関大志望の受験生は最後の最後では他の受験生が対策不足になりやすい分野で差がつきやすいです。それが日本史の文化史と史料問題です。具体的な対策としては、日本史史料一問一答と資料集を組み合わせながら学習しつつ、攻略日本史テーマ・文化史を活用して、間違えた部分は金谷の日本史なぜと流れがわかる本で確認していきましょう。
- また用語暗記についても早慶志望以上は星1もしっかりと覚えて、用語暗記の量も増やしていきましょう。どんどんタテの流れを理解していっている時だからこそ、重箱の隅をつつくような細かい用語が頻出される可能性の高い大学を志望している受験生は後悔のないよう徹底的に星1以上は完璧に1問1答を覚えている状況にしましょう。
→特に現代の日本史やそれぞれ細かい知識を難関大志望は習得したいが、沼っても仕方がないので、とにかく間違えたらその範囲を徹底復習するを繰り返す。この時に解く参考書はHISTORIA、攻略世界史の近・現代史およびテーマ・文化史がおすすめ。早慶以下には共通テストの過去問やセンター試験の過去問がおすすめ。終わり次第各大学の過去問へ
- 細かい知識にこだわりすぎても早慶以上の大学を志望する受験生にとっては偏差値の伸び悩みにも繋がりやすいので「HISTORIA」もしくは「実力をつける日本史100題」と「攻略日本史 近・現代史」を通して難易度の高い問題を解く回数を増やして、間違えた分野、年代を資料集、用語集、講義本を活用して徹底的に復習していきましょう。それが終わり次第、志望大学の過去問に入っていきましょう。過去問の復習も同じように資料集、用語集、講義本を活用して確認していきましょう。
- 早慶以下の受験生は日本史の共通テストの過去問およびセンター試験の過去問とその志望校の日本史の過去問を解いて、講義本と一問一答と年代暗記法での復習を中心に取り組んでいきましょう。ちなみに用語集の活用は志望校が早慶以下の人にとっては、余計な知識も入ってきやすいので、あまり推奨しませんが、早慶以上の受験生には全部覚えても良いと言って良いほど非常に効果的です。
▽日本史のおすすめの参考書ルートの図解

▽日本史のおすすめの参考書一覧はこちら

実際にやってよかった短期間で日本史の偏差値が伸びる勉強法3選
結論から述べると、短期間で日本史の偏差値を伸ばすために最も効果的な勉強法は、年号を軸にしたタテの流れの徹底暗記、一問一答を使った星2以上の用語の完璧な習得、そして金谷の講義本を使った因果関係の理解の3つです。
元祖日本史年代暗記法を使った年号の徹底暗記
日本史の学習において年号は全ての土台となる知識であり、年号を覚えることでタテの流れが一気に明確になります。
元祖日本史年代暗記法には主要な出来事の年号が語呂合わせとともに収録されているため、楽しみながら効率的に年号を覚えることができます。
年号暗記を行う際には1日45分程度の時間を確保して、毎日コツコツと進めていくことが重要です。 最初は覚えるのに時間がかかりますが、1週間も続ければ自然とリズムができて暗記のスピードが上がっていきます。
また覚えた年号は一問一答を解く際に常に意識することで、用語と年号を紐づけて記憶することができます。
日本史一問一答のフル活用
2つ目の勉強法は東進の一問一答を使った用語の完璧な習得です。
一問一答には重要度に応じて星がついており、まずは星2と星3の用語を確実に覚えることから始めます。
星2と星3だけでも全て覚えれば、共通テストレベルから中堅私大レベルまでの問題には十分対応できる力が身につきます。
一問一答を使う際のポイントは、ただ単語を覚えるだけでなく、必ず講義本で該当する部分を読んでから取り組むことです。
講義本でタテの因果関係を理解してから一問一答で用語を確認することで、バラバラの知識ではなく体系的な知識として定着させることができます。
また間違えた問題には印をつけておき、翌日必ず復習することで記憶の定着率が飛躍的に向上します。
金谷の日本史なぜと流れがわかる本の活用
3つ目の勉強法は金谷の日本史なぜと流れがわかる本を使った因果関係の理解です。
この講義本は日本史の出来事を単なる暗記ではなく、なぜその出来事が起こったのかという因果関係を丁寧に説明してくれます。
因果関係を理解することで、記述問題や論述問題にも対応できる本質的な理解力が身につきます。
金谷の講義本を読む際には1日30分程度の時間を使って、じっくりと内容を理解しながら進めていきます。
受験本番まで1年以上時間があるなら、日本史の通史は実況中継を活用して習得していくパターンもおすすめの勉強法です。
読み終わった範囲については、時代と流れで覚える問題集を使ってすぐにアウトプットすることで、理解した内容を確実に定着させることができます。また間違えた問題や理解が曖昧な部分については、再度講義本に戻って確認するというサイクルを繰り返すことが重要です。
分野別におすすめの大学受験の日本史の勉強法
分野別におすすめの大学受験の日本史の勉強法を解説します。
山川の日本史の教科書を使った大学受験の日本史の通史の勉強法
結論から述べると、通史の対策で最も重要なのは年号と人物を軸にしてタテの流れを完璧に理解することです。
通史は日本史の基礎となる部分であり、ここをしっかりと固めることができれば記述問題や文化史の対策もスムーズに進めることができます。
具体的には金谷の日本史なぜと流れがわかる本と時代と流れで覚える問題集、そして東進の一問一答を組み合わせて学習していきます。
通史の学習を始める際には、まず1日30分かけて金谷の講義本を読んで大枠を掴むことから始めます。 この段階では細かい用語を全て覚えようとするのではなく、その時代の特徴や大きな流れを理解することに集中します。
講義本を読み終わったら、すぐに時代と流れで覚える問題集を30分かけて解いて、年号とタテの流れを意識しながら知識を定着させていきます。
時代と流れで覚える問題集を使う際のポイントは、必ず年号を意識して解答することです。 この問題集は年代順に問題が配列されているため、自然とタテの流れを意識しながら学習を進めることができます。
また因果関係を意識して解答することで、単なる暗記ではなく歴史の本質的な理解につながります。
問題集を解き終わったら、1日60分かけて東進の一問一答で用語を暗記していきます。 最初は星2と星3の用語を確実に覚えることを目標にして、徐々に星1の用語にも手を広げていきます。
一問一答を使う際には、金谷の講義本で読んだ内容を思い出しながら解答することで、タテの因果関係を理解しながら用語を覚えることができます。
1日の学習の最後には30分かけて講義本で復習を行います。 この復習の時間では、一問一答で間違えた用語や理解が曖昧だった部分を中心に講義本を読み直します。
復習を習慣化することで、知識の抜け漏れを防ぎながら確実に実力をつけていくことができます。
通史の学習が一通り終わったら、3ヶ月目に入る頃に元祖日本史年代暗記法を使って年号を一気に覚えていきます。 この段階では1日45分程度を年号暗記に充てることで、主要な出来事の年号を確実に覚えることができます。
年号を覚えることで、それまでバラバラだった知識が時系列に沿って整理され、タテの流れが一気に明確になります。
通史の学習では復習のサイクルを確立することも非常に重要です。
おすすめの方法は、1つの時代を学習し終わったら必ずその時代全体を講義本で読み直し、一問一答で用語を確認するというサイクルを作ることです。
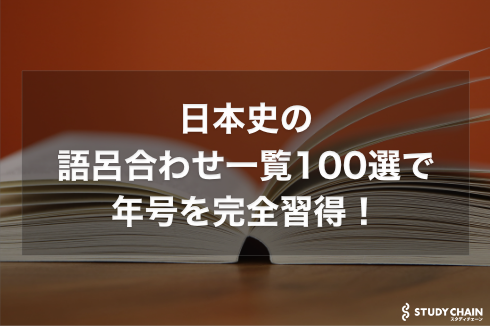 【大学受験】日本史を語呂合わせ一覧70選で年号を完全習得!語呂合わせ一覧を紹介
【大学受験】日本史を語呂合わせ一覧70選で年号を完全習得!語呂合わせ一覧を紹介 一問一答を使った大学受験の日本史の勉強法
一問一答を使った勉強法では、まず星2と星3の用語を完璧に覚えることを最優先にします。
ただし一問一答だけで勉強するのではなく、必ず講義本で流れを理解してから取り組むことが重要です。 講義本でタテの因果関係を理解した上で一問一答を解くことで、バラバラの知識ではなく体系的な知識として定着します。
一問一答を解く際には、間違えた問題に印をつけて翌日必ず復習するサイクルを作ります。
また用語を覚えるだけでなく、その用語が歴史の中でどのような役割を果たしたのかも意識して覚えることが大切です。
難関大志望の受験生は星1の用語も含めて全て覚えることを目標にして、細かい知識まで徹底的に暗記していきます。
▽日本史のおすすめの一問一答を知りたい人はこちら
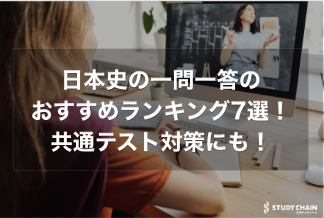 【大学受験】日本史の一問一答のおすすめランキング7選を紹介!共通テスト対策にも!
【大学受験】日本史の一問一答のおすすめランキング7選を紹介!共通テスト対策にも! 日本史の実況中継を使った大学受験の勉強法
日本史の実況中継を使った勉強法では、まず1日1講ずつ読み進めて歴史の流れを掴むことから始めます。
実況中継は講義形式で書かれているため、まるで授業を受けているような感覚で楽しく学習を進めることができます。 1講を読み終わったら、その範囲の一問一答を解いて知識を定着させることが重要です。
実況中継の最大の特徴は、詳しい説明と豊富なエピソードで記憶に残りやすい点にあります。
特に因果関係の説明が丁寧なため、なぜその出来事が起こったのかを理解しながら学習できます。 2周目以降は苦手な時代を重点的に読み直して、理解が曖昧な部分を完璧にしていきます。
大学受験の日本史の史料問題の勉強法
日本史の史料問題の勉強法では、まず日本史史料一問一答を使って頻出史料を覚えることから始めます。
史料を覚える際には、その史料が作成された時代背景や作成者、内容の要点をセットで覚えることが重要です。
史料一問一答を使う際には、必ず資料集と併せて学習することをおすすめします。
資料集には史料の原文や現代語訳が詳しく載っているため、視覚的にも記憶することができます。
また史料の特徴的なキーワードを覚えておきつつ、史料問題を過去問などで演習量を積み重ねていくことで、初見の史料でも時代や内容を推測する力が身につきます。
難関大志望の受験生は5ヶ月目以降に攻略日本史テーマと文化史も活用して、より難易度の高い史料問題にも対応できる力をつけていきます。
大学受験の日本史の文化史の勉強法
結論から述べると、文化史の対策では時代ごとに文化の特徴を整理して覚えることが最も効果的です。
文化史は通史と比べて対策が後回しになりがちですが、入試では必ず出題される分野であり、しっかりと対策すれば確実に得点できる分野でもあります。 具体的には金谷の文化史編を使って主要な文化財や文化人を時代ごとに整理して覚えていきます。
文化史の学習を始める際には、まず各時代の文化の特徴を大まかに理解することから始めます。 例えば飛鳥文化は仏教伝来の影響を受けた文化、国風文化は唐風から脱却した日本独自の文化というように、各時代の文化を特徴づけるキーワードを押さえておきます。
このキーワードを軸にして個別の文化財や文化人を覚えていくことで、体系的に文化史を理解することができます。
金谷の文化史編を読む際には、1日30分程度の時間を使ってじっくりと内容を理解していきます。
文化史は用語が難しく、建築様式や仏像の形式など専門的な知識も多いため、最初は理解するのに時間がかかります。
しかし資料集の写真や図版と併せて学習することで、視覚的にも記憶することができ、理解が深まります。
文化史の学習では資料集の活用が非常に重要です。
文化財は実際の写真を見て視覚的に覚えることで、試験でも思い出しやすくなります。
また建築様式や仏像の様式は言葉だけで理解するのは難しいため、必ず資料集の写真を見ながら特徴を確認することが大切です。
文化史の用語を覚える際には、時代と文化人と作品をセットで覚えることを心がけます。
例えば平安時代前期の貞観文化において空海が東寺を建立したというように、時代と人物と作品を関連づけて覚えることで、バラバラの知識として覚えるよりも記憶に定着しやすくなります。
また同じ人物が複数の作品を残している場合は、それらをまとめて覚えることで効率的に学習を進めることができます。
4ヶ月目以降は講義本で学習した内容を一問一答で確認していきます。
東進の一問一答には文化史の問題も豊富に収録されているため、星2以上の用語を確実に覚えることで共通テストから中堅私大レベルまでの文化史の問題には十分対応できます。
難関大志望の受験生は星1の用語も含めて全ての文化史の用語を覚えることを目標にします。
5ヶ月目以降は難関大志望の受験生に限り、攻略日本史テーマと文化史を使ってより高度な文化史の学習を進めます。
この問題集には難易度の高い文化史の問題が収録されており、早慶以上の難関大の文化史対策に最適です。 間違えた問題については金谷の文化史編で確認し、さらに資料集や用語集も活用して徹底的に復習します。
文化史の学習において最も差がつくのは、マイナーな文化財や文化人まで覚えているかどうかです。
主要な文化財や文化人は多くの受験生が覚えているため、そこでは差がつきにくくなっています。
しかし難関大の入試では、講義本の欄外に小さく載っているような細かい知識が問われることもあるため、時間に余裕がある受験生は用語集も活用して幅広く知識を身につけることをおすすめします。
文化史は通史と比べて対策にかける時間が少なくなりがちですが、入試での出題頻度を考えると十分な対策時間を確保する必要があります。
おすすめのタイミングは通史の学習が一通り終わった4ヶ月目から本格的に文化史の対策を始めることです。
この時期であれば通史の知識が頭に入っているため、各時代の文化史も理解しやすくなっています。
文化史の復習では、時代ごとにまとめノートを作成することも効果的です。
各時代の文化の特徴、主要な文化人、代表的な作品を1ページにまとめておくことで、試験前に効率的に復習することができます。
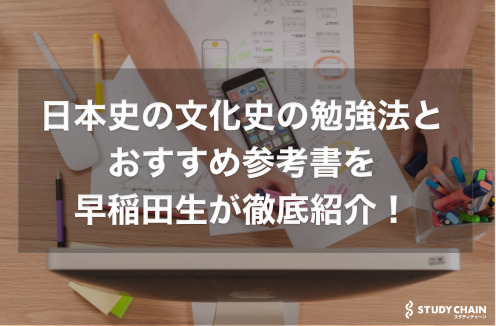 【大学受験】日本史の文化史の勉強法とおすすめ参考書を早稲田生が紹介!
【大学受験】日本史の文化史の勉強法とおすすめ参考書を早稲田生が紹介! 大学受験の日本史の記述対策の勉強法
結論から述べると、記述問題の対策では因果関係を論理的に説明できる力を養うことが最も重要です。
記述問題では単に用語を知っているだけでなく、その出来事がなぜ起こったのか、どのような影響を与えたのかを説明する力が求められます。
そのため普段の学習から因果関係を意識して知識を整理しておくことが記述問題対策の基本となります。
記述問題の対策を始める際には、まず金谷の日本史なぜと流れがわかる本を使って因果関係を徹底的に理解することから始めます。 この講義本は出来事の背景や影響を丁寧に説明してくれるため、記述問題で必要な論理的思考力を養うのに最適です。
講義本を読む際には、なぜその出来事が起こったのか、その結果何が変わったのかという2点を常に意識して読み進めることが重要です。
因果関係を理解したら、次は実際に記述問題を解いて論理的な文章を書く練習を始めます。 難関大志望の受験生は基礎問題精講や実力をつける日本史100題に収録されている記述問題から取り組んでいきます。
最初は模範解答を参考にしながらで構わないので、因果関係を論理的に説明する文章の書き方を学んでいきます。
記述問題を解く際のポイントは、必ず年号と人物を明記することです。
年号を書くことで時代背景が明確になり、人物を書くことで誰が主体となって行動したのかが明確になります。
また原因と結果を明確に区別して書くことで、論理的で分かりやすい解答を作成することができます。
共通テスト対策に効果的な日本史の勉強法
結論から述べると、共通テストで9割を取るためには年号を軸にしたタテの流れの完璧な理解と、星2以上の用語の確実な暗記が必須です。
共通テストの日本史で9割を取るためには、全体を通して年号と因果関係の理解が最も重要なポイントになります。
共通テストの日本史では細かい用語よりも、歴史の流れを理解しているかどうかが重視される傾向にあるため、因果関係を意識した学習が効果的です。
具体的には金谷の日本史なぜと流れがわかる本で大枠を掴みつつ、時代と流れで覚える問題集で年号とタテの流れを徹底的に暗記していきます。
また共通テストで9割を安定して取るためには文化史の対策も欠かせません。
文化史は共通テストでも必ず出題される分野であり、しっかりと対策すれば確実に得点できる分野でもあります。
金谷の文化史編を使って主要な文化財や文化人を時代ごとに整理して覚えていくことで、文化史の問題にも自信を持って解答できるようになります。また資料集を活用して視覚的な情報も一緒に覚えておくことで、写真の問題にも対応できる力が身につきます。
 共通テストの日本史で9割取れる勉強法を徹底解説!
共通テストの日本史で9割取れる勉強法を徹底解説! 1年で大学受験の日本史の偏差値を40から70にする勉強法
1年で大学受験の日本史の偏差値を40から70にする勉強法を解説します。
→通史と基礎用語の理解を習慣化する。(平日:20分「実況中継 日本史」→20分「時代と流れで覚える!」→40分「日本史一問一答 完全版[東進]」→10分復習/土日:同じ流れで2時間)
毎日「実況中継 日本史」で通史を確認し、出来事のつながりを意識して読み進めます。
「時代と流れで覚える!」で年号と因果関係を整理しながら、「日本史一問一答 完全版[東進]」で星2・星3を反復暗記します。
→「元祖日本史の年代暗記法」で年号暗記を強化。(平日:30分「元祖日本史の年代暗記法」→30分「実況中継 日本史」→30分「日本史一問一答 完全版[東進]」/土日:45分「元祖日本史の年代暗記法」→30分「実況中継」→30分「一問一答」→15分復習)
「元祖日本史の年代暗記法」で語呂と流れを使って年号を定着させ、多くの合格者もこの方法で一気に点数を伸ばしました。
「実況中継 日本史」で因果関係を確認し、「日本史一問一答 完全版[東進]」で理解と暗記が本当に定着しているかを毎日チェックします。
→文化史と演習を並行しながら得点力を底上げ。(平日:30分「基礎問題精講 日本史」or「共通テストへの道 日本史」→30分「実況中継 日本史 文化史編」→30分「日本史一問一答 完全版[東進]」/土日:45分問題集→30分文化史→30分「日本史史料一問一答」→15分復習)
「基礎問題精講 日本史」や「共通テストへの道 日本史」でアウトプットを行い、苦手分野を洗い出します。
文化史は「実況中継 日本史 文化史編」で毎日確認し、土日は「日本史史料一問一答」で史料暗記を進めることで差をつけます。
→実戦演習で完成度を高める。(平日:30分「実力をつける日本史100題」or「HISTORIA」→30分「攻略日本史 近・現代史」→30分「日本史一問一答 完全版[東進]」/土日:60分過去問→30分「実況中継 日本史」→30分復習)
「実力をつける日本史100題」や「HISTORIA」で難度の高い問題を解き、アウトプットを繰り返すことが合格への最短ルートです。
土日は志望校の過去問を解き、出題傾向を分析して「実況中継 日本史」と用語集で徹底復習することで完成度を高めるのがおすすめの日本史の勉強法です。
8ヶ月で大学受験の日本史の偏差値を40から70にする勉強法
8ヶ月で大学受験の日本史の偏差値を40から70にする勉強法の順番を解説します。
→まずは通史理解と基礎用語の暗記を徹底する。(時間配分:30分「金谷の日本史 なぜと流れがわかる本」→30分「時代と流れで覚える!」→45分「日本史一問一答 完全版[東進]」→15分復習)
「金谷の日本史 なぜと流れがわかる本」で毎日通史を読み進め、因果関係を意識しながら大枠を掴みましょう。「時代と流れで覚える!」を使って年号と出来事の順序を関連付け、タテの流れを意識して整理します。「日本史一問一答 完全版[東進]」では星2と星3を中心に暗記し、必ずその日のうちに金谷で確認して復習します。
→年号を軸に歴史の流れを固める。(時間配分:45分「金谷の日本史 なぜと流れがわかる本」→45分「元祖日本史の年代暗記法」→30分「日本史一問一答 完全版[東進]」)
「元祖日本史の年代暗記法」を毎日使い、語呂合わせを声に出して年号を徹底的に覚えましょう。
「金谷の日本史 なぜと流れがわかる本」で出来事の原因と結果を結びつけ、流れを理解しながら暗記を強化します。
「日本史一問一答 完全版[東進]」で年号や人物を確認し、暗記とアウトプットを結びつける習慣を作りましょう。
→志望校別に問題演習を開始。難関大は「基礎問題精講 日本史」、共通テストレベルは「共通テストへの道 日本史」を解く。(時間配分:45分「金谷の日本史」→30分問題集→30分「日本史一問一答 完全版[東進]」→15分「金谷の日本史 文化史編」)
問題演習で解けなかった範囲をそのままにせず、「金谷の日本史」に戻って流れを再確認します。
「基礎問題精講 日本史」や「共通テストへの道 日本史」を解き、必ず弱点を洗い出して暗記の優先度を上げましょう。
「金谷の日本史 文化史編」を使って文化史の暗記をスタートし、通史と同じように整理して定着させます。
→差がつく文化史と史料問題を重点対策。(時間配分:30分「金谷の日本史」→30分「日本史一問一答 完全版[東進]」→30分「日本史史料一問一答」→30分「攻略日本史 テーマ史・文化史」)
文化史は「攻略日本史 テーマ史・文化史」で体系的に整理し、分野ごとにまとめて覚えていきましょう。
史料問題は「日本史史料一問一答」を使い、出典と内容を関連付けて暗記することが重要です。
間違えた部分は必ず「金谷の日本史」で流れを確認し、知識を単発で終わらせないようにします。
→実戦的な問題演習を通して弱点を徹底補強。(時間配分:30分「金谷の日本史」→45分「実力をつける日本史100題」or「HISTORIA」→30分「日本史一問一答 完全版[東進]」→15分「日本史 用語集」)
「実力をつける日本史100題」や「HISTORIA」で本番に近い形式の問題を解き、アウトプット力を高めます。
間違えた問題はその場で「用語集」と「金谷の日本史」に戻って確認し、抜けを確実に潰しましょう。
「日本史一問一答 完全版[東進]」は星1にも触れ始め、細かい知識まで得点できる状態を目指します。
→志望校の過去問に本格的に取り組む。(時間配分:60分過去問→30分「金谷の日本史」→30分「日本史一問一答 完全版[東進]」)
志望校の過去問を10〜15年分解き、出題の傾向や頻出テーマを把握します。間違えた分野は「用語集」や「金谷の日本史」で復習し、次に出題されても必ず正解できるようにしましょう。
大学受験の日本史の勉強法の実践におすすめの参考書一覧
大学受験の日本史の勉強法の実践におすすめの参考書を解説します。
元祖日本史の年代暗記法
元祖日本史の年代暗記法は、日本史の主要な出来事の年号を語呂合わせで効率的に覚えることができる参考書です。
年号は日本史学習の土台となる知識であり、年号を完璧に覚えることでタテの流れが一気に明確になります。
元祖日本史の年代暗記法は語呂合わせが面白く工夫されているため、楽しみながら自然と年号を記憶することができます。
共通テストでも私大入試でも年号の前後関係を問う問題は頻出されるため、確実に得点を積み重ねることができます。
時代と流れで覚える日本史用語
時代と流れで覚える日本史用語は、年代順に問題が配列されているため、自然とタテの流れを意識しながら学習を進めることができる問題集です。
年号とタテの流れと因果関係を同時に学習できる点が最大の特徴であり、単なる用語暗記ではなく歴史の流れを理解しながら覚えることができます。
時代と流れで覚える日本史用語は金谷の講義本で大枠を掴んだ後に使うことで、知識を確実に定着させることができます。
金谷の日本史なぜと流れがわかる本
金谷の日本史なぜと流れがわかる本は、日本史の出来事を単なる暗記ではなく、なぜその出来事が起こったのかという因果関係を丁寧に説明してくれる講義本です。
日本史の難しいポイントとして登場人物が多いことと年号が細かいからこそ、因果関係の説明が詳しいため、記述問題や論述問題にも対応できる本質的な理解力が身につきます。
金谷の日本史なぜと流れがわかる本は歴史の流れを論理的に理解しながら学習を進めることができるため、日本史学習の軸となる参考書です。
1日30分程度の時間を使ってじっくりと内容を理解しながら読み進めることで、日本史全体の大きな流れを掴むことができます。
読み終わった範囲については、時代と流れで覚える問題集や一問一答を使ってすぐにアウトプットすることで、理解した内容を確実に定着させることができます。
▽おすすめの日本史の参考書の使い方やレベルが知りたい方はこちら
大学受験の日本史対策におすすめの参考書ルート
大学受験の日本史対策におすすめの参考書ルートを解説します。
| 月 | 勉強内容 | 使用参考書(出版社) |
|---|---|---|
| 1〜2ヶ月目 | 年号・人物軸で通史理解 | 「金谷の日本史 なぜと流れがわかる本」(東進ブックス)/「時代と流れで覚える!日本史用語」(東進ブックス)/「東進 日本史一問一答」(東進ブックス) |
| 3ヶ月目 | 年号暗記の徹底 | 「元祖 日本史年代暗記法」(東進ブックス)/「金谷の日本史」復習 |
| 4ヶ月目 | 問題演習+文化史導入 | 「基礎問題精講」(旺文社)/「共通テストへの道 日本史」(Z会)/「金谷の文化史」 |
| 5ヶ月目 | 難関対策(文化・史料) | 「日本史 史料一問一答」(東進ブックス)/「攻略日本史 テーマ・文化史」(Z会)/「資料集」(山川) |
| 6ヶ月目 | 現代史+過去問演習 | 「HISTORIA」(Z会)/「実力をつける日本史100題」(Z会)/「攻略日本史 近現代史」(Z会)/「志望校別過去問」 |
志望校別におすすめの日本史の大学受験対策の勉強法
志望校別におすすめの日本史の大学受験対策の勉強法を解説します。
東大志望におすすめの大学受験の日本史の勉強法
東京大学の日本史は論述問題が中心となるため、単なる暗記だけでは対応できません。歴史的な出来事の背景や因果関係を深く理解し、それを自分の言葉で説明できる力が求められます。
学習の初期段階では、講義系の参考書を使って日本史全体の大きな流れをつかむことから始めます。
この段階で重要なのは、なぜその出来事が起きたのか、その結果どうなったのかという因果関係を常に意識することです。年号の暗記も必須ですが、東大の場合は年号そのものを答えさせるよりも、時代の前後関係を問う問題が多いため、出来事の順序を正確に把握することが重要になります。
論述対策としては、まず100字程度の短い論述から練習を始めることをおすすめします。与えられたテーマについて、原因や背景や結果を簡潔にまとめる訓練を繰り返すことで、長文の論述にも対応できる基礎力が身につきます。また過去問演習では、解答を作成した後に模範解答と比較し、自分に足りない視点や知識を洗い出す作業が不可欠です。
慶應義塾大学志望におすすめの大学受験の日本史の勉強法
慶應義塾大学の日本史は学部によって出題傾向が大きく異なりますが、共通して言えるのは細かい知識まで問われる傾向が強いことです。特に文学部や経済学部では、教科書の欄外に載っているような用語まで出題されることがあります。
学習戦略としては、まず基礎的な用語を確実に押さえた上で、段階的に知識の範囲を広げていく方法が効果的です。一問一答形式の問題集を使う際には、最初は重要度の高い用語から覚え始め、それが完璧になったら次のレベルの用語に進むという流れで学習を進めます。
慶應を目指す場合は、一問一答の全ての用語を覚えるくらいの気持ちで取り組む必要があります。また用語集の活用も非常におすすめです。
文化史の対策も慶應合格には必須です。他の受験生が手薄になりがちな分野だからこそ、ここで差をつけることができます。美術作品や文学作品の名称だけでなく、その作品が生まれた時代背景や特徴まで理解しておくことが重要です。文化史専用の参考書を使って、作品の画像や写真を見ながら覚えることで、記憶に定着しやすくなります。
また慶應の問題は正誤問題が多く出題される傾向があります。正誤問題は曖昧な知識では正解できないため、用語の定義や歴史的事実を正確に理解しておく必要があります。過去問を解く際には、なぜその選択肢が正しいのか、または誤っているのかを説明できるまで復習することが大切です。
早稲田大学志望におすすめの大学受験の日本史の勉強法
早稲田大学の日本史は学部によって難易度に差がありますが、全体的に見ると教科書レベルを超えた発展的な内容まで出題されることが特徴です。特に政治経済学部や法学部では、現代史の出題比重が高く、戦後史まで丁寧に学習しておく必要があります。
基礎固めの段階では、まず通史を完璧にすることを最優先に考えます。早稲田の問題は難しいと言われますが、実は基礎的な知識を正確に理解していれば解ける問題も多く含まれています。そのため講義系の参考書を繰り返し読み込み、歴史の流れと因果関係をしっかりと頭に入れることが重要です。
年号の暗記は早稲田対策において特に重要になります。早稲田の問題では年代整序問題が頻出されるため、主要な出来事の年号は確実に覚えておく必要があります。年号暗記用の参考書を活用し、語呂合わせなども使いながら効率的に覚えていくことをおすすめします。また年号を覚える際には、その出来事の前後関係も意識することで、より深い理解につながります。
テーマ史の対策も早稲田合格には欠かせません。政治史や経済史や外交史など、特定のテーマに沿って歴史を横断的に理解する力が求められます。テーマ史専用の問題集を使って、複数の時代にわたる歴史の流れを整理しておくことが効果的です。
過去問演習では、志望学部の出題傾向を徹底的に分析することが重要です。学部によって出題される時代や分野に偏りがあるため、その傾向に合わせて学習の重点を調整していく必要があります。
MARCH志望におすすめの大学受験の日本史の勉強法
関関同立志望におすすめの大学受験の日本史の勉強法
効果的な日本史のノートの取り方
日本史の成績を効率的に伸ばすためには、ノートの使い方が非常に重要になります。ノートは単なる記録ツールではなく、知識を整理し記憶を定着させるための強力な武器となります。
効果的なノート作りの基本は、タテの流れとヨコのつながりを意識することです。タテの流れとは時代の順序や因果関係を指し、ヨコのつながりとは同じ時代における政治や経済や文化の関連性を意味します。この2つの軸を意識してノートを作ることで、日本史の全体像が驚くほど明確になります。
具体的なノート作成の手順としては、まず講義本を読みながら重要な年号と人物名を中心に書き出していきます。年号は日本史学習の骨組みとなるため、必ず左側の余白に大きく記載して目立たせることが効果的です。その横に出来事や人物名を書き、さらにその右側に簡単な因果関係や背景をメモしていきます。
ノートの復習方法も工夫が必要です。最初に作ったノートは情報が散らばりがちなので、定期的に見返しながら赤ペンで補足情報を追記したり、矢印で関連事項をつないだりすることで、より理解が深まります。また問題集で間違えた箇所はノートに戻って該当部分を確認し、なぜ間違えたのかを分析することが大切です。
学年別に高校生におすすめの大学受験の日本史の勉強法
高校生の学年別におすすめの大学受験の日本史の勉強法を解説します。
高校3年生におすすめの日本史の勉強法
高校3年生の時期には定期テストの範囲を一時的に暗記するだけではもったいないです。そのため一問一答のような大学受験でも使える教材を活用して定期テストの勉強をすることで受験対策にも直結する学習ができます。
具体的には金谷の日本史なぜと流れがわかる本のような講義系の参考書を使って時代の流れと因果関係を理解することから始めましょう。その後に東進の一問一答で星2以上の用語を確実に覚えていくことが重要です。また元祖日本史の年代暗記法を使って年号を徹底的に覚えることで大学受験の土台を作ることができます。
さらに文化史や史料問題にも早めに取り組むことで他の受験生との差をつけることができます。特に早慶以上の難関大学を志望する受験生は定期テストの勉強をしながら日本史史料一問一答や攻略日本史テーマ文化史などの参考書にも取り組むことで受験に必要な力を養うことができます。
高校2年生におすすめの日本史の勉強法
結論として高校2年生は日本史の基礎固めを徹底的に行う時期であり、定期テストを通して年号と人物を軸にした学習を進めることが大切です。
高校2年生の段階では教科書の太字レベルの重要用語を確実に覚えることを最優先にしましょう。この時期に基礎を固めておくことで高校3年生になってから本格的な受験勉強を始める際にスムーズに進めることができます。
定期テストの勉強をする際には教科書を何度も読み込むことに加えて、時代と流れで覚える日本史Bのような年号を中心にした参考書を活用することをおすすめします。年号を覚えることで時代の流れを把握しやすくなり、出来事の前後関係や因果関係を理解することができるようになります。
また高校2年生のうちから一問一答を使って用語を覚える習慣をつけておくことも重要です。ただし高校2年生の段階では星3や星2の頻出用語を中心に覚えていけば十分です。復習ノートを作って間違えた問題や覚えにくい用語をまとめておくことで効率的に復習することができます。
高校1年生におすすめ日本史の勉強法
結論として高校1年生は日本史の学習習慣を身につけることと歴史の流れを大まかに把握することを目標にしましょう。
高校1年生の日本史は中学校で学んだ内容をより深く掘り下げていく形で進んでいきます。そのため最初は難しく感じるかもしれませんが、焦らずに教科書の内容を丁寧に理解していくことが大切です。
定期テストの勉強では教科書の太字になっている用語を中心に覚えていきましょう。ただし単語だけを暗記するのではなく、どのような流れでその出来事が起きたのかを理解することが重要です。声に出して説明できるレベルまで理解を深めることで記憶に定着しやすくなります。
また高校1年生のうちから復習する習慣をつけておくことも大切です。定期テストが終わったらその範囲をもう一度見直すことで忘れにくくなります。資料集や図版なども活用して視覚的に覚えることで理解が深まります。プリントや授業のノートは必ず保管しておいて定期テスト前に見直せるようにしておきましょう。
目的別におすすめの日本史の勉強法
目的別におすすめの日本史の勉強法を解説します。
定期テスト対策におすすめの日本史の勉強法
結論として日本史の定期テストで9割以上を取るためには試験の1週間前までに6割から7割程度の完成度にしておくことが必須です。
具体的には試験の2週間前から1週間前までの期間で教科書を最低でも3回以上読み込むことが大切です。この際にただ読むだけではなく年号と人物を中心に覚えていくことを意識しましょう。年号は時代の流れを把握するための軸となるため最優先で覚えていく必要があります。
そして1週間前から4日前まではアウトプット中心の勉強に切り替えます。
問題集を解いて間違えた箇所をノートにまとめることで効率的に復習することができます。この時期には資料集の図版や文化財の写真にも必ず目を通しておきましょう。
試験の3日前から前日までは苦手な分野の整理と最終確認に集中します。新しい知識を増やすのではなく、これまでにまとめてきたノートを何度も見直すことが効果的です。前日は十分な睡眠を取ることを最優先にして当日の朝に15分程度の復習をすることで記憶を鮮明にして試験に臨むことができます。
▽日本史の定期テスト対策のおすすめの勉強法をもっと詳しく知りたい方はこちら
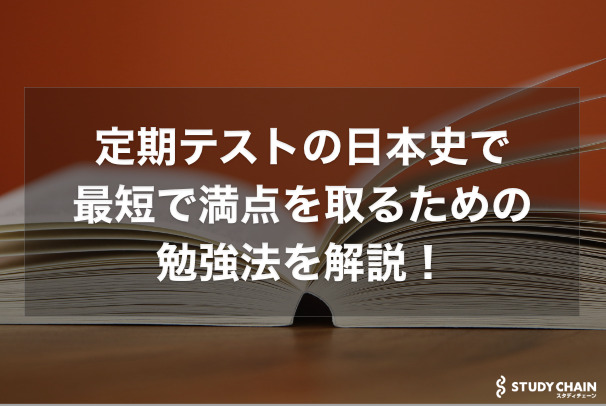 定期テストで日本史満点を取る勉強法を解説!前日のノート活用法も!
定期テストで日本史満点を取る勉強法を解説!前日のノート活用法も! 日本史の定期テスト前日の一夜漬けにおすすめの勉強法
日本史の前日の一夜漬けでは教科書の太字とプリントの重要箇所を中心に復習しましょう。新しい内容に手を広げるのではなく、これまでの授業で先生が強調していた部分や配布されたプリントの内容を重点的に確認することが効率的です。
そして試験当日の朝にもう一度復習することで記憶を定着させることができます。
まとめ
今回は、ゼロから東大に受かる日本史の勉強法から共通テストで9割取れる勉強法、そして分野別の対策まで徹底的に解説しました。