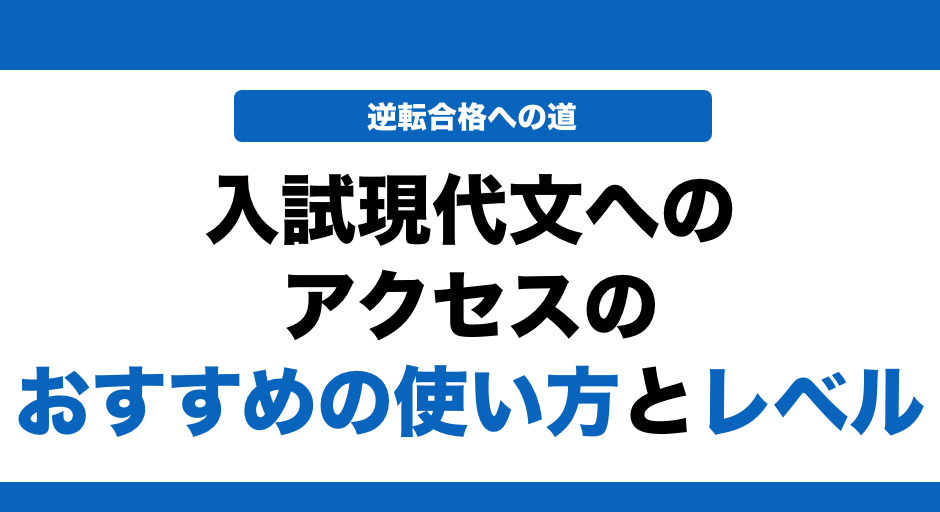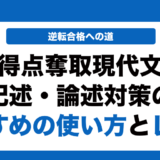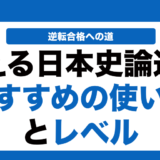本サイトの表記には、一部プロモーションを含みます
入試現代文へのアクセスのおすすめの使い方と勉強法を徹底解説します。
入試現代文へのアクセスのレベルや難易度についても具体的に解説します。また実際にやってみておすすめの入試現代文へのアクセスの参考書としての進め方や順番についても紹介します。

【この記事の監修者:逆転合格特化塾塾長竹本明弘】
政経の参考書として一問一答形式の知識をまとめて得られる参考書はあまりないため、政経ハンドブックも含めて自分が使いやすいと感じたものを使ってまとめて暗記していくと良いです。
入試現代文へのアクセスのレベル
入試現代文へのアクセスのレベルを段階的に解説します。
入試現代文へのアクセスのレベルと難易度
結論として、入試現代文へのアクセスのレベルは基本編から完成編まで段階的に設定されており、基礎から最難関大学レベルまで対応できる参考書です。基本編は現代文の読解の基礎を固めたい受験生向け、発展編は標準レベルの国公立大学や私立大学を目指す受験生向け、完成編は難関大学で現代文を得点源にしたい受験生向けとなっています。
基本編は共通テストで5割程度の得点力、模試での全国偏差値が50前後の受験生が対象です。発展編は共通テストで6割程度の得点力、全国偏差値が60前後の受験生を想定しています。完成編は共通テストで8割以上を安定して取れる、全国偏差値が65以上の受験生が取り組むべきレベルとなっています。

【この記事の監修者:逆転合格特化塾塾長竹本明弘】
入試現代文へのアクセスは基本編から始めれば現代文がまったくわからない受験生でも取り組める参考書です。一方で完成編は早慶レベルの難関私立大学や旧帝大レベルの記述問題にも対応できる高いレベルの参考書なので、自分の実力に合わせて適切なレベルを選ぶことが合格への近道です。
入試現代文へのアクセスの習熟度別のレベル
入試現代文へのアクセスの習熟度別のレベルを解説します。
レベル1:基本編の問題を解いて正答率が5割程度取れる段階です。この段階では文章の構造分析がまだ不十分で、解説を読みながら現代文の読み方の基礎を理解していく時期です。
レベル2:基本編の問題で正答率が7割程度取れる段階です。意味段落の区切り方や対比構造などの基本的な文章構造が理解できるようになり、偏差値は50から55程度になります。
レベル3:基本編の問題で正答率が9割以上取れる段階です。基礎的な現代文の読み方が身につき、発展編へ進む準備が整った状態で、偏差値は55から60程度になります。
レベル4:発展編の問題で正答率が7割程度取れる段階です。より複雑な論理構造の文章にも対応できるようになり、完成編へ進める実力がついた状態で、偏差値は60から65程度になります。
レベル5:完成編の問題で正答率が6割以上安定して取れる段階です。難関大学レベルの抽象度の高い文章でも論理構造を正確に把握でき、偏差値は65から70程度になります。
入試現代文へのアクセスのおすすめの使い方
入試現代文へのアクセスのおすすめの使い方を解説します。
入試現代文へのアクセスの使い方として最初に重要なのは、問題をコピーして解くことです。この参考書には解法のヒントが豊富に記載されているため、何度も繰り返し解く必要があります。問題集に直接書き込んでしまうと2周目以降の学習効果が下がってしまうため、必ずコピーを取って取り組みましょう。
問題を解く際は30分から40分程度の時間を設定して、自力で文章を読み解きます。この時に重要なのは、対比構造や意味段落を意識しながら文章の構造を分析することです。筆者がどのような主張をどのように展開しているのか、起承転結の流れはどうなっているか、2項対立の構造があるかなどを考えながら読み進めます。また指示語が何を指しているのかを確認することも、文章理解の精度を高めるために欠かせません。
入試現代文へのアクセスの使い方で最も重要なのが、自分の分析と解説の比較です。問題を解き終わったら、まず自分が行った文章構造の分析と解説に載っている分析を照らし合わせます。意味段落の区切り方が正しかったか、筆者の主張の展開を正確に把握できていたか、解法のアプローチは適切だったかを細かく確認していきます。
入試現代文へのアクセスは解説が非常に詳しく、問題文そのものの解説が充実している点が最大の特徴です。他の参考書では扱われない問題文の構造分析が詳細に記載されているため、この解説を活用して自分の読み方を修正していくことが、レベルアップの鍵となります。解説に納得できない部分があれば、学校の国語の先生に質問するなどして必ず疑問を解消しましょう。
入試現代文へのアクセスの使い方として、一度解いただけで終わらせないことが大切です。特に初見の問題で対応できなかった文章構造の分析パターンは、繰り返し解くことで身につけていく必要があります。2周目以降はコピーした問題を使って、前回よりも短い時間で解けるように意識しながら取り組みます。
また各レベルで設定されている完了目安を参考に、次のレベルへ進むタイミングを判断します。基本編であれば正答率が9割を超えたら発展編へ、発展編であれば正答率が7割に達したら完成編へと進んでいきます。焦って次のレベルに進むのではなく、確実に現在のレベルの内容を習得してから次の段階へ進むことで、入試現代文へのアクセスの効果を最大限に引き出せます。
入試現代文へのアクセスの習得にかかる時間
入試現代文へのアクセスの習得にかかる時間を解説します。
入試現代文へのアクセスは各レベルに16問が収録されているため、1問あたりの学習時間を考慮すると、1つのレベルを完了するには約1ヶ月程度が目安となります。1問を解くのに30分から40分、解説の確認と復習に30分程度かかるため、1日1問のペースで進めると2週間で1周できます。ただし入試現代文へのアクセスは1周だけでは十分な効果が得られないため、最低でも2周は繰り返す必要があります。
基本編から完成編まで全て取り組む場合は、合計で3ヶ月から4ヶ月程度の学習期間を見込んでおく必要があります。ただし受験生の現在のレベルや1日に確保できる学習時間によって、この期間は変動します。現代文に多くの時間を割ける受験生であれば、より短期間での習得も可能です。逆に他の科目との兼ね合いで現代文に割ける時間が限られている場合は、自分に必要なレベルのみを集中的に学習する選択も有効です。
入試現代文へのアクセスを使う時の注意点
入試現代文へのアクセスを使う時の注意点を解説します。
入試現代文へのアクセスを使う際の最も重要な注意点は、問題文の構造分析と解法の比較を納得するまで徹底的に行うことです。なぜそのような文章構造になるのか、なぜその解答アプローチが正しいのかを理解せずに次の問題に進んでも、実力は向上しません。解説を読んで分かった気になるのではなく、自分の言葉で説明できるレベルまで理解を深める必要があります。
また自分のレベルに合っていない問題集を使っても効果が薄いため、現在の実力を正確に把握して適切なレベルから始めることが重要です。共通テストの過去問や模試の結果を参考に、基本編、発展編、完成編のどれから取り組むべきかを判断しましょう。背伸びして難しいレベルから始めると挫折の原因になりますし、簡単すぎるレベルでは学習効果が限定的になってしまいます。
さらに入試現代文へのアクセスには重要な現代文キーワードの解説が含まれていますが、志望校によってはこれだけでは語彙力が不足する可能性があります。特に難関大学を目指す受験生は、別途現代文キーワード集を併用することをおすすめします。
入試現代文へのアクセスの特徴
入試現代文へのアクセスにはいくつかの際立った特徴があります。
最大の特徴は問題文そのものの解説が非常に詳しい点です。多くの現代文の参考書では設問の解説が中心ですが、入試現代文へのアクセスでは問題文が意味段落ごとに区切られ、筆者の主張がどのように展開されているかが丁寧に説明されています。この問題文解説により、受験生は文章構造を正確に把握する力を養うことができます。
また頻出する現代文キーワードの解説が充実している点も特徴です。入試で出題される文章のテーマは実は限られており、繰り返し登場する重要語句を理解することで読解力が大きく向上します。入試現代文へのアクセスでは一度出てきた語句を忘れないような構成になっており、段階的に語彙力を高められます。
さらに良問が厳選されている点も見逃せません。河合塾が長年の入試分析に基づいて選び抜いた問題が収録されているため、効率的に実力を伸ばすことができます。各レベルに16問という適切な問題数も、挫折せずに完走できる要因となっています。
入試現代文へのアクセスのメリット
入試現代文へのアクセスのメリットを解説します。
文章構造の理解が深まる
入試現代文へのアクセスの最大のメリットは、文章構造を正確に把握する力が身につく点です。問題文の詳細な解説により、筆者の論理展開や意味段落の区切り方を学べます。この力は入試本番でどのような文章が出題されても対応できる応用力につながります。フィーリングで解いていた受験生も、入試現代文へのアクセスを通じて論理的な読解方法を習得できるでしょう。
段階的にレベルアップできる
入試現代文へのアクセスは基本編、発展編、完成編という3段階のレベル設定により、無理なく実力を伸ばせる点がメリットです。現在の学力に合わせて適切なレベルから始められるため、挫折しにくい構成になっています。また各レベルの完了目安が明確に示されているため、次のステップに進むタイミングも判断しやすくなっています。自分の成長を実感しながら学習を進められる点は、モチベーション維持にもつながります。
解説の質が非常に高い
入試現代文へのアクセスは解説の質の高さで多くの受験生から支持されています。ただ答えを示すだけでなく、なぜその答えになるのかという過程が丁寧に説明されているため、納得しながら学習を進められます。また解説を読むことで、自分では気づけなかった文章の読み方や解法のアプローチを学べます。河合塾の長年のノウハウが詰まった解説は、独学で現代文を学ぶ受験生にとって貴重な指針となるでしょう。
入試現代文へのアクセスのデメリット
入試現代文へのアクセスのデメリットを解説します。
問題数が限られている
入試現代文へのアクセスのデメリットとして、各レベルに16問しか収録されていない点が挙げられます。現代文は演習量を増やすことで実力が向上する面もあるため、16問だけでは不十分に感じる受験生もいるかもしれません。特に完成編まで終えた後、さらに演習を積みたい場合は別の問題集を追加する必要があります。ただし入試現代文へのアクセスは質の高い問題が厳選されているため、1問1問を丁寧に復習すれば十分な効果は得られます。
要約問題の解答が基本編にはない
入試現代文へのアクセスの基本編には要約問題の模範解答が掲載されていないというデメリットがあります。発展編と完成編には要約の解答がついていますが、基本編で要約練習をしたい受験生は自分で要約を作成しても正解がわからず不安になるかもしれません。要約練習を重視したい受験生は、基本レベルから要約の解答がついている他の参考書を検討する必要があります。
志望校によっては語彙力が不足する
入試現代文へのアクセスには重要な現代文キーワードの解説が含まれていますが、最難関大学を目指す受験生にとってはこれだけでは語彙力が不足する可能性があります。特に早慶レベルや旧帝大レベルの入試では、より専門的な語彙や抽象的な概念の理解が求められます。そのため入試現代文へのアクセスと並行して、専門の現代文キーワード集を使った学習も必要になるでしょう。
入試現代文へのアクセスに関するよくある質問
入試現代文へのアクセスに関するよくある質問を解説します。
- 入試現代文へのアクセスの完成編が難しすぎる場合はどうすればよいですか?
- 入試現代文へのアクセスの完成編が難しすぎると感じる場合は、無理に進めずに発展編に戻ることをおすすめします。完成編は偏差値65以上の受験生を対象としており、早慶レベルの抽象的な文章が多く含まれています。発展編を繰り返し解いて正答率を8割以上に高めてから、改めて完成編に挑戦する方が効率的です。また完成編に取り組む前に、現代文キーワード集で語彙力を強化しておくことも有効です。焦らず段階的にレベルアップすることが、入試現代文へのアクセスを効果的に活用する秘訣です。
- 入試現代文へのアクセスと現代文ポラリスの違いは何ですか?
- 入試現代文へのアクセスと現代文ポラリスの大きな違いは、要約問題への対応です。現代文ポラリスは全レベルで要約の解答が掲載されているため、要約力を重点的に鍛えたい受験生に適しています。一方、入試現代文へのアクセスは問題文の構造分析の解説が非常に詳しく、論理的な読解力を養うことに重点を置いています。基本編で要約練習も行いたい受験生には現代文ポラリスがおすすめですが、文章構造の理解を深めたい受験生には入試現代文へのアクセスの方が向いているでしょう。
- 入試現代文へのアクセスと現代文読解力の開発講座はどちらがおすすめですか?
- 入試現代文へのアクセスと現代文読解力の開発講座では、解説の詳しさという点で入試現代文へのアクセスに軍配が上がります。入試現代文へのアクセスは問題文そのものの解説が充実しており、文章構造の分析方法を段階的に学べる点が特徴です。一方、現代文読解力の開発講座は問題数が多く演習量を確保したい受験生に向いています。初めて本格的に現代文の勉強をする受験生や、文章構造の読み取り方を基礎から学びたい受験生には入試現代文へのアクセスの方がおすすめです。
- 入試現代文へのアクセスは何周すればよいですか?
- 入試現代文へのアクセスは最低でも2周、できれば3周以上繰り返すことをおすすめします。1周目は問題を解いて解説を読み、文章構造の分析方法や解法を理解することに重点を置きます。2周目はコピーした問題を使って、学んだ分析方法を実践しながら解いていきます。3周目以降は時間を計りながら解き、より短時間で正確に解答できるようにトレーニングします。入試現代文へのアクセスには解法のヒントが豊富に含まれているため、繰り返し解くことで初見の問題にも対応できる力が身につきます。
- 入試現代文へのアクセスは基本編から始めるべきですか?
- 入試現代文へのアクセスを基本編から始めるかどうかは、現在の学力によって判断すべきです。共通テストの過去問で5割程度しか取れない、または模試の偏差値が50前後の受験生は基本編から始めることをおすすめします。一方で共通テストで6割以上取れる受験生は発展編から、8割以上取れる受験生は完成編から始めても問題ありません。自分のレベルより易しすぎる問題集を使っても効果が限定的なので、まずは共通テストの過去問や模試で自分の実力を確認してから適切なレベルを選びましょう。