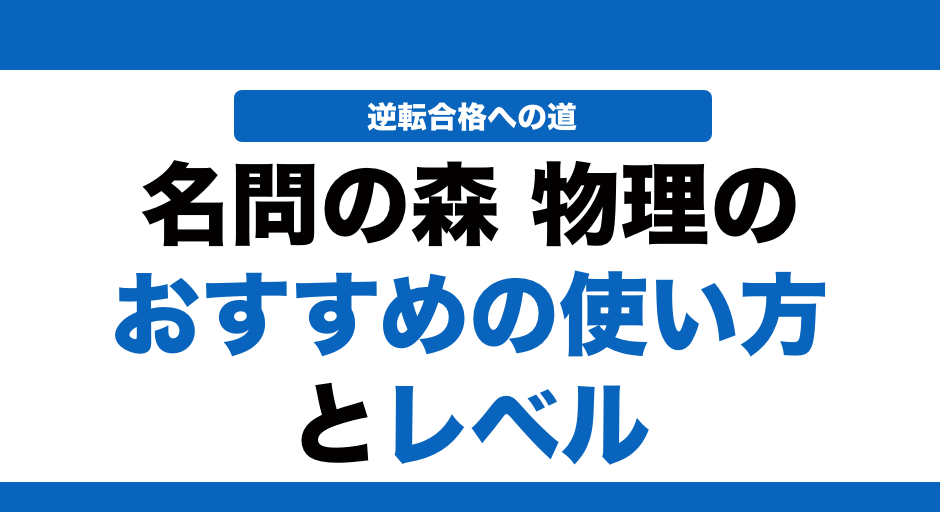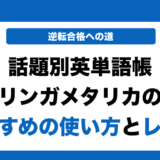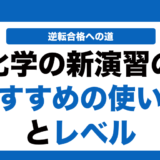本サイトの表記には、一部プロモーションを含みます
【物理】名門の森のおすすめの使い方と勉強法を徹底解説します。
【物理】名門の森のレベルや難易度についても具体的に解説します。また実際にやってみた上でのおすすめの【物理】名門の森の参考書としての進め方や順番についても紹介します。

【この記事の監修者:逆転合格特化塾塾長竹本明弘】
これまで個別指導塾の塾長として早慶に現役生および浪人生を含めて合計で300人以上の合格者を輩出してきました。参考書の使い方や各教科の勉強法について紹介しているのでぜひ参考にしてみてください。
名問の森物理のレベル
名問の森物理のレベルを解説します。
名問の森物理のレベルと難易度
名問の森物理のレベルは難関大学入試対策レベルの参考書です。この参考書は東京大学や京都大学、大阪大学、名古屋大学といった旧帝国大学レベルの問題に対応できる実力を養成することを目的としています。
また早稲田大学や慶應義塾大学などの難関私立大学の入試問題にも対応可能な難易度となっています。名問の森物理は良問の風を終えた受験生が次のステップとして取り組むべき参考書であり、基礎的な知識がすでに身についていることが前提となります。
したがって初学者や物理の基礎が固まっていない受験生がいきなり取り組むには難易度が高すぎる参考書といえるでしょう。名問の森物理に取り組む前には教科書傍用問題集や良問の風である程度の実力をつけておく必要があります。

【この記事の監修者:逆転合格特化塾塾長竹本明弘】
名問の森物理は旧帝大や早慶レベルを目指す受験生向けの問題集です。良問の風で偏差値67.5程度まで到達してから取り組むべき参考書で、この参考書を8割以上解けるようになれば偏差値75レベルに到達できる非常に実践的な教材です。
名問の森物理の習熟度別のレベル
名問の森物理の習熟度別のレベルを2段階に分けて解説していきます。
レベル1は名問の森物理の5割以上の問題が自力で解けるようになった状態です。この段階では難関大学の入試問題に対してある程度の対応力がついてきた状態といえます。
レベル2は名問の森物理の8割以上の問題が自力で解けるようになった状態で、この段階に到達すると偏差値75レベルに相当します。全統記述模試などの河合塾の模試で偏差値75を取れる実力がつくため、旧帝大や早慶といった最難関大学の入試にも十分対応できる力が身についた状態です。
名問の森物理をレベル2まで習得できれば物理の入試問題で高得点を狙える実力が完成したといえるでしょう。ただし名問の森物理だけで偏差値75に到達するわけではなく、その前の段階として良問の風などの基礎的な問題集をしっかりと習得しておくことが前提条件となります。
名問の森物理のおすすめの使い方
名問の森物理のおすすめの使い方を3段階に分けて解説していきます。
名問の森物理では最初から問題形式で取り組んでいきましょう。すでに教科書傍用問題集や良問の風で基礎は固めているため、わからない問題があってもすぐに解説を見て構いません。
まずはPoint & Hintの部分をしっかりと読み込んでください。この部分には問題を解くために必要な知識の核心が書かれており、知識の応用力を高めるために非常に重要です。
その後LECTUREを読んで内容をしっかりと理解しましょう。名問の森物理では解説が非常に丁寧に書かれているため、解説を読むことで問題の解き方や考え方を学ぶことができます。
名問の森物理で問題を解いたら必ず◯×マークをつけていきましょう。自力で解けた問題には◯マークを、解けなかった問題には×マークをつけていきます。
このマーキングは小問単位で行うことが重要です。×マークはダメな印ではなく復習が必要な問題であることを示すマークなので、どの問題を優先的に復習すべきかを明確にするために役立ちます。
名問の森物理で定期テストや模試の範囲を1周したら、再び最初に戻って◯マークが一度もついていない問題を中心に復習していきましょう。一度◯マークがついた問題は模試の1週間前まで復習しなくても大丈夫です。
名問の森物理では何度も復習を繰り返して解ける問題を増やしていくことが大切です。模試の1週間前には特に何度も×マークがついた後に◯マークになった問題を優先的に復習しましょう。
受験勉強の時間の90パーセント以上は復習に費やされるため、効率的に復習するには解ける問題を解かないことが最も重要になります。名問の森物理で◯×マークを累積させることで、復習すべき問題を明確にできます。
最終的には名問の森物理の全問題を瞬殺できる状態を目標にしましょう。この状態に到達すれば難関大学の入試問題にも十分対応できる実力が身についているはずです。
名問の森物理の習得にかかる時間
名問の森物理の習得にかかる時間について解説していきます。
名問の森物理は全140問で構成されており、1問あたり平均30分かかります。単純計算で全問題を1周するだけで70時間程度必要になります。
ただし名問の森物理は1周だけでは習得できないため、復習を含めると相当な時間が必要です。受験生の学習状況にもよりますが、名問の森物理をレベル2まで習得するには3ヶ月から4ヶ月程度かかると考えておくとよいでしょう。
1日2時間程度の学習時間を確保できる受験生であれば、4ヶ月程度で名問の森物理を完成させることができます。ただし前提として良問の風をしっかり習得していることが必要で、基礎が固まっていない状態で名問の森物理に取り組むとさらに時間がかかってしまいます。
名問の森物理を使う時の注意点
名問の森物理を使う時の注意点をいくつか解説していきます。
まず名問の森物理に取り組む前に必ず良問の風を習得レベル2にしておく必要があります。良問の風で偏差値67.5近くに到達していない状態で名問の森物理に入ると、難易度が高すぎて挫折してしまう可能性が高いです。
また名問の森物理だけで偏差値75に到達できるわけではないという点にも注意が必要です。名問の森物理はあくまで良問の風などの基礎的な問題集で培った実力をさらに伸ばすための教材であり、基礎ができていない状態では効果を発揮できません。
さらに名問の森物理では瞬殺できる状態をゴールとすることが重要です。時間をかければ解けるというレベルではなく、入試本番で素早く正確に解ける力を身につけることを目指しましょう。
名問の森物理の特徴
名問の森物理にはいくつかの特徴があります。
まず名問の森物理は力学・熱・波動1と波動2・電磁気・原子の2冊に分かれており、物理の全範囲を網羅しています。各分野ごとに段階的に学習を進められる構成になっているため、苦手分野を集中的に対策することも可能です。
また名問の森物理にはPoint & HintとLECTUREという解説が充実しています。Point & Hintでは問題を解くために必要な知識の核心部分が簡潔にまとめられており、LECTUREでは詳しい解説が展開されています。
さらに名問の森物理は河合塾シリーズの参考書であり、河合塾の長年のノウハウが詰まった良質な問題が収録されています。東京大学や京都大学などの旧帝大をはじめ、早稲田大学や慶應義塾大学といった難関私立大学の入試問題にも対応できる実践的な内容となっています。
名問の森物理のメリット
名問の森物理のメリットを解説します。
難関大学入試に対応できる実力が身につく
名問の森物理の最大のメリットは難関大学入試に対応できる実力が身につくことです。旧帝大や早慶といった最難関大学の入試問題を解くために必要な思考力や応用力を養成できます。
名問の森物理を8割以上解けるようになれば偏差値75レベルに到達できるため、入試本番で高得点を狙える実力が完成します。実際に名問の森物理を使って多くの受験生が東京大学や京都大学などの難関大学に合格しています。
解説が充実していて理解しやすい
名問の森物理ではPoint & HintとLECTUREという2段階の解説が用意されています。Point & Hintで問題の核心を素早く把握でき、LECTUREで詳しい解説を読むことで深い理解が得られます。
この解説の充実度により、名問の森物理では難しい問題でも自学自習で理解を深めることが可能です。独学で物理の実力を伸ばしたい受験生にとって非常に使いやすい構成になっています。
問題の質が高く入試で頻出の内容が学べる
名問の森物理に収録されている問題は河合塾が厳選した良質な問題ばかりです。入試で頻出の重要問題が網羅されているため、効率的に入試対策を進めることができます。
名問の森物理で学んだ解法や考え方は実際の入試問題でも応用できるものばかりで、無駄のない学習が可能です。限られた時間の中で効率よく物理の実力を伸ばしたい受験生にとって最適な教材といえるでしょう。
名問の森物理のデメリット
名問の森物理のデメリットを解説します。
基礎が固まっていないと取り組めない
名問の森物理の最大のデメリットは基礎が固まっていないと取り組めないことです。良問の風を習得レベル2まで仕上げていないと、名問の森物理の問題は難しすぎて挫折してしまう可能性が高いです。
物理の偏差値が60未満の受験生や物理の基礎知識が不十分な受験生は、まず教科書傍用問題集や良問の風で基礎を固めてから名問の森物理に取り組むべきでしょう。段階を踏んだ学習が重要になります。
1問あたりの所要時間が長い
名問の森物理では1問あたり平均30分かかるため、1周するだけでも相当な時間が必要になります。受験生の中には時間が足りなくて名問の森物理を最後まで終わらせられないケースもあります。
特に受験直前期に名問の森物理に取り組み始めると時間が足りなくなる可能性が高いです。名問の森物理は遅くとも受験の半年前には開始し、計画的に学習を進めていく必要があります。
次のレベルの市販教材が少ない
名問の森物理を完成させた後、さらに上のレベルを目指す場合に適した市販教材が少ないという点もデメリットです。東京大学や京都大学を目指す受験生の中には名問の森物理だけでは物足りないと感じる人もいるでしょう。
そのような受験生は物理重要問題集や各大学の過去問に進むことになりますが、名問の森物理と過去問の間を埋める教材が少ない状況です。塾や予備校のオリジナル教材を使える環境にない受験生は工夫が必要になります。
名問の森物理に関するよくある質問
名問の森物理に関するよくある質問を解説します。
- 名問の森物理はいつから始めるべきですか?
- 名問の森物理を始める時期は良問の風を習得レベル2まで仕上げてからが適切です。偏差値でいえば67.5近くに到達してから名問の森物理に取り組むべきでしょう。
時期としては遅くとも受験の半年前には名問の森物理を開始することをおすすめします。名問の森物理は全140問あり1問あたり平均30分かかるため、十分な時間を確保して計画的に学習を進める必要があります。
焦って早い段階で名問の森物理に取り組むよりも、良問の風をしっかり仕上げてから名問の森物理に入る方が結果的に効率的です。
- 名問の森物理と良問の風の違いは何ですか?
- 名問の森物理と良問の風の最も大きな違いは難易度です。良問の風は物理の基礎から標準レベルの問題を扱っているのに対し、名問の森物理は難関大学入試レベルの応用問題を扱っています。
良問の風で偏差値67.5レベルまで到達し、名問の森物理で偏差値75レベルを目指すという位置づけになっています。したがって学習の順序としては必ず良問の風を先に終わらせてから名問の森物理に取り組むべきです。
両者は同じ河合塾シリーズの参考書であり、良問の風から名問の森物理へとスムーズに接続できる構成になっています。
- 名問の森物理は共通テスト対策に使えますか?
- 名問の森物理は共通テスト対策としては難易度が高すぎるため、あまりおすすめできません。共通テストは基礎的な知識と標準的な問題を素早く正確に解く力が求められるため、名問の森物理よりも良問の風レベルの問題集の方が適しています。
共通テストのみで物理を使う受験生は、良問の風を終えた後に名問の森物理ではなく共通テストの過去問や予想問題集に取り組むべきでしょう。名問の森物理は二次試験で物理が必要な受験生向けの教材です。
ただし共通テストで満点近くを目指す受験生であれば、名問の森物理で応用力をつけることで共通テストの難しい問題にも対応できるようになります。
- 名問の森物理を終えた後は何をすればよいですか?
- 名問の森物理を終えた後は志望校の過去問演習に入ることをおすすめします。名問の森物理で偏差値75レベルの実力がついていれば、ほとんどの大学の入試問題に対応できるはずです。
東京大学や京都大学を志望する受験生の中には、名問の森物理の後に物理重要問題集に取り組む人もいます。ただし物理重要問題集は非常にボリュームがあるため、時間に余裕がある受験生のみが取り組むべきでしょう。
過去問演習では名問の森物理で学んだ解法や考え方を実際の入試問題でどう活用するかを意識しながら取り組むことが重要です。
- 名問の森物理は独学でも使えますか?
- 名問の森物理は独学でも十分使える参考書です。Point & HintとLECTUREという充実した解説があるため、わからない問題でも解説を読めば理解できる構成になっています。
ただし独学で名問の森物理に取り組む場合は、わからない問題があってもすぐに解説を見てよいというスタンスで進めることが重要です。難しい問題に長時間悩み続けるよりも、解説を読んで理解する方が効率的に学習を進められます。
また独学の場合は◯×マークをつけて復習すべき問題を明確にすることが特に重要になります。名問の森物理を計画的に進めることで、独学でも十分に難関大学合格レベルの実力をつけることができます。