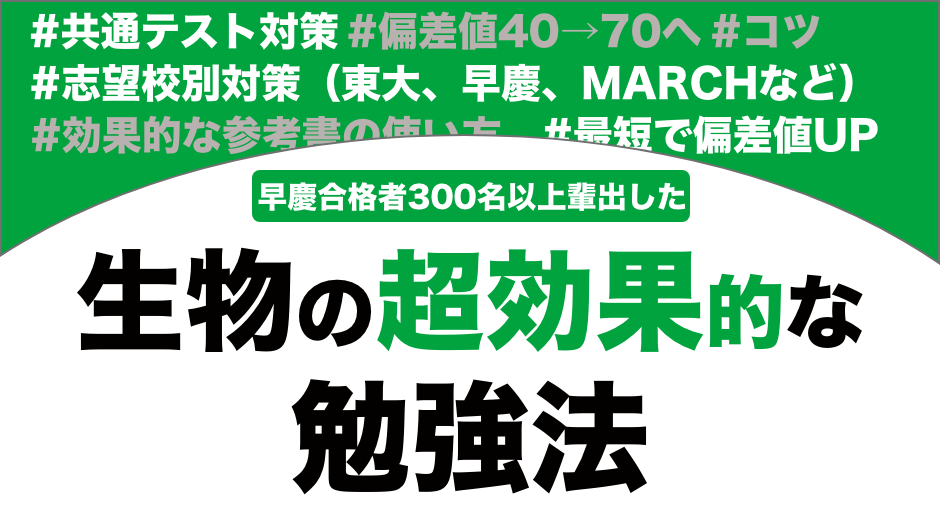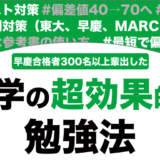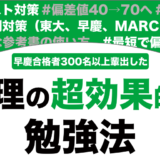本サイトの表記には、一部プロモーションを含みます
生物の大学受験対策におすすめの勉強法を完全解説します。
共通テストから東大・早稲田・慶應・MARCH志望まで志望校別対策、細胞・遺伝・代謝・進化・生態など分野別勉強法から実験考察問題対策の勉強法から定期テスト対策の勉強法やゼロから偏差値を伸ばす勉強法の順番まで網羅的に紹介します。

【この記事の監修者:逆転合格特化塾塾長「竹本明弘」
これまで逆転合格特化塾の塾長として早慶に現役生および浪人生を含めて合計で300人以上の合格者を輩出してきました。その中で共通テストの生物で9割以上を取った生徒もたくさんおり、実際に指導する中でゼロからでも生物の偏差値70まで到達した大学受験対策の生物の勉強法や使ってよかった参考書およびおすすめの生物の勉強の順番を解説したいと思います。
いきなり最終結論!ゼロから東大に受かる生物の勉強法を徹底解説!
結論として、生物の偏差値を6ヶ月で40から70にする勉強法としては以下のようになります。
→学校の授業をよく聞いていたという人は大森徹の最強講義126選を最初から講義本として使っても良いですが、それでない人は高校これでわかる生物・生物基礎の2冊を講義本としてスタートしましょう。
- 生物は学校の授業を聞いていて、これまで知識が溜まっている人と溜まっていない人で大きくスタートラインが変わってきます。そのため、高校これでわかる生物や生物基礎を使い、問題集は高校これでわかる基礎問題集生物、生物基礎を使いながら基礎段階における知識の習得を進めていくことをおすすめします。
- 進学校に通っていたり、授業を聞いていた人は、受験本番まで大森徹の最強講義を徹底理解、暗記していく気持ちで講義本として選びつつ、問題集はリードlightノート生物・生物基礎を進めていきましょう。
→生物は基礎事項については漏れなく習得していった方が後々の伸びにつながってくるので、3ヶ月目も時間をかけて知識の重点補強を行いましょう。
- 生物が苦手という人は高校これでわかる生物・生物基礎の問題集が終わり次第、まだ時間があるという人は生物の必修整理ノートを使って基礎事項のおさらいとしての学習をし、基礎レベルの学習を完成させていきましょう。
- 進学校に通っていたり、授業を聞いていた人はリードlightノート生物が終わり次第、ここからは間違えた回数を増やしていき、自分がまだ理解していないような問題や分野をみつけていくことが重要です。理系標準問題集生物と生物の基礎問題精講を解き進めながら、間違った部分は大森徹の最強講義126で確認するというのを繰り返していきましょう。
→応用レベルの生物の問題演習を通して知識を使える知識に変えていく作業を繰り返し行う。講義本の活用が応用レベルの問題を解く鍵になる。
- ここからは「理系標準問題集」から「生物の基礎問題精講」を解き進めつつ、時間がある人は生物の良問問題集に取り掛かりつつも、間違えたら必ず表や図でも正しく理解できるように大森徹の最強講義126を使って知識を問題を解くときに使える知識にどんどん変えていきましょう。
→分野別の対策も進めていきつつ、解き方にフォーカスして得点力の向上をテーマに学習を進める。
- 弱点補強として、志望校の問題の傾向にもよりますが、良問問題集の生物は引き続き取り組みつつも大森徹の生物実験・考察問題の解法、大森徹の生物遺伝問題の解法、大森徹の生物計算・グラフ問題の解法の3冊を通して、解き方の強化をしていきましょう。問題集を通しての演習でも十分力はつきますが、この3冊に関しては集中的に早めに取り組んだほうが早く理解が進みます。
→過去問演習を通してなぜその答えになるのかを徹底的に追求しつつ、問題ごとに解き方を再現性を持って理解できるようにする。
- 生物は最後に大森徹の最強問題集172に取り組みつつ、過去問演習に入れるかどうかが早慶以上のレベルを目指す受験生においては重要な流れとなってきます。
- また、過去問演習においては講義本は大森徹の最強講義126をフル活用しながら、取り組みつつ、弱点補強として使った解法の参考書も使いながら、間違えた問題は解き方と知識の原理などの理解においてもなぜ間違えたのかをなぜこれが答えになるのかを必ず確認するようにしましょう。


共通テストで9割取れる生物の勉強法
共通テスト生物で9割以上を獲得するためには基礎知識の完璧な習得と実験考察問題への対応力が欠かせません。
まず基礎知識については教科書レベルの内容を漏れなく理解することが重要です。共通テストでは教科書に載っている図表やグラフの読み取りが頻出するため、ただ用語を暗記するだけでなく、なぜそうなるのかという原理まで理解する必要があります。
高校これでわかる生物や大森徹の最強講義126選などの講義系参考書を使い、図や表を見ながら知識を整理していくことが効果的です。
次に実験考察問題への対策として、過去問や予想問題集を使って問題形式に慣れることが大切です。
共通テストの生物は初見の実験データを提示され、そこから考察する力が問われます。このタイプの問題は基礎知識を応用する練習を重ねることで確実に得点できるようになります。
▽共通テスト対策におすすめの生物の勉強法はこちら
 共通テストの生物の超効率的な勉強法を徹底解説!
共通テストの生物の超効率的な勉強法を徹底解説! 実際にやってよかった短期間で生物の偏差値が伸びる勉強法3選
実際にやってよかった生物のおすすめの勉強法を解説します。
講義本と問題集を並行して進める勉強法
1つ目は講義本と問題集を並行して進める学習法です。生物は理解と定着を同時に進めることで学習効率が格段に上がります。講義本で学んだ内容をすぐに問題集で確認することで、知識が使える形で頭に残るようになります。
具体的には1つの単元を講義本で理解したら、その日のうちに対応する問題集の問題を解くというサイクルを繰り返すことが効果的です。
間違えた問題に印をつけて繰り返し復習する方法
2つ目の生物のやってよかった勉強法は間違えた問題に印をつけて繰り返し復習する方法です。
生物は一度解いただけでは定着しないことが多いため、間違えた問題には必ず印をつけ、後日もう一度解き直すことが重要です。
特に理系標準問題集や生物の基礎問題精講などの応用レベルの問題集では、2回目3回目と解くたびに新しい発見があります。間違えた回数が多い分野こそ自分の弱点であるため、そこを重点的に補強することで偏差値は確実に上がります。
図表を自分で描いて整理する学習法
生物は視覚的に理解することが非常に重要な科目です。
細胞の構造や代謝の流れ、遺伝の仕組みなどは自分の手で図を描くことで頭の中が整理され、試験本番でも正確に思い出せるようになります。特に苦手な分野については何度も図を描き直すことで確実に理解が深まります。
分野別におすすめの大学受験対策の生物の勉強法
分野別におすすめの大学受験対策の生物の勉強法を解説します。
生物の実験考察問題の大学受験対策におすすめの勉強法
実験考察問題は生物の入試で最も差がつく分野であり、対策次第で大きく得点を伸ばすことができます。
実験考察問題の基本は実験の目的と方法を正確に理解することです。
問題文で提示される実験がなぜ行われたのか、どのような仮説を検証しようとしているのかを読み取る力が求められます。そのためには日頃から教科書や資料集に載っている実験の意義を理解しながら学習することが大切です。また実験結果から何が言えるのかを論理的に考える訓練も必要です。
具体的な対策としては大森徹の生物実験・考察問題の解法などの専門書を使い、様々なタイプの実験考察問題に触れることが効果的です。この手の参考書では実験の組み立て方や結果の読み取り方が体系的に解説されており、考察問題の解き方のコツを身につけることができます。また過去問演習を通して、志望校で頻出の実験パターンを把握しておくことも重要です。
さらに実験考察問題では対照実験の理解が欠かせません。なぜ対照実験が必要なのか、どの条件を変えてどの条件を揃えるのかを正確に判断できるようになることで、初見の実験問題にも対応できる力がつきます。日々の学習の中で実験の設計について意識的に考える習慣をつけることをおすすめします。
生物の記述・論述問題の大学受験対策におすすめの勉強法
記述・論述問題は国公立大学の二次試験で頻出であり、確実な対策が必要です。
記述問題で高得点を取るためには正確な知識と論理的な文章構成力の両方が求められます。まず用語の正確な理解が基本となります。例えば能動輸送と受動輸送の違いや、転写と翻訳のプロセスなど、似た用語を混同せずに使い分けられるようになることが重要です。そのためには講義本を繰り返し読み込み、用語の定義を正確に覚えることが第一歩となります。
次に論理的な文章を書く練習が必要です。生物の論述問題では単に知識を羅列するのではなく、因果関係を明確にして説明することが求められます。なぜそうなるのかという理由を常に意識しながら文章を組み立てる練習をすることで、採点者に伝わる解答が書けるようになります。また字数制限がある場合は、要点を絞って簡潔に書く力も必要です。
実践的な対策としては過去問の模範解答を分析することが効果的です。どのような構成で書かれているか、どの知識が使われているかを研究し、それを真似て自分でも書いてみることで文章力が向上します。
大学受験対策のノートを使った生物の勉強法
大学受験対策の生物の勉強でノートを使う最大のメリットは、複雑な生命現象を図や表で整理しながら理解できる点にあります。教科書や参考書を読むだけでは頭に入りにくい細胞分裂の過程や遺伝の仕組みも、自分の手でノートに書き写すことで記憶に残りやすくなります。
特に生物は暗記科目と思われがちですが、実際には理解が必要な科目であるため、ノートに自分なりの言葉で説明を加えることが重要です。
具体的なノート作成方法としては、まず講義本や授業で学んだ内容を左ページにまとめ、右ページには問題集で間違えた箇所や補足説明を書き込む方法が効果的です。
また、生物用語は必ず定義と一緒に書き、関連する用語同士を矢印で結ぶことで、知識のつながりが見えやすくなります。
さらに、ノートにまとめる際には色分けを工夫することも大切です。
例えば、重要な生物用語は青色、間違えやすいポイントは赤色、補足説明は緑色といった具合に色を使い分けることで、復習時に視覚的に情報を整理できます。
ただし、色を使いすぎるとかえって見づらくなるため、3色から4色程度に抑えることをおすすめします。ノートは作ることが目的ではなく、理解と記憶のための道具であることを忘れないでください。
志望校別におすすめの大学受験の生物の勉強法
志望校別におすすめの大学受験の生物の勉強法を解説します。
東大志望の大学受験生におすすめの生物の勉強法
東大の生物で求められるのは、初見の実験データから論理的に結論を導く考察力です。過去には実際の論文から引用した実験結果が出題され、受験生がその場で実験の目的や結果の意味を考える問題が出されています。
単なる用語暗記では対応できず、生命現象のメカニズムを分子レベルや細胞レベルで説明できる力が必須となります。東大が受験生の思考力を最も重視しているからこそ、毎年必ず実験考察問題が出題されるのです。
学習の流れとしては、まず高校これでわかる生物により基礎を固め、その後すぐに大森徹の最強講義126選へ移行します。この参考書は生命現象の背景にある化学的な仕組みや進化的な意義まで解説されており、東大レベルの深い理解を得るために最適です。
基礎固めができたら理系標準問題集生物と生物の基礎問題精講に取り組みますが、目標は正解を出すことではなく、なぜその答えになるのかを論理的に説明できるようになることです。
東大の生物は記述式が中心であり、論理の筋道が正しければ部分点も得られるため、常になぜそうなるのかを言語化する訓練が求められます。
応用段階では大森徹の生物実験考察問題の解法を重点的に学習し、対照実験の設定方法や実験結果から何が言えるかを考える力を養います。
慶應義塾大学志望の大学受験生におすすめの生物の勉強法
慶應の生物は日本の私立大学最高峰の難易度を誇り、教科書範囲を超えた発展的内容が平然と出題されます。
医学部では大学初年度レベルの生化学や分子生物学の知識が前提となり、理工学部では物理や化学の知識を使って生命現象を説明させる問題が頻出です。これは大学での学習に耐えうる基礎学力を入学時点で求めているためであり、表面的な理解では太刀打ちできません。
基礎段階から大森徹の最強講義126選を完璧にマスターすることを目標とし、並行して理系標準問題集生物と生物の基礎問題精講で正解率100パーセントを目指します。
慶應は選択式が中心で1問の配点が大きいため、1問のミスが合否を分けるからです。標準レベルの演習が固まったら、大森徹の生物遺伝問題の解法と計算グラフ問題の解法に集中的に取り組み、最も差がつく遺伝問題と計算問題を得点源に変えます。
仕上げとして生物の良問問題集や大森徹の最強問題集172で実戦力を磨き、過去問演習では巧妙に作られた各選択肢を一つ一つ丁寧に検証する力を養うことが合格には不可欠です。
定期テスト対策におすすめの生物の勉強法
定期テスト対策におすすめの生物の勉強法を解説します。
高校生におすすめの生物の定期テスト対策の勉強法
結論として、生物の定期テストで高得点を取るためには、2週間前からの計画的な学習が必要です。
まずテスト2週間前には範囲を完全に把握して、教科書の内容を理解することから始めます。この段階では暗記よりも、光合成や呼吸、遺伝などの生命現象がなぜ起こるのか、どのような順序で進むのかを理解することが大切です。理解が曖昧な部分は高校これでわかる生物や生物基礎を使って、原理からしっかり確認しましょう。
次に1週間前からは、理解した内容を実際に問題で使える知識に変えていく段階に入ります。学校のワークや問題集を解き、間違えた問題には必ず印をつけて、なぜ間違えたのかを分析します。この時期は毎日30分程度、前日に間違えた問題の復習から始めることで、確実に弱点を潰していくことができます。
テスト3日前になったら、これまでに間違えた問題を総復習して、資料集の重要な図を整理します。DNAの複製や光合成の仕組み、神経伝達の構造など、頻出の図は自分で描けるようになるまで練習することが高得点への近道です。
ノートに自分の手で実際に書き込む形で図と用語をセットで覚えることで、記憶が長期的に定着して、テスト本番でもスムーズに思い出せるようになります。
高校生の生物の定期テストの前日の一夜漬けにおすすめの勉強法
結論として、定期テスト前日の一夜漬けでは、新しい知識を詰め込むのではなく、これまでに学んだ内容を思い出すことに集中します。
前日は60分から90分程度の学習時間を確保して、間違えた問題、苦手な図、重要語句の3つに絞って復習を行います。最も効果的な方法は、声に出して説明する勉強法です。例えば有糸分裂の流れを説明してみる、DNAとRNAの違いを言ってみるといった形で、自分の口で言えるかを確認します。
説明できない部分があれば、すぐに参考書を開いて原理を見直してください。生物は理解を言語化できるかどうかが高得点の分かれ目になるため、単なる暗記ではなく説明できる状態を目指します。
最後に教科書の太字やまとめページを読み返して、全体の流れを整理しておきましょう。まとめノートを復習できるように作っておくとより効果的です。
学年別に高校生におすすめの生物の勉強法
学年別に高校生におすすめの生物の勉強法を解説します。
高校3年生におすすめの生物の勉強法
結論として、高校3年生は大学受験を見据えた応用力を養う勉強法が必要です。
この時期は定期テスト対策だけでなく、受験で使える知識を身につけることを意識します。講義本としては大森徹の最強講義126選を使い、原理から徹底的に理解を深めていきましょう。この参考書は受験生向けに作られており、複雑な生命現象も体系的に学べる内容になっています。
問題演習では理系標準問題集生物や生物の基礎問題精講を使って、応用レベルの問題に取り組みます。間違えた問題は必ず講義本に戻って、なぜその答えになるのかを確認することが重要です。また、遺伝や実験考察、グラフ問題など、苦手分野がある場合は大森徹の生物実験や考察問題の解法、遺伝問題の解法などの専門書を使って集中的に対策を行います。
定期テストの勉強と受験勉強を分けて考えるのではなく、定期テストの範囲を受験レベルまで深く理解することで、両方の対策を同時に進めることができます。
高校2年生におすすめの生物の勉強法
結論として、高校2年生は基礎知識を確実に定着させながら、応用問題にも取り組み始める時期です。
この学年では、生物基礎から生物への移行期にあたるため、基礎事項に漏れがないかを確認することが最優先です。高校これでわかる生物や生物基礎を使って、曖昧な部分を残さないように学習を進めます。授業をしっかり聞いている人は、大森徹の最強講義126選を使い始めても良い時期です。
問題演習ではリードlightノート生物や生物基礎を使って、定期テスト範囲の問題を繰り返し解きます。間違えた問題は必ず印をつけて、何度も復習することで確実に知識を定着させます。また、生物の必修整理ノートを使って、図と用語を関連づけながら覚えることも効果的です。
高校1年生におすすめの生物の勉強法
結論として、高校1年生は生物基礎を完璧にマスターすることに集中します。
高校に入学したばかりの1年生にとって、生物は暗記科目だと思われがちですが、実際には理解が必要な科目です。教科書を読むだけでなく、細胞の構造や酵素の働き、遺伝子の仕組みなど、なぜそうなるのかを理解しながら学習を進めます。高校これでわかる生物基礎は、初学者でも理解しやすい解説が特徴なので、授業の予習復習に最適です。
定期テスト対策としては、まず授業ノートと教科書を照らし合わせて、重要なポイントを整理します。その後、学校のワークや問題集を使って実際に問題を解いてみましょう。
まとめ
今回は生物の大学受験対策におすすめの勉強法を解説しました。生物の勉強法についてのまとめは以下のようになります。
| ▽おすすめの生物の参考書の使い方やレベルが知りたい方はこちら |
| 生物の良問問題集の使い方とレベル【参考書解説】 |
| セミナー生物の使い方とレベル【参考書解説】 |
| 生物の大森徹の最強問題集159問の使い方とレベル【参考書解説】 |
| ▽生物のおすすめの勉強法はこちら |
| 共通テストの生物のおすすめの勉強法 |
| 定期テスト対策におすすめの生物の勉強法 |
| 【大学受験】生物の超効率的な勉強法を徹底解説! |
| 大学受験向け生物のおすすめの勉強法 |
| ▽生物のおすすめの参考書はこちら |
| 【大学受験】生物基礎のおすすめの参考書ランキング10選を紹介!共通テストから定期テスト対策まで |
| 生物のおすすめの参考書ランキング |