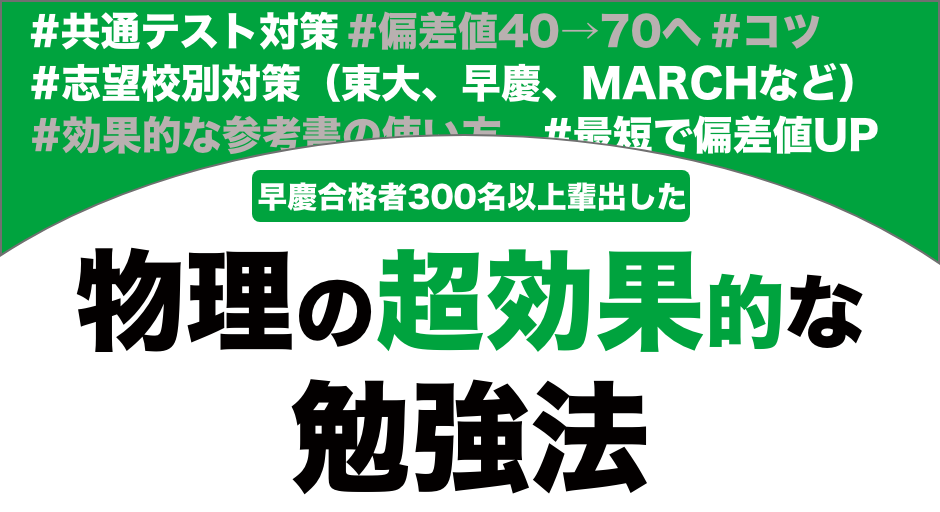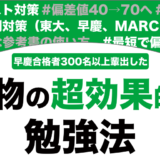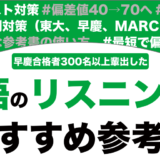本サイトの表記には、一部プロモーションを含みます
物理の大学受験対策に勉強法を解説します。物理の共通テスト対策向けの勉強法から東大・早稲田・慶應・MARCH志望まで志望校別対策、力学・電磁気・熱力学・波動・原子など分野別勉強法、公式活用・問題演習対策、定期テスト対策、ゼロから偏差値を伸ばす勉強法の順番まで紹介します。

【この記事の監修者:逆転合格特化塾塾長「竹本明弘」
これまで逆転合格特化塾の塾長として早慶に現役生および浪人生を含めて合計で300人以上の合格者を輩出してきました。その中で共通テストの物理で9割以上を取った生徒もたくさんおり、実際に指導する中でゼロからでも物理の偏差値70まで到達した大学受験対策の物理の勉強法や使ってよかった参考書およびおすすめの物理の勉強の順番を解説したいと思います。
いきなり最終結論!ゼロから東大に受かる物理の勉強法を徹底解説!
結論として、物理の偏差値を6ヶ月で40から70にする勉強法としては以下のようになります。
→学校の授業を聞いていたか聞いていなかったかによって大きく異なるが、無理やり難易度の高い参考書から始めないことが重要。
- 物理は学校の授業をほとんど聞いていなかったという人にはわからない分野は映像授業などで確認することをおすすめします。try itやスタディサプリなどを使いつつ、わからない分野を理解していくもしくは物理のインプット講義という映像授業もセットになった物理の講義本を使い、理解を進めつつ、理解しやすい物理+物理基礎という問題集形式の参考書を解き進めていくことをおすすめします。
- 進学校に通っていたり、学校の授業をしっかりと聞いていたという人は物理のエッセンスを解きながら、わからない分野は漆原の物理基礎・物理が面白いほどわかる本を使って確認していくことをおすすめします。(正直このやり方の方がスピードは圧倒的に早いですが、難易度が上がれば上がるほどいちいち基礎分野を確認する時間はもったいないので、高校のレベルがそこまで高くない限りは時間がかかっても物理は映像授業と並行して取り組むことをおすすめします。
→良問の風を解き進めつつ、わからない分野は漆原で確認する連続ループ。
- 物理は基礎段階での知識習得はもちろん重要ですが、何よりも大事なのは解法のレパートリーを増やしていくことが重要です。この問題の時はこういった解き方で答えるというように進学校以外の人は「理解しやすい物理+物理基礎」+「良問の風」を使いながら、例えば力学の「理解しやすい物理+物理基礎」が終わったら、「良問の風」の力学の範囲をやるというようにして、力学における解法のレパートリーをどんどん増やしていきましょう。
- 進学校に通っている人は「物理のエッセンス」をやりつつ、「良問の風」を解いていくことをおすすめします。
- また補足ですが、物理には微分積分の知識が必要にもなってくるので、数学の学習計画との兼ね合いも大事です。
→物理の応用レベル段階として名門の森およびベストセレクト物理を進めていく。(早慶以上を目指す人はベストセレクト物理は必要なし)
- 共通テストしか物理を使わないという人はこの段階で共通テストの物理の過去問集に入っていきましょう。結局共通テスト物理は特にですが、自分がどこで間違えやすいのかを分野およびどういう計算があるときなどで把握して、そこの苦手を講義本も含めて克服できるかが重要です。
- 難関大志望の受験生は良問の風が終わり次第名門の森に入っていきましょう。ここからは解法のレパートリーを増やしていくというよりはどの問題に対してどの解法を使うべきかなどの問題の分析力を高めることも重要になってきます。
→継続して名門の森を解き進めつつ、苦手な分野は良問の風に戻りながら復習を進める。名門の森が終わり次第、東大京大志望は物理重要問題集に入っていく。
- 早慶以上を志望する受験生は公式暗記や典型問題のパターンとして解法を覚えていても解けない問題がどんどん出てくるので、難問に出会うごとにどうしたらその解き方が思いつくか?や答えを出すまでの今まで覚えていきた解法の組み合わせ方を徹底的に分析しましょう。
- その積み重ねを名門の森から物理重要問題集から東大の物理の過去問まで連続して取り組めるかどうかが非常に重要です。過去問には11月には入れるようにそれまでに参考書はしっかりと終わらせられるようにしましょう。


大学受験の共通テストで9割取れる物理の勉強法
結論から述べると、共通テスト物理で9割を取るための勉強法は、基礎理解1ヶ月、基礎問題演習1ヶ月、共通テスト形式対応2ヶ月、過去問演習と最終調整1ヶ月の計5ヶ月で達成できます。
最初の1ヶ月は物理現象の原理理解に集中します。
漆原晃の物理基礎・物理が面白いほどわかる本または宇宙一わかりやすい高校物理を使い、力学から順番に各分野の基礎を学びます。1日90分の学習時間のうち60分を講義本の読み込みに使い、残り30分でリードLightノート物理基礎・物理の基本問題を解いて知識を定着させます。公式を暗記するのではなく、なぜその公式が成り立つのかという原理を理解することが共通テスト物理の高得点につながります。
2ヶ月目は物理のエッセンスを使った基礎問題演習に取り組みます。力学・波動編と熱・電磁気・原子編を1日90分かけて解き進め、解けなかった問題は必ず講義本に戻って原理から理解し直します。運動方程式の立て方やエネルギー保存則の使い方といった頻出パターンをこの時期に完璧にすることで、共通テスト物理の得点が安定します。
3ヶ月目から4ヶ月目は共通テスト形式の実戦演習期間です。共通テスト総合問題集物理や短期攻略共通テスト物理基礎・物理を使い、1日60分で大問2つ分を本番形式で解きます。共通テスト物理ではグラフやデータの読み取り、実験考察問題の分析力が得点差を生むため、この時期に多様な問題形式に慣れることが重要です。間違えた問題は物理のエッセンスに戻って類題で補強し、知識を確実に定着させます。
最後の1ヶ月は過去問演習と最終調整です。共通テスト過去問研究物理基礎・物理や共通テスト過去問レビュー物理基礎・物理を使い、最低10回分以上の過去問を本番と同じ条件で解きます。解説を丁寧に読み込み、なぜその選択肢が正解なのか、他の選択肢がなぜ誤りなのかを言語化できるようにすることで、初見の問題でも高得点が取れる力が身につきます。
▽物理の共通テスト対策におすすめの勉強法はこちら
 共通テストの物理の超効果的な勉強法を解説!
共通テストの物理の超効果的な勉強法を解説! 実際にやってよかった短期間で物理の偏差値が伸びる勉強法3選
実際にやってよかったおすすめの物理の勉強法を解説します。
基礎理解と原理の言語化トレーニング
結論から述べると、物理の偏差値を短期間で伸ばすための第一の勉強法は、公式の暗記ではなく物理現象の原理を自分の言葉で説明できるようにすることです。
漆原晃の物理基礎・物理が面白いほどわかる本や宇宙一わかりやすい高校物理を使い、力学から順に各分野の基礎を学びます。1日60分は講義形式の参考書で理論を学び、残り30分でリードLightノート物理基礎・物理の問題を解いて知識の定着を図ります。なぜこの公式を使うのか、どんな原理で導かれるのかを常に意識しながら学ぶことで、応用問題にも対応できる本質的な理解が身につきます。
2ヶ月目は物理のエッセンスを中心に全範囲の基礎問題を完成させます。この解法を使う理由や公式の導出過程、他のアプローチとの違いをノートにまとめ、自分の言葉で再現できるようにすることが偏差値アップの鍵です。丸暗記型の学習では限界があるため、理解の深さと再現力を両立させることが短期間で成績を伸ばすための最重要ポイントです。
解法パターンの習得と問題分析力の強化
結論から述べると、物理の偏差値を短期間で伸ばすための第二の勉強法は、解法のレパートリーを増やしながら問題の分析力を高めることです。
良問の風を使って標準レベルの問題演習に取り組みます。力学の運動方程式やエネルギー保存、波動の式や電磁誘導といった頻出分野を中心に演習し、この問題の時はこういった解き方で答えるという解法パターンを体に覚え込ませます。わからない分野は漆原の講義本に戻って確認する繰り返しが重要です。
理解しやすい物理プラス物理基礎と良問の風を組み合わせ、例えば力学の基礎が終わったら良問の風の力学範囲に入るというように進めることで、各分野における解法のレパートリーを効率的に増やせます。解答を見て終わりではなく、なぜその方法を使うのかを自分の言葉で説明できるようにすることで、初見問題にも対応できる応用力が身につきます。
過去問演習と弱点分析の徹底
結論から述べると、物理の偏差値を短期間で伸ばすための第三の勉強法は、過去問演習を通じて自分の弱点を徹底的に分析し潰していくことです。
名門の森やベストセレクト物理で応用レベルの問題に取り組みながら、どの問題に対してどの解法を使うべきかという問題の分析力を高めます。早慶以上を志望する受験生は公式暗記や典型問題のパターンだけでは解けない難問に出会うため、どうしたらその解き方が思いつくか、答えを出すまでの解法の組み合わせ方を徹底的に分析します。
共通テストのみ使用する人はこの段階で共通テスト物理の過去問集に入り、自分がどこで間違えやすいのかを分野ごとに把握します。難関大志望の受験生は名門の森が終わり次第、東大京大志望なら物理重要問題集に進みます。過去問には11月から入れるよう、それまでに参考書をしっかり終わらせることが短期間で偏差値を最大限伸ばすための重要な戦略です。
分野別におすすめの大学受験対策の物理の勉強法
分野別におすすめの大学受験対策の物理の勉強法を解説します。
力学の大学受験対策におすすめの勉強法
結論から述べると、力学で高得点を取るための勉強法は、力のつり合いとエネルギー保存則を完璧に理解し、運動方程式の立て方を身につけることです。
力学は物理の中で最も配点が高く、他分野の土台にもなる重要な分野です。まず漆原晃の物理基礎・物理が面白いほどわかる本を使い、力の合成と分解、作用反作用の法則、運動の三法則といった基本概念を理解します。公式を暗記するのではなく、なぜその式が成り立つのかを図を描きながら理解することが重要です。
物理のエッセンスの力学・波動編で基礎問題を解きながら、力のつり合いの式やエネルギー保存則の使い分けを練習します。特に斜面上の物体、ばねを含む運動、円運動、単振動といった頻出テーマは繰り返し演習して解法パターンを完璧にします。良問の風に進んだら、複合問題でどの法則を適用すべきかを判断する力を養います。
難関大学を目指す人は名門の森で応用力を鍛えます。力学では複数の物体が絡む問題や、条件が複雑な問題が出題されるため、問題文から正確に運動方程式を立てる練習が不可欠です。また数学の微分積分の知識が必要になる問題もあるため、数学の学習計画との兼ね合いも考えながら進めることが効率的な勉強法です。
波動の大学受験対策におすすめの勉強法
結論から述べると、波動で高得点を取るための勉強法は、波の式を完璧に理解し、干渉と定常波の図を正確に描けるようにすることです。
波動は視覚的な理解が重要な分野です。宇宙一わかりやすい高校物理や漆原晃の講義本を使い、波の基本式や重ね合わせの原理、反射と屈折の法則を学びます。波の式における位相のずれや経路差の概念は、図を描きながら理解することで定着しやすくなります。
物理のエッセンスで基本問題を解く際は、波の干渉、定常波、音波のドップラー効果、光の干渉といった頻出テーマを重点的に練習します。特にヤングの実験やくさび形空気層、回折格子といった干渉問題は共通テストでも頻出なので、グラフと図を使って視覚的に理解することが重要です。リードLightノートで簡単な計算問題を繰り返すことで、波長や振動数の関係式を確実に使えるようにします。
良問の風以降は、複数の波が重なる複合問題や、音波と光波の両方が絡む問題に取り組みます。波動では公式の丸暗記ではなく、波の伝わり方や重なり方を図で表現できることが高得点の鍵です。
名門の森では応用的な干渉問題や、条件が複雑な定常波の問題にも対応できる力を養います。
電磁気学の大学受験対策におすすめの勉強法
結論から述べると、電磁気学で高得点を取るための勉強法は、電場と磁場の違いを明確に理解し、電磁誘導の仕組みを図で説明できるようにすることです。
電磁気学は力学と並んで配点が高く、難関大学では複雑な回路問題や電磁誘導の問題が頻出します。まず漆原晃の物理基礎・物理が面白いほどわかる本で、クーロンの法則、電場と電位、コンデンサー、オームの法則、キルヒホッフの法則といった基本概念を理解します。電場と磁場は混同しやすいため、それぞれの性質と公式を整理しながら学ぶことが重要です。
物理のエッセンスの熱・電磁気・原子編で基礎問題を解きながら、直流回路の計算、コンデンサーの合成、電流が作る磁場、電磁誘導の法則を練習します。特に電磁誘導は共通テストでも二次試験でも頻出なので、フレミングの法則やレンツの法則を使って磁場の向きや誘導起電力の向きを正確に判断できるようにします。
良問の風以降は、複雑な回路問題や交流回路、電磁波の問題に取り組みます。難関大学では複数のコンデンサーや抵抗が絡む回路や、導体棒が磁場中を運動する電磁誘導の問題が出題されるため、図を描いて状況を整理する習慣をつけることが高得点への近道です。名門の森では応用的な電磁誘導問題や、微分積分を使った解法にも対応できる力を完成させます。
大学受験対策のノートを使った物理の勉強法
物理のノート活用法として最も効果的なのは公式の導出過程を自分の言葉でまとめることです。
物理は単に公式を暗記するだけでは応用問題に対応できません。なぜその公式が成り立つのか、どのような条件下で使えるのかをノートに詳しく書き込むことで理解が深まります。
例えば運動方程式から単振動の式を導く過程や、エネルギー保存則が成り立つ条件などを自分の手で書いて確認することが重要です。
また問題演習で間違えた箇所をノートに記録することも効果的な勉強法です。
間違えた問題はなぜ間違えたのか、どの公式を使うべきだったのか、どこで考え方を誤ったのかを詳しく分析してノートに残します。
この作業を繰り返すことで自分の弱点パターンが見えてきて、同じミスを防ぐことができます。
さらにノートには図やグラフを積極的に描くことをおすすめします。
志望校別におすすめの大学受験の物理の勉強法
志望校別におすすめの大学受験の物理の勉強法を解説します。
東大志望の大学受験生におすすめの物理の勉強法
東大物理で高得点を狙うには典型問題の瞬殺と公式の適用条件の深い理解が必須です。
東大物理は配点60点で試験時間は75分前後となっており、大問1は力学、大問2は電磁気学、大問3は波動か熱力学という出題傾向が毎年ほぼ固定されています。
問題文が長く状況把握に時間がかかる上に、標準レベルからやや難レベルの問題が大量に出題されるため、時間内にすべて解くことは非常に困難です。
そのため各大問の前半部分を確実に正解することが合格への近道となります。
具体的な勉強法としては物理のエッセンスで基礎を固めた後、良問の風で典型パターンを習得し、名問の森で応用力を養うという流れが効果的です。
さらに余裕があれば難問題の系統とその解き方に取り組むことで東大レベルの複雑な設定にも対応できる力が身につきます。
力学では単振動と円運動が頻出であり、運動方程式から導出できる力を養うことが重要です。
電磁気では電磁誘導と直流回路が多く出題されるため、磁場と絡めた問題のパターン演習が必須となります。
過去問演習は11月には開始できるよう計画的に参考書を進めることが合格のポイントです。
慶應義塾大学志望の大学受験生におすすめの物理の勉強法
慶應義塾大学の物理は学部によって出題傾向が異なるため志望学部に合わせた対策が必要です。
特に医学部では原子分野からの出題が比較的多いため、この分野の対策を怠らないことが重要となります。
理工学部では標準的な問題から応用問題まで幅広く出題されるため、基礎から応用まで段階的に学習を進める必要があります。
勉強法としては物理のエッセンスで基礎を固めた後、良問の風で標準レベルの問題に慣れることから始めます。
その後、名問の森や物理重要問題集で応用力を養い、過去問演習で慶應特有の出題形式に慣れることが合格への道筋です。
慶應の物理は思考力と計算力の両方が求められるため、公式の丸暗記ではなく原理からの理解を心がける必要があります。
また試験時間に対して問題量が多いため、解くべき問題を見極める判断力も重要です。
難問に時間をかけすぎず、標準問題を確実に得点する戦略が効果的となります。
過去問は10月から始めて、時間配分や問題を解く順番を意識した演習を重ねることをおすすめします。
早稲田大学志望の大学受験生におすすめの物理の勉強法
早稲田大学理工学部の物理は典型的な設定で発展的な内容を問う問題が多く出題されます。
試験時間は理科2科目で120分、物理は大問3題で構成され、第1問はマーク形式、第2問と第3問は記述形式です。
力学では相対運動と単振動に関する問題が頻出であり、これらの考え方を深く理解することが高得点への鍵となります。
電磁気ではコンデンサーと磁場中を運動する導体棒が頻出テーマですが、基礎的な考え方を発展させて解く応用問題が出題されます。
勉強法としては教科書内容をしっかり理解した上で、物理のエッセンスや入門問題精講で基礎を固めることから始めます。
次に良問の風や基礎問題精講で典型問題の解法をインプットし、短時間で解けるようになるまで繰り返し演習します。
その後、名問の森や実戦物理重要問題集で応用力を養い、早稲田レベルの問題に対応できる力をつけます。
現役生は遅くとも夏休みには応用問題に取り組み始めることが重要です。
過去問演習では時間を意識して解くこと、解ける問題から先に解くこと、問題文を適切に解釈して既知の解法に当てはめることの3点を意識しましょう。
▽物理のおすすめの参考書はこちら
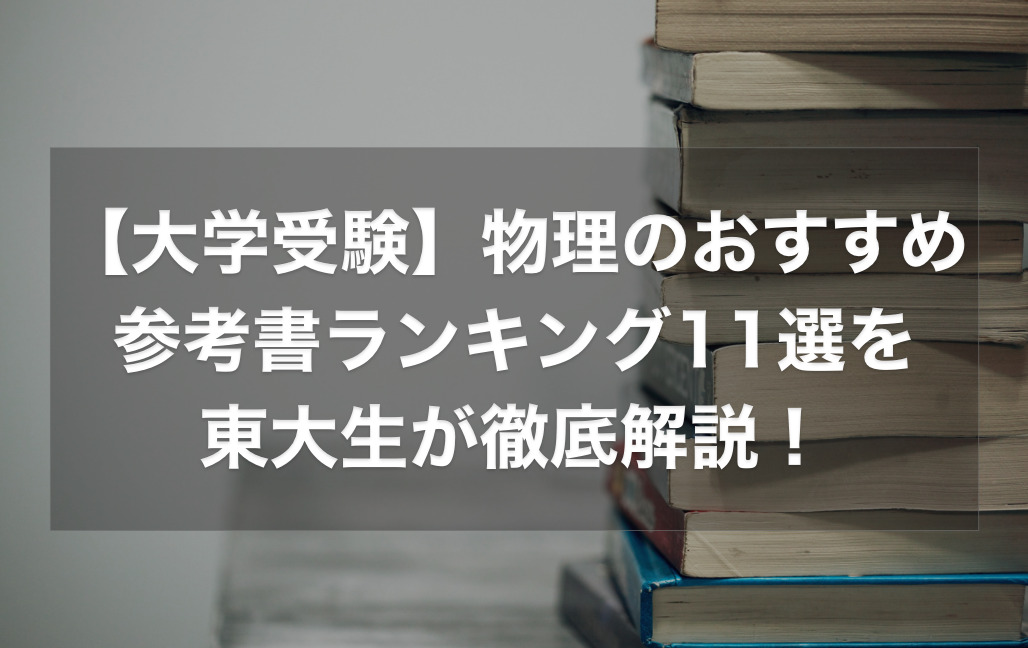 物理のおすすめの参考書ランキング17選を徹底解説!【大学受験】
物理のおすすめの参考書ランキング17選を徹底解説!【大学受験】 定期テスト対策におすすめの物理の勉強法
定期テスト対策におすすめの物理の勉強法を解説します。
高校生におすすめの物理の定期テスト対策の勉強法
物理の定期テストで高得点を取るには、公式の丸暗記だけでは不十分です。
現象を理解し、なぜその公式を使うのかを自分の言葉で説明できる力が必要になります。効率的な対策としては、まず教科書とノートで授業内容を整理し、公式の意味と使える条件を確認することから始めます。
理解が不十分な単元は、講義系の参考書を活用して基礎から学び直すことが大切です。宇宙一わかりやすい高校物理や橋元の物理をはじめからていねいになどの参考書は、図解が豊富で現象をイメージしやすくなります。
演習では教科書の例題や章末問題を中心に解き、間違えた問題はなぜ間違えたのかをノートに書き出して分析します。この時、解答を見る前に自分でどこまで考えられるかを試すことが重要です。
理解と演習を繰り返すことで、定期テストで応用問題が出ても対応できる実力が身につきます。目安として2週間前から計画的に取り組めば、9割以上の得点も十分に狙えます。
高校生の物理の定期テストの前日の一夜漬けにおすすめの勉強法
前日の一夜漬けでは、新しい問題に手を出さず復習に集中することが鉄則です。
まず授業ノートと自分がこれまでに解いた問題を見返し、重要公式と単位、よく間違える計算パターンを最終確認します。特に力学では力の向きと大きさ、電磁気では右手の法則や電流の向きなど、ミスしやすいポイントを重点的にチェックします。
不安な単元がある場合は、講義系参考書の該当ページを軽く読み直して現象のイメージを整理しましょう。全てを完璧にしようとせず、頻出問題と自分が苦手な分野に絞って取り組むことが時間の限られた前日では効果的です。
睡眠時間を削らず、最低でも6時間は確保することが大切です。徹夜で詰め込むより、しっかり寝た方が本番での集中力と思考力が高まります。
前日は基礎の確認と苦手分野の補強に徹し、新しい知識を入れようとしないことが一夜漬けの勉強法では最も重要なポイントです。
▽物理の定期テスト対策におすすめの勉強法はこちら
 定期テストの物理のおすすめの勉強法を徹底解説!
定期テストの物理のおすすめの勉強法を徹底解説! 学年別に高校生におすすめの物理の勉強法
学年別に高校生におすすめの物理の勉強法を解説します。
高校3年生におすすめの物理の勉強法
高校3年生は受験を見据えた実践力の養成が最優先になります。
この時期には基礎固めは終えておき、入試レベルの問題演習に取り組む必要があります。まず良問の風や名門の森といった標準から応用レベルの問題集で、幅広い出題パターンに触れることが大切です。
難関大学を目指す受験生は、どの問題にどの解法を適用するかという判断力を磨くことが求められます。単に公式を当てはめるのではなく、問題文から条件を正確に読み取り、複数の解法を組み合わせて答えを導く訓練が必要です。
高校2年生におすすめの物理の勉強法
高校2年生は基礎を固めつつ応用力を伸ばす重要な時期です。
この学年では物理の全範囲を学習することが多いため、各単元をしっかり理解しながら進めることが大切です。授業で習った内容はその日のうちに復習し、教科書の例題は必ず自力で解けるようにしましょう。
理解が不十分な単元は放置せず、すぐに講義系参考書や映像授業で補強します。漆原晃の物理基礎と物理が面白いほどわかる本は、詳しい解説で理解を深めるのに適しています。
演習では物理のエッセンスなどの標準的な問題集を使い、解法のパターンを身につけていきます。力学、電磁気、波動、熱力学の順に進め、各分野の基本問題が確実に解けるようになってから次に進むことが効果的です。
この時期に基礎を疎かにすると3年生で苦労するため、わからない問題があればすぐに先生や友達に質問し、理解の穴を作らないことが重要です。
高校1年生におすすめの物理の勉強法
高校1年生は物理の基礎を正しく理解することが最も大切です。
中学の理科とは異なり、高校物理では数学を使った論理的な思考が求められます。最初は公式の意味や使い方がわからず戸惑うかもしれませんが、焦らず一つ一つ丁寧に理解していくことが重要です。
授業では先生の説明をしっかり聞き、板書だけでなくなぜそうなるのかという説明も必ずノートに書き留めます。教科書の例題は授業後すぐに自分で解き直し、解けなかった問題は解説を読んで理解します。
この時期に宇宙一わかりやすい高校物理のような初学者向けの参考書を用意しておくと、授業で理解できなかった部分を自分で補うことができます。図やイラストが多い参考書は、現象をイメージする力を鍛えるのに役立ちます。
まとめ
大学受験対策の物理のおすすめの勉強法について解説しました。
物理の勉強法についてのまとめは以下のようになります。