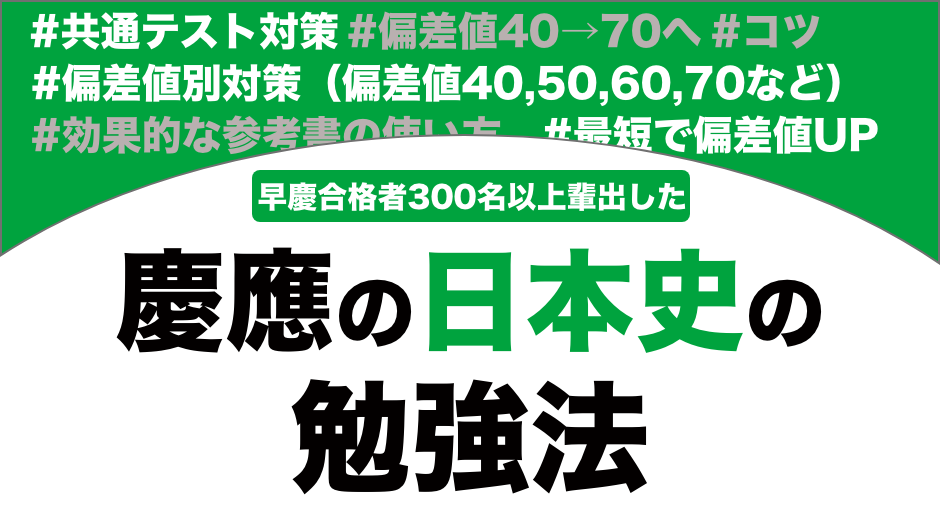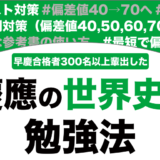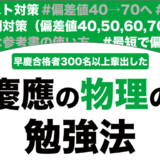本サイトの表記には、一部プロモーションを含みます
慶應義塾に合格できる効果的な日本史の勉強法を解説します。慶應義塾の日本史対策に実際にやってよかった勉強法とその順番も合わせて紹介します。また慶應義塾の日本史対策におすすめの参考書も合わせて紹介します。
いきなり最終結論!慶應義塾に合格するための日本史の勉強法の順番
実際にやって良かった慶應義塾大学に合格できる日本史の勉強法とその順番を解説します。
慶應義塾大学の日本史は学部によって難易度に差があるものの、いずれの学部も基礎知識の徹底が前提となります。この段階では年号と人物を軸に日本史全体の流れを理解することが最優先です。金谷の日本史なぜと流れがわかる本を1日30分で読める範囲を読み、大枠を掴みます。次に時代と流れで覚える日本史B用語を使って年号とタテの流れ、因果関係を意識しながら覚えていきます。最後に東進の日本史B一問一答を使って用語を星2、星3から確実に暗記していきます。
一問一答を使う際は金谷の講義本を読みながらタテの因果関係を理解することが重要です。単純な用語の暗記ではなく、その用語がどの時代のどのような文脈で登場するのかを意識して覚えていきます。慶應義塾大学の日本史では空所補充問題が多く出題されるため、この段階で基礎用語を漢字で正確に書けるようにしておく必要があります。1日の勉強時間は合計2時間30分を目安とし、講義本30分、時代と流れで覚える30分、一問一答60分、講義本での復習30分という配分で進めます。
この段階は最初の1ヶ月から2ヶ月をかけて徹底的に取り組みます。日本史の偏差値を一気に上げるための土台作りとなるため、焦らずに確実に基礎を固めることが大切です。特に慶應の商学部を志望する受験生は、この基礎レベルの問題で確実に得点する必要があるため、星2以上の用語は完璧に覚えている状態を目指します。
おすすめの参考書 金谷の日本史なぜと流れがわかる本シリーズ 時代と流れで覚える日本史B用語 東進日本史B一問一答
3ヶ月目のメインテーマは年号を一気に覚えていくことです。慶應義塾大学の経済学部では年代配列問題で月まで問われることがあり、法学部でも史料問題で時代の正確な把握が求められます。元祖日本史年代暗記法をフル活用して年号を徹底的に覚えていきます。1日45分を年代暗記法に充て、時間が取れる人は60分以上使うことが理想的です。
年号を覚える際は、ただ数字を暗記するのではなく、その出来事が起きた背景や前後の歴史の流れと結びつけて理解します。金谷の日本史なぜと流れがわかる本を1日45分読み、タテの因果関係を理解しながら年号を覚えていきます。東進の日本史B一問一答は1日30分継続し、星2以上の用語を何度も復習して完璧に覚えます。最後に講義本で30分復習する時間を設けて知識の定着を図ります。
この段階では特に政治史の流れを重点的に覚えていきます。慶應義塾大学では学部を問わず政治史の出題が多いため、各時代の政治体制や重要な改革、法令の内容を理解しておく必要があります。また慶應の法学部では法政史が頻出であるため、律令制度や江戸時代の法制度、明治以降の憲法や法律に関する知識を深めていきます。
おすすめの参考書 金谷の日本史なぜと流れがわかる本シリーズ 元祖日本史年代暗記法 東進日本史B一問一答
4ヶ月目からはアウトプット中心の学習に切り替えます。日本史は完璧に覚えたと思っていても実際には覚えていなかった知識がどんどん見つかる科目です。慶應義塾大学の法学部や文学部を志望する受験生は日本史基礎問題精講を使ってアウトプットしながら、自分のまだ覚えきれていない分野を1つ1つ洗い出していきます。商学部や経済学部を志望する受験生は共通テストへの道日本史を解いて、どの年代が苦手なのかを見つけていきます。
問題を解いて間違えた部分は金谷の日本史で該当する範囲を復習し、一問一答でも用語を暗記し直します。さらに文化史の学習も本格的に始めます。金谷の日本史文化史編を1日15分読み、該当する範囲を覚えていきます。慶應の文学部では文化史の出題が16%を占めるため、この段階でしっかりと対策しておく必要があります。1日の時間配分は講義本45分、問題集30分、一問一答30分、文化史15分、復習30分となります。
慶應義塾大学の入試では教科書レベルを超える知識も問われるため、この段階で用語集の活用を始めます。山川出版社の日本史B用語集を使い、問題で出会った知らない用語を調べて知識を補強していきます。特に法学部や文学部志望者は用語集を徹底的に活用することで、細かい知識問題にも対応できる力を身につけます。
おすすめの参考書 金谷の日本史なぜと流れがわかる本シリーズ 日本史基礎問題精講または共通テストへの道日本史 東進日本史B一問一答 金谷の日本史文化史編 山川出版社日本史B用語集
5ヶ月目は慶應義塾大学の日本史で差がつきやすい分野である文化史と史料問題に重点的に取り組みます。文学部志望者は攻略日本史テーマ・文化史を活用して文化史の知識を深めます。商学部や経済学部志望者は金谷の日本史文化史編を繰り返し読むことで対応できます。文化史を学習する際は、ただ作品名や作者を覚えるのではなく、その作品が生まれた時代背景や文化の特徴と結びつけて理解することが重要です。
史料問題の対策として日本史史料一問一答を使います。慶應義塾大学の入試では未見史料が出題されることも多いため、史料を読み解く力を養う必要があります。山川出版社の詳説日本史史料集を1冊繰り返し読み込み、解説も含めて理解します。史料集を徹底的に読み込むことで、初見の史料でも読解できる力を身につけることができます。1日30分を史料問題の対策に充てます。
用語暗記についても法学部や文学部志望者は東進の日本史B一問一答の星1もしっかりと覚えていきます。タテの流れを理解している段階だからこそ、重箱の隅をつつくような細かい用語も文脈の中で覚えることができます。1日の時間配分は講義本30分、一問一答30分、史料問題30分、文化史の学習と復習60分となります。
おすすめの参考書 金谷の日本史なぜと流れがわかる本シリーズ 東進日本史B一問一答 日本史史料一問一答 山川出版社詳説日本史史料集 攻略日本史テーマ・文化史 金谷の日本史文化史編
6ヶ月目は慶應義塾大学の日本史で特に重要となるテーマ史の対策を完成させます。経済史、文化史、労働史、外交史など分野別の歴史が頻出であるため、攻略日本史近・現代史を使ってテーマ別に知識を整理していきます。特に経済学部志望者は経済史の知識が合否を分けるため、土地制度史や財政史、貿易史などを体系的に理解する必要があります。
HISTORIAまたは実力をつける日本史100題を使って難易度の高い問題を解く回数を増やします。間違えた分野や年代については、資料集、用語集、講義本を活用して徹底的に復習していきます。慶應義塾大学の入試では現代史の出題も見られるため、戦後史についても丁寧に学習を進めます。ただし細かい知識にこだわりすぎると偏差値の伸び悩みにつながるため、過去問分析を通じて頻出分野を見極めることが大切です。
法学部志望者は語群が多いマーク式問題に慣れるため、過去問を繰り返し解いて時間短縮の方法を研究します。文学部志望者は100字論述の対策として、事象の背景や理由、意図まで説明できるように論述問題集で練習します。商学部志望者は基本問題を確実に得点するため、教科書レベルの知識を完璧にします。経済学部志望者は論述問題の対策を重点的に行い、教科書を読み込んで流れを人に説明できるレベルで理解します。
おすすめの参考書 HISTORIAまたは実力をつける日本史100題 攻略日本史近・現代史 山川出版社日本史B用語集 山川出版社詳説日本史史料集 金谷の日本史なぜと流れがわかる本シリーズ
難易度の高い問題集が終わり次第、志望大学の過去問に入っていきます。慶應義塾大学は学部ごとに出題傾向が大きく異なるため、志望学部の過去問を最低10年分は解く必要があります。過去問を解く際は本番と同じ時間配分で取り組み、自分の弱点を洗い出します。間違えた問題については資料集、用語集、講義本を活用して確認していきます。時間に余裕がある受験生は慶應義塾大学入試対策用日本史問題集を使って他学部の問題にも挑戦します。
法学部志望者は語群から正解を探すスピードを上げるため、同類事項をまとめておくなどの工夫をします。また一字一句を吟味する癖をつけて、ケアレスミスを防ぎます。商学部志望者は記述問題で漢字を正確に書けるように練習します。選択肢が一覧となっているため、周辺の情報から推測する力も養います。経済学部志望者は論述問題で教科書の表現を参考にしながら、簡潔で正確な文章を書く練習をします。文学部志望者は100字論述で因果関係を明確に説明できるように訓練します。
共通テストを受験する場合は、共通テストの過去問およびセンター試験の過去問も解いて、講義本と一問一答と年代暗記法での復習を中心に取り組みます。用語集の活用については、法学部や文学部志望者は全部覚えても良いと言えるほど効果的ですが、商学部や経済学部志望者は余計な知識も入ってきやすいため、過去問で出会った知らない用語を調べる使い方が推奨されます。最後まで基礎の徹底と弱点の補強を繰り返すことが、慶應義塾大学合格への確実な道となります。
おすすめの参考書 慶應義塾大学の過去問 慶應義塾大学入試対策用日本史問題集 山川出版社日本史B用語集 山川出版社詳説日本史史料集 共通テストの過去問およびセンター試験の過去問


慶應義塾の日本史の学部ごとの特徴と対策
慶應義塾大学の日本史は学部によって出題形式や傾向が大きく異なるため、志望学部に合わせた対策が必要です。
経済学部の日本史は論述問題が中心となっており、特に経済史や社会経済に関する内容が頻出します。200字から400字程度の論述が求められるため、タテの流れと因果関係を正確に理解し、それを自分の言葉で説明できる力が必要です。年号を軸にした時代の流れの把握が特に重要となります。
法学部の日本史はマークシート形式が中心で、細かい知識や史料問題が多く出題されます。用語の正確な理解と人物・年号の暗記が合格の鍵となります。特に政治史や外交史の出題が多いため、これらの分野を重点的に学習することが大切です。
文学部の日本史は記述式と論述式が混在しており、文化史の比重が非常に高いことが特徴です。文化史は他の受験生が対策不足になりやすい分野であるため、ここで差をつけることができます。また史料問題も頻出するため、史料集を活用した学習が効果的です。
商学部の日本史は論述問題が出題され、特に近現代史の出題が多い傾向にあります。明治以降の経済発展や産業の変化について詳しく学習しておく必要があります。商学部では統計資料を用いた問題も出題されるため、資料集を活用した学習が重要です。
慶應義塾の日本史対策に実際にやってよかった勉強法3選
慶應義塾大学の日本史で高得点を取るために効果的だった勉強法を3つ紹介します。
まず1つ目は金谷の日本史なぜと流れがわかる本と一問一答を往復する勉強法です。

この勉強法では1日30分を金谷の講義本に使い、タテの流れと因果関係を理解することに集中します。次に60分を東進の一問一答に使い、星2と星3の用語を徹底的に暗記していきます。最後に30分を使って金谷の講義本で復習を行います。
この勉強法の効果が高い理由は、理解と暗記を同時に進められる点にあります。金谷の講義本で流れを理解してから一問一答で用語を覚えることで、バラバラの知識ではなく体系的な知識として定着させることができます。特に慶應の日本史は単なる暗記では対応できない問題が多いため、この往復学習が非常に効果的です。
2つ目は元祖日本史年代暗記法を使った年号の徹底暗記です。1日45分以上を元祖日本史年代暗記法に使い、年号を語呂合わせで覚えていきます。年号を覚える際には必ず金谷の講義本でその出来事の背景と因果関係を確認し、一問一答で関連用語もあわせて暗記します。この3つの参考書を連動させることで知識が定着しやすくなります。
慶應の経済学部や商学部の論述問題では、複数の出来事を時系列で説明する必要があるため、年号を軸にした学習が合格の鍵となります。年号を覚えることでタテの流れが明確になり、論述問題でも自信を持って解答できるようになります。また法学部のマークシート問題でも年号の知識は非常に有効です。
3つ目は文化史と史料問題の重点対策です。1日30分を日本史史料一問一答に使い、30分を攻略日本史テーマ文化史に使います。間違えた部分は必ず金谷の文化史で確認し、資料集で実際の作品や史料を視覚的に確認します。この勉強法は特に慶應の文学部志望者には必須です。
文化史と史料問題は多くの受験生が対策不足になる分野であるため、ここで差をつけることができます。特に慶應の文学部では文化史の比重が高く、他の受験生がほとんど対策していない細かい文化史の知識が問われることもあります。また史料問題は初見の史料が出題されることもあるため、史料を読み解く力を養うことが重要です。
慶應義塾の日本史の勉強法の実践におすすめの参考書
慶應義塾大学の日本史対策に効果的な参考書を紹介します。
金谷の日本史なぜと流れがわかる本
金谷の日本史なぜと流れがわかる本は、日本史の流れを理解するための最適な参考書です。この参考書は因果関係を重視した構成になっており、なぜその出来事が起きたのかを丁寧に説明しています。1日30分で読める範囲を設定し、タテの流れを意識しながら読み進めることが大切です。慶應の論述問題対策としては、この参考書で流れを理解することが必須となります。
東進の一問一答は、日本史の用語を効率的に暗記できる参考書です。星1から星3までレベル分けされており、まずは星2と星3を完璧にすることを目指します。慶應の法学部志望者は星1まで完璧に覚える必要があります。
一問一答を使う際は、必ず金谷の講義本でタテの流れを理解してから使うことで、バラバラの知識ではなく体系的な知識として定着させることができます。
元祖日本史年代暗記法
元祖日本史年代暗記法は、年号を語呂合わせで効率的に覚えられる参考書です。慶應の経済学部や商学部の論述問題では年号を軸にした説明が求められるため、この参考書は必須です。1日45分以上を使って徹底的に暗記し、覚えた年号は必ず金谷の講義本で確認して流れと結びつけることが重要です。年号を覚えることでタテの流れが明確になります。
攻略日本史テーマ文化史
攻略日本史テーマ文化史は、慶應の文学部志望者には必須の参考書です。文化史をテーマ別に整理しており、効率的に学習できます。この参考書で間違えた部分は必ず金谷の文化史で確認し、資料集で実際の作品を視覚的に確認することが大切です。文化史は他の受験生が対策不足になりやすい分野であるため、ここで差をつけることができます。
日本史史料一問一答
日本史史料一問一答は、史料問題対策に最適な参考書です。慶應の入試では初見の史料が出題されることも多いため、多くの史料に触れて読解力を養う必要があります。この参考書を1日30分使い、史料の内容と時代背景を結びつけて理解することが重要です。資料集と併用することで、史料問題への対応力が大きく向上します。
まとめ
今回は、慶應義塾大学の日本史対策について学部ごとの特徴と効果的な勉強法を解説しました。
慶應義塾の日本史対策についてのまとめは以下のようになります。