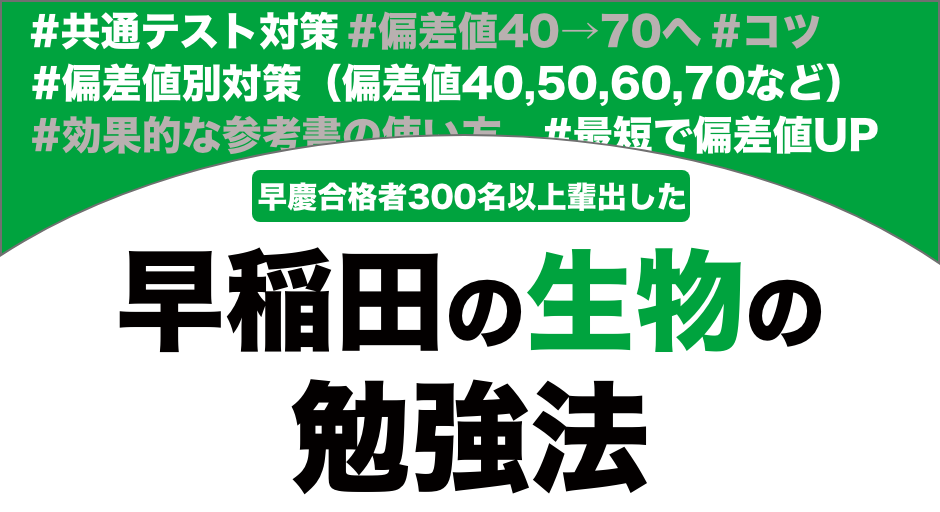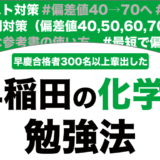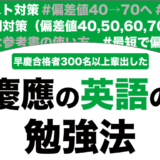本サイトの表記には、一部プロモーションを含みます
早稲田に合格できる効果的な生物の勉強法を解説します。早稲田の生物対策に実際にやってよかった勉強法とその順番も合わせて紹介します。また早稲田の生物対策におすすめの参考書も合わせて紹介します。
いきなり最終結論!早稲田に合格するための生物の勉強法の順番
実際にやって良かった早稲田に合格するための生物の勉強法の順番を解説します。
生物という科目は暗記が重要と思われがちですが、実際には理解と暗記を同時に進めることで効率的に成績を伸ばすことができます。この段階では、学校の授業をしっかり聞いていた人と、そうでない人でスタート地点が大きく異なるため、自分のレベルに合わせた参考書選びが最も重要です。授業を真面目に受けていなかった人は、まず高校これでわかる生物と生物基礎の2冊を使って、中学理科の復習も含めた基礎固めから始めましょう。
これらの参考書は図やイラストが豊富で、生物現象の仕組みを視覚的に理解できるように作られているため、初学者でもスムーズに学習を進められます。各単元を読んだら、必ず高校これでわかる基礎問題集生物と生物基礎を使って問題演習を行い、理解度を確認してください。もし間違えた問題があれば、すぐに講義本に戻って該当箇所を読み直し、なぜ間違えたのかを徹底的に分析することが大切です。
一方、進学校に通っていて授業をしっかり聞いていた人は、大森徹の最強講義126選を講義本として選び、リードライトノート生物と生物基礎を問題集として使いましょう。大森徹の最強講義は早稲田レベルの入試に対応できる詳しさがあり、この参考書を完璧に理解すれば、理工学部の記述問題にも対応できる力が身につきます。この段階では1日2時間の勉強時間を確保し、全範囲を一通り学習することを目標に進めてください。
使うべきおすすめの参考書:高校これでわかる生物、高校これでわかる生物基礎、高校これでわかる基礎問題集生物、高校これでわかる基礎問題集生物基礎、大森徹の最強講義126選、リードライトノート生物、リードライトノート生物基礎
2ヶ月目も引き続き基礎事項の習得に時間をかけます。生物は基礎段階での知識の漏れがあると、後の応用問題で大きく苦労することになるため、焦らず丁寧に学習を進めることが重要です。1ヶ月目に使った問題集が終わった人は、間違えた問題を中心に2周目に入り、なぜ間違えたのかを分析しながら復習を進めてください。
生物が苦手という人は、高校これでわかる生物と生物基礎の問題集が終わったら、まだ時間に余裕があれば生物の必修整理ノートを使って基礎事項のおさらいをしましょう。この参考書は穴埋め形式になっているため、重要用語の定着と知識の整理に最適です。書き込みながら学習することで、記憶に定着しやすくなり、基礎レベルの学習を完成させることができます。
進学校に通っていて授業を聞いていた人は、リードライトノート生物が終わり次第、理系標準問題集生物と生物の基礎問題精講に取り組み始めましょう。この段階から、間違えた問題には必ずチェックマークをつけ、自分がまだ理解していない分野を明確にしていくことが重要です。間違えた部分は必ず大森徹の最強講義126で該当箇所を確認し、表や図も含めて正しく理解できるまで繰り返し読み込んでください。
使うべきおすすめの参考書:生物の必修整理ノート、理系標準問題集生物、生物の基礎問題精講
3ヶ月目も基礎事項の漏れをなくすことに重点を置きます。早稲田大学の生物は標準レベルの問題が中心ですが、その分基礎知識の正確な理解と定着が合格の分かれ目となるため、この時期にしっかりと固めておくことが後々の伸びにつながります。特に理工学部を志望する人は、遺伝情報、細胞、生殖発生の分野を重点的に学習し、記述式で説明できるレベルまで理解を深めておきましょう。
生物が苦手という人は、生物の必修整理ノートを使って基礎事項の総復習を行い、まだ理解が不十分な単元があれば高校これでわかる生物と生物基礎に戻って学び直してください。この段階で基礎レベルの問題集を完璧にしておくことが、次の応用レベルへの橋渡しとなります。基礎問題で間違えた箇所は、なぜ間違えたのかを必ずノートにまとめ、自分だけの弱点ノートを作成することをおすすめします。
進学校に通っていて授業を聞いていた人は、理系標準問題集生物と生物の基礎問題精講を解き進めながら、間違えた回数を記録していきましょう。3回以上間違えた問題は特に注意が必要な分野なので、大森徹の最強講義126を使って該当箇所を徹底的に読み込み、理解できるまで繰り返し復習してください。この時期から講義本を辞書的に使う習慣をつけることで、知識を体系的に整理できるようになります。
使うべきおすすめの参考書:生物の必修整理ノート、理系標準問題集生物、生物の基礎問題精講、大森徹の最強講義126選
4ヶ月目からは応用レベルの問題演習を通して、知識を使える知識に変えていく作業を繰り返し行います。早稲田大学の生物は標準レベルが中心ですが、複数の知識を組み合わせて解く問題や、初見の実験考察問題が出題されるため、単なる暗記では対応できません。講義本を活用して、なぜそうなるのかという原理を理解しながら問題を解くことが、応用レベルの問題を解く鍵となります。
全員が理系標準問題集生物と生物の基礎問題精講を解き進めつつ、時間がある人は生物の良問問題集にも取り掛かりましょう。これらの問題集は早稲田レベルの入試問題を意識した構成になっているため、実戦的な力を養うことができます。間違えた問題は必ず大森徹の最強講義126を使って、表や図も含めて正しく理解できるように復習してください。
特に理工学部を志望する人は、記述問題や論述問題に対応できるよう、答えを見る前に自分の言葉で説明する練習を始めましょう。人間科学部を志望する人は、グラフや図表を読み取る問題に慣れるため、データ分析型の問題を重点的に解くことをおすすめします。教育学部を志望する人は、実験考察問題に力を入れ、問題文から必要な情報を読み取って論理的に考える訓練を始めてください。
使うべきおすすめの参考書:理系標準問題集生物、生物の基礎問題精講、生物の良問問題集、大森徹の最強講義126選
5ヶ月目は分野別の対策を進めつつ、解き方にフォーカスして得点力の向上をテーマに学習を進めます。早稲田大学の生物では、遺伝問題、実験考察問題、計算グラフ問題など、特定の分野で差がつきやすい問題が出題されるため、これらの分野を集中的に強化することが合格への近道となります。志望校の問題傾向にもよりますが、良問問題集の生物に引き続き取り組みつつ、大森徹の生物実験考察問題の解法、大森徹の生物遺伝問題の解法、大森徹の生物計算グラフ問題の解法の3冊を通して、解き方の強化を進めましょう。
これら3冊の参考書は、問題のパターンごとに解法が整理されているため、集中的に早めに取り組んだ方が理解が進みます。特に理工学部を志望する人は遺伝問題と実験考察問題、人間科学部を志望する人は計算グラフ問題を重点的に学習してください。教育学部を志望する人は実験考察問題の解法を徹底的にマスターし、問題文の情報から何が読み取れるかを素早く判断できる力を養いましょう。
また、この時期からは過去問研究も並行して進めることをおすすめします。まだ本格的に解くのではなく、どのような問題が出題されているか、どの分野が頻出かを把握するために、過去問に目を通しておくことが重要です。志望学部の出題形式や時間配分を意識しながら、自分に足りない力は何かを分析し、残り1ヶ月の学習計画を立てましょう。
使うべきおすすめの参考書:生物の良問問題集、大森徹の生物実験考察問題の解法、大森徹の生物遺伝問題の解法、大森徹の生物計算グラフ問題の解法
6ヶ月目は過去問演習を通して、なぜその答えになるのかを徹底的に追求しつつ、問題ごとに解き方を再現性を持って理解できるようにします。早稲田大学の生物は学部によって出題形式が異なるため、志望学部の過去問を最低10年分は解いて、出題パターンと時間配分を完璧にマスターしておくことが重要です。過去問を解く際は、必ず本番と同じ制限時間で取り組み、時間配分の感覚を身につけてください。
生物は最後に大森徹の最強問題集172に取り組みつつ、過去問演習に入れるかどうかが早慶以上のレベルを目指す受験生においては重要な流れとなります。この問題集は難関大学の入試問題を厳選して収録しているため、早稲田レベルの実戦力を養うのに最適です。過去問演習においては、大森徹の最強講義126をフル活用しながら取り組みつつ、弱点補強として使った解法の参考書も併用してください。
間違えた問題は、解き方と知識の原理などの理解においても、なぜ間違えたのか、なぜこれが答えになるのかを必ず確認するようにしましょう。特に理工学部を志望する人は記述問題の添削を先生にお願いし、論述の書き方を磨いてください。人間科学部を志望する人は、マークシート特有の選択肢の見極め方を意識し、正文誤文選択問題の精度を高めましょう。教育学部を志望する人は、思考力を問う問題に対して、問題文の情報を整理して論理的に考える訓練を繰り返してください。
使うべきおすすめの参考書:大森徹の最強問題集172、大森徹の最強講義126選、早稲田大学の過去問(赤本)、大森徹の生物実験考察問題の解法、大森徹の生物遺伝問題の解法、大森徹の生物計算グラフ問題の解法
早稲田の生物の学部ごとの特徴と対策
早稲田大学で生物を利用できる学部は主に理工学術院の先進理工学部、基幹理工学部、創造理工学部と、教育学部の理学科生物学専修です。
理工学部の生物は全体的に標準レベルですが、記号選択問題がほとんどなく、ほぼすべてが記述式となっています。
さらに論述問題も複数出題されるため、知識を正確に言葉で表現する力が必要です。
出題分野としては遺伝情報、細胞、生殖・発生からの出題が非常に多くなっています。
合格には生物で5割5分から6割程度の正答率が必要であり、先進理工学部では6割弱の正答率を目標にすることが推奨されます。
一方、教育学部の生物学専修では物理学や化学的な思考を取り入れた問題が出題され、異なる分野の知識を柔軟に統合して考える力が問われます。
マイクロプラスチックなどの現代的な環境問題を題材に、分子レベルから生態系レベルまでの多面的な解析力が求められるのが特徴です。
早稲田の生物対策に実際にやってよかった勉強法3選
早稲田の生物で合格点を取るために効果的な勉強法を3つ紹介します。
1つ目は記述式問題への徹底対策です。
早稲田の生物は記号選択問題がほとんどなく記述式が中心のため、用語を正確に書けるようにすることが必須です。
一問一答形式で用語を書く練習を繰り返し、スペルミスや漢字の間違いをなくすことが重要になります。
2つ目は大森徹の最強講義126選を軸にした知識の体系化です。
早稲田の生物では表や図を使って知識を説明できる深い理解が求められます。
講義本を何度も読み返し、間違えた問題は必ず該当ページに戻って関連知識を確認することで、問題を解くときに使える知識へと変えていくことができます。
3つ目は実験考察問題と計算問題への特化した対策です。
早稲田では教科書に載っていないような設定の問題が多く出題されるため、大森徹の生物実験・考察問題の解法や計算・グラフ問題の解法を使って解き方のパターンを習得することが効果的です。
これらの参考書に早めに取り組むことで理解が格段に進みます。
早稲田の生物の勉強法の実践におすすめの参考書
早稲田の生物対策におすすめの参考書を段階別に紹介します。
まず基礎固めの段階では高校これでわかる生物・生物基礎の2冊を講義本として使用することをおすすめします。
授業をしっかり聞いていた人は大森徹の最強講義126選を最初から使っても良いですが、基礎に不安がある人は高校これでわかるシリーズでスタートするのが安全です。
問題集としてはリードlightノート生物・生物基礎で基礎事項を確認しながら進めていきましょう。
応用段階では理系標準問題集生物と生物の基礎問題精講を解き進めることが効果的です。
理系標準問題集は国公立寄りの内容ですが、バランス良く力をつけることができます。
生物の基礎問題精講は私立大学の選択式問題が多く収録されており、MARCHや私立医学部を受験する人に特におすすめです。
最終段階では大森徹の最強問題集172に取り組み、過去問演習へと進んでいきます。
早稲田レベルを目指す受験生にとって、この問題集に取り組めるかどうかが合否の分かれ目となります。
また弱点分野に応じて大森徹の生物遺伝問題の解法や計算・グラフ問題の解法を使って集中的に強化していくことも重要です。
まとめ
今回は早稲田大学の生物の学部ごとの特徴と効果的な勉強法について解説しました。
早稲田の生物についてのまとめは以下のようになります。