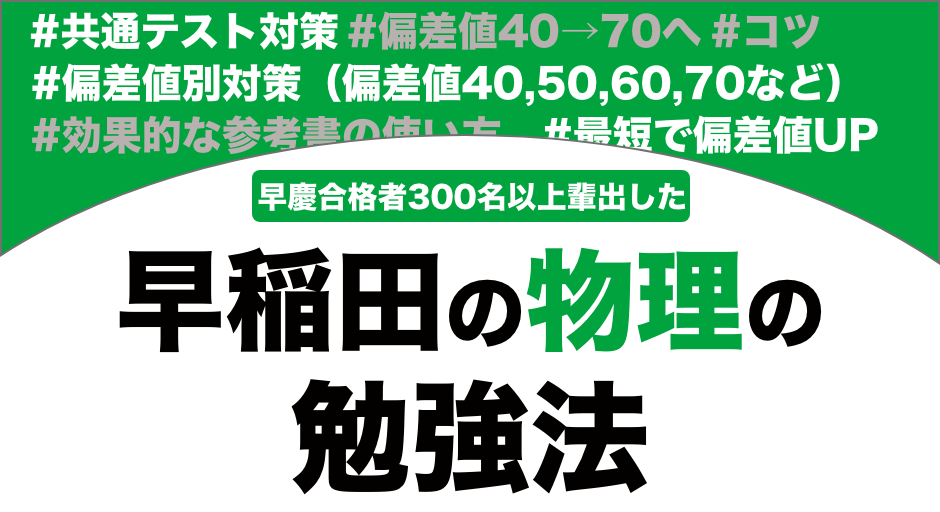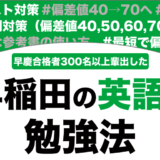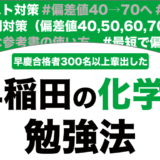本サイトの表記には、一部プロモーションを含みます
早稲田に合格できる効果的な物理の勉強法を解説します。早稲田の物理対策に実際にやってよかった勉強法とその順番も合わせて紹介します。また早稲田の物理対策におすすめの参考書も合わせて紹介します。
いきなり最終結論!早稲田に合格するための物理の勉強法の順番
早稲田に合格するための物理の勉強法の順番を解説します。
この段階では物理の基本概念と公式の理解に集中します。高校の授業をしっかり聞いていた人と聞いていなかった人で進め方が変わりますが、焦って難しい参考書に手を出さないことが最も重要です。物理は暗記科目ではなく理解する科目であるため、なぜその公式が成り立つのか、どういう状況で使うのかを徹底的に理解することが必要です。
学校の授業をあまり聞いていなかった人は、映像授業を活用して基礎から学び直すことをおすすめします。スタディサプリやtry itなどの映像授業で物理現象をビジュアルで理解しながら、同時に問題集を解いて知識を定着させていきます。この時期は焦らず丁寧に学習を進めることが、後の応用力につながります。
進学校に通っていて授業をしっかり聞いていた人は、物理のエッセンスから始めて、わからない部分だけ講義本で確認する方法が効率的です。ただし理解が曖昧なまま進むと後で苦労するため、少しでもわからない部分があれば必ず講義本に戻って確認しましょう。数学の微分積分の知識も物理では必要になるため、数学の学習計画との調整も重要です。
この段階のおすすめ参考書は、映像授業派の人はスタディサプリ物理またはtry it物理と理解しやすい物理プラス物理基礎です。講義本派の人は漆原の物理基礎と物理が面白いほどわかる本と物理のエッセンスです。
この段階では物理の解法のレパートリーを増やしていくことが最優先となります。基礎固めができたら、入試に頻出の典型問題を徹底的に解いていく時期です。物理は基礎段階での知識習得も重要ですが、何よりも大事なのは解法のレパートリーを増やすことです。
良問の風を中心に問題演習を進めていきます。分野ごとに学習を進めることをおすすめします。例えば力学の基礎問題集が終わったら、すぐに良問の風の力学に入るという方法です。こうすることで、その分野における解法のレパートリーをまとめて増やすことができ、知識の定着も良くなります。
わからない問題に出会ったら、すぐに講義本に戻って確認する習慣をつけましょう。この問題の時はこういった解き方で答えるという解法のパターンを体に染み込ませることが重要です。早稲田の物理は力学と電磁気が最重要分野であるため、この2分野には特に時間をかけて学習することをおすすめします。
この段階のおすすめ参考書は、良問の風物理と漆原の物理基礎と物理が面白いほどわかる本です。進学校の人は引き続き物理のエッセンスも併用します。
この段階では早稲田レベルの応用問題に対応できる力を養成します。良問の風が終わったら、名門の森に進んでいきます。名門の森は早慶上位校レベルの問題が収録されており、早稲田の物理で合格点を取るためには必須の問題集です。
ここからは単に解法のレパートリーを増やすだけでなく、どの問題に対してどの解法を使うべきかという問題の分析力を高めることが重要になってきます。問題文を読んで物理現象をイメージし、適切な解法を選択できる力を養います。早稲田の物理は力学と電磁気が毎年必ず出題されるため、この2分野は名門の森で徹底的に鍛えておく必要があります。
波動と熱力学も理工学部では必ず1題出題されるため、偏りなく学習することが大切です。名門の森を解いていて、基礎が怪しいと感じた分野があれば、すぐに良問の風や講義本に戻って復習しましょう。基礎が固まっていない状態で応用問題ばかり解いても効果は薄いです。
この段階のおすすめ参考書は、名門の森物理と良問の風物理です。復習用に漆原の物理基礎と物理が面白いほどわかる本も手元に置いておきます。
この段階では早稲田の最難関レベルに対応できる力を完成させます。名門の森が8割以上解けるようになったら、東大京大レベルを志望する人は物理重要問題集に進みます。早慶レベルを志望する人は名門の森を繰り返し解いて完璧にすることに集中しましょう。
早稲田の物理は公式暗記や典型問題のパターンとして解法を覚えているだけでは解けない問題が出題されます。難問に出会うごとに、どうしたらその解き方が思いつくか、答えを出すまでの今まで覚えてきた解法の組み合わせ方を徹底的に分析することが必要です。この積み重ねが本番での得点力につながります。
この時期には苦手な分野を徹底的に潰していくことも重要です。名門の森を解いていて苦手だと感じた分野は、良問の風に戻って基礎から復習します。物理は一つの分野の理解が曖昧だと、それが原因で他の分野の問題も解けなくなることがあるため、弱点を残さないことが大切です。
この段階のおすすめ参考書は、物理重要問題集と名門の森物理と良問の風物理です。
この段階では早稲田の過去問を使って実戦力を完成させます。11月には過去問演習に入れるように、それまでに参考書をしっかりと終わらせることが重要です。過去問は最低でも10年分、できれば15年分は解くことをおすすめします。
早稲田の物理は問題量が非常に多いため、時間配分の練習が必須です。理工学部を志望する人は化学と合わせて120分で解く練習をします。最初は時間内に解き終わらなくても気にせず、まずは全問題を丁寧に解いてみましょう。その後、どの問題から解けば効率的か、どこで時間がかかりすぎたかを分析します。
過去問を解く中で、似たような物理現象が繰り返し出題されていることに気づくはずです。早稲田の物理は典型的な物理現象をベースに複雑な計算を求めることが多いため、過去問で出題された物理現象は完璧に理解しておきましょう。間違えた問題や解けなかった問題は必ず復習し、どこで間違えたのか、どうすれば解けたのかを分析することが重要です。
この段階のおすすめ参考書は、早稲田大学理工学部の過去問と早稲田大学教育学部の過去問です。志望学部以外の過去問も時間があれば解いておくと良いでしょう。


早稲田の物理の学部ごとの特徴と対策
早稲田大学の理工学部は基幹理工学部、先進理工学部、創造理工学部の3つに分かれています。
物理の試験は化学と合わせて120分で解答する形式となっており、配点は理科2科目合わせて120点満点です。
物理は大問3題構成となっており、第1問がマークシート式で第2問と第3問が記述式となります。
力学と電磁気の分野から毎年必ず2題出題されることが特徴です。
残りの1題は波動か熱力学が年度ごとに交互に出題される傾向があります。
学科によって物理と化学の配点比率が異なることにも注意が必要です。
物理学科と応用物理学科では物理と化学の配点比率が2対1となり、物理が80点で化学が40点という物理重視の配点となります。
化学・生命化学科や応用化学科では物理と化学の配点比率が1対2となり、化学重視の配点です。
生命医科学科と電気・情報生命工学科では物理、化学、生物から2科目を選択する形式となっています。
早稲田の物理は問題量が非常に多く、時間との戦いになることが最大の特徴です。
計算を伴う問題が多く出題され、1つ1つの問題に対して解答する十分な時間の余裕はありません。
早稲田の物理対策に実際にやってよかった勉強法3選
早稲田の物理対策として最も効果的な勉強法は力学と電磁気の徹底強化です。
この2分野は毎年必ず大問2つ分が出題されるため、ここで確実に得点することが合格への近道となります。
力学ではばねでつながった2物体の運動や惑星の楕円運動など様々な題材が扱われます。
電磁気では電磁誘導やコンデンサーの問題が頻出となるため、定石問題から応用問題まで幅広い問題パターンに触れておくことが重要です。
2つ目の勉強法は時間配分を意識した過去問演習です。
早稲田の物理は試験時間に対して問題量が非常に多いため、スピーディーな解答が求められます。
過去問演習では60分以内に解き切ることを目標にして、解きやすい問題から先に解く練習をすることが大切です。
時間内に終わらなかったらなぜ終わらなかったのか、もっと速く解くには何が足りないかをしっかり分析しましょう。
3つ目の勉強法は複雑な計算問題への対策です。
早稲田の物理は物理現象そのものは典型的であっても、複雑な計算を求められることが多いです。
そのため計算力を高めるために問題集を繰り返し解くことと、計算ミスを減らすための工夫が必要になります。
時間がかかりすぎると判断したら途中で別の問題に移るなど、臨機応変な対応も常に意識しておくことが合格への秘訣です。
早稲田の物理の勉強法の実践におすすめの参考書
早稲田の物理の勉強法の実践におすすめの参考書を紹介します。
物理のエッセンス
物理のエッセンスは早稲田の物理対策の基礎固めに最適な参考書です。
河合出版から出版されているこの参考書は物理を学ぶ上で重要な感覚的な理解と問題を実際に解く上で大切な考え方の両方を効率的に学習できます。
掲載している問題は実際の入試問題の解析にもとづいて構成されており、基礎から学びつつ共通テスト対策も十分可能です。
力学114問、波動70問、熱33問、電磁気95問、原子40問という問題構成となっています。
比較的薄い参考書のため物理に苦手意識があってもまずはやってみようと思えるボリューム感であることも特徴です。
良問の風
良問の風は物理のエッセンスの次に取り組むべき問題集です。
センター試験から関関同立、MARCHレベルの問題で構成されており、全部で148題の良問が収録されています。
物理のエッセンスと名門の森の橋渡しとして出版された問題集であり、難易度差を埋めるための最適な教材となっています。
著者の浜島先生の書かれた本は解説が素晴らしく、俗にこういった問題集は解説があまり詳しくないものが多いのですが本書は解説がとても丁寧です。
早稲田レベルを目指す受験生はこの良問の風で解法のレパートリーを増やしていくことが重要になります。
名門の森
名門の森は早稲田以上の難関大学を志望する受験生に必須の問題集です。
良問の風が終わり次第取り組むべき教材であり、旧帝大や早慶などの超難関大学レベルの問題が収録されています。
物理のエッセンスから名門の森への難易度差が激しいため脱落者が多いことも事実でしたが、良問の風を挟むことで無理なくステップアップできます。
名門の森では解法のレパートリーを増やしていくというよりもどの問題に対してどの解法を使うべきかなどの問題の分析力を高めることが重要になります。
早慶以上を志望する受験生は公式暗記や典型問題のパターンとして解法を覚えていても解けない問題がどんどん出てくるので、難問に出会うごとにどうしたらその解き方が思いつくかを徹底的に分析しましょう。
まとめ
今回は早稲田大学の物理について学部ごとの特徴と対策、実際にやってよかった勉強法、おすすめの参考書を解説しました。
早稲田の物理についてのまとめは以下のようになります。