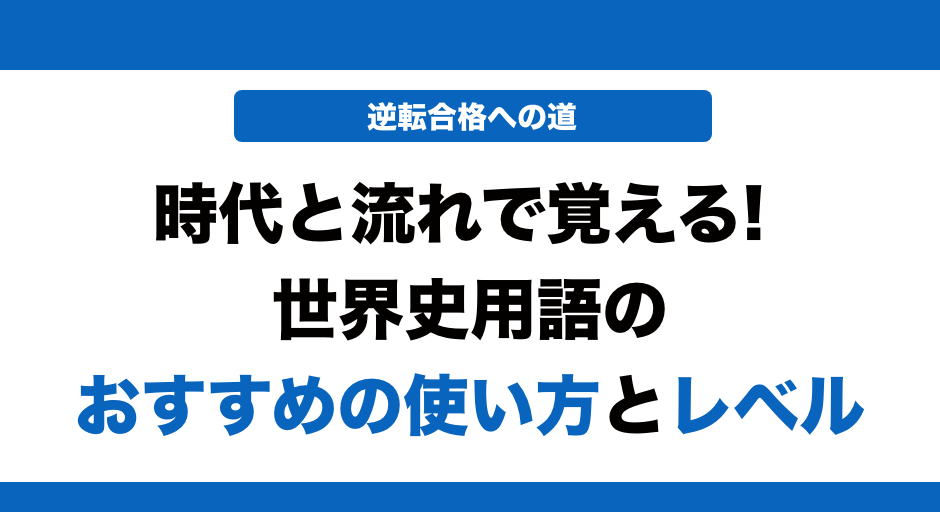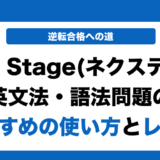本サイトの表記には、一部プロモーションを含みます
時代と流れで覚える世界史用語のおすすめの使い方と勉強法を徹底解説します。
時代と流れで覚える世界史用語のレベルや難易度についても具体的に解説します。また実際にやってみた上でのおすすめの時代と流れで覚える世界史用語の参考書としての進め方や順番についても紹介します。

【この記事の監修者:逆転合格特化塾塾長竹本明弘】
これまで個別指導塾の塾長として早慶に現役生および浪人生を含めて合計で300人以上の合格者を輩出してきました。参考書の使い方や各教科の勉強法について紹介しているのでぜひ参考にしてみてください。
時代と流れで覚える世界史用語のレベル
時代と流れで覚える世界史用語のレベルを解説します。
時代と流れで覚える世界史用語のレベルと難易度
時代と流れで覚える世界史用語のレベルは、教科書範囲内の知識を扱う標準レベルの参考書です。共通テストや国公立大学の二次試験における論述問題に対応できる内容となっており、難関私立大学でも8割程度の得点を目指せる構成になっています。
この参考書は世界史の基礎から標準レベルまでを網羅しているため、世界史の学習を始めたばかりの受験生でも無理なく取り組めます。ただし早稲田大学や慶應義塾大学のような教科書範囲を超える細かい知識が求められる大学には、この参考書だけでは不十分な点に注意が必要です。
時代と流れで覚える世界史用語は、用語の暗記だけでなく歴史の流れを理解しながら学習できる点が大きな特徴となっています。単なる一問一答形式とは異なり、時代背景や因果関係を把握しながら知識を定着させることができるため、論述問題にも対応できる力が身につきます。

【この記事の監修者:逆転合格特化塾塾長竹本明弘】
時代と流れで覚える世界史用語は、偏差値50から65程度を目指す受験生に最適な参考書です。流れの中で用語を覚えられるため、単なる暗記に陥らず歴史を理解しながら学習できます。国公立大学志望者や共通テストで高得点を狙う受験生には特におすすめですが、早慶のような最難関私立を目指す場合は、この参考書を終えた後により詳しい一問一答に進む必要があります。
時代と流れで覚える世界史用語の習熟度別のレベル
レベル1は、時代と流れで覚える世界史用語を一通り読み終えた段階です。まだ知識は定着していませんが、世界史の全体像を把握できている状態といえます。
レベル2は、重要用語チェックの5割が答えられるレベルです。基本的な用語が頭に入り始めており、世界史の学習が軌道に乗ってきた段階といえます。
レベル3は、重要用語チェックの8割が答えられるレベルで、偏差値60相当の実力です。共通テストや中堅国公立大学レベルの問題に対応できる知識が身についています。
レベル4は、流れで覚えるセクションと時代と場所をつかむセクションの赤字部分の5割が答えられるレベルです。歴史の流れの中で用語を理解できるようになっており、論述問題への対応力も向上しています。
レベル5は、流れで覚えるセクションと時代と場所をつかむセクションの赤字部分の8割が答えられるレベルで、偏差値65相当の実力です。時代と流れで覚える世界史用語を完璧に習得した状態であり、難関国公立大学の二次試験にも対応できる力が身についています。
時代と流れで覚える世界史用語のおすすめの使い方
時代と流れで覚える世界史用語のおすすめの使い方を段階別に解説します。
時代と流れで覚える世界史用語の使い方として、まず重要用語チェックを赤シートで隠してテスト形式で取り組むことから始めます。この段階では完璧を目指さず、どの用語を覚えていてどの用語を覚えていないのかを確認することが重要です。
間違えた用語には印をつけておき、繰り返し確認できるようにしましょう。時代と流れで覚える世界史用語は赤シート対応なので、効率的に暗記学習を進めることができます。
最初は1テーマに40分程度かかるかもしれませんが、慣れてくれば30分程度で終わるようになります。焦らずに着実に進めることが、時代と流れで覚える世界史用語を使いこなすコツです。
重要用語チェックである程度の知識が身についたら、流れで覚えるセクションに取り組みます。右ページの文章を赤シートで隠しながら、歴史の流れの中で用語を覚えていくことがこの段階の目標です。
時代と流れで覚える世界史用語の最大の特徴であるこのセクションでは、単なる用語の暗記ではなく、なぜその出来事が起こったのか、どのような結果をもたらしたのかという因果関係を理解しながら学習できます。この使い方こそが、論述問題に強くなる秘訣です。
文章をそのまま覚えることで、国公立大学の二次試験における論述問題でも活用できる知識が身につきます。時代と流れで覚える世界史用語のレベルを最大限に引き上げるためには、この段階を丁寧に進めることが不可欠です。
最後に左ページの時代と場所をつかむセクションを活用して、表や地図で視覚的に歴史を整理します。いつ、どこで、何が起きたのかを空間的・時間的に把握することで、知識が立体的に理解できるようになります。
この段階では、右ページの文章との関連性を意識しながら学習することが重要です。時代と流れで覚える世界史用語は地図や図解が豊富なので、視覚的な記憶として定着させることができます。
赤字部分を赤シートで隠して答えられるか確認しながら、完璧に仕上げていきましょう。時代と流れで覚える世界史用語の使い方をマスターすれば、世界史の成績は確実に向上します。
▽おすすめの時代と流れで覚える世界史用語の図解

| ▽おすすめの世界史の参考書の使い方やレベルが知りたい方はこちら |
| ストーリーでわかる世界史探究の使い方とレベル【参考書解説】 |
| 実力をつける世界史100題の使い方とレベル【参考書解説】 |
| 【東進】世界史一問一答完全版の使い方とレベル【参考書解説】 |
| 斎藤の世界史一問一答の使い方とレベル【参考書解説】 |
時代と流れで覚える世界史用語の習得にかかる時間
時代と流れで覚える世界史用語は全80テーマで構成されており、1テーマあたり30分が標準的な学習時間とされています。単純計算すると、1周するのに40時間かかることになります。
ただし実際には、受験生の現在のレベルや学習ペースによって必要な時間は変わってきます。世界史を初めて学ぶ受験生の場合、1テーマに40分から50分程度かかることもあるでしょう。
時代と流れで覚える世界史用語を完全に習得するには、最低でも3周は必要です。1周目は理解と暗記に時間がかかりますが、2周目以降は復習が中心となるため、1周にかかる時間は徐々に短くなっていきます。毎日2時間の学習時間を確保できれば、2ヶ月程度で時代と流れで覚える世界史用語のレベル3から4に到達できるでしょう。
時代と流れで覚える世界史用語を使う時の注意点
時代と流れで覚える世界史用語を使う際の最大の注意点は、この参考書だけで満足しないことです。特に早稲田大学や慶應義塾大学のような教科書範囲外の細かい知識を問う大学を志望する受験生は、この参考書を終えた後に斎藤の世界史B一問一答などのより詳しい教材に取り組む必要があります。
また、流れで覚えることのデメリットとして、特定の文脈でしか用語を思い出せなくなる可能性があります。時代と流れで覚える世界史用語で学んだ知識を、様々な角度から問われても答えられるよう、過去問演習などを通じてアウトプットの練習も並行して行いましょう。
さらに、時代と流れで覚える世界史用語は教科書と併用することをおすすめします。この参考書はあくまでインプット用の教材であり、教科書の内容を補完する位置づけと考えるとよいでしょう。教科書で大きな流れを理解し、時代と流れで覚える世界史用語で知識を定着させるという使い方が効果的です。
時代と流れで覚える世界史用語の特徴
時代と流れで覚える世界史用語の最大の特徴は、従来の一問一答形式とは異なり、歴史の流れの中で用語を覚えられる点です。時代と場所をつかむセクションと流れで覚えるセクションが連動しており、時代背景を理解しながら知識をインプットできます。
左ページは表や地図、写真などの図解で構成されており、視覚的に歴史を把握できる工夫がされています。いつ、どこで何が起きたのかを空間的・時間的に整理しながら学習できるため、記憶に残りやすい構成となっています。
右ページの文章は、そのまま論述問題の解答として使えるほど完成度が高い内容です。時代と流れで覚える世界史用語のレベルの高さは、この文章の質の高さにも表れています。東京大学の二次試験のような難関大学の論述問題にも対応できる知識が身につきます。
時代と流れで覚える世界史用語のメリット
時代と流れで覚える世界史用語のメリットを解説します。
流れと用語を同時に習得できる
時代と流れで覚える世界史用語の最大のメリットは、歴史の流れと用語を同時に習得できる点です。従来の一問一答形式では、用語は覚えられても歴史の文脈が理解できないという問題がありました。
この参考書を使えば、なぜその出来事が起こったのか、どのような結果をもたらしたのかという因果関係を理解しながら学習できます。時代と流れで覚える世界史用語の使い方を工夫すれば、論述問題への対応力も自然と身につきます。
流れで覚えることで、知識が断片的にならず体系的に整理されるため、忘れにくくなるというメリットもあります。受験生にとって効率的な学習方法といえるでしょう。
赤シートでテスト形式の学習ができる
時代と流れで覚える世界史用語は赤シートに対応しているため、テスト形式で繰り返し学習できます。覚えるべき用語は赤字になっており、赤シートで隠すことで自分がどれだけ覚えているか確認できます。
このテスト形式の学習は、アクティブリコールという記憶定着に効果的な学習方法です。ただ読むだけよりも、思い出そうとする行為が記憶を強化します。時代と流れで覚える世界史用語のレベルを着実に上げていくには、この機能を最大限活用することが重要です。
スキマ時間にも取り組みやすく、通学時間などを有効活用できる点も受験生にとって大きなメリットです。
地図や図解が豊富で視覚的に理解できる
時代と流れで覚える世界史用語には、地図や図解が豊富に掲載されています。左ページの視覚情報と右ページの文章情報を組み合わせることで、多角的に歴史を理解できます。
地図を見ながら学習することで、地理的な位置関係や領土の変遷を把握できます。世界史では場所の理解が非常に重要なので、この特徴は時代と流れで覚える世界史用語の大きな強みです。
視覚的な記憶は文字だけの記憶よりも定着しやすいため、学習効率が向上します。受験生の理解を助ける工夫が随所に施されています。
時代と流れで覚える世界史用語のデメリット
時代と流れで覚える世界史用語のデメリットを解説します。
早慶レベルには知識量が不足している
時代と流れで覚える世界史用語のデメリットとして、早稲田大学や慶應義塾大学のような最難関私立大学には知識量が不足している点が挙げられます。この参考書は教科書範囲内の知識を扱っているため、教科書範囲外から出題される大学には対応できません。
早慶を第一志望とする受験生は、時代と流れで覚える世界史用語を基礎固めとして使用し、その後により詳しい一問一答に進む必要があります。時代と流れで覚える世界史用語のレベルだけでは、これらの大学で高得点を取ることは難しいでしょう。
ただし、この参考書で基礎を固めてから発展的な学習に進めば、知識が体系的に整理されているため、より効率的に学習を進められます。
特定の流れでしか思い出せなくなる可能性がある
時代と流れで覚える世界史用語のもう一つのデメリットは、流れで覚えるがゆえに、その流れでしか用語を思い出せなくなる可能性がある点です。この使い方の落とし穴に注意しなければなりません。
入試問題では様々な角度から知識が問われるため、文脈が変わると答えられないという事態は避けなければなりません。時代と流れで覚える世界史用語で学習した後は、必ず過去問などで多様な出題形式に触れることが重要です。
この問題を克服するには、時代と流れで覚える世界史用語を使いながら、並行して他の問題集にも取り組むことをおすすめします。受験生は一つの教材に依存しすぎないよう注意しましょう。
時代と流れで覚える世界史用語に関するよくある質問
時代と流れで覚える世界史用語に関するよくある質問を紹介します。
- 時代と流れで覚える世界史用語は国公立二次の論述対策になりますか?
- 時代と流れで覚える世界史用語は、国公立大学の二次試験における論述対策として非常に有効です。右ページの文章は論述問題の解答として使えるレベルの完成度があり、歴史の流れを説明する力が身につきます。
特に東京大学や京都大学のような難関国公立大学の論述問題にも対応できる知識が含まれています。時代と流れで覚える世界史用語の文章をそのまま覚えることで、論述の型も自然と身につきます。
ただし、時代と流れで覚える世界史用語で基礎を固めた後は、志望大学の過去問を使った実践的な論述練習も必要です。受験生は知識のインプットとアウトプットをバランスよく行いましょう。
- 時代と流れで覚える世界史用語だけで共通テストは何点取れますか?
- 時代と流れで覚える世界史用語を完璧に仕上げれば、共通テストで8割から9割程度の得点が期待できます。この参考書は教科書範囲の知識を網羅しており、共通テストの出題範囲とよく合致しているためです。
ただし、時代と流れで覚える世界史用語だけでなく、過去問演習も並行して行うことが高得点への鍵となります。知識があっても問題形式に慣れていないと、本番で実力を発揮できません。
時代と流れで覚える世界史用語のレベルを最大限に引き上げた上で、共通テスト対策の問題集にも取り組めば、満点に近い得点も可能です。受験生は計画的に学習を進めましょう。
- 時代と流れで覚える世界史用語は何周すれば完璧になりますか?
- 時代と流れで覚える世界史用語を完璧に仕上げるには、最低でも3周は必要です。1周目は理解と暗記、2周目は定着、3周目は総仕上げという流れで進めるとよいでしょう。
ただし、受験生によって必要な周回数は異なります。時代と流れで覚える世界史用語のレベル5に到達するまでには、4周や5周必要な場合もあります。重要なのは周回数ではなく、どれだけ内容を理解し記憶できたかです。
赤シートで隠したときに8割以上答えられるようになれば、次の教材に進んでも問題ありません。時代と流れで覚える世界史用語の使い方として、完璧を目指すよりも効率を重視することも大切です。
- 時代と流れで覚える世界史用語と一問一答はどちらを先にやるべきですか?
- 時代と流れで覚える世界史用語を先に使い、その後で一問一答に取り組むことをおすすめします。流れを理解してから細かい知識を詰めていく方が、効率的に学習できるからです。
時代と流れで覚える世界史用語で歴史の因果関係や時代背景を理解しておけば、一問一答で覚える用語も文脈の中で理解できるため、記憶に定着しやすくなります。逆に一問一答から始めると、知識が断片的になりがちです。
ただし、時代と流れで覚える世界史用語を使いながら、基本的な用語は一問一答で確認するという並行学習も効果的です。受験生の学習スタイルに合わせて選択しましょう。
- 時代と流れで覚える世界史用語は世界史の初学者でも使えますか?
- 時代と流れで覚える世界史用語は、世界史の初学者でも使える参考書です。ただし、全く世界史の知識がない状態では少し難しく感じる可能性があります。
もし定期テストで赤点を取っていたり、授業を全く聞いていなかった受験生の場合は、まずマンガで世界史が面白いほどわかる本などの導入書から始めることをおすすめします。その後、時代と流れで覚える世界史用語に取り組めば、スムーズに学習を進められるでしょう。
ある程度世界史の全体像が頭に入っている受験生であれば、時代と流れで覚える世界史用語から学習を始めても問題ありません。自分のレベルに合わせて判断しましょう。
- 時代と流れで覚える世界史用語と教科書はどちらを中心に使うべきですか?
- 時代と流れで覚える世界史用語と教科書は、どちらか一方ではなく両方を併用することをおすすめします。教科書で大きな歴史の流れを理解し、時代と流れで覚える世界史用語で知識を定着させるという使い方が理想的です。
教科書は情報量が多く網羅性がありますが、受験対策としては効率が悪い面もあります。一方、時代と流れで覚える世界史用語は受験に必要な知識に特化しているため、効率的に学習できます。
受験生は教科書を通読した後、時代と流れで覚える世界史用語で重要ポイントを押さえるという流れで学習を進めると、世界史の成績を効率的に伸ばせるでしょう。時代と流れで覚える世界史用語のレベルを着実に上げていくことが合格への近道です。