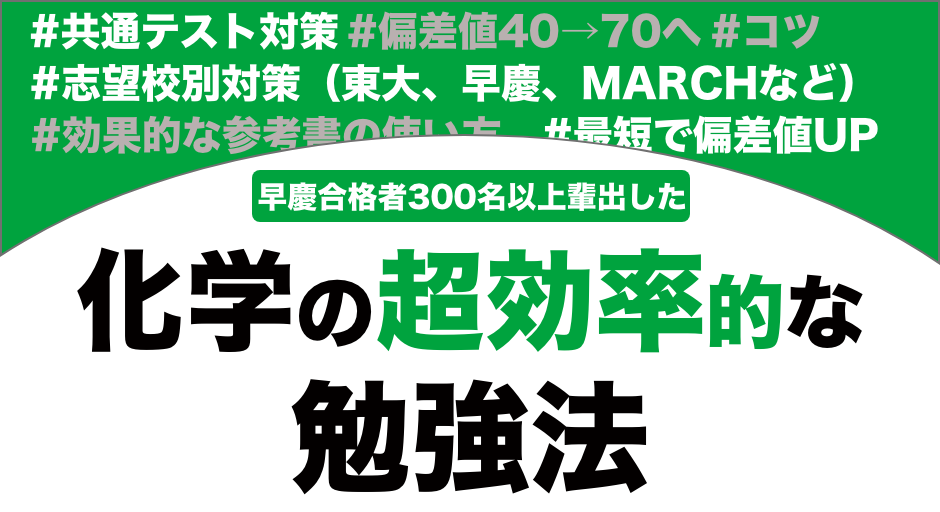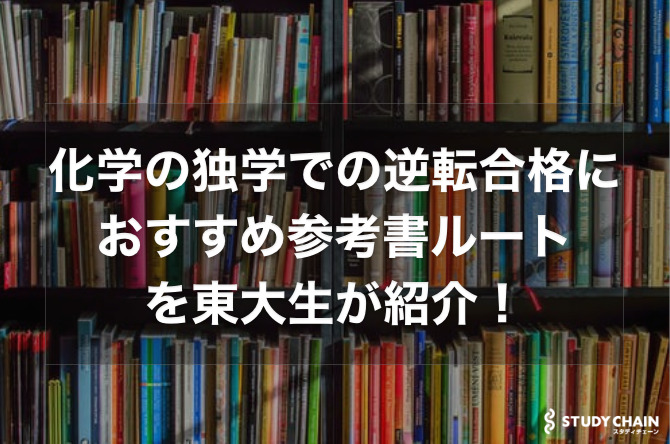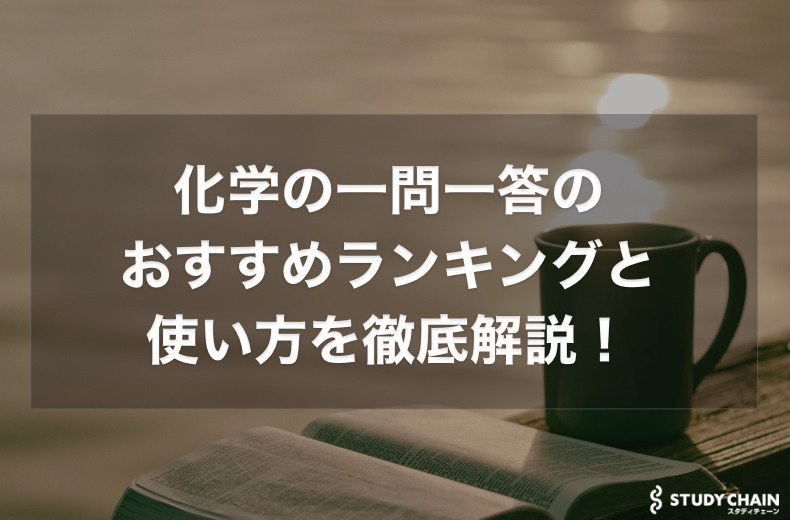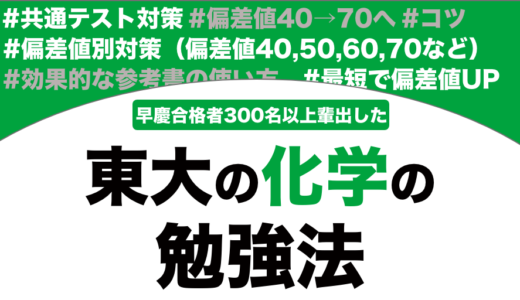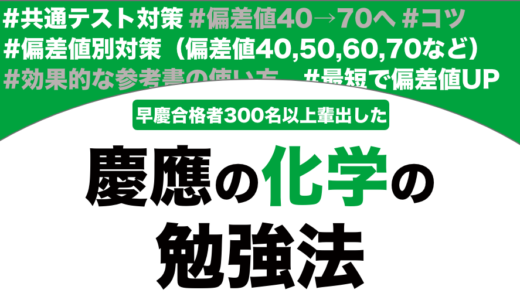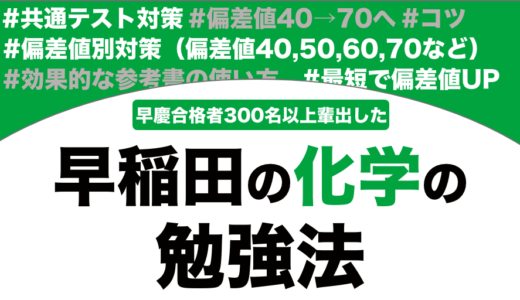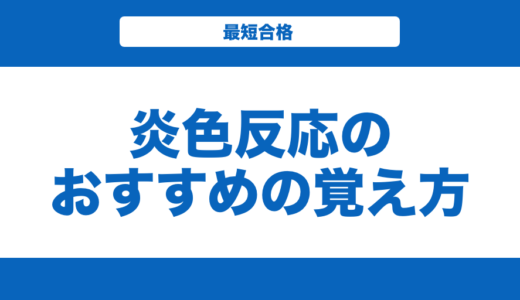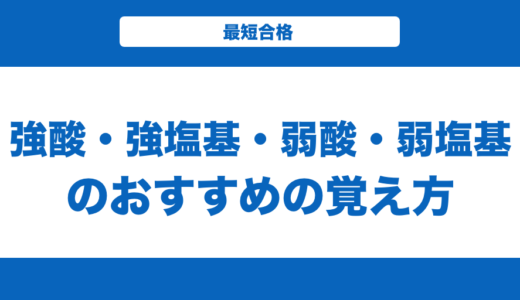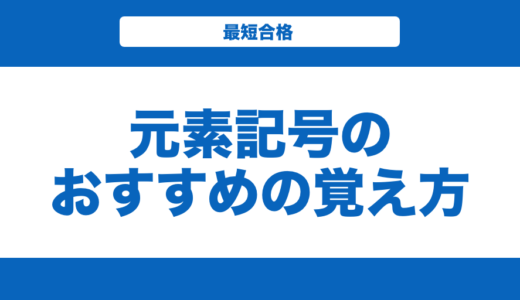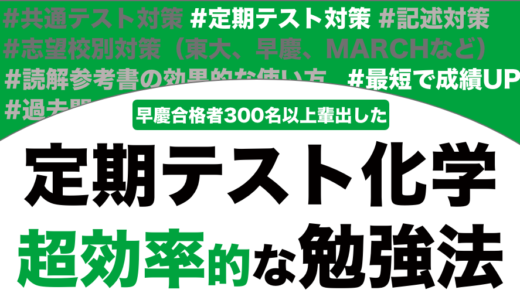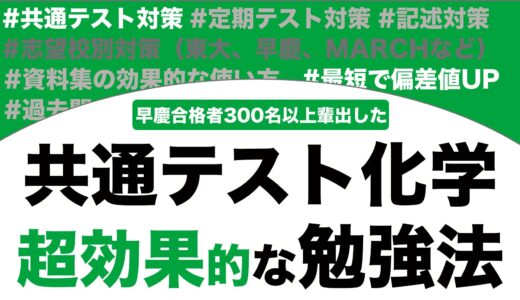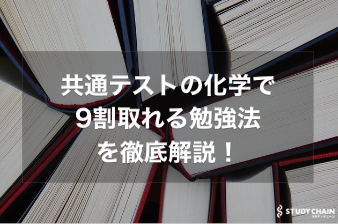大学受験の化学の超効率的な勉強法を解説します。
また志望校別の東大、京大、早稲田や難関大志望におすすめの化学の勉強法から実際にやってよかった化学の勉強法から共通テスト対策におすすめの化学の勉強法も解説します。
また化学の勉強法の実践におすすめの参考書から大学受験の化学のおすすめの勉強法の順番も解説します。

【この記事の監修者:逆転合格特化塾塾長「竹本明弘」】
これまでオンライン予備校「逆転合格特化塾」の塾長として早慶に現役生および浪人生を含めて合計で300人以上の合格者を輩出してきました。
その中で共通テストの化学で満点を取った生徒もたくさんおり、実際に指導する中でゼロからでも化学の偏差値70まで到達した大学受験対策の化学の勉強法やおすすめの参考書およびやってよかった化学の勉強の順番を解説したいと思います。
いきなり最終結論!偏差値30から70になる化学の勉強法TOP3を徹底解説!
結論から述べると、化学の偏差値を30から70に上げるための勉強法TOP3は「基礎知識の徹底的な理解と暗記」と「計算力の強化」と「原理の深い理解」の3つです。
第1位は基礎知識の徹底的な理解と暗記です。
化学は暗記科目ではありませんが、基本となる化学式や反応式、物質の性質などを正確に覚えていないと応用問題は解けません。進学校に通っている人は鎌田シリーズや福間の無機化学の講義を使い、そうでない人は宇宙一わかりやすい高校化学シリーズがおすすめです。これらの参考書を繰り返し読み込むことで化学の土台が完成します。
第2位は計算力の強化です。
化学では理論化学を中心に計算問題が頻出します。モル計算や化学平衡、熱化学方程式などの計算は練習量がものを言う分野です。リードライトノート化学や化学計算問題の解き方などの問題集を使って、毎日計算問題に触れる習慣をつけることが重要になります。最初は時間がかかっても諦めずに解き続けることで必ず解けるようになります。
第3位は原理の深い理解です。
化学は丸暗記だけでは偏差値70には到達しません。なぜその反応が起こるのか、なぜその性質を持つのかという原理を理解することで応用力が身につきます。間違えた問題は必ず講義系の参考書に戻って原理を確認する習慣をつけましょう。この作業を繰り返すことで化学の本質的な理解が深まり、初見の問題にも対応できる力が養われます。
大学受験対策におすすめの化学の勉強法の順番
大学受験対策におすすめの化学の勉強法の順番を解説します。
この時期は化学における基礎的な知識の獲得と基本的な計算スキルを習得することに重点を置きます。進学校に在籍しているかどうかによって活用する教材は大きく異なってきます。
進学校に在籍している受験生は、鎌田の理論化学の講義(旺文社)、鎌田の有機化学の講義(旺文社)、福間の無機化学の講義(旺文社)をしっかりと読み込みながら、並行してリードLightノート化学(数研出版)を進めていくことで、化学の基礎段階で出題される問題を中心に理解と暗記ができるように取り組んでいきましょう。
進学校に在籍していない受験生は、宇宙一わかりやすい高校化学理論化学・無機化学(学研プラス)を活用していくとよいでしょう。問題集については、学校でセミナー化学基礎・化学(第一学習社)を使用している方はそれを活用し、使用していない方は理解しやすい化学基礎・化学(文英堂)を使うことをおすすめします。
また化学の基礎力を身につける上では、序盤における知識の習得も大切ですが、同時に計算力も非常に重要になってきます。問題集の1周目が終了した段階で、化学計算問題の解き方を活用して計算力もしっかりと身につけていくようにしましょう。
この時期はアウトプットの量を増やしていきながらも、何度も講義形式の参考書に戻って構造や理由を徹底的に確認することが大切です。
化学の基礎問題精講(旺文社)もしくは化学の全レベル問題集3(旺文社)を活用して、化学の応用段階のアウトプットも増やしていくようにしましょう。その際に必ず間違える回数は増えてくると考えられますので、毎回宇宙一もしくは大学受験Doシリーズの鎌田、福間などの講義形式の参考書で構造や知識の深掘りを実施するようにしましょう。
化学という科目は学習時間をかけることで共通テスト70%程度まではすぐに到達できますが、その後は問題集を解いて間違えたら講義形式の参考書を確認するというサイクルを繰り返し実践しないと必ず成績の伸び悩みが発生します。
早慶レベル以上の志望校を目指している受験生は、この段階で講義形式の参考書として化学の新研究(三省堂)を導入しましょう。共通テスト対策を進める受験生は、共通テスト化学実験・資料の考察問題24(河合出版)と共通テスト実践模試化学(駿台文庫)を進めていきます。
早慶レベル以上の志望校を目指す受験生は、ここからさらに細かい部分の理解や難問への対応力が必要となってくるため、辞書的な活用をする化学の新研究(三省堂)を使用していきましょう。また全レベル問題集化学の4(旺文社)を先に取り組んでから、化学の重要問題集(数研出版)に進みながら、化学の新研究(三省堂)で確認するというリズムを繰り返し実施していきましょう。
共通テスト化学については、難関大志望の受験生は特に進める必要はありません。正しく学習を進めていれば知識面において解けない問題が生じることはありませんので、それよりも志望校の問題を解けるようになるための訓練に時間を使っていきましょう。
また共通テスト対策のみで化学が必要という受験生は、ここから共通テスト化学の実践模試に取り組みながら、共通テスト化学実験・資料の考察問題24(河合出版)に取り組んで、共通テスト特有の化学の問題の解き方を習得していきましょう。
難関大志望の受験生は、化学においては原理の理解と苦手分野の克服を両方同時にどんどん実施していきましょう。化学の重要問題集(数研出版)などを活用しながら復習と新研究(三省堂)などでの原理理解が重要になります。
難関大志望の受験生は、どんどん難易度の高い参考書に進めば進むほど良いということではありません。どれだけ原理や仕組みを理解できているかが重要になるため、究極的には資料集や新研究(三省堂)に掲載されている仕組みなどを全て把握している方が良いという話になります。そこまで実施する必要はありませんが、それくらい原理の理解は重要になってくるため、重要問題集(数研出版)などを間違えるたびに正しくその分野を理解するということに重点的に時間を使っていきましょう。解く時間30%に対して理解する時間は70%程度が一番の時間配分かと考えられます。
過去問演習期間となります。


共通テスト対策におすすめの化学の勉強法
共通テスト対策におすすめの化学の勉強法を解説します。
共通テスト対策におすすめの化学の勉強法(基礎編)
共通テスト化学で安定して6割から7割を取るためには基礎固めが最優先です。
まずは教科書レベルの知識を完璧にすることから始めましょう。共通テストは基礎的な知識を正確に理解しているかを問う問題が中心となっています。セミナー化学基礎・化学や理解しやすい化学基礎・化学などの基礎レベルの問題集を1周することで基本的な出題パターンに慣れることができます。
次に重要なのが化学用語の正確な理解です。共通テストでは選択肢の文章を正確に読み取る力が求められます。例えば酸化と還元の定義、電子の授受、酸化数の変化などの基本用語を曖昧にしたままにしないことが大切です。わからない用語が出てきたら必ず講義系の参考書で確認する癖をつけましょう。
最後に計算問題の基礎練習も欠かせません。共通テストの計算問題は複雑ではありませんが、正確さとスピードが求められます。毎日10問程度の計算練習を続けることで計算ミスを減らし、本番でも落ち着いて解けるようになります。基礎レベルの計算を確実に得点源にすることが共通テストで高得点を取るための第一歩です。
共通テストで9割取れるおすすめの化学の勉強法(応用編)
共通テストで9割取れるおすすめの化学の勉強法を解説します。
この時期は化学の土台となる基礎知識をしっかりと身につけることに集中します。在籍している高校のレベルによって適切な教材が異なってきますので、自分に合ったものを選びましょう。進学校で学んでいる方は、鎌田の理論化学の講義や鎌田の有機化学の講義、福間の無機化学の講義をじっくり読み進めることをおすすめします。
進学校ではない環境で学んでいる方には、宇宙一わかりやすい高校化学の理論化学編と無機化学編が最適です。問題集については学校でセミナー化学基礎と化学を使用している場合はそれを活用し、使用していない場合は理解しやすい化学基礎と化学を選ぶとよいでしょう。問題集の1周目が完了した時点で、化学計算問題の解き方という参考書を使って計算問題に特化した訓練を行いましょう。
この段階では実際に問題を解く量を増やしながら、わからない部分が出てきたら必ず講義系の参考書に戻って確認する習慣をつけていきます。化学の基礎問題精講または化学の全レベル問題集3を使用して、応用レベルの問題にも挑戦していきましょう。間違えた問題に出会うたびに、講義本を開いて該当する分野の構造や知識を掘り下げて確認していきます。
化学という科目は学習時間をしっかり確保すれば共通テストで7割程度までは比較的早く到達できます。しかしそこから先のレベルに進むためには、問題集で間違えた箇所を講義本で確認するというサイクルを徹底的に繰り返すことが必須です。このサイクルを怠ると必ず成績が伸び悩む時期が訪れますので、面倒でも毎回きちんと復習することを心がけましょう。
4ヶ月目に入ったら、共通テストに特化した対策を本格的に始めていきます。共通テスト化学実験と資料の考察問題24という参考書に取り組み始めましょう。共通テストでは実験の考察問題や資料を読み取る問題が頻出するため、この参考書で特有の思考法を身につけることができます。
同時に共通テスト実践模試化学にも着手して、実際の試験と同じ時間配分で問題を解く練習を重ねていきます。時間を計りながら問題を解き、解答スピードと正確性の両方を高めていくことが大切です。間違えた問題については必ず解説を読み込み、なぜ間違えたのかを分析する習慣をつけてください。
5ヶ月目は実戦的な演習を通じて得点力を高めながら、自分の弱点分野を集中的に補強していく時期です。化学の重要問題集などのやや難易度の高い問題集に取り組むことで、思考力を鍛えることができます。問題を解く時間と復習して理解する時間の配分は、3対7くらいを目安にすると効果的な学習ができます。
共通テストで9割を取るためには、苦手分野を徹底的になくしていくことが不可欠です。模擬試験や問題演習を通じて、自分がどの分野で間違いやすいのかを常に把握しておきましょう。1問を解いたら必ずその問題で問われている原理や考え方を完全に理解してから次に進むようにしましょう。
最終段階では共通テストの過去問演習を中心に据えて、本番を想定した実践的な訓練を行います。共通テストの過去問は少なくとも5年分、できれば10年分程度を解くことをおすすめします。本番と同じ時間配分で解くことで、時間管理の感覚を身につけることができます。
過去問演習を進める際には、分野ごとに自分の弱点を分析することが大切です。どの分野の問題で間違いやすいのかを記録しておき、間違いが多い分野については集中的に復習時間を確保します。試験直前期は新しいことに手を出すよりも、これまで使ってきた参考書や間違えた問題の復習に時間を使いましょう。
 共通テストの化学の超効率的な勉強法を解説!【大学受験】
共通テストの化学の超効率的な勉強法を解説!【大学受験】 実際にやってよかった化学の大学受験対策の勉強法3選
実際にやってよかった化学の大学受験対策の勉強法を3つ紹介します。
1つ目は間違えた問題を必ず講義本に戻って確認する勉強法です。
問題集を解いて間違えたらすぐに解説を読むだけでなく、鎌田シリーズや宇宙一わかりやすい高校化学などの講義系参考書でその分野全体を復習します。この方法により表面的な理解ではなく本質的な理解ができるようになり、類似問題にも対応できる力が身につきます。解く時間よりも理解する時間を多く取ることが化学の成績向上の秘訣です。
2つ目は苦手分析シートを作る方法です。
過去問や問題集を解く際に、どの分野で何回間違えたかを記録していきます。簡単に分野名を書いて間違えるたびに印をつけるだけで構いません。この作業により自分の苦手分野が客観的に把握でき、効率的な復習計画が立てられます。印が多くついた分野は重点的に時間を使って原理から学び直しましょう。
3つ目は毎日必ず化学に触れる習慣をつけることです。
化学は1日でも離れると計算力や知識の定着度が落ちてしまう科目です。忙しい日でも最低15分は化学の問題を解いたり講義本を読んだりする時間を確保しましょう。継続的に化学に触れることで知識が長期記憶として定着し、入試本番でも確実に力を発揮できるようになります。
分野別におすすめの大学受験対策の化学の勉強法
分野別におすすめの大学受験対策の化学の勉強法を解説します。
化学の計算問題の大学受験対策におすすめの勉強法
まず基礎的な計算力を身につけることから始めましょう。モル計算や濃度計算などの基本的な計算は化学のあらゆる分野で必要になります。化学計算問題の解き方などの専用問題集を使って、計算のパターンを体に染み込ませることが重要です。最初は時間がかかっても正確に解くことを優先し、慣れてきたらスピードを上げていきましょう。
次に計算問題を解く際の手順を固定化することが大切です。問題文から必要な情報を抜き出す、単位を揃える、有効数字を確認するなど、毎回同じ手順で解くことでミスを減らせます。特に入試本番では緊張してケアレスミスが起こりやすいので、普段の練習から丁寧に解く習慣をつけておくことが合格への近道です。
最後に難易度の高い計算問題にも挑戦しましょう。化学の重要問題集などを使って、複数の知識を組み合わせる複雑な計算問題に取り組みます。難しい問題でつまずいたら必ず基礎に戻って確認し、どの部分で躓いているのかを明確にすることが重要です。難問を解く力は一朝一夕では身につきませんが、諦めずに挑戦し続けることで確実に実力がついていきます。
化学の実験考察問題の大学受験対策におすすめの勉強法
実験考察問題は共通テストや私立大学で頻出の重要分野です。
まず基本的な実験操作や器具の使い方を正確に理解することが第一歩です。ガスバーナーの使い方、ろ過の手順、滴定の方法など、教科書や資料集に載っている基本的な実験手順を覚えましょう。これらの知識がないと実験考察問題の問題文自体が理解できなくなってしまいます。
次に実験結果からの考察力を養うことが重要です。グラフや表のデータから何が読み取れるか、なぜその結果になったのかを論理的に考える訓練が必要です。共通テスト化学実験・資料の考察問題24などの専用問題集を使って、データ分析の練習を重ねましょう。最初は解説を読んでも理解しにくいかもしれませんが、繰り返し練習することで確実に考察力が身につきます。
最後に実験の目的と原理を常に意識することが大切です。この実験で何を調べたいのか、なぜこの操作が必要なのかを考えながら問題を解く習慣をつけましょう。原理を理解していれば初見の実験問題でも対応できる応用力が養われます。講義系参考書の実験に関する記述も丁寧に読み込むことをおすすめします。
化学の論述問題の大学受験対策におすすめの勉強法
論述問題は国公立大学の二次試験で出題される重要な問題形式です。
まず化学用語を正確に理解し使えるようにすることが基本です。論述問題では専門用語を使って現象や原理を説明する必要があります。酸化還元反応、電離平衡、ルシャトリエの原理など、重要な用語とその定義を正確に覚えましょう。曖昧な理解のままでは採点者に伝わる答案は書けません。
次に答案の書き方を学ぶことが重要です。論述問題では結論から書く、理由を明確にする、専門用語を適切に使うなどのルールがあります。過去問の模範解答を何度も読んで、どのような構成で書かれているかを研究しましょう。自分で答案を書いたら学校の先生や塾の講師に添削してもらうことで、採点者に伝わる答案作成力が身につきます。
最後に論述問題の演習量を確保することが合格への鍵です。論述問題は読むだけでなく実際に書いてみないと力がつきません。週に最低3問は論述問題を解いて添削を受けるサイクルを作りましょう。最初は時間がかかっても構いません。継続的に練習することで徐々に短時間で質の高い答案が書けるようになり、入試本番でも自信を持って解答できるようになります。
大学受験対策のノートを使った化学の勉強法
結論から述べると化学のノート作りは基礎知識の整理と計算力向上に最も効果を発揮します。
化学のノートは大きく分けて理論化学、無機化学、有機化学の3分野に分けて作成するのがおすすめです。それぞれの分野で学んだ重要な反応式や計算方法、暗記事項を自分の言葉でまとめることで理解が深まります。特に理論化学では計算問題の解法パターンをノートに整理しておくと復習時に役立ちます。
ノート作りで最も重要なのは問題を解いて間違えた箇所を必ず記録することです。間違えた問題の横にどこで間違えたのか、なぜ間違えたのかを赤ペンで書き込むことで自分の弱点が明確になります。また無機化学の暗記事項は色分けしてまとめることで視覚的に記憶しやすくなります。
さらに化学のノートには講義本で学んだ原理や仕組みも書き写すことが大切です。単に公式を覚えるだけでなく、なぜその公式が成り立つのかという背景まで理解することで応用問題にも対応できる力が身につきます。定期的にノートを見返して知識の定着を確認しましょう。
志望校別におすすめの大学受験の化学の勉強法
志望校別におすすめの大学受験の化学の勉強法を解説します。
東大志望の大学受験生におすすめの化学の勉強法
結論として東大の化学で合格点を取るには原理の深い理解と計算力の両立が必須です。
東大の化学は単純な暗記では対応できない思考力を問う問題が多く出題されます。そのため最初の2ヶ月は講義本を使って化学の基礎となる原理をしっかり学ぶことが重要です。進学校に通っている受験生は鎌田シリーズや福間の無機化学の講義を使い、基礎問題集と並行して進めることで土台を固めます。
3ヶ月目からは応用レベルの問題集に取り組みながら間違えた問題は必ず講義本に戻って原理を確認します。東大の化学は実験考察問題が頻出なので、化学の新研究を辞書として活用しながら重要問題集レベルの演習を重ねることが効果的です。理解する時間を解く時間の2倍以上かけることで思考力が養われます。
6ヶ月目には過去問演習を始めて出題傾向を把握します。東大化学は時間配分も重要なので、本番と同じ時間で解く練習を繰り返しましょう。苦手分野を分析シートで管理して重点的に復習することで本番での得点力が高まります。
京大志望の大学受験生におすすめの化学の勉強法
結論として京大の化学は標準的な問題を確実に解く力と有機化学の深い理解が求められます。
京大の化学は東大ほど奇抜な問題は少なく、教科書レベルから標準レベルの問題が中心です。ただし有機化学の構造決定問題は複雑で時間がかかるため、有機化学に特に力を入れる必要があります。最初の2ヶ月で理論化学と無機化学の基礎を固めつつ、有機化学は反応機構まで丁寧に学びます。
3ヶ月目から4ヶ月目にかけては化学の全レベル問題集や基礎問題精講を使って標準問題の演習量を増やします。京大は計算ミスが命取りになるので、計算問題集を使って正確に素早く計算する訓練も欠かせません。間違えた問題は講義本で原理を確認して理解を深めます。
5ヶ月目には化学の重要問題集で応用力を鍛えます。京大の有機化学は構造決定だけでなく合成経路を問う問題も出るため、有機化学の反応パターンを整理しておくことが大切です。過去問演習では時間内に全問解ききる練習を重ねて本番に備えましょう。
早稲田大学志望の大学受験生におすすめの化学の勉強法
結論として早稲田の化学は学部によって難易度が異なるため志望学部の傾向把握が最優先です。
早稲田の理工学部や先進理工学部の化学は難易度が高く、教科書レベルを超えた知識も要求されます。一方で人間科学部や社会科学部は標準的な問題が中心なので、志望学部に合わせた対策が必要です。最初の2ヶ月は基礎固めに集中して、進学校でない受験生は宇宙一わかりやすい化学を使って理解を深めます。
3ヶ月目からは応用問題に取り組みながら、理工系学部志望者は4ヶ月目で化学の新研究を導入します。早稲田の理工系は細かい知識を問う問題が多いため、新研究レベルの詳しい解説が役立ちます。全レベル問題集の4や重要問題集で演習を重ねて応用力を養います。
5ヶ月目以降は過去問演習と苦手分野の克服に時間を使います。早稲田は学部ごとに出題傾向が大きく異なるので、志望学部の過去問を最低5年分は解いて傾向をつかみましょう。理論化学と有機化学の配点が高い傾向があるため、この2分野を重点的に仕上げることが合格への近道です。
慶應義塾大学志望の大学受験生におすすめの化学の勉強法
結論として慶應の化学は理工学部と薬学部で大きく難易度が異なり学部別対策が合格の鍵です。
慶應の理工学部の化学は標準から応用レベルの問題がバランスよく出題されます。薬学部は有機化学の比重が高く、医学部は生命科学に関連した化学が出題されることが特徴です。最初の2ヶ月は講義本と基礎問題集を使って化学の土台を作り、計算問題集で計算力も同時に鍛えます。
3ヶ月目から4ヶ月目は応用レベルの演習に移ります。薬学部志望者は特に有機化学に時間をかけて、反応機構や合成経路を徹底的に理解します。理工学部志望者は理論化学の計算問題と無機化学の知識問題をバランスよく学習して、化学の新研究で細かい知識も補強します。
5ヶ月目には重要問題集で実戦力を高めます。慶應は問題の難易度が年度によって変動するため、過去問演習では様々な難易度の問題に対応できる力を養います。6ヶ月目の過去問演習では時間配分を意識して、得点源となる分野を確実に得点する戦略を立てることが重要です。
化学の大学受験対策におすすめの参考書
化学の大学受験対策におすすめの参考書を紹介します。
宇宙一わかりやすい高校化学
化学が苦手な方や化学を初めて勉強する方のために作られた参考書が宇宙一わかりやすい高校化学です。理論化学編、無機化学編、有機化学編の3冊に分かれており、左ページに解説、右ページにイラストという見開き完結型の構成になっています。表紙は可愛らしいイラストで一見簡単そうに見えますが、高校化学で必要な内容を全て網羅しており大学入試対策にも十分活用できる本格的な参考書です。
化学の現象を擬人化やゴロで覚える工夫がされており、理屈抜きで暗記しなければならない部分も有意味暗記に変えることができます。別冊問題集も付属しているため、読んだ内容をすぐに演習で確認することが可能です。進学校に通っていない方や化学に苦手意識がある方は、この参考書から化学の勉強をスタートすることで共通テスト7割程度までスムーズに到達できるでしょう。
化学の新研究
東京大学や京都大学、東京工業大学などの超難関大学を目指す方のための化学の辞書的な存在となる参考書が化学の新研究です。
総ページ数775ページという圧倒的な情報量を誇り、高校化学で扱われる理論化学から無機化学、有機化学まで全範囲を網羅しています。化学のなぜそうなるのかという原理や仕組みを徹底的に解説しており、教科書では触れられない応用的な内容まで詳しく学ぶことができます。
この参考書は辞書のように使うことが前提となっており、1ページ目から順番に読み進めていくものではありません。問題集を解いていて分からない部分が出てきたときや、より深い理解が必要なときに該当箇所を調べて使うのが正しい活用方法です。早慶以上の難関大学を目指す受験生は、化学の重要問題集などの問題集を解きながら化学の新研究で原理や仕組みを確認するというサイクルを繰り返すことで実力を伸ばすことができます。
化学共通テスト実験・資料の考察問題24
共通テスト化学で出題が増えている思考型問題に特化した対策問題集が化学共通テスト実験・資料の考察問題24です。共通テスト化学では長めの文章から条件を読み解く問題やグラフをかいて考える問題など、単純な知識だけでは解けない思考力を試す問題が多く出題されるようになっています。この問題集には共通テスト試行調査の分析結果をもとに作成されたオリジナルの思考型問題が24題収録されており、実践的な演習を積むことができます。
これまでに覚えた化学の知識と実験や資料から読み取れる情報を掛け合わせることで、共通テスト特有の読解力や思考力を養うことができる構成になっています。共通テスト対策のみで化学が必要という方は、化学の基礎固めが終わった段階でこの問題集に取り組むことをおすすめします。問題数も適度で取り組みやすく、共通テスト化学の実験考察問題で満点を取りたい方に最適な一冊となっています。
鎌田の理論化学、有機化学の講義と福間の無機化学の講義

進学校に通っている方や化学の基礎を効率よく固めたい方に最適なのが大学受験Doシリーズの鎌田の理論化学の講義、鎌田の有機化学の講義、福間の無機化学の講義の3冊セットです。
多くの受験生が解けない原因になっている見落としがちで重要な事柄を丁寧に説明しているため、解けない原因を根本的に解決できる構成になっています。
特に福間の無機化学の講義は、他の参考書にはない観点から無機化学を解説しており暗記量を大幅に減少させることができる点が大きな魅力です。各参考書には入試で使える最重要ポイント総整理という別冊まとめが付属しており、赤セルシート対応で暗記にも便利です。この3冊をしっかり仕上げれば、マーチレベルの大学には十分対応できる実力が身につきます。
期間別におすすめの大学受験対策の化学の勉強法
期間別におすすめの大学受験対策の化学の勉強法を解説します。
夏休みにおすすめの大学受験対策の化学の勉強法
夏休みは化学の基礎固めと応用力を養う絶好の機会です。この時期は1日2時間から3時間程度の学習時間を確保し、理論化学・無機化学・有機化学の3分野をバランスよく進めることが必要です。
進学校に在籍している受験生は、鎌田の理論化学の講義や福間の無機化学の講義などの講義系参考書を読み込みながら、リードライトノート化学で演習を重ねることで基礎レベルの問題を完全に理解できます。
一方で進学校以外の高校に通う受験生は、宇宙一わかりやすい高校化学シリーズを活用することで、丁寧な説明から化学の本質を理解できるようになります。
夏休み期間中は特に計算力の強化が重要となるため、問題集を1周終えた段階で化学計算問題の解き方を使って計算スピードと正確性を高めていくことをおすすめします。
また間違えた問題については必ず講義本に戻り、なぜその答えになるのかという原理を徹底的に確認する習慣をつけることで、秋以降の成績向上につながります。
冬休みにおすすめの大学受験対策の化学の勉強法
冬休みは共通テスト直前期であり、実戦演習と弱点克服に集中する時期です。
共通テスト対策が必要な受験生は、共通テスト化学実験や資料の考察問題24を活用して、共通テスト特有の問題形式に慣れることが合格点獲得の鍵となります。
過去問演習を進める際には、時間配分を意識しながら本番と同じ条件で解くことで実戦力が身につきます。
難関私立大学や国立大学の二次試験で化学が必要な受験生は、冬休み期間中に志望校の過去問演習を本格的に開始します。
化学の重要問題集などの応用レベルの問題集を使用しながら、間違えた問題については化学の新研究などの詳しい参考書で原理を確認することが重要です。
また分野別に苦手分析を行い、どの分野で間違いが多いかを記録しておくことで、残りの期間で優先的に対策すべき内容が明確になります。
定期テスト対策におすすめの化学の勉強法
定期テスト対策におすすめの化学の勉強法を解説します。
まずは問題を実際に解いてみて、間違えるたびに教科書に戻ってじっくりと内容を読み込んでいくことから学習をスタートさせましょう。なぜこの化学反応が発生するのか、なぜこの計算公式を用いるのか、その意味や理由を考えながら読み進めていくことが後々の得点アップにつながっていきます。
教科書だけでは理解しにくい部分は、宇宙一わかりやすい高校化学を使ってていねいに補強していきます。この参考書は理論化学と無機化学と有機化学の原理について、図解や講義のような口調で徹底的に解説してくれるため、暗記ではなく理解に基づいた学習を実践できます。
理論化学ではモル計算や化学反応式の意味、無機化学では反応条件や例外的なケース、有機化学では反応経路や構造式の変化を、図や解説を使って整理することができます。この時期から元素記号や化学式、化学反応式などの暗記作業も並行して始めておいてください。
短い時間でも大丈夫ですので、毎日同じ範囲を3日間連続で繰り返すことによって、記憶がしっかりと頭の中に定着していきます。問題集についてはこの段階で1周目に取りかかり、間違えた問題には必ずチェックをつけておき、講義本で確認しながら復習を進めていきます。
定期テスト1週間前になったら、本格的に演習問題を解いていく期間に入ります。この時点で定期テストの化学を解いたときに7割程度は正解できる状態を作っておくことが、9割突破を実現するための大きな鍵になってきます。
問題集の1周目を完全に終わらせて、間違えた問題を中心にもう一度解き直していきましょう。セミナー化学や学校で配布されている問題集を使って、繰り返し問題を解いていくことで解答パターンを体に覚え込ませていきます。
理論化学の計算問題では途中の式をていねいに書き、無機化学では図表や語呂合わせを活用し、有機化学では反応経路を線で整理していくことを意識してください。ここで重要なのがまとめノートの作成です。
自分の言葉で要点をまとめたノートを作成して、化学反応式や重要な語句を赤ペンで書き込んでおき、赤シートで隠しながら暗記のチェックを繰り返していきます。通学時間や休み時間にも確認できるよう暗記カードを作っておくと、短い時間でも高い定着率を実現できます。
化学の定期テスト直前の対策としては、演習を通じて学んだ知識を完璧に使いこなせる状態にしていく総仕上げの段階に入ります。間違えた問題を集中的に解き直していき、問題集は2周目から3周目へと進めていきましょう。
2周目以降は印をつけた問題を中心に繰り返し解いていき、なぜ間違えたのかという理由を講義本で確認していきます。理論化学では計算の手順、有機化学では構造式の書き方、無機化学では図表を見ながら声に出して読んでいく方法が非常に効果的です。
特に理論化学の計算問題、有機化学の反応経路、無機化学の色や沈殿など、定期テストでよく出題されるパターンを何度も繰り返していくことが得点の安定につながります。まとめノートを読みながら自分で説明できるかチェックし、説明できない部分があれば重点的に復習を行っていきます。
計算問題は途中式を省略せずに書く練習を繰り返して、本番で焦らず確実に解けるようにしておきましょう。問題を解く際には必ず時間を測って、本番と同じような緊張感の中で取り組んでいくことをおすすめします。
 定期テストの化学のおすすめの勉強法を徹底解説!
定期テストの化学のおすすめの勉強法を徹底解説! 学年別に高校生におすすめの化学の勉強法
学年別に高校生におすすめの化学の勉強法を解説します。
高校3年生におすすめの化学の勉強法
高校3年生は受験本番に向けて、基礎の確認から応用問題への対応力強化まで総合的な学力向上が求められます。
春から夏にかけては化学の基礎問題精講や化学の全レベル問題集3を使用して、頻出問題のパターンを徹底的に身につけることが大切です。
問題を解く際には単に答えを覚えるのではなく、なぜその解法を使うのかという理由まで説明できるレベルを目指します。
秋以降は志望校のレベルに応じて学習内容を調整することが必要です。
早慶以上の難関大学を目指す受験生は、化学の新研究を辞書として活用しながら化学の重要問題集に取り組み、細かい知識や難問への対応力を養います。
一方で共通テストのみで化学を使用する受験生は、共通テスト対策に特化した問題集を繰り返し解くことで高得点を狙えます。
高校2年生におすすめの化学の勉強法
高校2年生は化学基礎から化学への移行期であり、理論化学・無機化学・有機化学の全分野を学習する重要な時期です。
学校の授業進度に合わせて講義系参考書を読み込み、セミナー化学やリードライトノート化学などの学校傍用問題集を確実に理解することが基本となります。
この時期に化学の土台をしっかり固めておくことで、高校3年生になってからの受験勉強がスムーズに進みます。
また高校2年生のうちから計算問題への対応力を高めておくことも重要です。
化学計算問題の解き方などの計算特化型の参考書を使用して、モル計算や化学平衡の計算問題を素早く正確に解けるように練習します。
定期テストごとに間違えた問題をノートにまとめ、なぜ間違えたのかを分析する習慣をつけることで、自分の弱点を把握しながら効率的に学習を進めることができます。
高校1年生におすすめの化学の勉強法
高校1年生はまず化学基礎をしっかりマスターすることが最優先です。
化学基礎では物質の構成や化学反応、酸と塩基など、今後の化学学習の土台となる重要な概念を学びます。
宇宙一わかりやすい高校化学基礎や理解しやすい化学基礎などの丁寧な解説がある参考書を使用して、一つ一つの概念を確実に理解することが大切です。
学校の授業で理解できなかった部分は、その日のうちに参考書を使って復習する習慣をつけることで、わからない部分を積み残さずに進めることができます。
また化学基礎の計算問題は、後の化学での計算問題の基礎となるため、モル計算や濃度計算を完璧にマスターしておくことが重要です。
定期テストで高得点を取ることを目標にしながら、基礎知識を着実に積み上げていくことで、高校2年生以降の学習がスムーズになります。
まとめ
今回は、大学受験における化学の勉強法について期間別と学年別に解説しました。
化学の勉強法についてのまとめは以下のようになります。
| ▽化学のおすすめの勉強法はこちら |
| 共通テストの化学のおすすめの勉強法 |
| 定期テスト対策におすすめの化学の勉強法 |
| 化学のおすすめの勉強法を東大生が徹底解説【大学受験】 |
| ▽化学のおすすめの参考書はこちら |
| 化学のおすすめの参考書ランキング11選を東大生が解説!【大学受験】 |
| 化学の一問一答のおすすめランキングと使い方を徹底解説!共通テスト対策! |
| ▽おすすめの化学の参考書の使い方やレベルが知りたい方はこちら |
| 化学の良問問題集の使い方とレベル【参考書解説】 |
| 化学の新演習の使い方とレベル【参考書解説】 |
| 化学の重要問題集の使い方とレベル【参考書解説】 |
| セミナー化学の使い方とレベル【参考書解説】 |