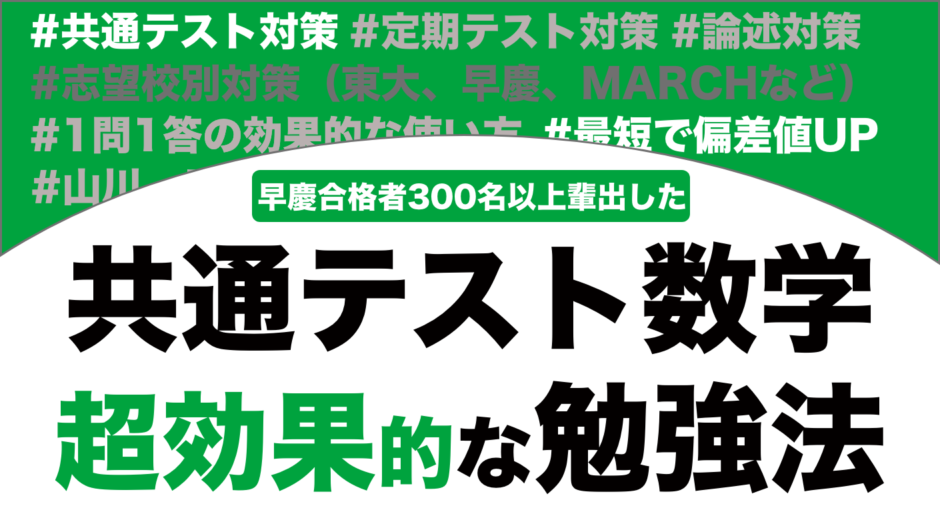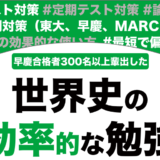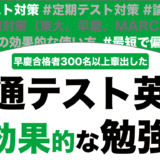本サイトの表記には、一部プロモーションを含みます
共通テスト数学の得点アップに役立つ学習法を徹底解説します。
共通テスト数学で8割を目指すための効率的な勉強法から、短期間で高得点を取るための実践的な学習法を紹介します。
さらに、共通テスト数学で満点を狙うための学習戦略や、文系・理系それぞれに最適な勉強法もあわせて解説します。

【この記事の監修者:逆転合格特化塾塾長「竹本明弘」
これまで早慶に現役生および浪人生を含めて合計で300人以上合格者を輩出してきました。その中で数学で共通テスト9割や東大や京大への合格者もおり、実際に指導する中でゼロからでも共通テスト9割まで到達した数学の共通テスト対策の勉強法や使ってよかった参考書およびおすすめの数学の勉強の順番を解説したいと思います。
共通テストの数学で9割取れる勉強法
共通テストの数学で9割が取れる勉強法を解説します。
短期間で共通テストの数学で9割を達成するための勉強法になっているので、ぜひ参考にしてみてください。
共通テスト数学で高得点を取るためには、まず教科書レベルの基礎を徹底的に理解することが最優先です。最初の1ヶ月は、全範囲をざっと通して「なぜその解法になるのか」を理解することを重視しましょう。使用する参考書は「はじめからはじめる数学1・A・2・B」(東進ブックス)または「入門問題精講」(旺文社)です。数学が苦手な人は、映像授業で理解を深めるのが効果的です。Try ITやスタディサプリなどを活用し、わからない単元はすぐに補強します。この期間の目標は「基礎レベルの例題を読めば理解できる状態」にすることです。
共通テスト数学は「典型問題を素早く正確に処理できる力」が問われます。2ヶ月目は「基礎問題精講」(旺文社)や「黄色チャート」(数研出版)を使い、各単元の基本問題を繰り返し解いていきましょう。勉強法としては、1日あたり2時間のうち30分を解法の復習に充て、残り90分を問題演習に使うのが理想です。特に間違えた問題には印をつけ、2回目・3回目の演習で確実に正答できるようにします。共通テスト数学の問題は、スピードと正確さの両方が要求されるため、解法を理解するだけでなく「自力で再現できる」ことが必須です。
この時期からは、共通テスト本番を意識した時間配分の練習を始めます。「Focus Gold数学ⅠAⅡB」(啓林館)や「基礎問題精講」を活用し、特に苦手な単元(確率・数列・ベクトルなど)を優先的に潰していきましょう。勉強法のコツは「1問を丁寧に解き、なぜそう解けるのかを自分の言葉で説明できるようにすること」です。さらに、共通テスト数学は誘導型問題が多いため、設問文を丁寧に読み取る練習も重要です。時間を計って演習を行い、80分の試験時間の中でどこに時間をかけるべきか感覚をつかみましょう。
4ヶ月目は、共通テストの過去問演習を中心に進めます。「共通テスト過去問研究 数学ⅠA・ⅡB」(河合塾シリーズ)を使用し、年度ごとに通しで解いてください。勉強法としては、1日90分のうち60分で演習、30分で解説確認を行い、間違えた問題の原因を分析します。共通テストは知識よりも「処理力」と「パターン認識」が重要なため、同じミスを二度と繰り返さない意識を持ちましょう。得点戦略としては、難問に固執せず「確実に取れる問題を落とさない」ことが9割達成の鍵です。問題ごとの難易度を見極める力もこの時期に養います。
最終月は、共通テスト本番を想定した実戦演習を中心に行います。「共通テスト実戦模試 数学ⅠA・ⅡB」(Z会)や「共通テスト総合問題集」(駿台文庫)を活用して、実際の試験と同じ80分で解く練習を繰り返します。勉強法のポイントは「本番環境の再現」と「復習の徹底」です。間違えた問題は、原因を分類し、計算ミス・時間不足・理解不足のどれかを明確にしましょう。特に本番直前は、共通テスト頻出のテーマ(整数・確率・数列・ベクトル)を優先的に復習します。最終的には、「本番でいつも通りの力を出せる状態」に仕上げることが目標です。

共通テストの数学で満点を取るためにおすすめの勉強法
共通テストの数学で満点が取れる勉強法を3つ紹介します。
共通テスト数学で満点が取れる勉強法①基礎レベルの解法暗記
共通テスト数学で満点を狙うためには、まず全範囲の「解法の理由」を理解しておくことが不可欠です。最初の2ヶ月は、教科書レベルの基礎を確実に固め、なぜその式変形になるのか、なぜその考え方が正しいのかを論理的に説明できる状態を目指しましょう。使用する参考書は「はじめからはじめる数学Ⅰ・A・Ⅱ・B」(東進ブックス)または「入門問題精講」(旺文社)がおすすめです。
特に数学が苦手な人は、Try ITやスタディサプリなどの映像授業を活用し、つまずいた単元を即座に補強します。この時期は、基礎例題をすべて理解し、教科書レベルの問題なら確実に正答できる状態を完成させることが満点への第一歩です。
共通テスト数学で満点が取れる勉強法②典型問題の完全習得とスピード強化
3ヶ月目は、共通テスト数学特有の「誘導型・処理型」問題に対応できる力を養います。使用するのは「基礎問題精講」(旺文社)や「黄色チャート」(数研出版)です。各単元の典型問題を繰り返し演習し、最短手順で正答にたどり着けるように訓練します。共通テストではスピードと正確さの両立が重要なため、1問あたりの処理時間を意識しながら、毎回の演習で制限時間を設けて解く練習を行いましょう。
苦手分野(確率・数列・ベクトルなど)は「Focus Gold数学ⅠAⅡB」(啓林館)を使って深掘りし、どの形式の問題にも対応できる柔軟な解法を身につけます。
共通テスト数学で満点が取れる勉強法②過去問と模試による実戦最終調整
共通テスト数学で満点を取るための「本番力」を仕上げる総仕上げの時期です。使用する参考書は「共通テスト過去問研究 数学ⅠA・ⅡB」(河合塾シリーズ)、「共通テスト実戦模試 数学ⅠA・ⅡB」(Z会)、「共通テスト総合問題集」(駿台文庫)の3冊です。
過去5年分の問題を年度ごとに通しで解き、80分という制限時間内で得点を最大化する感覚を身につけましょう。
共通テスト数学の過去問演習後は必ず解説を丁寧に読み込み、間違えた原因を「理解不足」「読取ミス」「計算ミス」に分類し、原因ごとに再演習して弱点を潰します。共通テスト数学で満点を取るには、難問に固執するのではなく、確実に取れる問題を一問も落とさないことが最重要です。
文系におすすめの共通テスト数学の勉強法
文系の共通テスト数学では、数学ⅠAの基礎定着と典型問題の処理力が最優先です。まずは「はじめからはじめる数学ⅠA」(東進ブックス)で、解法の理由を理解しながら全範囲を1周します。
その後、「基礎問題精講数学」(旺文社)を使って、頻出の典型問題を何度も解き、スピードと正確さを両立させましょう。
特に、数と式・二次関数・データの分析・確率は得点源です。共通テストでは誘導に従って計算を進める問題が多いため、「設問文の読み取り」と「条件整理の手順」をパターン化することが得点アップの鍵です。
仕上げに「共通テスト過去問研究 数学ⅠA」(河合塾シリーズ)を使い、時間内に80点以上を安定して取れる演習力を養いましょう。
▽文系数学の参考書ルートが知りたい方はこちら
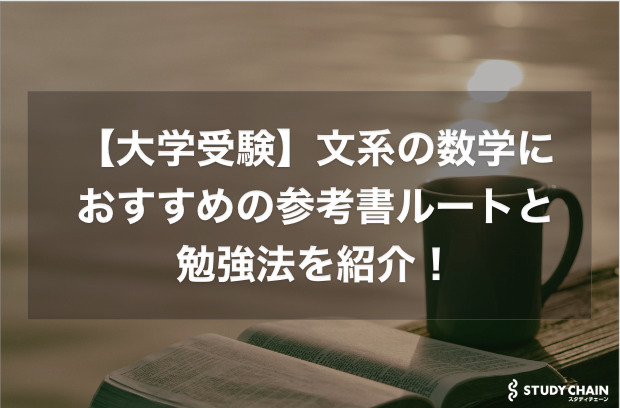 【大学受験】文系の数学におすすめの参考書ルートと進め方を徹底解説!
【大学受験】文系の数学におすすめの参考書ルートと進め方を徹底解説! 理系におすすめの共通テスト数学の勉強法
理系の共通テスト数学では、共通テスト対策で終わらない人がほとんどだからこそ、数学ⅠA・ⅡBの全範囲を高精度で処理できる力を追求することをおすすめします。
まずは「入門問題精講数学」(旺文社)や「青チャート」(数研出版)を使い、基礎~標準レベルの典型問題を徹底的に解き込みます。
解法を「理解」だけでなく「再現」できるようにするのが重要です。その後、「Focus Gold数学ⅠAⅡB」(啓林館)で苦手単元(数列・ベクトル・微積・確率)を集中的に演習し、スピードを意識した解答練習を行いましょう。
数学の過去問演習には「共通テスト実戦模試 数学ⅠA・ⅡB」(Z会)を使用し、本番と同じ80分で解く訓練を重ねることが満点への近道です。特に時間配分を意識し、「取れる問題から確実に取る」得点戦略を身につければ、9割〜満点も十分狙えます。
| ▽おすすめの数学の勉強法をもっと知りたい方はこちら |
| 定期テスト対策におすすめの数学の勉強法 |
| 【大学受験】数学の超効率的な勉強法を徹底解説! |
| 大学受験向け数学のおすすめの勉強法 |
共通テスト数学で8割を取るためにおすすめの勉強法と参考書一覧
共通テスト数学で8割取るためには徹底した数学の解法暗記と共通テスト数学の解き方をマスターすることの2つが非常に重要です。
共通テストの数学対策に実際に使ってよかった数学の参考書も合わせて紹介するのでぜひ参考にしてみてください。
最初の二ヶ月は共通テスト数学 集中講義シリーズ(旺文社)で全範囲を一通り学び、なぜその式変形になるのか、なぜその解法を選ぶのかを理解することを意識します。学習後はきめる!共通テスト数学(学研プラス)を使い、同じ範囲を復習しながら要点を整理します。公式や定義をただ覚えるのではなく、条件と結果のつながりを自分の言葉で説明できるようにすることが大切です。この時期に基礎の考え方を固めておくことで、後の誘導型問題にも対応できるようになります。
三ヶ月目から四ヶ月目は数学I・A 緑チャート(数研出版)で典型問題を繰り返し解き、考え方と処理手順を体に覚えさせます。特に数と式、二次関数、データの分析、確率、整数の五分野を中心に毎日演習を積み重ねます。前半三十分で復習、後半九十分で演習を行い、間違えた問題には印をつけて数日後に解き直す習慣をつけましょう。きめる!共通テスト数学(学研プラス)を使って重要公式や頻出テーマを短時間で確認し、どの分野も解法をすぐに思い出せる状態にします。
最後の一ヶ月はきめる!共通テスト数学(学研プラス)と共通テスト数学 集中講義シリーズ(旺文社)の実戦問題を使い、八十分の本番形式で過去問演習を繰り返します。解いた後は間違えた原因を理解不足、読取ミス、計算ミスに分類し、同じ失敗を防ぐための復習を徹底します。時間配分を意識して、取れる問題を確実に取りきる得点戦略を身につけましょう。直前期は数学I・A 緑チャート(数研出版)で苦手分野を重点的に復習し、試験本番で安定して八割を超えられる実力に仕上げます。
▽数学1・Aのおすすめの参考書一覧

▽数学2・Bのおすすめの参考書一覧

▽数学3・Cのおすすめの参考書一覧

▽数学のおすすめの参考書ルート

▽共通テスト対策のおすすめの勉強法一覧