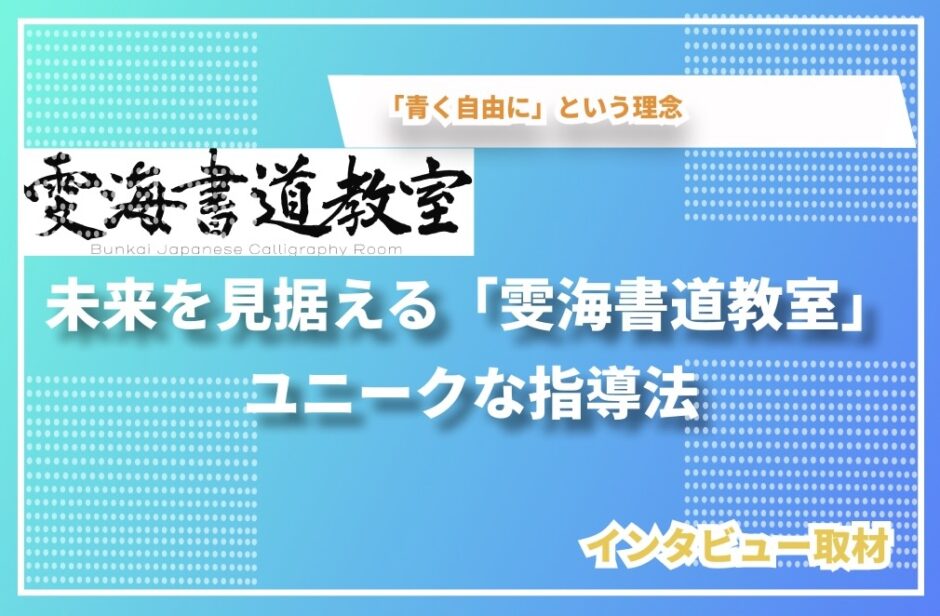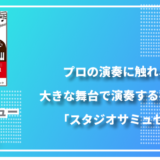雯海書道教室は、通常の技術指導にとどまらない独自のアプローチで注目を集めています。「青く自由に」という理念のもと、子どもたちの自発性とコミュニケーション能力を重視した指導を行い、地域コミュニティの中心としての役割も担っています。未来の教育環境の変化を見据えた服部氏の教育観に迫ります。

子どもの自由な表現を大切にする書道教室
ー教室ではどういった方を対象に、どのような指導を行っているのか、教室の概要について教えてください!
小学校に入学する前の6歳ぐらいから高校生を対象に子供の書道教室をやっています。埼玉県川越市でやっていて、普通の書道教室は基本的に入塾したら段級取得といって、教科書を買って作品を提出して級から始まって段を取っていくって感じなんですけど、うちもそれはやってるんですけど、それと同時にそれをしなくてもいいよっていう風にどっちでも出来るようにしています。資格を取るかどうかは本人に判断を委ねていて、強制ではないっていうところです。
あと、書道教室って地域コミュニティの中心になりえるなと思って、もう少しで4年になるんですけど開校して最初の年からずっと春にお花見をしたり、夏にバーベキューしたり、遠足的な感じで休日に美術館に行ったりとか、そういう活動もしてました。
書道教室開校のきっかけ
ー書道教室を始められた経緯やきっかけについて教えてください!
僕は高校1年生までずっと書道を習ってたんですけど、その後専門学校に通って映像とかを習っていました。ただ、社会人になってから再び習い始めて、師匠の元で学んでいる内に、書道教室ってもっとこういうこと出来るんじゃないかとか、そういう風な想像が働いてきまして、そこで資格を取ってから、たまたま知り合いに場所を貸してくださる人がいたので、開講してみたっていう感じですね。
会話とコミュニケーションを重視した独自のアプローチ
ー他の教室にはない特徴や、教室としての1番のアピールポイントについて教えてください!
書道教室で言うと、黙々と机に向かって紙に向かってやるようなイメージであるんですけど、とにかく喋らないことが結構基本になってくるんですけど、うちの書道教室は子供だけっていうのもあって、やっぱり子供同士での会話だったりとか、コミュニケーションが活発になりやすいんですね。それは時として盛り上がり過ぎて他の子供に迷惑あったりもするんですけど、僕はそれは盛り上がり過ぎなければ良いっていう方針で、とにかく私からは子供達に結構質問をするんですね。
もちろん休み時間のことだったり学校のことだったりとかも聞くし、それと繋げて書道のことについても「なんでこういう風に書いたの?」とか「これとこれどっちが自分では上手いと思う?」とか「失敗したところはどこ?」とか、いう風に会話を結構するんですね。自分から発信、何て言うんでしょう、自分から意見を述べられたりとか、自分から表現する力を養いたいと思っています。
子供のみにしてるのは、やっぱり大人が入ってくると、子供のそういう部分っていうのは結構隠されちゃって、敢えて子供だけにすることによって、その自発的な子供の表現を促していくっていう感じです。それが他の書道教室と違うかなとは思います。
「青く自由に」という教室の理念
ー現在受講されている方を指導する際に、特に意識していることや、教室全体としての方針があれば教えてください!
とにかく自分で自分のするべきこと、することしたいことを決めさせるっていうことをしています。この低学年の子に結構聞くんですが、「どっちの作品が自分では良いと思う?それを1つ提出しましょう」といった時に、「どっちでも良い」とか「同じ」とか、そういう風に答えちゃう子って結構いるんですね。
でも、実は探っていくと、こっちの作品よりもこっちの作品の方がいい部分があったりとか、2つ作品があったら「こっちのここの部分は特に失敗した」と思うとか、あと名前だったら「名前はこっちの方が上手く書けた」とか、結構探っていくとそういうところが見つかります。とにかく自分で決めさせるっていうことを結構意識的にやっていますね。
教室の大きな目標として、「青く自由に」という言葉を掲げています。「青く」っていうのは未熟さですよね。未熟さを自分で認めつつ、「自由に」っていうのは、自分で自分のことを決めていきましょうっていうことを大切に伝えています。
子どもたちに合わせた柔軟なプラン
ー現在提供されているコースやプランがあれば教えてください!
通常の教室では子供クラスって言うんですけど、小学校から高校生までで、別にクラスはその学年がどうとかいってクラスを変えてるわけじゃなくて、単純に通いたい時間に来てもらうっていう感じで、その価格とかもどの学年も一緒ですし、そういった面では、クラスは時間だけで変えてないかなと思います。
でも、夏休みとか冬休みに学校から出される特別な課題があって、そういうのをやっていいよっていう機会を作ってるんですね。夏休みと冬休みにそれは単発クラスみたいな感じで、書道教室に普段通ってない子供も参加できるように門戸を広げて地域の人に来てもらうって感じです。
教育環境の変化を見据えた今後の展望
ー今後こういった点をより強化していきたいことや、新しく進めていきたい取り組みがあれば教えてください!
子供の為の書道教室っていうのを変えないんですね。それはなぜかっていうと、1番は僕の問題かもしれないですね。もちろんどんなビジネスもそうですけど、やっぱり頭の容量を使う。子供に対しても、実は脳のリソースをすごい使っちゃう。僕はそういうタイプでして、どっちかに絞らないと、結構頭いっぱいいっぱいになっちゃうなっていう感じもして、一度大人クラスも作ったんですけど、あんまり上手くいかなかった時期がありまして、疲れちゃったので、やっぱり子供1本にしていこうという風にしています。
子供の教育の場っていうのはかなり大きく変わっていくかなっていう風には自分も思ってまして、小学校中学校のあり方もそうですよ。やっぱり大きいのは、中学校の部活が無くなるっていうことですね。その点でやっぱり学校と生徒の付き合い方っていうか、関係がやっぱ変わっていくなっていう風に感じていて、そこで1つの第2の学校として役割を果たしてるなとは思ってるんですね。
書道教室に通うきっかけはそれぞれ目的が実は違って、最初はやっぱり字が上手くなりたいとかいう風な同じようなことを言うんですけど、習っていく内に友達に会いに来たっていう目的になっちゃう子もいれば、習い事続けてること自体が価値で別にそんなに上手くななくてもいいと思ってる子もいれば、あとやっぱり普通に段級を自分のレベルを上げていって資格を取りたいという子もいれば、学校の展覧会で選ばれたいっていう高い目標の子もいて、そういういろんな子を集めているコミュニティとして、子どもたちとのコミュニケーションがメインだと自分では思っています。
実はその字を上手くさせることも大事なんですけど、それよりも僕の中で上に置いてるのが、コミュニケーション。そのコミュニケーションの種となるのが、言葉であり文章であり文字であり、結局すべて繋がってると思うんですよね。
そのコミュニケーションを養うつもりで言うと、P4Cって知ってますか?P4Cというのは、アメリカでやっている哲学を皆で話し合うっていうものなんですけど、要は1つの議題について、それぞれが何人か集まって話すんですけど、それぞれが自分の意見を持って発表し合うっていう場で、子供達集めて何か課題を皆で解決したりとか、互いの意見を聞き合うような機会を設けて、そういう場面って結構意外に学校ではなかったりもするので、そういう学校にも無いような機会を月1回でもいいから、作っていきたいなとは思っています。
これから書道を始める方へのメッセージ
ー今後、受講を考えられている生徒さんや保護者の方々に何かお伝えしたいメッセージがあればお願いします!
きっかけは結構何でもいいと思っています。習い事をするとか、勉強するとか、何か目標を見つけて達成しようとするとか。親御さんで多いのが、親御さん自身のコンプレックスで迷っているということですね。問題というか、皆さん仕方ないとは思うんですけど、教育方針が揺らいでしまうっていうことは。ただ、もっと親御さんには自信を持ってほしい。
僕は子供達に自分自身で決めなさいって結構言っていて、自分自身で決めたことは結構達成しやすい。モチベーションが続きやすいとは思ってるんですね。でも、書道教室に通い始めって、子供自身が文字が上手くなりたいはもちろんあるんですけど、もう1つあるのが、親御さんが習わせたいとか、子供の字が汚いと思ったから、書道教室でやってほしいと思って習わせに来ましたみたいな。
一見、それって親に決めさせられてるじゃんみたいに思うんですけど、僕はそこは別に悪くないと思って、少なからず、どんな人も「理由はわからないけど連れてこられた」経験はあるなとは思うんですね。始まりは単なるきっかけであって、少なからず、どの過程もあるなとは思うんですね。一言で言うと、きっかけは何でもいい。理由は何でもいいからとにかく始めてみるっていうことですね。始めることによって、また続けることによって、何かが変わっていくはずで、それを見つめてゆっくり育てていきましょうっていうことを伝えていきたいです。