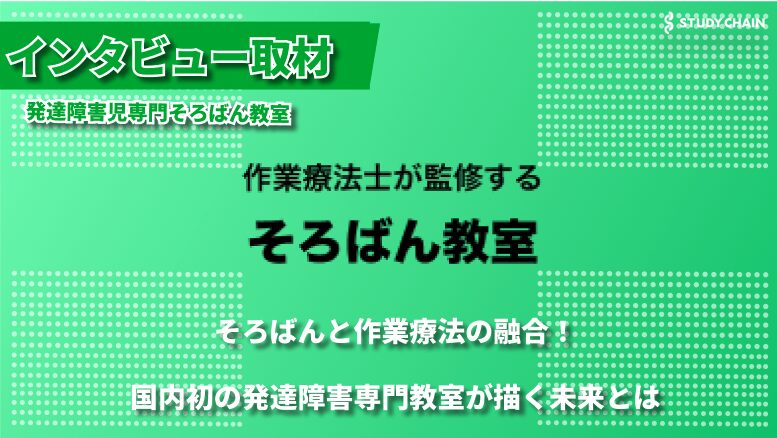発達障害のあるお子様に向けた専門的なそろばん教室が、2025年6月に開校します。通常のそろばん学習に加え、作業療法士による専門的なケアを取り入れた独自のカリキュラムを提供。
五感を活かした学習方法で、お子様の感覚統合の改善を目指します。算数教室15年の実績を持つ運営母体が、教育の新たな可能性に挑戦します。今回は代表の宮本さんに特徴や今後の展望等についてインタビューしました。

サービス概要
ー発達障害専門そろばん教室について、どのようなサービスを提供されているのか教えてください。
宮本さん:発達障害のお子様向けに、そろばんと作業療法を組み合わせた独自のカリキュラムを提供しています。週1回60分のレッスンで、そろばんの指導と作業療法士による専門的なケアを1対1で行います。通常のそろばん教室とは異なり、五感を活用した学習方法を取り入れ、感覚統合の改善を目指します。
設立の経緯
ー教室設立のきっかけについて教えてください。
宮本さん:もともと算数教室を15年ほど運営していました。その後、母のパーキンソン病の介護を通じて医療関係者との繋がりができ、自費リハビリのマッチングサイトを立ち上げたのですが、その過程で作業療法士との対話を重ね、発達障害のお子様向けのそろばん教室の必要性を感じました。
日本には発達障害に特化したそろばん教室が少ないのが実情です。またこれまでの50年間の指導経験から、発達障害のお子様を持つご家庭からのニーズも多くありました。そこで、作業療法士と協力して、新しい形の教室を立ち上げることを決意しました。
特徴とアピールポイント
ー記事を読む方に向けて、主なアピールポイントを教えてください。
宮本さん:大きく3つのポイントがあります。
- 日本で前例のない取り組みであること
- 独自のカリキュラムと教材を用意していること
- 五感を生かした学習方法を採用していること
発達障害のお子様の場合、例えばADHDの方は激しい貧乏ゆすりが1日中止まらないなど、頭で考えていることと体で感じていることに乖離があります。そのため、目で見る、耳で聞く、触るといった感覚と、頭で認識・思考する部分をうまく統合できるよう支援していきます。
そういった意味でそろばんは五感を活用した計算の取り組みとして非常に効果的です。
さらに、一般的なそろばん教室では指導者1人に対して30人程度の生徒を教えるのが一般的ですが、当教室では必ず1対1での指導を行います。そろばんの講師と作業療法士の2名体制で、お子様一人ひとりに寄り添った指導を実現しています。
オンライン指導も予定しており、これは発達障害のお子様にとって大きなメリットになると考えています。慣れ親しんだ自宅という環境で、ご両親と一緒にレッスンを受けられることで、より効果的な学習が期待できます。
入会時には作業療法士による評価を実施し、お子様の特性に合わせて適切なカリキュラムと教材を選定します。例えば多動性が強い場合と、落ち着きがある場合では、まったく異なるアプローチが必要になります。これは50年のそろばん教室運営の経験と、作業療法の専門知識を組み合わせることで実現できる、独自の強みです。

指導方針と特徴的な取り組み
ーレッスンの具体的な内容について教えてください。
宮本さん:60分のレッスンは、そろばん学習と作業療法を組み合わせた構成になっています。例えば、30分をそろばん、15分を作業療法的なアプローチ、残りの15分を指先を使った算数の取り組みというように、お子様の状態に応じて柔軟に時間配分を調整します。
入会時には作業療法士による評価を行い、お子様一人ひとりの特性に合わせたカリキュラムを作成します。例えば、コンパスを使って花びらを描くような課題は、算数の学習でありながら、作業療法的な効果も期待できます。
コースと料金体系
ー料金体系について教えてください。
宮本さん:週1回60分のレッスンで月額27,000円となっています。一般的なそろばん教室と比べると高額ですが、作業療法士による専門的な評価とケア、1対1での指導、独自のカリキュラムと教材が含まれています。
今後のビジョン
ー今後の展開について教えてください。
宮本さん:まずは三鷹市や千葉市からスタートし、将来的には日本全国での展開を目指しています。また、オンラインでの指導も予定しています。発達障害のお子様の場合、慣れた環境でご家族と一緒に学べるというオンラインならではのメリットがあると考えています。
読者へのメッセージ
ー最後に、記事を読んでいる方へメッセージをお願いします。
宮本さん:子どもの教育において最も大切なのは、人間性のインプットです。発達障害のお子様は、自分の感情は理解できても、周囲の人の気持ちや状況を理解することが難しい場合があります。私たちが目指すのは、そろばんができるようになることだけではなく、お子様が人としての喜びや悲しみを周りの子どもたちと同じように共有できるようになることです。
作業療法士やそろばんの指導者など、異なる専門性を持つスタッフが協力しながら、人として大切なものを身につけられる場を作っていきたいと考えています。