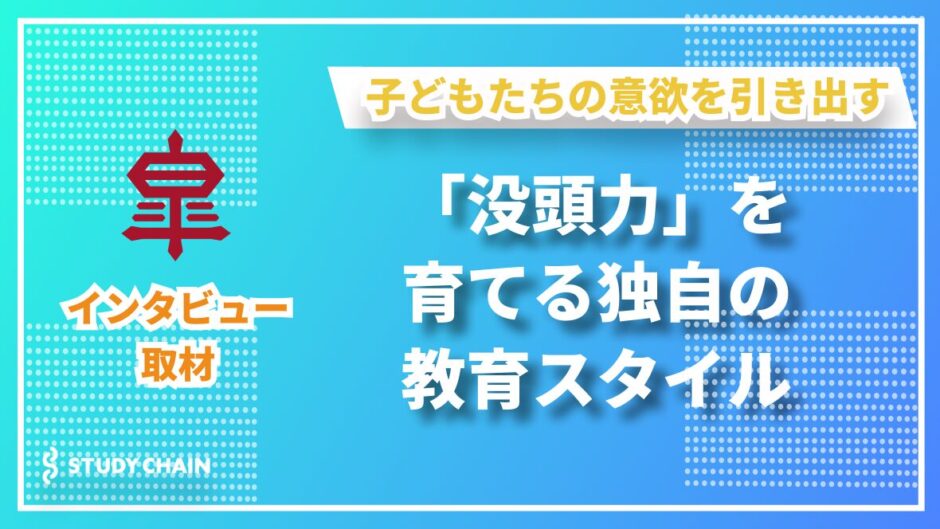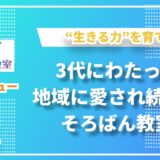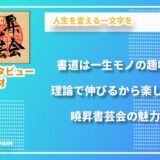大阪府で180名以上の生徒が通う「皐月珠算道場」は、幼児から中学生まで幅広い年代が在籍し、学年の枠を超えて学び合う“多世代教育”を実践しています。本インタビューでは、教室を主宰する井上さんに、そろばん学習を通して育む「没頭力」や、自主性を尊重した指導方針、独自教材を用いた成長支援など、具体的な取り組みについて伺いました。
単なる計算力だけでなく、子どもたちが夢中になれる環境をどう整えているのか、そして「一流を未来に送る」という理念のもとに、社会で活きる力をどのように育てているのか。全国大会出場を果たす実力派教室のリアルな声を通じて、現代の子育て・教育におけるヒントが詰まった一記事となっています。
珠算に少しでも興味がある方や、子どもの集中力・自立心を伸ばしたいと考える保護者の方にぜひ読んでいただきたい内容です。
ーまずはじめに、どんな方を対象に、どんな指導をされているのか教えてください!

皐月珠算道場主宰 井上さん:幼稚園・保育園の年長さんから、中学3年生ぐらいまでのお子さんが在籍しています。珠算学習を中心に指導しており、それに付随して「珠算式暗算」の指導に力を入れています。
ー珠算式暗算というのは、いわゆるフラッシュ暗算とはまた違うんですか?
井上さん:珠算式暗算というのは、頭の中でそろばんの珠をイメージし、そのイメージを動かして計算する、という方法です。この方法で計算できるように、そして上手にイメージできるように練習する手段の1つがフラッシュ暗算と考えております。目的と手段、なので考え方や仕組みはほぼ同じです。フラッシュ暗算は基本的に足し算で、イメージしている珠を素早く動かして計算する、イメージを強固にする手段として練習に取り入れることもあります。引き算、かけ算、わり算は、実際に教材を使って、最初は机の上で指を動かしながら、そこにないそろばんを、そこにあるかのようにイメージし続けて、珠を動かします。いずれにしても、頭の中でそろばんの珠をイメージし、そのイメージを動かして計算するというのが、珠算式暗算です。
ーなるほど、ありがとうございます。では、この教室を始められたきっかけについても教えてください!
井上さん:2018年に、偶然知り合いの方から「息子にそろばんを教えてくれないか?」と頼まれたのがきっかけだったんです。「いいですよ!」と軽く引き受けたのが始まりでした。
最初はその子と、お友達の2人だけだったんですけど、そこから少しずつ人数が増えていって…今年の5月で7年目を迎えますが、今では180人くらいの教室になってます。特に大きな宣伝とかはしてないんですけど、ありがたいことに口コミで広がっていってくれて。
ーもともと先生自身もそろばんをされてたんですか?
井上さん:そうですね。私自身は小学校1年生から中学2年生くらいまでそろばんを習っていました。そろばんは大好きですが、まさか自分が教える側になるとは思ってなかったですね。
ーありがとうございます。では、他のそろばん教室とは違う「皐月珠算道場ならでは」の特徴はどんなところになりますか?
井上さん:様々なそろばん教室があるので、重なる部分も多々あるかと思うんですけど、「多世代教育」を取り入れているのは一つの特徴だと思います。
学年で区切らずに、例えば1年生と6年生が隣同士で学ぶ、という環境にしていて。そうすることで、年下の子が上の子を見て「自分もあんな風になりたいな」って思えたり、上の子は下の子に見られてる意識が出たりして、すごくいい影響が生まれるんですよね。少し前までは地域の大きめの公園がそういう性質を持っていたりしたのですが、最近は減ってきているように感じており、意識して教室の環境を作っています。
次に、生徒それぞれの学習過程に合わせて最適な学習環境を用意している点が特徴的かなと思います。現在スタッフが8名いるのですが、基礎〜中級ぐらいまでは理解が中心なので、分かりにくいところはすぐに聞けるよう、マンツーマンに近い環境を用意しています。ただ、上級になってくると、さらに上達するためには切磋琢磨できる環境が必要になってきますので、そこはちょっと雰囲気を変えて、自分で目標を立てて、自分で進んでいく環境、そろばんを存分に学習できる環境を用意しています。
ーなるほど、「自分で進む力」を育てるというのも大きなテーマなんですね。そして…「没頭力」という言葉がとても印象的だったのですが、これはどういう意味合いなんでしょうか?
井上さん:そろばん学習では、計算力や情報処理能力というものが注目されやすく、もちろんそれも大事なのですが、うちはそれよりも「没頭力」っていう、いわば集中力のさらにその先にある力を育てたいと思っています。
私の中では、「没頭力」というのは“自分でスイッチを入れて、どっぷりその世界に入り込める力”というイメージです。いわゆる受動的な刺激から始まる集中ではなく、能動的な、自分の内側から「やりたい」「できるようになりたい」という気持ちや好奇心から始まり、それに向かって没頭していく。そういう力を養うには、珠算学習はとてもいい学習なんですよね。
ーそんな没頭力を育てるために、具体的にどんな取り組みをされてるんですか?
井上さん:まず、初級の最初の単元から、制限時間付きのチェックテストを実施しています。限られた時間の中で、”速さ”と”正確さ”という二律背反を同時に追求する中に、没頭のスイッチがあると考えているので、できる限り早い段階から、没頭状態を経験できるような環境作りに取り組んでいます。
即時答え合わせにもこだわっています。正誤のフィードバックが早いというのも、没頭の要素の1つだと考えています。計算が終わって、先生の机に持っていって採点してもらう。のではなく、常時スタッフが巡回して1問ごとであっても正誤を伝え、その場で必要に応じて指導しています。
教材もほぼ全てオリジナルで作っていて、「2割復習、6割現状、2割挑戦」というバランスにしています。常に実力の少し上、ギリギリのラインに安心してチャレンジできるような教材作りに取り組んでいます。
他には、年に4回、教室内大会を開催したり、外部のそろばん競技大会に参加したり、習熟度によって効果的な没頭スイッチを押せる環境作りに取り組んでいます。
ー指導するうえで意識しているスタンスや考え方についても、もう少し詳しく伺ってもいいですか?
井上さん:一番大事にしてるのは「子どもの自主性」です。こちらから「これやって、あれやって、今日はみんなでこれをしよう」って言うのではなくて、子ども自身に「今日はこれやってみようかな」とか「これ、やってみたい」と思ってもらい、伝えてもらうことを意識してます。
最初に「今日は何がしたい?」と聞いて、それに対して「じゃあこういう方法があるよ」とか、「これやってみたらどう?」っていう風に提案するようにしてるんです。対面教育に近いと思います。で、そのための選択肢をたくさん用意しておく。声かけは、天気とか、季節とか、その子の性格とか…大げさではなく、いろんな要素を観ながら微調整しています。
ー現在提供されているコースについても教えてください!
井上さん:大きく3つあって、まずは「30分コース」。これは初めての習い事として、お試しで始めてみたいという方や、60分集中できるか不安という方向けで、基本的に幼児さんが対象ですね。週に1回、30分の授業を実施しています。
次に「通常コース」があって、これは週1回〜週4回まで、それぞれ60分の授業で通っていただいてます。目的に合わせて週の回数を提案しています。
最後に「選手コース」というのがあって、もっともっとそろばんを上手くなりたい!とか、そろばんが大好き!という子たちが通っています。内容もかなり特殊で、通常の授業とは練習内容が全然違います。今年は近畿で1位の生徒を輩出することができ、昨年は大阪1位の生徒を輩出することができました。今は全国優勝を目指して練習しています。(いずれも4年生以下の部)
ーすごい実績ですね…!では今後、さらに取り組んでいきたいことや、強化したい点があれば教えてください!
井上さん::「一流を未来におくる」というのが教室の理念で、没頭力を他の分野に「応用できる力」を育てたいなと思っています。
没頭力や向上心、自信を身につけた上で、それを自分の興味のある分野に応用していけるような、そんな力を子どもたちに持ってもらいたい。社会に出たときに、「あの時のそろばんの経験が役に立ったな」って思ってもらえるように、試行錯誤しています。
100人いると一番は1人だけですが、一流は100人なれる可能性があります。そういう世界観を持ち続けたいですね。
ー最後に、これから入会を考えている方へメッセージをお願いします!
井上さん:そろばん学習には、可能性が無限にあると考えています。私自身もそう実感しています。
習熟するまでに時間はかかりますが、時間をかける価値がある習い事だと思います。
あと、「没頭力」という言葉をもう一度強調したいのですが、これは、時間の密度を変える力なんです。同じ10分でも、集中力が高ければ、その10分が濃密になる。10代のうちに身につけておくと、その先の何十年の密度が変わる。本当に人生が変わると思うんです。
できるだけ早くとは言いませんが、将来の「時間の質」を変えるような力を、そろばん学習で培ってもらえたら嬉しいですね。