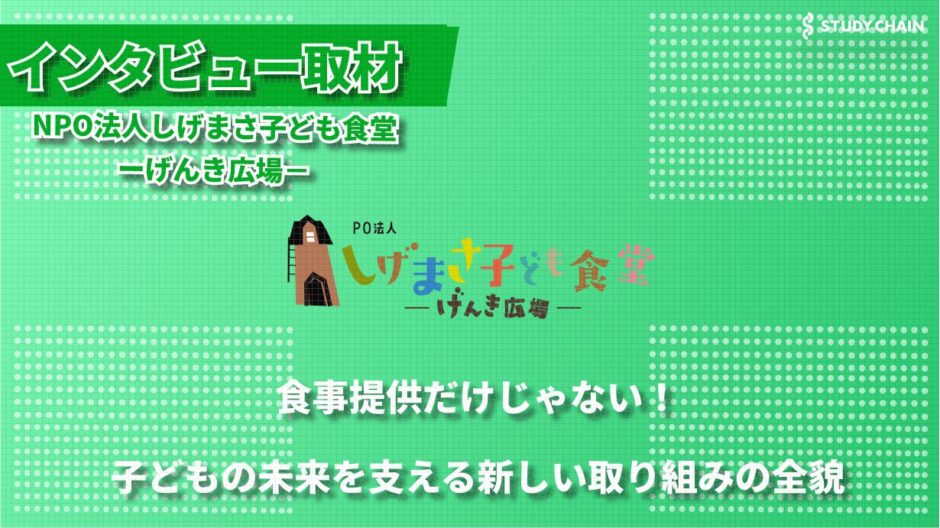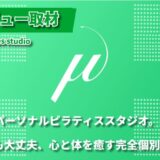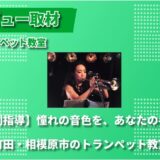NHKの番組視聴をきっかけに始まったしげまさ子ども食堂。旧大分県三重農業高等学校の農場跡地を活動拠点に、子ども食堂、学習支援、お弁当配布など、地域に根ざした活動を展開しています。時にはヤギと触れ合いながら、子どもたちがのびのびと過ごせる空間を目指す同社の取り組みについて事務局長の首藤さんにインタビューしました!

NPO法人しげまさ子ども食堂ーげんき広場-の概要
ー現在の主な活動内容を教えてください。
首藤さん:私たちの活動は、大きく5つの柱で構成されています。まず基幹となる「子ども食堂」は月2回、第2・第4土曜日に開催。クリスマスなどのイベント時には50人以上の子どもたちが集まり、普段は15人程度と、アットホームな雰囲気で運営しています。
季節を通していろんな体験活動やイベントを開催しています。例えば年末のクリスマスカップケーキ作りでは、50人程度の子どもたちが集まりましたが、普段はいつも参加する子どもたちと一緒にご飯を食べています。
2つ目の柱である「学習支援」は、特に中学生を対象とした無料の学習サポートを提供しています。この活動は、子どもたちが自分で学習を何とかしたいと自分で申し込むことを大切にしています。
3つ目の事業はコロナ禍をきっかけに始まった「お弁当作り」です。豊後大野市の子育て支援課と連携して、食事の提供を行っています。当事者には、見守りが目的であることをお話しせずにサービスとして提供しています。
そして4つ目の活動として、日本財団さんの「子ども第三の居場所の」事業 しげまさげんき広場があります。この取り組みは来年度から豊後大野市での児童育成支援拠点事業として継続予定です。
これらの活動すべてにおいて、地域の方々のボランティアや支援者の協力を得ながら、子どもたちが安心して過ごせる環境づくりを心がけています。活動予定は市内5つの小学校に2か月に1回カレンダーを配布し、地域の子どもたちやご家族に広く周知しています。
設立のきっかけと活動の変遷
ー設立のきっかけについて教えていただけますか。
首藤さん:すべては一本のテレビ番組との出会いから始まりました。私と夫がNHKの「あさイチ」を視聴していた時、子ども食堂と学習支援の取り組みが特集されていたんです。その時、紹介された活動が地域に根差したものだったので、自分たちにもできるかもしれないと思って、栗林さんに話を聞きたいと上京しました。
その思いを具体化するため、実際に上京して豊島区の「認定NPO法人豊島子どもWAKUWAKUネットワーク」の栗林さんにお会いし、栗林さんが参加されるイベントに参加してお話をさせていただきました。
ただし、すぐには活動を始められませんでした。すぐに活動を始められなかった理由は、私とつれあいの意見が違っていたからです。彼は、賛同者を多く集めて基盤をつくってから始めるべきだと考え、私はまずは始めることから始めようと思っていたのです。
結局、何もできずに1年が過ぎようとしたときに栗林さんから、「いろんな地域で立ち上げたこども食堂が集まるから首藤さんも来ない?」
と誘われて行ってみると、3か月前に始めたという団体の方がいて、すごく驚きました。その時に栗林さんから、「首藤さんたちのように何かしたいと思っている人はきっとたくさんいるからその人たちのアンテナに向かってキックオフミーティングを開催してみたら?」とアドバイスをもらい2016年の2月に開催しました。
県内外から80名近くの方々が参加して下さって、私たちが4月に子ども食堂を始めるので手伝ってくださいとお願いし、そこから月に2回の子ども食堂を続けています。
現在は設立から9年目を迎え、当初は想像もしていなかったような活動の広がりを実感しています。テレビ番組との出会いから始まった小さな一歩が、今では地域に根差した子どもの居場所として成長していることを、とても嬉しく思っています。
活動の特徴とビジョン
ー他の子ども食堂との違いについて教えてください。
首藤さん:私たちの最大の特徴は、専門家ではなく地域住民が主体となって運営している点です。子育てを一段落させた世代、若い世代、シニア世代など、様々な年代のスタッフが関わっています。確かに、組織基盤は現在も発展途上であり、運営面での課題に直面することもあります。しかし、それ以上に、必要だと感じたことに対して柔軟かつスピーディーに対応できる機動力が私たちの強みとなっています。
特筆すべきは、活動を通じて生まれる「つながり」の広がりです。例えば、最初は子どもを連れてくるだけだった保護者が、活動に興味を持ち、徐々にスタッフのような役割を担うようになっていきます。送迎の際に保護者同士で自然と会話が生まれ、その輪が広がっていく。そんな光景は、私たちの目指す地域コミュニティの形そのものだと感じています。
子どもたちとの関わり方
ー子どもたちと接する上で大切にしていることは何ですか。
首藤さん:9年間の活動を通じて、私たちの子どもたちへの関わり方は少しずつ進化してきました。最も大切にしているのは、「ここは学校ではない」という認識です。子どもたちが安心して自分を表現できる場所であることを第一に考えています。
もちろん、危険な行為や他の子どもたちに迷惑をかける行動については、大人として適切な指導を行います。しかし、何よりも大切にしたいのは、その時の子ども自身の気持ちを聞くこと、そしてその気持ちをゆっくりでいいから自分の言葉で話せることだと思います。
ほかにどんな方法があったのか、どうなりたいのかを一緒に考える「味方」だと思っていただけますと幸いです。
今後の展望
ー今後の活動についてのビジョンをお聞かせください。
首藤さん:活動を始めてから9年が経過し、最初に関わった子どもたちが高校生や社会人になりつつある中で、新たな課題が見えてきています。特に注力したいのが、学校を卒業した後の子どもたちへの支援です。
就労支援については、特に慎重に取り組んでいく必要があると考えています。現代は働き方が多様化し、従来の就職支援だけでは対応できない状況があります。そのため、私自身もダイバーシティ就労について積極的に学びを深めているところです。
本人の強みを生かすことができる働き方を見つけ、継続して働く際に大切な生活支援など本人だけでなく雇用している企業の方へのサポートも必要になると思います。
支援者へのメッセージ
ー最後に、支援を考えている方々へメッセージをお願いします。
首藤さん:おそらく、この記事を読んでくださっている方々の地域にも、支援を必要としている子どもたちがいるのではないでしょうか。必ずしも経済的な困窮だけが課題ではありません。友達との関係に悩んでいる子、家族との時間が取れない子、将来に不安を感じている子など、子どもたちの抱える課題は実に多様です。
私たちの経験から言えることは、子どもたちを支援する時に専門性のない私たちができることは、いろんな団体や専門家の方々、多くの企業や自治体の方々、応援してくれるたくさんの人とつながることです。「子どもたちのために何かしたい」その想いでこれからも行動していきます。
具体的な支援の方法はたくさんあります。私たちの活動では、ボランティアスタッフとして直接子どもたちと関わっていただくことはもちろん、食材や学用品などの物資提供、活動資金としての寄付など、様々な形での支援を受け付けています。また、SNSでの情報拡散や、地域での口コミも、私たちにとっては大きな支援となります。
また、企業の方々にもぜひご支援をご検討いただきたいと思います。例えば、就労体験の受け入れや、専門的なスキルを活かした講座の開催など、企業ならではの支援の形があると考えています。子どもたちが将来の可能性を広げていくためには、様々な大人との出会いが必要不可欠です。
ご支援をお考えの方は、ぜひお気軽に申し込みフォームからご連絡ください。また、見学や相談だけでも歓迎いたします。皆様のお力添えが、子どもたちの明るい未来への一歩となることを、心より願っています。