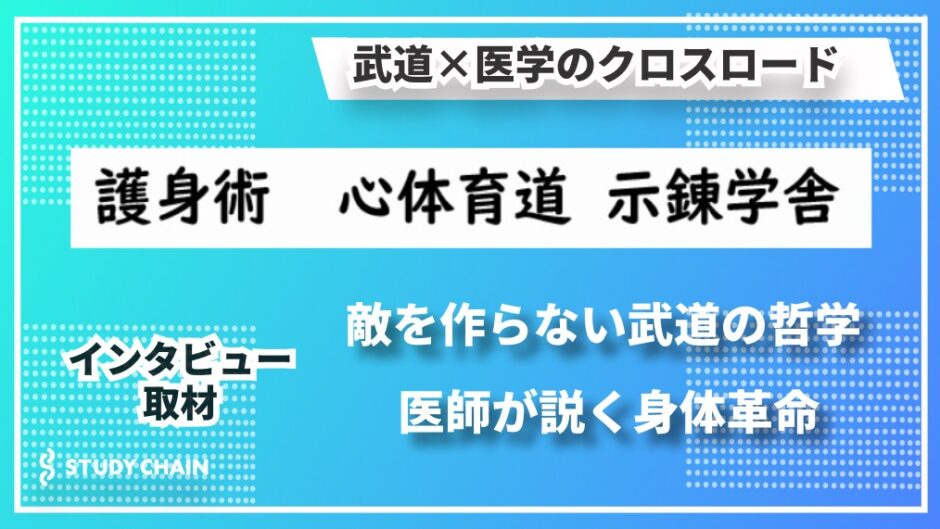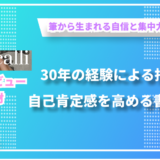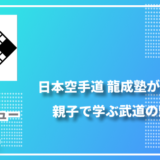今回のインタビューは、医師の資格を持つ空手道場『護身術 心体育道 示錬学舎(以下、心体育道 示錬学舎)』の濵﨑秀崇(はまさき ひでたか)代表にお話を伺いました。『心体育道 示錬学舎』は従来の空手道場とは一線を画す独自の理念と方法論を持つ道場です。試合や勝敗にこだわらず、左右のバランスを重視した技の練習や、科学的根拠に基づいた「脱力」の時間を取り入れるなど、健康効果を最大限に考慮した稽古が特徴です。また、「表の捌き」と「裏の捌き」という独自の概念を通して、護身術としての技術だけでなく、生活習慣や心の状態まで含めた道場生の総合的な成長を目指しています。医学的知見と武道の精神を融合させた『心体育道 示錬学舎』の独自のアプローチについて、詳しくご紹介します。

1998年 松濤館空手に入門
2002-2008年 医学部在学中に空手道部を創設し、心体育道直轄道場で稽古を積む
2008-2016年 鎌倉市、東京都で心体育道の稽古・指導を行う
2017年 鹿児島に帰郷し心体育道の道場を開設
2022年 心体育道示錬学舎代表に就任
2024年 東京都町田市に新道場を開設
医師・医学博士
日本スポーツ協会公認スポーツドクター
医師の視点で創造する武道の新境地 — 5歳から高齢者まで学ぶ道場
ー濵﨑さま、本日はどうぞよろしくお願いいたします!まず、『心体育道 示錬学舎』の概要についてなのですが、どういった方を対象にしているのか、そしてどのような指導を行っているのか教えてくださいますか?
濵﨑秀崇代表(以下敬称略):対象年齢は5歳以降で、年齢の上限は特に設けていません。私は昨年鹿児島から東京に転居してきて、東京の町田道場を立ち上げたばかりなのでまだ道場生がいないのですが、鹿児島、大田区、藤沢の3つの道場があり、そこでは5歳から72歳までの道場生が稽古に励んでいます。
稽古内容としては、一般的な空手の突きや蹴りの技術を教えながらも、健康増進のための体操やダーマ・ヨーガの姿勢・動作、また西式健康法という日本人の西勝造先生が考案された呼吸法や体のバランスを整える体操を取り入れているのが特色です。
私自身は学生時代から空手を始め、現在は内科医をしています。医師として健康や体の使い方を専門的に指導できるという点が、弊道場の強みだと考えています。
広島大学から始まった革新的武道の旅 — 示錬学舎誕生秘話

ー『心体育道 示錬学舎』を立ち上げられた経緯やきっかけについて教えてくださいますか?
濵﨑:広島大学の医学部在籍時に、大学内に別流派の空手部を自分で立ち上げたのがきっかけです。その空手部は今も学生たちが活動していますが、私個人としては身体のことをより深く学んでいく中で、単に空手で体を動かすだけでなく、健康効果や身体教育効果を追求したいと思い、さまざまな武道や健康法を探っていました。そこで出会ったのが、廣原 誠(ひろはら まこと)先生が指導されている「心体育道」という武道でした。
大学卒業後は鎌倉の武道館で一人で稽古をしていましたが、仲間を増やしたいと思ってホームページを作成したところ、現在大田区の道場責任者をしている方から連絡があり、二人で週に一回稽古をするようになりました。その活動が徐々に広がりまして、大田区に道場を開設することになりました。
最初は「濵﨑道場」という名称でしたが、3年前(2025年現在)に廣原先生から「自分の道場名を新しく決めて、独自の路線を進めていきなさい」とアドバイスをいただき、道場生たちと相談した結果『心体育道 示錬学舎』という道場になりました。
ー「示錬学舎」という名前にはどのような意味が込められているんですか?
濵﨑:「鍛錬」の「錬」は「練る」ということで、継続して心と体を練磨していくという姿勢を表しています。日本刀を鍛錬するように自分の心と体を錬っていきます。私たち指導者はそういう姿を道場生たちに示し、「学舎」は学びの場という意味で、道場生が子どもから大人まで、何かを学んでほしいという願いを込めています。
稽古を継続することの価値や、道場生同士でお互いを尊重しながら技を向上させること、また道場が一つの場となって社会的な交流が広がるなど、さまざまな学び合いの場であってほしいという思いから「示錬学舎」と名付けました。
‟勝つ”よりも、‟負けない”武道哲学 — 試合のない示錬学舎の革命的アプローチ

ー他の空手道場にはない特徴や、アピールポイントがあればぜひ教えてください。
濵﨑:一般的な空手道場と大きく異なる点は、試合がないということです。大会や、技を決められた形で競う試合形式の稽古は行いません。
もう一つの特徴は、一般的な空手では右利きなら左構えで右手や右足を中心に使うといった、強みをさらに強化する傾向があるのですが、心体育道では左右のバランスを重視します。左のパンチをしたら次は右のパンチというように、体の左右のバランスが乱れないような稽古を心がけています。これを継続することで健康効果にもつながると考えています。
また、長時間体を動かし続けると筋肉が過剰に緊張して体に負担がかかるため、適度な運動の後に床に寝そべって「脱力」する時間を設けています。この時に腹式呼吸を行い、交感神経の興奮を抑えて副交感神経の活動を高め、体へのダメージ蓄積を防いでいます。これも弊道場の特徴的な取り組みですね。
ーホームページに「勝つことではなく負けないことを学ぶ」という言葉がありましたが、これはどういう意味ですか?
濵﨑:これは廣原先生の哲学です。「世の中に敵はいない、敵を作るのは自分自身だ」という考え方に基づいています。相手を痛めつければ相手は怪我をしますが、自分の人生にもネガティブな影響を与えます。また自分が勝つことだけを目的に激しい稽古や試合をすると、交感神経が過度に緊張し続け、心と体に良い影響を与えません。
道場生たちが共に成長していくためには、「相手を倒す」という発想ではなく、互いに高め合う関係が大切です。そのためには試合形式よりも、協力して学ぶ形式が適していると考えています。
空手から発展した護身術なので、身を守ることが主目的となります。力と力でぶつかれば強い方が勝つので、いかに相手の力を捌いて自分が負けないようにするかが重要です。心体育道の技には急所を狙ったり、目を狙ったり、鼓膜を破るといった激しい技もありますが、これらは危険から逃れるために急所を的確に狙い、自分が安全なポジションを確保したら、それ以上は戦わないという考え方で使用するために稽古しています。
科学的健康法の秘密 — 金魚運動から背腹運動まで独自の体調管理術
ー先ほどお話しされていた「西式健康法」について、もう少し詳しく教えていただけますか?
濵﨑:西式健康法の中から稽古に採り入れている主な運動法は以下のようなものですね。
まず「金魚運動」は、頭の下に手を組んで床に力を抜いて仰向けになり、金魚が泳ぐような感じで頭を左右に振る運動です。これにより背骨のゆがみを整えます。
次に「毛管運動」は、一般的に「ゴキブリ体操」とも呼ばれるもので、仰向けに寝た状態で手足を高く上げて小刻みに振る運動です。手足の末端に滞留した血液を心臓方向へ戻す効果があります。特にデスクワークなど座りっぱなしの仕事をしていると重力の影響で下肢に血液が滞りがちですが、この簡単な運動でそれを解消できます。
そして「合掌合蹠運動」は、手のひらを合わせる「合掌」と足の裏を合わせる「合蹠」を行います。体の中心に両足を寄せた状態で呼吸を整え、手足を伸展・屈曲させる運動を繰り返します。左右の手が離れないようにすることで左右均等な動きになり、骨格や筋肉のバランスを整えます。
さらに「背腹運動」というものもあります。横隔膜は不随意筋なので直接意識的に動かせませんが、腹筋を意識的に凹ませたり膨らませたりすることで横隔膜に刺激を与え、内臓の自律神経系のバランスを調整します。
これらが西式健康法から取り入れた体操法です。
間違いを否定しない自由な稽古法 — 子どもたちの創造性を引き出す指導

ー生徒さんたちに指導する際に、特に意識していることや信念などがあればぜひお伺いしたいです!
濵﨑:私が最も心がけているのは、特に子どもたちに対して「それは間違っている」と否定しないことです。心体育道を含め、型や基本技には決まった形がありますが、子どもたち一人ひとり体の構造も違えば、筋力、体力、柔軟性もそれぞれ異なります。一見すると型と違う姿勢や技の出し方であっても、その子にとっては合理的な可能性があるので、「私のやり方をそのまま真似なさい」とは言いません。
上達してくると「捌き」という、通常の空手でいう組手のような練習を行いますが、ここでは型や教えられた技にとらわれず、自由に自分のアイディアで技を出すよう促しています。子どもたちは指示されたことをそのまま実行することに慣れているので最初は戸惑いますが、次第に自分なりの技を生み出すようになり、私が思いもしなかった効果的な技を見せてくれることもあります。
ーホームページで「表の捌き」と「裏の捌き」というワードを目にしました。こちらについて説明していただけますか?
濵﨑:「表の捌き」は護身術としての技術を指します。立ち方、受け、投げ、突き、蹴り、打ちなど、自分の身体を守るための具体的な技術です。
一方、「裏の捌き」は、「表」が身を守る技術なら、「裏」は自分自身の体調を整える生活習慣、食事、そして心の状態などを指します。表の捌きと裏の捌き、両方を車の両輪のように鍛え上げていくことで、人間として大きく成長し、より完成された状態に近づいていくというイメージです。
多くの空手道場では試合での勝利や大会での好成績が目標となるため、私たちが重視する「裏の捌き」はそこに直接結びつかないかもしれません。体づくりのために栄養摂取や筋力トレーニングを行うこともあるでしょうが、それは私たちが求める目標とは異なります。この点が他の道場との大きな違いだと思います。
ファミリーで学ぶ武道の道 — リーズナブルな会費で家族全員が成長できる場
ー提供されているコースについて、簡単に教えてくださいますか?
濵﨑:特別なコース分けはしておらず、初心者から中級者まで一緒に稽古を行っています。
唯一の区分として「ファミリークラス」があり、お子さんが入会した場合、保護者の方は会費不要で一緒に練習できるようにしています。これは家族全員で武道に親しんでもらいたいという考えからです。
一般的な道場でよく見られる初心者クラス、上級者クラス、試合クラスといった分け方はしていません。基本的には指導者が道場生一人ひとりを見ながら、全員で同じ練習をしつつも、個々の習熟度や特性に応じて個別指導を織り交ぜていく形をとっています。
ー会費が非常にリーズナブル(月額2000~3500円!)ですが、これはなぜですか?
濵﨑:道場生からいただいた会費は道場生に還元することを基本方針としています。ある程度資金が貯まれば、みんなで懇親会を開いてその費用に充てたり、各支部から道場生が廣原先生のもとで学ぶ機会を年に1〜2回設けていますので、その際の交通費に使ったりしています。
稽古場所の賃料は会費からまかなっていますが、基本的に道場コミュニティに還元することを目的としています。
明日への展望 — 各地に広がる心体育道の輪とさらなる進化
ー今後、こういった点をより強化していきたい、そして新たに取り組んでいきたいことがあれば教えてください。
濵﨑:すでに鹿児島や大田区に道場があり、今月からは熊本でも鹿児島道場を卒業した方が新たに道場を立ち上げる予定です。今後は各地の道場の交流や、廣原先生のもとで学ぶ合同イベントなどを充実させていきたいと考えています。
私が道場を運営する意義は、単に空手技術を教えることや強さを追求することだけではなく、道場での学びや気づきを日常生活や人生全体に活かしてもらうことにあります。そういった成長のきっかけを提供する場としてさらに発展させていきたいですね。
身体能力の高い子だけを対象にするのではなく、さまざまな特性や能力を持つ子どもたちが共に学び、それぞれを尊重し合える環境を大切にしていきたいと思っています。
心と体を整える武道のすすめ — 心体育道 示錬学舎からのメッセージ

ー最後に、『心体育道 示錬学舎』に興味を持たれた方々へ、メッセージをお願いします!
濵﨑:心体育道の稽古を通じて心と体を整え、共に楽しく学んでいきましょう。健康効果を重視した武道を通して、子どもから大人まで、それぞれの年齢や体力に合わせた成長の場を提供しています。左右のバランスを大切にし、適切な脱力と呼吸法によって心身のストレスを軽減しながら、護身術としての技術も身につけていただけます。単なる武道の稽古にとどまらず、日々の生活や人生全般に活かせる学びの場となることを目指していますので、ぜひ一度見学や体験にお越しください!