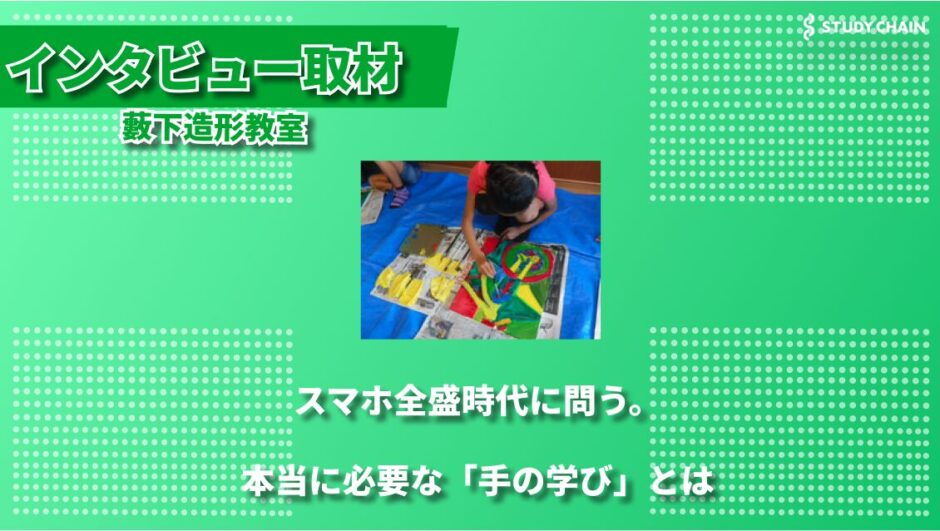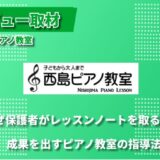京都で37年、子どもたちに造形教育を続けてきた藪下造形教室。便利さが増す現代だからこそ、手を動かすことの大切さを説く藪下さんに、教室の特徴や子どもたちへの想いを伺いました。

サービス概要
ー藪下造形教室ではどのような方を対象に、どのような指導を行っているのでしょうか?
藪下さん:幼児から小学生を中心に、絵画と工作を指導しています。絵画・工作といっても範囲が広く、染色や彫刻的な作品、木工作、さらには日本画や油絵まで、様々な造形活動を行っています。
レッスン時間は幼児が1時間半、小学生は2時間です。準備と後片付けを大切にしており、生徒たち自身で行うようにしています。実際の制作時間は50分から1時間程度となっています。
設立の経緯・きっかけ
ー造形教室を開こうと思ったきっかけを教えていただけますか?
藪下さん:1988年の開校以来、約37年教室を運営しています。きっかけは学生時代のアルバイト経験でした。
最初は中学校の美術教師として働き、その後小学校でも教鞭を執りましたが、その中で小さな子どもたちと美術との関わりの面白さに魅了されていったのです。
当時の京都には図工専科の教員という選択肢がなかったこともあり、独自の教室を開設することを決意しました。
特徴やアピールポイント
ー藪下造形教室の特徴や強みについて教えていただけますか?
藪下さん:「手は第二の脳である」という言葉があるように、手を使う活動は子どもの成長に大きな影響を与えます。
現代はボタン一つで何でもできる便利な時代です。だからこそ、実際に手を使って物を作り上げる経験が重要だと考えています。教室では両手を使うことを意識させ、たとえ面倒な作業でも避けずに取り組むよう指導しています。
時間はかかっても、一歩一歩作り上げていく過程そのものに価値があります。この経験は、将来直面する困難に対処する力を養うことにもつながるはずです。
また指導する側も、一人ひとりの子どもに目が行き届くよう工夫しています。私以外のスタッフが5名以下でひとりが付けるように配置し、スタッフと共に日々研究を重ねて丁寧な指導と子ども達との会話やコミュニケーションを心がけています。
幼児クラス(1時間半)、小学生クラス(2時間)、中高生・大学生向けの夜間クラスなど、年齢に応じたカリキュラムを用意していることも特徴です。
指導方針と具体的な取り組み
ー具体的な指導内容やスケジュールについて教えていただけますか?
藪下さん:基本的に1ヶ月で絵画1作品と工作1作品に取り組みますが、生徒の希望や作品の特性に応じて柔軟に対応しています。通常は3週間程度で1つの課題を完成させますが、油絵のように準備や工程が多い作品は、1ヶ月以上かけることもあります。
現在、幼稚園の会場を借りての3つの教室と、自宅での指導を合わせて4つの場所で展開しています。全ての生徒が確実に作品を完成できるよう、スタッフを多く配置してきめ細かなフォローを行っています。
また、中学生以上の生徒も受け入れており、夜間クラスでは大学生まで指導しています。趣味として美術を続けたい生徒のニーズにも応えています。
コースや料金体系
ー料金体系について教えていただけますか?
藪下さん:入会金、月謝ともに9,000円です。材料費は基本的に月謝に含まれています。ただし、油絵など特別な材料が必要な場合は別途徴収させていただくことがあります。中学生以上は試験期間などで出席が不規則になるため、出席回数に応じた料金設定としています。
今後のビジョン・展望
ー今後の展望についてお聞かせください。
藪下さん:新しいことを始めるというよりも、変化する子どもたちのニーズに柔軟に対応していきたいと考えています。現代の子どもたちは以前と比べて繊細になっているため、作品制作を通じて自信が持てるような声かけを今後も心がけて指導していきます。
中堅スタッフも揃い、私の経験も活かしながら、さらにコミュニケーションを大切にした指導を目指しています。
記事を読んでいる方へのメッセージ
ー最後に、体験レッスンや入会を検討されている方へメッセージをお願いします。
藪下さん:家庭でも生活の中で手を動かす機会を大切にしていただきたいと思います。特に小さなお子様は、お手伝いなどを通じてご家族と一緒に活動する時間を持つことが大切です。
また、面倒なことを避けるのではなく、壁を乗り越える力を育てていってほしいと思います。「すぐに飽きてしまう」という声をよく聞きますが、コツコツと取り組む姿勢を育てることで、必ず子どもたちは成長していきます。その過程をしっかりとサポートしていきたいと考えています。