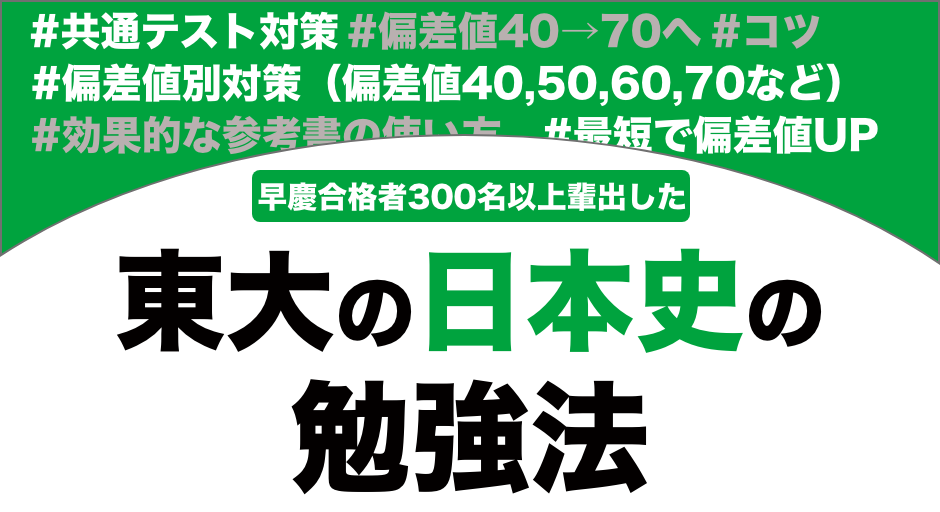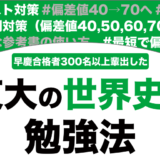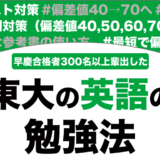本サイトの表記には、一部プロモーションを含みます
東京大学に合格できる日本史の勉強法を解説します。東大の日本史対策に実際にやってよかった勉強法とその順番も合わせて紹介します。また東大の日本史対策におすすめの参考書も合わせて紹介します。
いきなり最終結論!東大に合格するための日本史の勉強法の順番
結論として、日本史の東京大学に合格する勉強法とその順番を解説します。
特に東大日本史を攻略する上で「年号を軸にしたタテの流れの理解・把握」と「論述対策」と「ライバルと差をつける分野部分の知識習得」の3点を重要視した勉強法の順番となっています。
東大日本史で高得点を取るには年号を軸にしたタテの流れの把握が不可欠です。この段階では講義系の参考書で理解を深めつつ、年号を徹底的に暗記していきます。
金谷の日本史なぜと流れがわかる本を使って因果関係を意識しながら通史を学習します。1日30分から45分かけて読める範囲の大枠をつかみます。並行して元祖日本史年代暗記法を使い、主要な年号を語呂合わせで覚えていきます。年号暗記には1日45分以上時間をかけられると理想的です。
また東進の日本史一問一答を使って用語を覚えていきます。最初は星2と星3を確実に覚えることを目標にします。一問一答を使う時は単なる暗記ではなく、金谷の講義本で学んだタテの因果関係を思い出しながら取り組むことが大切です。年号と人物を2つの軸として日本史全体を覚える土台を作ります。
使うべき参考書 金谷の日本史なぜと流れがわかる本 元祖日本史年代暗記法 東進日本史一問一答
この段階から論述問題への対応を始めます。東大日本史は全問論述形式のため、知識を持っているだけでなく文章で表現する力が必要です。
日本史の論点という参考書を繰り返し読み込みます。この本は東大で頻出の論点を質問と解答形式でまとめており、国立対策には必須の教材です。何度も読み返して各論点の本質を理解しましょう。並行して基礎問題精講などの論述問題集で実際に答案を書く練習を始めます。
最初は字数を埋めることに苦労するかもしれませんが、徐々に書くべき内容を字数内にまとめることが課題となります。答案を書いたら必ず学校や予備校の先生に添削してもらいましょう。客観的な評価とフィードバックを受けることが論述力向上の鍵です。また詳説日本史研究を辞書的に使い、論述で使う知識の裏付けを確認します。
使うべき参考書 日本史の論点 基礎問題精講日本史 詳説日本史研究 山川日本史用語集
東大日本史では史料を読み解く力が重視されます。この段階では史料問題と文化史に重点的に取り組みます。
日本史史料一問一答を使って主要な史料に慣れていきます。史料問題では提示された史料の内容を正確に読み取り、それを歴史的知識と結びつけて考察する力が求められます。資料集も併用して視覚的な理解を深めましょう。
文化史については金谷の日本史文化史編を使って各時代の文化的特徴を整理します。文化史は政治史や社会史と関連付けて覚えることが重要です。攻略日本史テーマ文化史も活用して、文化史の出題パターンに慣れていきます。この段階で一問一答の星1の用語も少しずつ覚え始めましょう。
使うべき参考書 日本史史料一問一答 金谷の日本史文化史 攻略日本史テーマ文化史 山川日本史資料集
この段階から本格的に東大の過去問に取り組みます。東大日本史は独特の出題形式のため、過去問演習が最も効果的な対策となります。
東大の過去問を25年分から30年分解いていきます。最初は時間を気にせず、自分の最高と思う答案を作成することに集中します。問題の要求や指示を正確に把握することが何よりも重要です。東大の問題は要求を完璧に理解した段階で半分以上解答ができていると言えます。
答案を作成する際は提示された史料や課題文をすべて活用することを意識しましょう。また複数の解説書を参照することをおすすめします。東大日本史赤本、青本、鉄緑会の過去問集などを使い、様々な解説を比較検討して自分なりの最善の答案をまとめ直す作業が思考力を養います。
使うべき参考書 東大日本史27カ年 東大の日本史25カ年 鉄緑会東大日本史過去問集
最終段階では試験本番を想定した演習を行います。1題を15分以内で解答できるよう時間配分を意識した練習を積みます。
東大の日本史は4題で50分から55分が目安の時間配分です。1題あたり10分から13分で解く必要があります。時間内に要求を満たした答案を書けるよう、過去問や予備校の実戦問題集を使って演習を重ねます。
また近現代史は細かい知識が問われやすいため、HISTORIAもしくは実力をつける日本史100題を使って難易度の高い問題に触れておきます。ただし細かい知識にこだわりすぎると偏差値の伸び悩みにつながるため、間違えた分野を資料集、用語集、講義本で徹底復習することに重点を置きましょう。最後まで教科書レベルの基礎を大切にする姿勢が合格への近道です。
使うべき参考書 HISTORIA 実力をつける日本史100題 攻略日本史近現代史 駿台実戦模試過去問 河合塾オープン実戦問題集


東大の日本史の大問別対策
東大日本史の最大の特徴は、全問が論述形式で出題されることです。
東大日本史では600字程度の大論述が1題、120字から200字程度の中論述が3題程度出題されます。
東大日本史は例年、大問4題構成で出題されます。
第1問は古代から中世、第2問は中世から近世、第3問は近世から近代、第4問は近現代という時代配分が基本です。
各大問の特徴を理解して対策することが高得点への近道となります。
第1問は600字程度の大論述問題として出題されることが多いです。
古代から中世にかけての政治史、社会史、経済史のいずれかがテーマとなり、時代を超えた変化や継続性を論じる必要があります。
この問題では、複数の時代にまたがる歴史的な流れを整理して論理的に記述する力が求められます。
第2問から第4問は120字から200字程度の中論述問題が中心です。
史料問題が含まれることも多く、史料の読解力と歴史的背景の理解が同時に問われます。
特に近現代史では、政治史だけでなく経済史や外交史、社会史など多角的な視点が必要となります。
大問別対策として最も重要なのは、時代ごとの因果関係を明確に理解することです。
東大日本史では、なぜその出来事が起こったのか、その結果どうなったのかを論理的に説明する力が評価されます。
そのため、単に出来事を覚えるのではなく、歴史の流れの中での位置づけを常に意識して学習することが大切です。
東大の日本史対策に実際にやってよかった勉強法3選
ここでは実際に東大合格者が実践して効果があった勉強法を3つ紹介します。
金谷の日本史なぜと流れがわかる本を使った因果関係の徹底理解
1つ目は、金谷の日本史なぜと流れがわかる本を使った因果関係の徹底理解です。
東大日本史では歴史の因果関係を論理的に説明することが求められるため、単なる暗記では対応できません。
金谷の日本史を1日30分から45分かけて読み込み、なぜその出来事が起こったのか、その結果何が変わったのかを常に意識しながら学習します。
具体的には、読み終わった範囲について自分の言葉で説明できるかを確認することが重要です。
例えば、院政が始まった理由とその影響について、誰かに説明するつもりで声に出して説明してみましょう。
この作業を繰り返すことで、論述問題に必要な説明力が自然と身についていきます。
元祖日本史年代暗記法を使った年号の徹底暗記
2つ目は、元祖日本史年代暗記法を使った年号の徹底暗記です。
東大日本史の論述では、時代の流れを正確に把握していることが前提となります。
年号を軸に歴史を理解することで、出来事の前後関係や同時代性を正確に把握できるようになります。
この参考書を1日45分から60分使って、主要な年号を語呂合わせで覚えていきます。
特に政治史の転換点となる年号、重要な法令や事件の年号は確実に暗記しましょう。
年号が頭に入っていると、論述を書く際に時代の順序を間違えることがなくなり、説得力のある答案を作成できます。
東進の日本史一問一答を使った用語の段階的暗記
3つ目は、東進の日本史一問一答を使った用語の段階的暗記です。
東大日本史では高度な用語知識も必要となるため、星2と星3の用語は完璧に、星1の用語も8割以上は覚える必要があります。
一問一答は1日30分から60分かけて、金谷の日本史で学んだ範囲と連動させながら進めていきます。
ただし、用語を単体で覚えるのではなく、その用語が歴史の流れの中でどのような意味を持つのかを常に意識することが大切です。
例えば、荘園という用語を覚える際には、なぜ荘園が発達したのか、荘園の発達が政治にどう影響したのかまで理解しながら暗記します。
このように因果関係とセットで用語を覚えることで、論述問題で使える知識として定着させることができます。
東大の日本史の勉強法の実践におすすめの参考書
東大日本史の対策には、論述力を養成できる参考書選びが非常に重要です。
ここでは東大合格者が実際に使用して効果があった参考書を紹介します。
金谷の日本史なぜと流れがわかる本
金谷の日本史なぜと流れがわかる本は、東大日本史対策の基礎となる参考書です。
この参考書は歴史の因果関係を丁寧に解説しており、なぜその出来事が起こったのかを理解しながら学習を進められます。
金谷の日本史は原始から現代まで4冊に分かれていますが、全て読み込むことで歴史の大きな流れを把握できます。
東大日本史では単なる暗記ではなく、歴史的事象の背景や影響を説明する力が求められるため、この参考書での学習は必須です。
論述を書く際の土台となる知識を、この参考書を通して確実に身につけることができます。
元祖日本史年代暗記法
元祖日本史年代暗記法は、東大日本史で必須となる年号を効率的に覚えられる参考書です。
この参考書は語呂合わせを使って主要な年号を暗記できるように工夫されています。
東大日本史の論述では時代の前後関係を正確に把握していることが前提となるため、年号暗記は避けて通れません。
元祖日本史年代暗記法を使えば、重要な年号を短期間で確実に覚えることができます。
特に政治史の転換点や重要法令の年号は、この参考書を使って完璧に暗記しましょう。
東進の日本史一問一答
東進の日本史一問一答は、東大日本史に必要な用語を段階的に覚えられる参考書です。
この参考書は用語が星1から星3までレベル分けされており、自分の志望校に合わせて暗記する範囲を調整できます。
東大志望者は星2と星3を完璧にし、星1も8割以上は覚える必要があります。
一問一答を使う際は、用語を単体で覚えるのではなく、金谷の日本史で学んだ因果関係と結びつけながら暗記することが重要です。
このように用語と流れをセットで覚えることで、論述問題で使える実践的な知識として定着させることができます。
日本史史料一問一答
日本史史料一問一答は、東大日本史の史料問題対策に最適な参考書です。
東大日本史では毎年史料問題が出題されるため、主要な史料に触れておくことが必要です。
この参考書を使えば、重要史料の内容と歴史的背景を効率的に学習できます。
史料問題では、史料の内容を読み取るだけでなく、その史料が作られた歴史的背景まで説明する必要があります。
日本史史料一問一答で史料に慣れておくことで、本番でも落ち着いて対応できる力が身につきます。
攻略日本史テーマ史と文化史
攻略日本史テーマ史と文化史は、東大日本史の文化史対策に必須の参考書です。
東大日本史では文化史が単独で出題されることは少ないですが、政治史や社会史の文脈で文化史の知識が問われることがあります。
この参考書は文化史を時代ごとに整理して解説しており、文化の発展と社会背景の関係を理解できます。
特に仏教史や学問史は東大日本史で頻出のテーマであるため、この参考書でしっかりと対策しておきましょう。
金谷の文化史編と併用することで、より深い理解を得ることができます。
まとめ
今回は、東大の日本史の学部ごとの特徴と対策、実践的な勉強法について解説しました。
東大日本史の対策についてのまとめは以下のようになります。