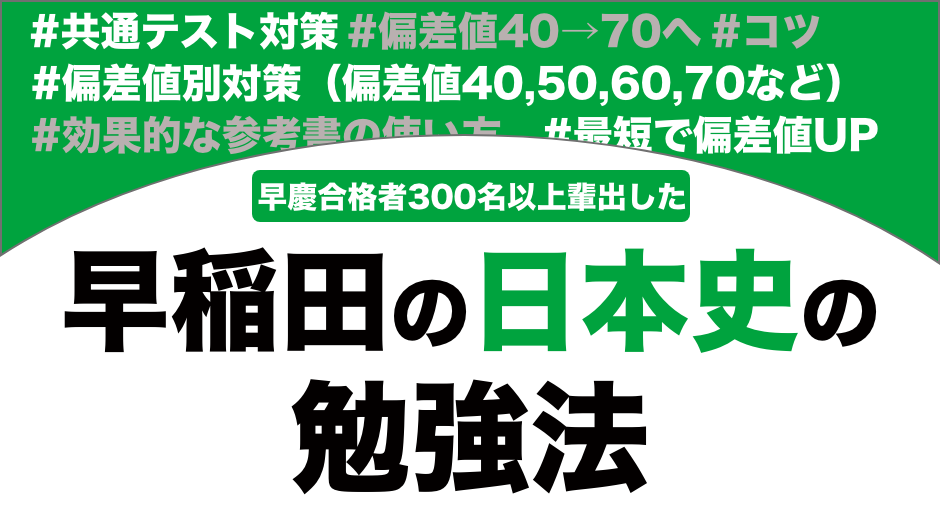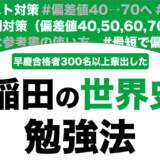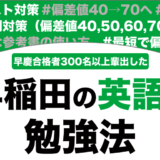本サイトの表記には、一部プロモーションを含みます
早稲田大学に受かるための日本史の超効率的な勉強法を解説します。
早稲田大学に合格した際に実際にやって良かった日本史の勉強法から使って良かった日本史の参考書からそれぞれの学部ごとの特徴も解説します。
いきなり最終結論!早稲田に合格するための日本史の勉強法の順番
早稲田に合格するための日本史の勉強法の順番を実際にやって良かった勉強法を中心に解説します。
また使って良かった日本史の参考書も紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
早稲田大学の日本史で合格点を取るためには、まず日本史全体の流れを理解することが最優先です。この段階では年号と人物を軸に日本史の骨格を作り上げることが重要になります。講義本で30分程度読める範囲の大枠を掴み、その後問題集で年号とタテの流れを意識して覚えていきます。
一問一答を使う際は、金谷の講義本を読みながらタテの因果関係を理解することが大切です。星2と星3の用語を確実に覚えることで、早稲田の基礎問題に対応できる力が身につきます。1日2時間30分の勉強時間を確保し、講義本30分、問題集30分、一問一答60分、復習30分という配分で進めていきます。
この期間は焦らずに、日本史の全体像をしっかりと把握することに集中します。早稲田大学の日本史は細かい知識を問う問題も出題されますが、まずは基本的な流れと重要用語を押さえることが合格への第一歩です。教科書レベルの内容を完璧にすることで、後の学習がスムーズに進みます。
おすすめの参考書:金谷の日本史なぜと流れがわかる本、時代と流れで覚える!日本史用語、東進日本史一問一答、山川出版社の教科書
3ヶ月目のメインテーマは年号を一気に覚えていくことです。早稲田大学の日本史では、出来事の順序や因果関係を問う問題が頻出するため、年号を軸にタテの流れを把握することが合格の鍵になります。元祖日本史年代暗記法を徹底的に活用し、1日45分以上の時間を年号暗記に充てることをおすすめします。
年号を覚える際は、ただ丸暗記するのではなく、金谷の講義本で因果関係を理解しながら進めることが重要です。その時代の用語を一問一答で星2以上は何度も復習して覚えていきます。時間が取れる人は1日60分以上を年号暗記に使うと、より効果的に定着させることができます。
この段階では、タテの流れを意識しながら、各時代の重要な出来事と人物を結びつけていきます。早稲田大学の日本史では、特に商学部や法学部で近現代史の出題が多いため、明治以降の年号は特に重点的に覚える必要があります。1日の勉強配分は、講義本45分、元祖日本史年代暗記法45分、一問一答30分、復習30分です。
おすすめの参考書:元祖日本史の年代暗記法、金谷の日本史なぜと流れがわかる本、東進日本史一問一答、山川出版社の詳説日本史ノート
4ヶ月目からはアウトプット中心の学習に移行します。早稲田大学の志望学部に応じて、難関大志望者は基礎問題精講でアウトプットしながら、自分のまだ覚えきれていない分野を1つ1つ洗い出していきます。間違えた部分は金谷の日本史で復習しつつ、一問一答でも用語を暗記していきます。
この時期から文化史の対策も本格的に始めます。早稲田大学では全学部で文化史が出題されるため、金谷の日本となぜと流れがわかる本の文化史編を使って該当する範囲を覚えていきます。文学部志望者は美術史も重点的に学習する必要があります。1日の勉強配分は、講義本45分、問題集30分、一問一答30分、文化史30分、復習15分です。
早稲田大学の中でも商学部や教育学部などを志望する受験生は、共通テストへの道日本史を解いて、どの年代が苦手なのかを見つけます。苦手な年代を発見したら、講義本で復習し、元祖日本史の年代暗記法で用語を暗記し、日本史の一問一答で用語確認を繰り返していきます。この段階では星2以上の用語暗記が特に重要です。
おすすめの参考書:日本史基礎問題精講、共通テストへの道日本史、金谷の日本史文化史、東進日本史一問一答、山川出版社の日本史図録
5ヶ月目は早稲田大学で差がつきやすい文化史と史料問題に集中して取り組みます。早稲田大学の日本史では、教科書や史料集に載っていない未見史料が多く出題されるため、史料中のキーワードから時代や出来事を推測する力が必要です。日本史史料一問一答と資料集を組み合わせながら学習していきます。
難関学部志望者は攻略日本史テーマ・文化史を活用し、間違えた部分は金谷の日本史なぜと流れがわかる本で確認していきます。商学部や教育学部などを志望する受験生は、金谷の文化史のみで十分対応できます。1日の勉強配分は、講義本30分、一問一答30分、日本史史料一問一答30分、文化史学習60分です。
用語暗記についても、法学部や商学部などの難関学部志望者は星1の用語もしっかりと覚えていきます。タテの流れを理解している段階だからこそ、重箱の隅をつつくような細かい用語が頻出される可能性の高い大学を志望している受験生は、星1以上を完璧に覚えている状況を目指します。史料問題対策では、頻出史料は完全に覚えるだけでなく、初見史料にも対応できる読解力を養います。
おすすめの参考書:日本史史料一問一答、攻略日本史テーマ・文化史、金谷の日本史文化史、山川出版社の日本史史料集、山川出版社の日本史図録
6ヶ月目は早稲田大学の各学部の傾向に合わせた対策を行います。法学部や商学部などの難関学部志望者は、HISTORIAもしくは実力をつける日本史100題と攻略日本史の近・現代史を使って難易度の高い問題を解く回数を増やします。間違えた分野や年代を資料集、用語集、講義本を活用して徹底的に復習していきます。
細かい知識にこだわりすぎると偏差値の伸び悩みにも繋がりやすいため、難易度の高い問題を解きながら間違えた部分を重点的に復習することが重要です。商学部志望者は特に経済史、産業史、金融史を重点的に学習し、短文論述の対策も行います。文学部志望者は前近代史を中心に学習を進め、美術史の対策を徹底します。
教育学部や人間科学部などを志望する受験生は、共通テストの過去問やセンター試験の過去問を解いて基礎力を固めます。過去問演習では、講義本と一問一答と年代暗記法での復習を中心に取り組んでいきます。用語集の活用は早稲田大学の難関学部志望者にとっては非常に効果的ですが、それ以外の学部志望者にとっては余計な知識も入ってきやすいため注意が必要です。
おすすめの参考書:HISTORIA、実力をつける日本史100題、攻略日本史近・現代史、早稲田大学入試対策用日本史問題集、山川出版社の日本史用語集
最終段階では志望学部の過去問を徹底的に解いていきます。早稲田大学の日本史は学部によって出題傾向が大きく異なるため、志望学部の過去問を最低でも10年分は解くことをおすすめします。法学部志望者は近現代史と戦後史を重点的に復習し、未見史料への対応力を高めます。商学部志望者は経済史の問題を繰り返し解き、時間配分の練習も行います。
文学部志望者は前近代史の問題を中心に演習し、美術史の知識を完璧にします。文化構想学部志望者はテーマ史の対策を徹底し、各時代を横断的に理解できているか確認します。教育学部志望者は史料問題と正誤問題を重点的に練習し、テーマ史への対応力を高めます。社会科学部志望者はマーク式の正誤問題に慣れ、各時代から均等に知識を習得します。
過去問演習では、間違えた問題を資料集、用語集、講義本を活用して徹底的に復習します。同じ問題を繰り返し解くことで、早稲田大学特有の出題形式に慣れることができます。時間配分も意識しながら演習を重ね、本番で実力を発揮できる状態を作ります。早稲田大学の日本史は基本から標準レベルの問題を確実に得点することが合格の鍵です。
おすすめの参考書:早稲田大学入試対策用日本史問題集、各学部の過去問、山川出版社の日本史用語集、山川出版社の日本史史料集、山川出版社の日本史図録


早稲田の日本史の学部ごとの特徴と対策
早稲田大学の日本史は学部ごとに出題傾向が大きく異なります。
早稲田大学の商学部は論述問題も含まれ問題数が多いためスピード勝負となります。
文学部では古代史と江戸時代の比重が高く美術史や考古学が必出です。 教育学部はテーマ史が必ず出題され正誤組み合わせ問題と史料問題の頻度が高いです。 文化構想学部は文化史と近現代史の出題が多く戦後史対策も必須となります。
どの学部も志望学部の過去問を最低10年分解いて傾向を把握することが合格への近道です。 学部別の特徴を理解し、それぞれに応じた対策を立てることが重要です。
早稲田の日本史対策に実際にやってよかった勉強法3選
早稲田の日本史対策に実際にやってよかった勉強法を3つ紹介します。
1つ目は教科書の徹底的な読み込みです。 早稲田の日本史は教科書の本文だけでなく欄外の注釈や図表からも頻繁に出題されます。 教科書を最低5周以上読み込み本文と欄外を完全に理解することが基礎固めになります。
2つ目は史料問題対策の徹底です。 早稲田のほぼ全学部で史料問題が頻出し特に未見史料が多く出題されます。
史料集の基本史料を覚えつつ史料中のキーワードから時代や出来事を推測する訓練が重要です。
3つ目は過去問演習を通じた実践力の養成です。 早稲田の日本史は傾向が安定しているため過去問演習が本番に直結します。
第一志望の学部は10年分解き間違えた問題は講義本や用語集で徹底復習することが合格への最短ルートです。
早稲田の日本史の勉強法の実践におすすめの参考書
早稲田の日本史の勉強法の実践におすすめの参考書を紹介します。
詳説日本史
山川出版社から出版されている詳説日本史は早稲田の日本史対策の基礎となる教科書です。 多くの高校で使用されており、早稲田大学の日本史問題のほとんどがこの教科書から出題されます。 本文だけでなく欄外の注釈や図表、写真の説明まで細かく読み込むことが重要です。
最初は本文を中心に読み込み、慣れてきたら欄外や注釈も含めて完全に暗記しましょう。 入試初期から本番まで継続して使用し、何度も読み返すことで日本史の流れと詳細な知識を同時に身につけることができます。
金谷の日本史なぜと流れがわかる本
この参考書は日本史の因果関係と時代の流れを理解するのに最適な講義形式の参考書です。 古代から近現代まで4冊に分かれており、教科書よりも読みやすく初学者でも取り組みやすい内容です。 なぜその出来事が起こったのかという因果関係を丁寧に解説しているため、暗記だけに頼らない理解が深まります。
1日30分程度で読める範囲を決めて繰り返し読み込み、日本史全体の大枠を掴むことが重要です。 教科書を読む前の導入として使用したり、教科書と並行して復習用として活用することで理解が格段に深まります。
時代と流れで覚える日本史用語
この問題集は年号と時代の流れを重視した構成になっており、タテの因果関係を意識しながら用語を覚えられます。 教科書や講義本で流れを理解した後に、この問題集で用語を定着させることで効率的に学習できます。
年号を最優先で覚えつつ、人物や出来事を時系列で整理して暗記することが可能です。
1日30分から45分程度を目安に取り組み、間違えた問題は必ず講義本に戻って確認しましょう。 早稲田の日本史では年号を軸にした出題が多いため、この問題集を完璧にすることで得点力が大きく向上します。
東進日本史一問一答
東進から出版されているこの一問一答は早稲田レベルの細かい用語まで網羅している定番の参考書です。 星の数で重要度が分かれており、早慶志望者は星1まで完璧に覚える必要があります。 単なる暗記ではなく、講義本で流れを理解した後に該当範囲の一問一答で用語を確認するという使い方が効果的です。
1日60分程度を目安に取り組み、星2と星3を最優先で覚え、余裕があれば星1まで手を広げましょう。 早稲田の入試本番では星1レベルの用語も普通に出題されるため、時間をかけて完璧にすることが合格への鍵です。
日本史史料一問一答
東進から出版されているこの史料問題集は早稲田で頻出する史料を網羅した必須の参考書です。 基本史料から難関私大レベルの史料まで幅広く掲載されており、解説も非常に詳しいです。
史料の内容だけでなく、史料が作成された時代背景やキーワードも合わせて覚えることが重要です。 1日30分程度を目安に取り組み、資料集と併用しながら視覚的にも史料を記憶しましょう。 早稲田では未見史料も出題されるため、この参考書で史料読解の基礎力を養うことが合格への必須条件です。
元祖日本史の年代暗記法
この参考書は語呂合わせで年号を効率的に暗記できる定番の年号暗記本です。 日本史の論述問題でも共通テスト対策でも、年号を軸にタテの流れを把握することが基礎力となります。
1日45分以上の時間を確保し、繰り返し音読しながら年号を完全に暗記しましょう。 年号を覚えることで時代の前後関係や因果関係が明確になり、正誤問題にも強くなります。
実力をつける日本史100題
Z会から出版されているこの問題集は早慶レベルの実践的な問題演習ができる定番の参考書です。
過去問をベースにした問題が多数収録されており、論述問題も含まれているため幅広い対策が可能です。 解説が非常に詳しく、間違えた問題を復習しながら周辺知識も同時に身につけることができます。
1日1時間程度を目安に取り組み、間違えた分野は講義本や用語集で徹底的に復習しましょう。 早稲田志望者はこの参考書の内容を完全に網羅することで、本番でも十分に戦える実力が身につきます。
攻略日本史近現代史
早稲田では特に近現代史の出題比率が高く、この参考書で重点的に対策することが重要です。 近現代史は学校の授業でも扱う時間が少なく対策不足になりがちな分野です。
この参考書では近現代史をテーマ別に整理して学習できるため、効率的に知識を補強できます。 1日30分程度を目安に取り組み、特に戦後史は細かい内閣ごとの政策まで暗記しましょう。
法学部や商学部を志望する受験生にとっては必須の参考書であり、この1冊で近現代史を完璧にすることができます。
金谷の日本史文化史
文化史は通史とは別に対策する必要があり、この参考書が最も効率的です。
早稲田では文学部を中心に文化史の出題比率が高く、美術作品の名称と外観を一致させる問題も頻出です。 講義形式で文化史の流れを理解しながら、作品名や作者を時代ごとに整理して覚えることができます。 1日30分程度を目安に取り組み、資料集と併用して視覚的にも作品を記憶しましょう。
文化史は他の受験生が対策不足になりやすい分野のため、この参考書を完璧にすることで大きく差をつけることができます。
日本史用語集
山川出版社から出版されている用語集は早稲田レベルの細かい知識を補強するための必須ツールです。
早稲田の日本史では1つの単語に対して複数の角度から出題されるため、用語集で多角的な情報を確認することが重要です。
過去問演習で出題された単語は必ず用語集で確認し、関連する情報まで暗記しましょう。勉強中にわからない用語や知識を深めたい単元があれば随時参照する辞書的な使い方が効果的です。
早慶以上の受験生にとっては用語集の内容を全て覚えても良いと言えるほど重要な参考書です。
早稲田大学入試対策用日本史問題集
この問題集は早稲田大学9学部の過去問をまとめた早稲田専用の対策問題集です。過去問集と比較して解説が非常に丁寧で、どの教材で学んだ知識かが明示されています。
時間的な余裕がある場合は過去問演習の前に取り組むことで、早稲田の出題傾向に慣れることができます。全ての問題を解く必要はなく、自分が受験する学部を中心に取り組めば十分です。
日本史の学習に時間をかけられる受験生にとっては、この1冊で早稲田の出題パターンを完全に掴むことができます。
まとめ
今回は早稲田大学の日本史の学部ごとの特徴と対策から実際に効果的な勉強法からおすすめの参考書について解説しました。
早稲田の日本史についてのまとめは以下のようになります。