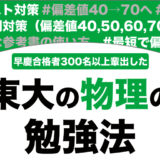本サイトの表記には、一部プロモーションを含みます
東大に合格できる効果的な物理の勉強法を解説します。東大の物理対策に実際にやってよかった勉強法とその順番も合わせて紹介します。また東大の物理対策におすすめの参考書も合わせて紹介します。
いきなり最終結論!東大に合格するための化学の勉強法の順番
結論として、東京大学に合格できる化学の勉強法とその順番を解説します。
東大化学で合格点を取るための最初のステップは、化学の全分野における基礎知識の完全な理解と計算力の養成です。この段階では教科書レベルの内容を完璧にすることを目指します。
進学校に通っている人は鎌田の理論化学の講義と福間の無機化学の講義を使って理論と無機の基礎を固めていきます。これらの参考書は東大レベルに対応できる深い理解を促してくれます。並行してリードlightノート化学で問題演習を行い、基礎的な計算問題や知識問題を確実に解けるようにしていきましょう。
進学校に通っていない人や化学に苦手意識がある人は宇宙一わかりやすい高校化学の理論化学編と無機化学編を使います。この参考書は図解が豊富で理解しやすく、基礎から丁寧に説明されているため化学が苦手な人でも取り組みやすい内容になっています。問題集は学校でセミナー化学基礎と化学を使っている人はそれを活用し、そうでない人は理解しやすい化学基礎と化学を使うのがおすすめです。
どちらのルートを選んでも、1周目が終わった段階で化学計算問題の解き方を使って計算力を強化していきます。東大化学では煩雑な計算問題が頻出するため、序盤で計算力をしっかりつけておくことが後の学習を楽にします。
使うべきおすすめの参考書 鎌田の理論化学の講義 福間の無機化学の講義 リードlightノート化学 宇宙一わかりやすい高校化学 セミナー化学基礎と化学 理解しやすい化学基礎と化学 化学計算問題の解き方
東大化学では第1問が有機化学からの出題となっており、複雑な構造決定問題や高分子化合物の問題が出題されます。この段階では有機化学の基礎を固めつつ、なぜそうなるのかという原理の理解を深めていきます。
有機化学の学習には鎌田の有機化学の講義を使います。この参考書は反応のメカニズムまで丁寧に解説しており、東大で問われる論述問題に対応できる力を養えます。有機化学は暗記科目と思われがちですが、東大では反応の理由を説明させる問題が多いため、なぜその反応が起こるのかを理解することが重要です。
並行して問題演習も進めていきます。セミナー化学やリードlightノート化学の有機分野を解き、間違えた問題は必ず講義本に戻って確認します。特に構造決定問題は繰り返し解いて解法パターンを身につけることが大切です。
この段階から化学の新研究を辞書として手元に置いておくことをおすすめします。化学の新研究は高校化学の範囲を超える内容も含んでおり、東大特有の深い知識を問う問題に対応できます。わからないことがあったときや、より深く理解したいときに参照する使い方が効果的です。
使うべきおすすめの参考書 鎌田の有機化学の講義 セミナー化学基礎と化学 リードlightノート化学 化学の新研究
基礎が固まったら、東大入試で頻出の標準レベルの問題を確実に解けるようにする段階に入ります。東大化学では難問も出題されますが、合格点を取るためには標準問題を確実に得点することが最も重要です。
この段階のメイン教材は化学の重要問題集です。重要問題集は全国の難関大受験生が使う定番の問題集で、東大入試で出題される標準レベルの問題がバランスよく収録されています。A問題とB問題に分かれており、まずはA問題を完璧にすることを目指します。
重要問題集を解く際は、ただ答えが合っているかを確認するだけでなく、途中計算の意味まで理解しながら進めることが大切です。間違えた問題は必ず講義本や化学の新研究に戻って、なぜ間違えたのかを徹底的に確認します。この作業を怠ると必ず伸び悩みが起こります。
重要問題集を2周から3周して完成度を高めたら、化学の基礎問題精講や化学の標準問題精講に取り組みます。これらの問題集は解説が詳しく、東大で問われる論述問題の対策にもなります。特に標準問題精講は論述問題が充実しているため、記述力を鍛えるのに最適です。
使うべきおすすめの参考書 化学の重要問題集 化学の基礎問題精講 化学の標準問題精講 化学の新研究
重要問題集で基礎固めができたら、東大特有の長い問題文を読み解く力と、論述問題に対応する力を鍛えていきます。この段階では東大で50点以上を狙える実力を養成します。
時間に余裕がある人や浪人生は化学の新演習に取り組みます。新演習は東大京大レベルの思考力を要する問題が全分野にわたって収録されており、難問への対応力を養えます。ただし、新演習は全問題をやる必要はなく、重要問題集で間違えた分野や苦手な分野を重点的に演習するのが効率的です。
論述問題の対策として化学記述と論述問題の完全対策を使います。この問題集は実際の入試で出題された記述と論述問題が多数収録されており、東大の無機化学や理論化学で頻出の論述問題に対応できる力が身につきます。論述問題は採点基準が厳しいため、何を書けば点数になるのかを意識しながら演習することが重要です。
東大化学では有機化学の構造決定問題が必ず出題されるため、有機化学演習で追加の演習を行うのも効果的です。複雑な構造決定問題を多く解くことで、本番で冷静に対応できる力が養われます。
使うべきおすすめの参考書 化学の新演習 化学記述と論述問題の完全対策 有機化学演習 化学の新研究
この段階では東大の過去問演習を通じて、本番で必要な時間配分と問題の取捨選択の感覚を身につけていきます。東大化学は75分で6つの中問を解く必要があるため、どの問題から解くか、どの問題を捨てるかの判断力が合否を分けます。
過去問は東大入試詳解25年化学を使って最低でも10年分、できれば25年分を解きます。25カ年は解説が詳しく、出題傾向の分析も掲載されているため東大対策に最適です。予算に余裕があれば鉄緑会東大化学問題集も併用すると、より多くの過去問に触れることができます。
過去問を解く際は必ず時間を計って解き、本番と同じ緊張感を持って取り組みます。解き終わったら採点して、どの分野で間違えたかを分析します。間違えた分野は重要問題集や新演習に戻って復習し、同じミスを繰り返さないようにします。
分野別に苦手分析シートを作ることをおすすめします。簡単な表で良いので、どの分野で何回間違えたかをカウントしていきます。たくさんマークがついた分野は化学の新研究で原理から確認し直し、重要問題集や新演習の該当分野を解き直します。この地道な作業が合格への近道になります。
使うべきおすすめの参考書 東大入試詳解25年化学 鉄緑会東大化学問題集 化学の重要問題集 化学の新演習 化学の新研究
東大志望者は共通テスト対策を後回しにしがちですが、共通テストで高得点を取ることも合格には重要です。この段階では共通テスト特有の問題形式に慣れつつ、二次試験の実力を維持していきます。
共通テスト対策は過去問演習が中心になります。共通テスト化学の過去問を5年分から10年分解き、時間配分と問題形式に慣れていきます。共通テストは知識問題が多いため、二次試験の勉強をしっかりやっていれば8割から9割は取れるはずです。
共通テスト特有の実験考察問題や資料問題が苦手な人は、共通テスト化学実験と資料の考察問題24を使って対策します。この問題集は共通テストで出題される実験問題の解き方を体系的に学べます。
並行して東大の過去問演習も継続します。この時期は新しい問題集に手を出すのではなく、今まで解いた問題の復習に時間を使います。重要問題集や新演習で間違えた問題を解き直し、苦手分野がないかを最終確認します。化学の新研究で知識の抜けがないかもチェックしておきます。
使うべきおすすめの参考書 共通テスト化学過去問 共通テスト化学実験と資料の考察問題24 東大入試詳解25年化学 鉄緑会東大化学問題集 化学の重要問題集 化学の新演習 化学の新研究


東大の化学の特徴
東大化学の試験時間は理科2科目で150分となり、化学には実質75分程度を配分することになります。大問は3問構成で、2017年度以降は第1問が有機化学、第2問が無機化学と理論化学の融合、第3問が理論化学という出題パターンが定着しています。
論述問題が年々増加傾向にあり、2025年度入試では13問もの論述問題が出題されました。文字数指定のない形式が多く、解答用紙に罫線が引かれているだけで解答欄が用意されていないため、自分でスペース配分を判断する必要があります。
頻出分野は化学平衡、有機化合物の構造決定、結晶格子などです。特に平衡問題は無機化学の知識と関連付けた融合問題として出題されることが多く、分野を超えた理解が求められます。
東大の化学対策に実際にやってよかった勉強法3選
東大化学で合格点を取るためには基礎固めから応用力の養成まで段階的な学習が必要です。ここでは実際に東大合格者が実践してきた効果的な勉強法を3つ紹介します。
まず1つ目は化学の基礎知識を徹底的に理解することです。東大化学では暗記だけでは対応できない思考力を問う問題が多く出題されます。そのため鎌田の理論化学の講義や福間の無機化学の講義などの講義系参考書を使って、なぜそうなるのかという原理を理解しながら進めることが重要です。
基礎問題精講やリードライトノート化学などの基礎レベルの問題集を1周終えたら、間違えた問題について必ず講義本に戻って原理を確認する習慣をつけましょう。この繰り返しによって単なる暗記ではない深い理解が身につきます。
2つ目は計算力と処理速度を徹底的に鍛えることです。東大化学は75分で大問3問を解く必要があり、時間との戦いになります。化学計算問題の解き方などの参考書を使って、典型的な計算問題を見た瞬間に解法が浮かぶレベルまで演習を重ねましょう。
重要問題集や化学の新演習を繰り返し解くことで、標準的な問題であれば3分以内に解けるようになることを目指します。時間を計りながら過去問演習を行い、どの問題にどれくらい時間をかけるべきか判断する力も養いましょう。
3つ目は論述対策を徹底することです。東大化学では年々論述問題が増加しており、現象の理由や実験結果の説明を簡潔に記述する力が求められます。化学の新研究を辞書として活用しながら、問題集で間違えた部分について自分の言葉で説明できるようノートにまとめる訓練が効果的です。
過去問や模試の論述問題は必ず添削を受けて、採点者に伝わる答案作りを意識しましょう。文字数制限がない問題では必要最小限の内容で簡潔に答えることが重要です。
東大の化学の勉強法の実践におすすめの参考書
東大化学の対策に効果的な参考書を紹介します。
化学の新研究
化学の新研究は東大受験生必携の参考書です。700ページを超える圧倒的な情報量で、教科書には載っていない詳しい原理や現象の説明が網羅されています。この参考書は最初から最後まで読み通すものではなく、辞書として使うのが正しい使い方です。
問題集を解いて疑問が生じたときや、講義本の説明だけでは理解できないときに該当箇所を調べることで、より深い理解が得られます。東大化学では初見の素材を扱った問題も出題されるため、幅広い知識を身につけられるこの参考書は大変有効です。
化学の重要問題集
化学の重要問題集は東大化学対策の中核となる問題集です。中堅大学から難関大学レベルの良問が数多く収録されており、基礎固めを終えた段階から取り組むべき一冊となります。A問題とB問題に分かれており、まずはA問題を完璧にしてからB問題に進むのが効率的です。
この問題集を最低3周は繰り返し、解けなかった問題には印をつけて重点的に復習しましょう。解説がやや簡潔なため、分からない部分は化学の新研究で補うとより効果的です。
化学の新演習
化学の新演習は重要問題集よりもさらに難易度の高い問題集です。東大で高得点を目指す受験生は重要問題集を終えた後にこの問題集に取り組むことをおすすめします。約200問の問題が収録されており、これを3周すれば東大化学で40点以上を安定して取れる実力が身につきます。
ただし解説はやや簡潔なため、化学の新研究と併用することが前提となります。時間に余裕がない場合は重要問題集を完璧にして過去問演習に移る方が効率的です。
東大の化学25ヵ年
東大の化学25ヵ年は過去問対策の決定版です。東大化学では過去問と類似した内容が出題されることもあるため、最低でも10年分は完璧に解ける状態にしておく必要があります。解答用紙の使い方や時間配分の感覚を掴むためにも、本番と同じ形式で演習することが重要です。
過去問演習では分野別に苦手分析シートを作成し、間違えた問題に印をつけてカウントしていくと効果的です。何度も間違える分野については化学の新研究で原理から確認し直しましょう。
鎌田の理論化学の講義と福間の無機化学の講義
鎌田の理論化学の講義と福間の無機化学の講義は基礎固めに最適な講義系参考書です。進学校に通っている受験生は高2の段階からこれらの参考書を読み込み、リードライトノート化学などの基礎問題集と併用することで効率的に学習を進められます。
イラストや図解が豊富で理解しやすく、なぜそうなるのかという原理を丁寧に説明しているため、化学が苦手な人でも取り組みやすい内容となっています。
まとめ
今回は東大の化学の学部ごとの特徴と対策について解説しました。
東大化学についてのまとめは以下のようになります。



逆転合格特化塾2.png)