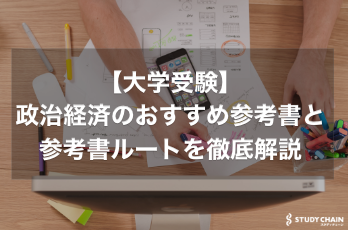本サイトの表記には、一部プロモーションを含みます
世界史の共通テストで9割取れる勉強法を徹底解説します。独学で進める世界史の勉強法におすすめの参考書や問題集、共通テストだけでなく二次試験で世界史を使う人にもおすすめの参考書、過去問の進め方について徹底解説していきます。

【この記事の監修者:逆転合格特化塾塾長「竹本明弘」
これまで早慶に現役生および浪人生を含めて合計で300人以上合格者を輩出してきました。その中で世界史選択の合格者もたくさんおり、実際に指導する中で良かった世界史共通テスト対策の勉強法や使ってよかった参考書を解説したいと思います。
いきなり最終結論!共通テストの世界史の勉強法の順番
共通テストの世界史の勉強法をゼロからでも共通テスト9割までどういう順番で勉強していけば達成できるのか解説します。
5ヶ月で共通テスト8割取れるようになる世界史の勉強法
- 世界史の勉強法として最初の目標は「全体像の把握」です。最初から細かく暗記しようとせず、まずはシンプルに通史を1周しましょう。定期テストなどで世界史がある程度得意、もしくは苦手意識が薄い人は、最初から「世界史探究」や「山川 世界史」を40分かけて読み進めるのが効率的です。もし赤点ばかりで基礎から不安な場合は、「マンガで世界史が面白いほどわかる本」で時代のストーリーをざっくり理解してから講義本に移行しましょう。
- 1日の世界史の勉強法として、まず40分間は講義本(山川 or 世界史探究)でその日の範囲を読み込み、時代の背景を理解します。次の30分は「時代と流れで覚える!世界史用語」を使い、読んだ範囲の重要用語を流れの中で確認します。最後の30分は「東進 世界史一問一答 完全版」を使って、星2以上の用語だけを繰り返し暗記しましょう。星0や星1の用語はまだ手をつけず、まずは「重要な流れ+中心語彙」を押さえることに集中します。毎回の復習では、前日や前々日に覚えた用語を5分間だけ口頭確認し、忘れている部分を即座に復習。こうした小さな積み重ねが、共通テスト世界史の土台となる知識の定着につながります。
- ここでは「完璧に覚える」よりも「時代のつながり」を意識し、国や地域がどう動いていったのかを頭の中にマップとして描けるようになるのが理想です。
- 世界史の勉強法では、「年号を意識したタテの流れの理解」が最重要です。毎日30分間、「超効率!世界史年代サーキットトレーニング」を使い、時代を縦軸で整理しましょう。出来事を単独で覚えるのではなく、「何の結果として起きたのか」「この後にどうつながったのか」という因果関係を理解すると、共通テスト世界史の並べ替え問題や正誤問題に強くなります。覚える際は、例えば「1789=フランス革命」だけでなく、「啓蒙思想の影響→旧体制の矛盾→革命勃発」と筋道をセットで意識するのがポイントです。
- 1周目より速いペースで通史を進め、出来事や用語を「なぜ起きたのか?」という観点で深掘りします。ここでの世界史の勉強法は、量より質です。講義本を40分読みながら、「この改革は何を目的に行われたのか」「この戦争はどんな背景があったのか」を書き込みながら理解していきましょう。その後、30分で「1問1答」を使ってその範囲を確認。用語の暗記にとどまらず、「どうしてその語句が重要なのか」を考えながら答えることが、世界史の思考力問題への最短ルートです。
- ここまでインプット中心だった勉強法に「アウトプット練習」を加えましょう。「世界史基礎問題精講」を30分活用し、各章の小問を通じて定着度をチェックします。間違えた箇所は講義本や「時代と流れで覚える」に戻って復習し、なぜ間違えたのかを必ず分析します。特に間違いの多いテーマはノートにまとめ、共通テスト世界史で頻出の「地域史」「テーマ史(宗教・経済)」を重点的に補強しましょう。
- この段階の世界史の勉強法では、知識の確認と定着が主軸です。1日30分の講義本で理解を再整理し、45分は「基礎問題精講」で実戦演習を行います。ここでは「問題を解く→間違える→原因を分析→復習する」という流れを徹底しましょう。残り30分で「一問一答」を回し、学習した範囲の用語をすぐに確認します。共通テスト世界史のように「知識+判断力」を問う問題形式に慣れていくことが目的です。
- 3ヶ月目までで身につけた年号の流れを活かし、ヨコのつながり(同時代の比較)を意識しましょう。具体的には、白紙ノートに時代ごとの世界地図を自分で描き、主要都市や領土の変化を整理する勉強法が効果的です。「世界史一問一答地図」も併用すれば、視覚と知識がリンクしやすくなります。また、用語集を参照し、似た用語や関連する出来事をまとめることで、共通テスト世界史の“ひっかけ選択肢”にも対応できるようになります。
- 「東進 世界史一問一答 完全版」は星2までの用語をこの時期に完璧に仕上げます。まだ覚え切れていない人は、基礎問題精講に使う時間を15分ほど削り、1問1答の復習に充てましょう。年号確認には「サーキットトレーニング」を短時間で取り入れ、忘れやすい数字を繰り返し刷り込むのがコツです。焦らず「覚える→使う→直す」のサイクルを続けることが、共通テスト世界史の安定得点につながります。
- ここからは実戦形式のアウトプットに本格的に取り組みます。「きめる!共通テスト世界史」や共通テストの過去問集を45分使い、実際の問題形式に慣れていきましょう。必ず時間を計り、共通テスト本番を意識してスピードと正確さを鍛えます。間違えた問題は放置せず、すぐに講義本や「時代と流れで覚える」で該当範囲を確認。問題演習の目的は間違いを見つけて直すことにあります。
- 共通テスト世界史は出題範囲が広く、苦手分野を放置すると致命傷になります。演習後は、間違えた問題を「時代別・地域別・テーマ別」に整理した分析ノートを作成しましょう。たとえば「中世ヨーロッパ」「イスラーム世界」「近代アジア」などカテゴリーごとに分けて記録し、間違えた理由(知識不足・混同・読解ミス)もメモします。弱点を見える化することが、次の復習を明確にし、世界史の勉強法として最も効率的です。
- 共通テストおよびセンター試験の過去問を10〜15年分解き、出題傾向と頻出テーマを徹底的に分析しましょう。特に「宗教改革」「産業革命」「帝国主義」「冷戦構造」などは毎年のように出る定番テーマです。過去問は“得点するため”ではなく、“知識を整理し、再確認するため”に使います。演習後は必ず講義本・用語集・一問一答で復習を行い、知識の抜けを潰していくことが、共通テスト世界史で安定して8割以上を取るための最短ルートです。


共通テストの世界史対策におすすめの勉強の手順
最初の1〜2ヶ月の世界史の共通テスト対策の勉強内容は、1日「40分:世界史探究(または山川)→30分:時代と流れで覚える!世界史用語→30分:東進 世界史一問一答 完全版→最後に復習」という流れで、年号と用語を重視しながら通史を1周する世界史の勉強法を実践しましょう。
世界史が苦手な人は「マンガで世界史が面白いほどわかる本」で全体像をつかみ、無理なく基礎固めをするのが効果的です。
3ヶ月目の世界史の共通テスト対策の勉強内容は「超効率!世界史年代サーキットトレーニング」で年号を整理し、タテの流れを意識した世界史の勉強法で共通テストの時系列問題に対応できる力を養います。

4ヶ月目の世界史の共通テスト対策の勉強内容は「講義本」「世界史基礎問題精講」「東進 世界史一問一答 完全版」「用語集」を組み合わせ、ヨコの流れや地図も含めた総合的な世界史の勉強法で得点力を強化しましょう。
5ヶ月目は「きめる!共通テスト世界史」や共通テストの過去問を中心に、分析と復習を繰り返す世界史の勉強法で苦手を克服し、10〜15年分の共通テスト演習で本番に対応できる実戦力を完成させます。

【この記事の監修者:逆転合格特化塾塾長竹本明弘】
▽実際にやってよかった世界史の勉強法10選を厳選して解説しました。
やってよかった世界史の共通テスト対策におすすめの勉強法3選
実際にやってよかった世界史の共通テスト対策におすすめの勉強法を3つ紹介します。
「読む→解く→覚える」を毎日ルーティン化する三段階インプット法

この世界史の勉強法は、講義本・時代と流れ・一問一答を1日の中で順番に使うことで、通史理解と暗記を同時に進める勉強法です。
世界史の講義本で背景や因果をつかみ、「時代と流れで覚える!」で構造を整理し、「東進 世界史一問一答 完全版」で知識を定着させます。毎日2時間続けるだけで、流れと用語が自然とリンクし、共通テスト世界史の思考問題にも対応できるようになります。
世界史の用語を単なる丸暗記ではなく、「なぜこの出来事が起きたのか」を意識して読むことが、この勉強法の最大のポイントです。
「超効率!世界史年代サーキットトレーニング」で年号×因果関係を可視化
共通テスト対策の世界史の参考書の中で一番使ってよかった参考書が、「超効率!世界史年代サーキットトレーニング」です。
もし「元祖世界史の年代暗記法」を使っている人はそれでも大丈夫です。
この世界史の勉強法は、年号を数字で覚えるのではなく、「背景→出来事→結果」という流れで理解するのが特徴です。
毎日30分「超効率!世界史年代サーキットトレーニング」に取り組み、出来事の因果関係を矢印で整理することで、タテの流れを強化します。たとえば「アヘン戦争=1840年」ではなく、原因から結果まで一連のストーリーで記憶することが大切です。タテの流れを意識したこの勉強法は、共通テスト世界史の時系列問題・正誤問題対策に非常に効果的です。
共通テスト対策の参考書と過去問でアウトプット中心の演習型勉強法
共通テスト世界史で高得点を取るために欠かせない過去問演習です。
「きめる!共通テスト世界史」や過去問を時間を計って解き、解答後は「分析ノート」で自分の間違えを時代・地域・テーマ別に整理します。講義本や用語集、一問一答に戻って復習し、苦手を確実に潰していくことで知識がどんどん使える知識に変わります。
10〜15年分の共通テストの過去問およびセンター試験の過去問演習を通して、自分の苦手がどんどん見えてきて、それをそれぞれ潰していくことができるのがこの勉強法の強みです。


世界史の共通テスト対策の勉強法
世界史の大学受験の共通テスト対策に効果的な勉強法を紹介します。
共通テストレベルの世界史の重要語句を覚えるがおすすめの勉強法
先に述べたような流れをつかむための簡易的な参考書や漫画からスタートして次に覚えるのは重要語句です。流れをつかむための参考書にも最重要語句は載っていますが、流れをつかむことに重点を置いている為、重要語句でさえも載っていないことがあります。
私は実際にナビゲーター世界史を受験生初期のころに愛用していました。ナビゲーターの単語を覚えきってから挑んだ共通テスト模試は60点しか取れず、選択肢に初めて見る単語があるといったレベルでした。
そこでせっかくインプットした流れと最重要語句に徐々に単語を肉付けしていくということが必要となってきます。
この単語の肉付けの作業は流れをつかんでいるとそんなに苦にならないはずですし、むしろどんどん新しいことが知れてさらに世界史が好きになっていくと思います!この重要単語は学校で使っているテキストでも、塾で使っている教科書でも何でもいいです!
ある程度覚えたら問題集を使う世界史のアウトプットの勉強法
世界史や日本史の勉強はインプットがすべてだと思ってる人は多いと思います。極論ではありますが、インプットだけで完全に知識を覚えられる人なら、アウトプットは入試本番だけでも大丈夫です。
ですがほとんどの普通の人はインプットだけでは覚えたつもりになっていることがほとんどであり、忘れていたり、別の角度からの問題に対応できないケースがほとんどです。
私自身も予備校の講師からは効率よく世界史の点数を挙げる勉強法はアウトプットして穴を見つけてその穴をを埋めていく事だと言われていましたが、なんだかんだインプットに重きを置いてしまっていました。
ですが直前期になって必然的に問題演習の機会が増えると、自分で把握していなかった苦手な分野であったり、逆にどんな問題でもほぼほぼ完璧に解ける分野も見つかったりしました。
世界史のアウトプットは苦手を見つけるためにおすすめの勉強法
アウトプットには苦手な分野をあぶりだして、穴を埋めるという効果がオーソドックスなものとして挙げられます。ですが私が過去問演習を通してアウトプットをすることによって見えてくるいいところは、理解しきっている分野の復習時間の削減ができるというところです。
核としているテキストを何回も赤シートで隠し反復していると、全部覚えていてスラスラ解答できる分野は勉強をしていて気持ちいいしストレスなく進めれると思います。ですが勉強はやはりつらい時にこそ頭がよくなるので、アウトプットから分かった穴を埋めて効率よく点数アップにつなげましょう!!
アウトプットはどれくらいの割合でやればいいですか?という質問をよく聞かれていたので答えるとインプット:アウトプットは結論、半々で行うのがベストだと思います!ですが意識としては4:6のイメージで行えばいいと思います。

イメージでという表現を使ったのは、やはりなんだかんだ暗記科目と思われインプット中心にやってしまうためイメージは4:6と書きました。アウトプットのほうが楽しいとは思うのでどんどん挑戦してみてください!
▽大学受験の世界史の勉強法をもっと詳しく知りたいという方はこちら
 【大学受験】世界史の超効率的な勉強法を徹底解説!
【大学受験】世界史の超効率的な勉強法を徹底解説! 世界史の共通テストで9割を取る勉強法のポイント
共通テストの世界史で9割を取るために重要なことは何個もありますがその中で知るだけで共通テストの点数が大きく変わる二つの事を紹介します。
インプットに時間をかける勉強法では共通テストでの世界史9割は厳しい
世界史は基本的にインプットといった通史の世界史の知識を頭に入れている勉強法が主です。このインプットの作業はとても重要ですが、知識をいくら詰め込んでもその世界史の知識が即座に出てこなければ共通テストの世界史は時間内に終わりません。
世界史の共通テストが時間との勝負であることは言うまでもなく、そのためにインプットの時間をできるだけ割き、アウトプットで世界史の知識を引き出せるようになることが重要です。
世界史の共通テストで9割を取ってくる受験生はとてつもない知識があるのではなく、浅く広い世界史の知識を他の受験生よりも引き出すスピードがとても速いのです。
世界史で苦手なところを残す勉強法は共通テストではおすすめできない
共通テストは毎年世界史のどの部分がでるかは誰にもわかりません。世界史の膨大な量の分野からどこが出てもいいように対策しておくのが定石ですが、多くの受験生が難点か苦手な部分を抱えて共通テストに挑みます。
一つでも苦手な部分があれば大問一つ分、つまり15点ほどを全く取れない状況になってしまいます。それは世界史の共通テストで9割を目指すには程遠いものになります。
ですので受験生は夏から受験期にかけて様々な模試で自分が世界史のどの部分が苦手なのかを理解し、その都度対策をしていくことが重要でしょう。
共通テストや二次試験の世界史の過去問の解答を見るときは各大問で回答率を計算してみると自分の世界史の弱い部分が割ると思います。


世界史の共通テストの過去問のおすすめの勉強法
世界史の勉強法のアウトプットで共通テストや二次試験の過去問を進めるのは受験生ならば絶対に通る道です。そこで世界史の共通テストなどの過去問を解く時の注意点をここで述べておきます。
世界史は過去問の勉強法は始める時期が重要
世界史の過去問をいつ始めようと迷っている人は多くいると思います。世界史の勉強法の中で過去問をは勉強法の中でも最終段階に位置します。
世界史の共通テストの過去問は基本的に秋から冬に始めるのがいいと言われてます。それはある程度世界史の知識が引き出せる状態にあり、世界史の模試などが一通り通史を終えた段階にあるからです。
世界史の共通テストは本当に部分ごとで構成されているので、共通テストの過去問や実践対策問題集などで世界史の知識を試し、自分の弱い分野を理解し早めに世界史の抜けがないようにしましょう。
二次試験の世界史の過去問はしっかり分析することがおすすめ
多くの受験生が世界史などの二次試験の過去問を解くだけで終わっていると思います。
しかし世界史でその解き方を行っていいのは共通テストまでです。世界史の二次試験は各大学で全く傾向が違います。時事問題の記述を求めてきたり、中国史の記述問題が多いなど本当にそれぞれの大学によって様々です。

ですので共通テストが終わり世界史の二次試験の対策に移る人はあらかじめ共通テストの前に二次試験ではどのあたりが多めに出るのかなどをチェックして共通テストの世界史の勉強に役立てるととても有効になります。
共通テストの世界史の特徴
まずは共通テストで8割〜9割取りたい人は必ず知っておきたい共通テストの世界史の特徴について確認していきましょう。
世界史は共通テストの勉強法では“重要単語”が多い
世界史って世界の何千年にわたる歴史を全部勉強するから覚えなきゃいけない重要単語がありえないくらい多いんだよね、その数なんと6000語と言われています。6000語って数字だけ見ると数に圧倒されるけど全然心配する必要はありません!
なぜなら英語と比べたら圧倒的に少ないし覚えやすいからです。早慶に合格するために必要な英単語数は10000語といわれています。
更にそこから熟語や英文法、構文解釈、速読の練習が必要となります。その事を考えると世界史を勉強するなんて楽だと思います
共通テストのための世界史の勉強法を確立できる受験生が少ない
大学受験のスタート時期ってどんなに早くても高校1年生からだよね?と思っている人がほとんどだと思います。逆に今まで高校受験頑張ってきたんだから高校2年生から始めたって十分だろと思う人も多いと思います。
かつての私もそう思っていましたし高校三年生から受験勉強を始めたので皆さんに偉そうに早く勉強しろとは言えません。ですが皆さんが目指すMARCH、関関同立、早慶に合格する多くは中高一貫の受験生なのです。
中高一貫校では中学一年生のころから公立学校の2倍くらいのスピード間で授業が進んでおり、開成、灘といった都会の最上位校は中三時点で普通の公立高校の生徒が3年間で習う分を先取り学習で中学生のうちに終わらせています。
流石に話し盛ってるだろ~と思うかもしれませんが、事実慶應の私の友人に開成出身の人がいますが高校一年生のころには早稲田の入試問題を周りに解いてるやつがいたと言っていました。
勉強法次第で世界史は日本史より共通テストで逆転しやすい
そのような最上位中高一貫校に通う生徒は中学受験の段階で日東駒専レベルの日本史は十分合格点はとれるともいわれています。
つまり日本史を選択すると高校一年生から始めたとしてもすでに中学3年分以上の勉強の差が出来ています。
こんな状態から逆転するのは大変だし不可能に近いですよね。
でも世界史はその差はありません。というのも中学受験では世界史を扱うことはほとんどなく中高一貫校の中学生も中学でほとんど学習していないからです。なので高校一年生の時点では受験エリートといわれるような人とも世界史においては差がないのです!
ここまで読んだら世界史でなら逆転合格をつかめるという意味がわかってきましたよね??これからの努力であのエリート集団に勝ち切りましょう!
世界史の共通テストで9割を取る土台は“世界史の基本的な用語”
世界史の勉強法において大体の流れがわかったら次に基本的な用語を覚えていきましょう。世界史ではあくまでも流れを頭に入れるのが先です。
世界史の基本的な用語とは共通テストで出題されるレベルの用語です。使う教材は流れを掴むために使用した教材でも構いません。
世界史の勉強法として使える用語のイメージとしては基本的な用語が一通り網羅されていれば、オッケーです。
この時に、大事なのは出来事の因果関係なども、まとめて覚えてしまうことです。そういった世界史の勉強のやり方をすることでより印象に残りやすくなります!
ここが一番の山ですが、頑張れば試験での大幅得点upが狙えるので頑張りましょう!
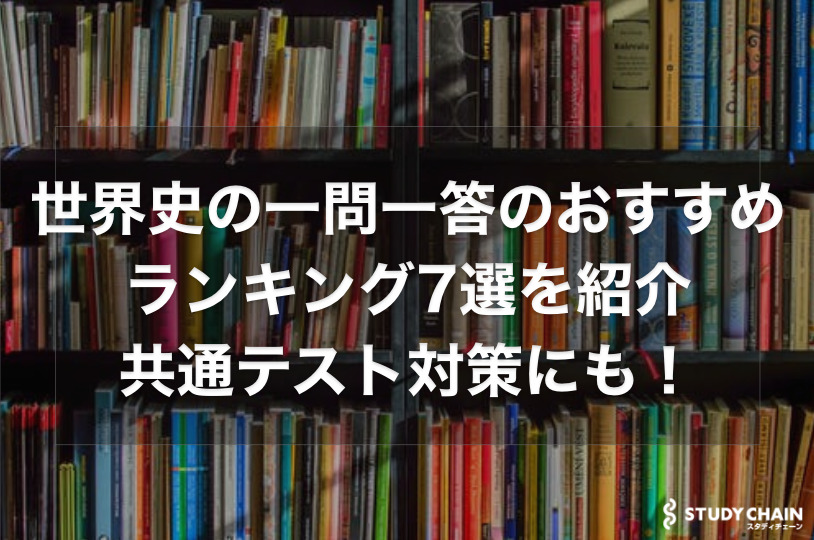 世界史の一問一答のおすすめランキング7選を解説!定期テスト対策にも!【大学受験】
世界史の一問一答のおすすめランキング7選を解説!定期テスト対策にも!【大学受験】 各志望校におすすめの世界史の勉強法を紹介!
世界史の勉強法は受験生の志望校によってかなり変わってきます。共通テストだけ世界史を使う人や二次試験までハイレベルな世界史の勉強法を要求されるなど様々です。
世界史の共通テストで9割を取ることのできるおすすめの勉強法とは
大学受験の世界史の勉強法として知らなければならないのは、自分にあった参考書と過去問に11月までに入る上でいつまでに基礎を固めていつから応用の問題を解くのかといった勉強計画が重要になります。
共通テストの世界史で9割をとるための勉強法は独学で進め行く上ではとても重要で下に貼っている記事を参考にして勉強を進めましょう!世界史の共通テストで9割をとることでしっかり二次試験や共通テスト利用で有利に進むことは間違いないのでまずは共通テストの過去問からしっかり対策していきましょう!
早難関大志望におすすめ。世界史の論述の勉強法や対策を解説
世界史の論述はもちろん旧帝大などを志望する人には必要ですが、論述が必要ない大学も数多くあります。ただ論述は世界史の勉強において時代の流れの整理や時代の年号の整理に非常に役立つためぜひそこで悩んでいる方は活用してみてください。
基本的に早慶の世界史は共通テストと違い記述の問題かつかなり深い内容で出題されます。ですので共通テストの勉強はもちろんのこと選択肢での出題される問題も記述で問われてもいいように対策をすることが重要です。
共通テストでは“世界史の流れを掴む”勉強法がおすすめ
共通テストの世界史の勉強法でまず何から始めようと考えている人が多いと思います。そこで、ここでは共通テストの世界史でなぜ“流れ”が重要になるのか、その対策を二点紹介します!
共通テストの世界史は選択肢なので絶対に間違えない勉強法を徹底する
世界史の共通テストは選択式の問題となっているので、まず部分点という概念がないです。ですので、世界史の共通テストの勉強法では絶対に間違えないように選択肢を絞る勉強法が必須です。
世界史の共通テストでは主に問題文の中から問いを投げられるので、流れがわかっていないとその問題文を読むのに時間を取られ問題を解く時間が無くなります。ですので共通テスト用の世界史のの問題集で対策を練っていくのがいいと思います。
“流れ”を掴む勉強法は二次試験の世界史の勉強法にも生きる
世界史の共通テストを終え二次試験にむけ問題集を解く時間があると思いますが、そこでも世界史の共通テストの勉強法が生きてきます。
共通テストではなく世界史の二次試験では主に記述問題が問われます。そこでは共通テストとは少し違う出題形式となりますが、100文字以下の記述問題が大きな得点源になります。
共通テストの勉強法で流れをつかめていると100文字程度の世界史の記述問題であればスムーズかつ高得点をねらえる解答をつくることができます。
共通テストの世界史の勉強法で流れを掴める参考書
ここでは先程説明した共通テストの世界史の流れを掴める参考書を紹介していきます!
漫画で世界史を学ぶなら“マンガで世界史が面白いほどわかる本”

この参考書は大学入試向けの解説書なので、マンガ部分だけでなく解説文も非常に多いです。そのため、世界史におけるより「勉強」という意識は強くなります。大学受験の世界史の橋渡しにはおすすめであり、学生にも分かりやすい丁寧な解説がされているため苦手な世界史もかみ砕いて覚えることができる参考書になります。
共通テストの世界史の勉強法として漫画を活用していく中で有名な歴史人物のマンガが楽しいと感じうる人は多いと思います。全てフルカラーで読みやすい。世界史の国ごとに古代から現代までを一気に読める点でおすすめできます。
世界史の中での時代ごとにいろいろな国に話が飛ぶため、教科書だけでは学習しにくいのが世界史の弱点で、そんな弱点を国別のカラーマンガで、その弱点をクリアしました。解説は、大手予備校の世界史の実力派講師が、わかりやすく語っています。世界史において13の国がどのようにして始まり、どのような歴史を歩んできたのか、スッキリと学べる参考書です。
大学入試 マンガで世界史が面白いほどわかる本をAmazonでみる
世界史の流れをわかりやすく掴むなら“タテから見る世界史”

先ほど述べたように、世界史の共通テストの勉強法に大切なのは物事の流れを「タテの流れ」で見ることと「ヨコの流れ」で見ることの2点が重要となってきます。
この参考書では共通テストの世界史の流れで大切なタテの流れを学べる参考書となっています。
共通テストの世界史の勉強法は大体わかるけれども「世界史の流れがつかめない…」という人へ。
世界史の教科書は古代~現代という時代の区切りで書かれているため、ローマの次はインド、その次は中国…とどんどん地域が飛んでいきます。そのため「通史の流れがイマイチつかめない」という悩みを抱えている人が非常に多いです。
この世界史の参考書では各国・地域ごとに通史を一気に整理して解説しているので、共通テストで出題されるような流れを簡単に理解することができます。
共通テストの世界史の勉強法において「ヨコ」を問う問題を解くためには、「タテ」の知識が不可欠です。「ヨコのつながり」がわからない、という人は「タテの流れ」を理解できていないということが多いです!
タテからのセットで“ヨコから見る世界史”

先ほど述べたように、世界史の勉強に大切なのは物事の流れを「タテの流れ」で見ることと「ヨコの流れ」で見ることの2点が重要となってきます。
この世界史の参考書では世界史の流れで大切なヨコの流れを学べる参考書となっています。世界史全体を時代ごとにヨコ割りにして整理し、同じ時代に他地域で起こった別々の出来事の因果関係を読み解いていきます。
特に難問の多い上位校の入試問題では、世界史全体を「ヨコから問う」問題が主流となっています。また、共通テストで知識量が重要と思われがちな正誤問題の対策も、出来事の相互の関連性を考えながら学ぶことがカギとなります。論述問題でも「ヨコ」の流れが問われます。
だからこそしっかりと今回紹介した参考書を使うことで皆さんの世界史の勉強法を見直すきっかけにもなると思います。
世界史で“土台”をつくる勉強法におすすめの参考書
世界史の共通テストではやはり土台となる世界史の知識や背景を学習する必要があります。ですのでそのような勉強法におすすめの参考書を紹介していきます!
漫画で進める世界史の勉強法は“教科書よりやさしい世界史”

この世界史の参考書は会話形式で構成されていて、イラストも美麗で、時間もかからず、非常に読みやすいといった長所をもつオールカラーの参考書です。
共通テストで世界史を使おうと決めた受験生や世界史を習う前に大枠をつかむことにも有効でありますし、習った後の時代の流れの把握にも有効活用できます。
一から世界史の学習、勉強を始めていく人は本書で基本事項を身につけることを目的として使用していきましょう。
そして、諸説世界史など世界史の流れをつかんできた人は本書を復習用のテキスト代わりに使っていきましょう。
世界史の超王道の参考書なら“ナビゲーター世界史”

世界史受験の王道かつおすすめの参考書!共通テストの世界史の勉強法がわからなかったら、とにかくナビゲーターをやることをお勧めします。
世界史の勉強をしていく中で教科書や他の参考書が難しいと感じたらまずはこの参考書で流れを抑えるのがおすすめです。教科書の無機質な文よりも口語的に出来事を関連して覚えることができます。
世界史の点数が爆伸びする時は“過去問と問題集”でアウトプット
共通テスト用の世界史の参考書を使ってある程度インプットが行われ、実力がついてきたら次に行わなければならないのが問題集を使う世界史のアウトプットです。
世界史の勉強法において特にしっかり勉強しなければならないのが問題集を解くということです。
世界史の記述問題集と言えば“実力をつける世界史100題”

共通テストの世界史の勉強法、参考書の中でも難易度のかなり高い問題が収録されており、とても難しい知識を問われますので、難関私大の世界史で高得点が取りたい人向けに仕上がっています。そのような点を踏まえ、世界史の学習や勉強を一から始める人や標準レベルの問題をこなしていきたい人にはオススメしません。
また、大学受験の世界史の参考書の中では内容が非常に濃いことから、短期間で世界史の総復習を行うことを目指す人にも不向きであるといえます。問題の内容としては、用語を問う記述問題が中心であり、語句や関連する知識を問う空欄補充問題や正誤問題も出題されています。
実力をつける世界史100題[改訂第3版] をAmazonでみる
共通テストの後は“合格へのトライ 世界史Bマスター問題集”

この参考書は世界史Bの用語を問う問題が出題され、解説文も詳しく書かれているといったオーソドックスな形の問題集です。この参考書はどちらかといえば問題演習に重点を置いた参考書ですので、始める前に世界史の流れや基本的なレベルの歴史事象をインプットしておく方が効果的です。
問題はセンター試験や共通テストレベルのものが中心です。共通テストにでるような世界史の用語、年号なども一つ一つしっかりと復習していけば基本レベルの問題は解けるようになるでしょう。
合格へのトライ 世界史Bマスター問題集 改訂版をAmazonでみる
難関大の世界史の知識を“世界史一問一答【完全版】”でインプット

有名な東進の一問一答シリーズ、構成は文章の穴を埋めていく式の問題が、重要度に応じて様々に出題されます。共通テストで世界史をつかうひとにもおすすめの参考書です。
1周目は最も★の数が多い問題だけ覚え、それ以外は2周目以降に覚える、というように優先順位づけをはっきりしましょう。参考書を読んで間もないうちに、該当範囲の重要用語を一問一答で暗記するようにすると、理解も促進され、より効果的な学習ができます。
まとめ
今回は世界史の共通テストの勉強法について解説していきましたが、いかがだったでしょうか?
世界史の共通テストは年によって難易度が本当に変わってくるので難易度に関係なく常に9割を目指せるように勉強法を確立させていきましょう。
▽共通テスト対策のおすすめの勉強法一覧

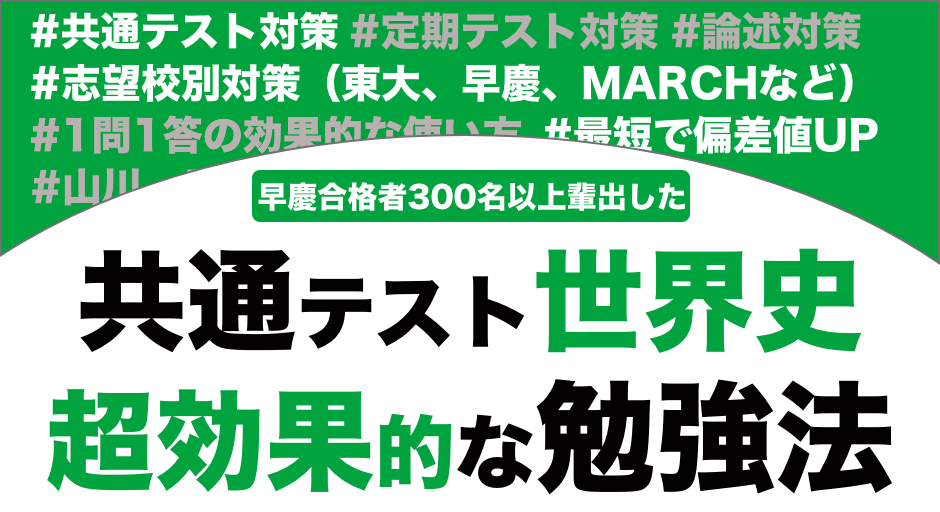

逆転合格特化塾2.png)

逆転合格特化塾.png)