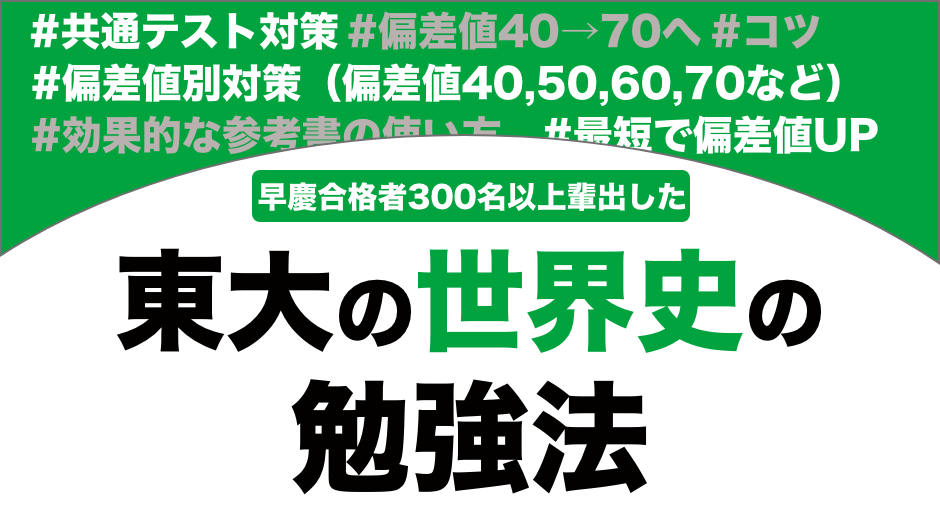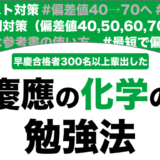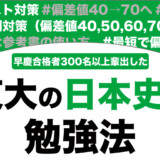本サイトの表記には、一部プロモーションを含みます
東大に合格できる効果的な世界史の勉強法を解説します。東大の世界史対策に実際にやってよかった勉強法とその順番も合わせて紹介します。また東大の世界史対策におすすめの参考書も合わせて紹介します。
いきなり最終結論!東大に合格するための世界史の勉強法の順番
東京大学に合格するための世界史の勉強法を解説します。
この段階では世界史の全体像を把握することに重点を置きます。まず教科書や講義本を使って古代から現代までの通史を一通り学習していきます。ここで大切なのは細かい知識の暗記よりも歴史の大きな流れを理解することです。
特に東大世界史では地域間の交流や同時代の比較が頻出するため、単に出来事を暗記するのではなく、なぜその事件が起きたのか、その背景にはどのような要因があったのかを意識しながら学習を進めていきます。また地図を常に参照しながら学習することで地理的な位置関係も把握していきましょう。
この時期は1日2時間程度の学習時間を確保し、40分は講義本を読み、30分は時代と流れで覚える世界史用語を使って理解を深め、残りの30分は星2以上の用語を一問一答で確認します。まずは星0と星1の用語は後回しにして構いません。2ヶ月から3ヶ月かけて通史の1周目を完成させることを目標にします。
使うべきおすすめの参考書:世界史探究または山川の詳説世界史 時代と流れで覚える世界史用語 山川世界史一問一答
通史の1周目が終わったら次は年号を中心としたタテの流れの学習に移ります。この段階では出来事の前後関係や因果関係をより深く理解することが目標となります。
年号を覚えることで歴史の出来事を時系列に沿って整理できるようになり、東大世界史で頻出の大論述でも的確な記述ができるようになります。1周目で学習した用語がなぜ起きたのか、どのような背景があったのかをより深く掘り下げていきましょう。
この時期の学習時間配分は1日2時間のうち40分を講義本の復習に充て、30分を年号サーキットトレーニング、30分を一問一答の復習に使います。2周目は1周目よりも早いペースで進められるはずですが、年号をしっかり覚えることで後の論述対策が格段に楽になります。1ヶ月から1ヶ月半で2周目を完成させましょう。
使うべきおすすめの参考書 超効率世界史年代サーキットトレーニング 元祖世界史年代暗記法 世界史探究または詳説世界史 山川世界史一問一答
この段階からは本格的な論述対策に入っていきます。東大世界史の特徴である論述問題に対応するため、短い論述から段階的に練習を始めます。
まず60字程度の短い論述から始めて、徐々に字数を増やしていく訓練を行います。論述を書く際には必ず採点基準を意識し、どのようなポイントを押さえれば加点されるのかを理解することが重要です。また地域史や海域史といったヨコの流れも意識的に学習していきます。
この時期は1日2時間半の学習時間を確保し、30分を講義本の復習、45分を論述問題集、45分を一問一答、残り30分を地図や資料集の確認に充てます。論述は必ず第三者に添削してもらうことをおすすめします。学校の先生や塾の講師に見てもらい、フィードバックを受けることで着実に力がついていきます。2ヶ月かけてこの段階を完成させましょう。
使うべきおすすめの参考書:みるみる論述力がつく世界史 判る解ける書ける世界史論述 詳説世界史論述問題集 各国別世界史ノート 世界史用語集 詳説世界史図録
この段階では共通テストの過去問やセンター試験の過去問を活用して実戦的な演習を積んでいきます。共通テストは基礎的な知識を確認する良い機会となります。
共通テストの問題を解くことで自分がどの時代のどの地域が苦手なのかを分析していきます。間違えた問題は必ず講義本や用語集に戻って確認し、苦手分野を一つずつ潰していきましょう。表を作って時代ごとや地域ごとに自分の弱点を整理すると効果的です。
1日2時間半の学習時間のうち30分を講義本の復習、45分を共通テスト問題集、45分を一問一答の復習、残り30分を苦手分野の補強に充てます。10年分から15年分の過去問に取り組むことで基礎知識を盤石なものにしていきます。この段階も2ヶ月程度かけてじっくり取り組んでいきましょう。
使うべきおすすめの参考書 きめる共通テスト世界史 共通テスト世界史過去問集 センター試験世界史過去問集 山川世界史一問一答 世界史用語集 詳説世界史図録
この段階では東大の過去問を使った本格的な論述演習に入ります。東大世界史の特徴である大論述は小論述の集合体と言われるように、これまで学習してきた知識を総動員して解答を作成していきます。
大論述では問題文をしっかり読み解き、何が求められているのかを正確に把握することが重要です。構成を考える時間も含めて35分から40分程度を目安に演習を行います。また東大では地域史や海域史が頻出するため、特定の地域に焦点を当てた学習も並行して進めていきます。
1日2時間半の学習時間のうち60分を過去問演習、60分を論述問題集の復習、30分を地域史や海域史の学習に充てます。過去問は最低でも10年分、できれば25年分に取り組むことで出題パターンを完全に把握していきます。この段階も2ヶ月かけてじっくり取り組んでいきましょう。
使うべきおすすめの参考書 東大の世界史25ヵ年 荒巻の新世界史の見取り図 詳説世界史論述問題集 各国別世界史ノート 世界史リブレット 山川世界史一問一答 世界史用語集
最終段階では東大の過去問演習を徹底的に行います。過去問は何年分解いたかよりもどれだけ丁寧に復習したかの方が重要です。
間違えた問題や書けなかった論述は必ず講義本や用語集に戻って確認します。また解答を作成した後は必ず添削を受けることで自分では気づかない改善点を見つけることができます。東大世界史では特に現代史の出題が増えているため、20世紀以降の歴史について細かいタテの流れやヨコの流れを徹底的に整理していきます。
1日2時間半の学習時間のうち60分を過去問演習、60分を間違えた問題の復習と講義本の確認、30分を苦手分野の最終確認に充てます。この段階では新しい参考書に手を出すのではなく、これまで使ってきた参考書を何度も繰り返し復習することが大切です。入試直前まで継続して取り組んでいきましょう。
使うべきおすすめの参考書 東大の世界史25ヵ年 詳説世界史論述問題集 攻略世界史各国史 HISTORIA 世界史探究または詳説世界史 山川世界史一問一答 世界史用語集 詳説世界史図録


東大世界史の特徴
東大世界史は600字の大論述を筆頭に、論述問題のみで構成されているため、単なる暗記では太刀打ちできません。歴史の因果関係や各地域のヨコのつながり、タテの流れを深く理解する必要があります。
最初の2ヶ月は世界史探究や講義本を使って通史の基礎を固め、次の3ヶ月で年号や地図を活用しながら通史を完成させます。その後4ヶ月かけて100字から300字程度の論述問題集で記述力を養い、最後の3ヶ月で東大の過去問を20年分以上解いて東大特有の出題形式に慣れることが合格への最短ルートです。
東大世界史は知識量だけでなく、その知識を使って歴史的な因果関係を説明する力が問われます。そのため通史の学習段階から常になぜこの事件が起きたのか、どのような影響を与えたのかを意識しながら勉強を進めることが重要です。
東大の世界史の学部ごとの特徴と対策
東大の世界史は文科一類、文科二類、文科三類で共通の問題が出題され、試験時間は150分で第1問から第3問まで全て論述形式です。
東大の世界史の大門別の特徴
第1問は600字の大論述が1題出題され、配点は60点中20点と非常に高くなっています。テーマは近現代史が中心で、複数の地域にまたがるテーマ史や文化交流史などが頻出です。
第2問と第3問は120字から200字程度の中論述が各3問程度出題され、古代から現代まで幅広い時代と地域から出題されます。特に東アジア史、イスラーム史、ヨーロッパ史のバランスが重要で、一つの地域に偏った勉強では対応できません。
東大の世界史の大問別の対策方法
第1問の大論述対策では、複数の地域や時代をまたぐテーマについて600字でまとめる練習が必須です。帝国主義、民族主義、宗教と政治の関係などの頻出テーマについて、自分なりの答案構成を作っておくことが有効です。
第2問と第3問の中論述対策では、各国史の流れを正確に把握することに加えて、同時代の他地域で何が起きていたかというヨコの関係を理解することが重要です。例えば19世紀のヨーロッパの動きがアジアやアフリカにどのような影響を与えたかを説明できるようにしておきましょう。
また全ての大問に共通して、歴史用語を正確に使いこなす力が求められます。単に出来事を羅列するのではなく、因果関係を明確にしながら論理的に記述することを常に意識して練習することが合格への鍵となります。
東大の世界史対策に実際にやってよかった勉強法3選
東大の世界史対策に実際にやってよかった勉強法を3つ紹介します。
通史学習で因果関係を徹底的に理解する勉強法
世界史探究や詳説世界史を読む際に、ただ読むだけではなく各事件の原因と結果を自分の言葉でノートにまとめる勉強法が非常に効果的です。1日2時間のうち1時間を講義本の読み込みに使い、残り1時間で読んだ範囲の重要事件について原因を3つ、結果を3つ書き出す練習をします。
例えばフランス革命であれば、原因として財政難、啓蒙思想の普及、身分制度への不満を挙げ、結果として王政の廃止、人権宣言の発布、ナポレオンの台頭などを書き出します。このように因果関係を意識して整理することで、東大の論述問題で求められる歴史的思考力が自然と身につきます。
この勉強法を3ヶ月継続すると、歴史の流れが立体的に見えるようになり、初見の論述問題でも論理的な答案を書けるようになります。特に近現代史では複雑な国際関係を理解する上で非常に有効な方法です。
年表と地図を使ったヨコの関係整理法
同じ時代に世界各地で何が起きていたかを把握するために、自分で年表を作成する勉強法が東大対策では必須です。1日30分を使って、100年単位で区切った年表に各地域の主要事件を書き込んでいきます。
例えば1850年から1900年の年表を作る際、ヨーロッパの帝国主義の動き、中国のアヘン戦争から義和団事件まで、日本の開国から日清戦争まで、インドのセポイの反乱、アフリカの分割などを同じ年表上に配置します。これにより各地域の動きの関連性が一目で分かるようになります。
同様に地図も自分で書く練習が効果的です。白紙の世界地図に各時代の主要国家や貿易ルート、戦争の場所などを書き込むことで、地理的な位置関係と歴史事象の関係が深く理解できます。この作業を毎日30分続けることで、東大の論述問題で求められる広い視野が養われます。
過去問の模範解答を分析して型を作る勉強法
東大の過去問を20年分集め、それぞれの模範解答を徹底的に分析する勉強法が合格への近道です。1日1時間を使って1年分の問題を解き、1時間かけて模範解答を分析します。
模範解答の分析では、どのような構成で書かれているか、どの程度の詳しさで説明しているか、どのような接続詞を使っているかを細かくチェックします。特に600字の大論述では、序論で問題提起、本論で地域ごとまたは時代ごとの説明、結論でまとめという構成が一般的です。
この型を自分のものにするために、同じテーマで複数年分の解答を比較し、共通する論述パターンを抽出します。例えば帝国主義をテーマにした問題では、経済的背景、政治的背景、イデオロギー的背景という3つの視点から説明する型が有効です。この勉強法を3ヶ月続けることで、どんな問題にも対応できる論述力が身につきます。
東大の世界史の勉強法の実践におすすめの参考書
東大の世界史の勉強法の実践におすすめの参考書を紹介します。
詳説世界史
山川出版社から出ている詳説世界史は東大世界史対策の基本となる教科書です。東大の論述問題は教科書レベルの知識を深く理解していることを前提としているため、この教科書を完璧にマスターすることが第一歩となります。
詳説世界史の特徴は、歴史の流れを丁寧に説明しながらも、重要な事件や人物について詳しく記述している点です。また欄外の注釈や図版も充実しており、本文だけでなく注釈まで読み込むことで東大レベルの知識が身につきます。
この教科書は通史学習の最初から最後まで使い続けることをおすすめします。1周目は全体の流れを把握するために1日30ページ程度のペースで読み進め、2周目以降は論述問題を解く際の辞書として活用します。特に因果関係が分からなくなった時は必ずこの教科書に戻って確認する習慣をつけましょう。
詳説世界史研究
山川出版社の詳説世界史研究は、詳説世界史よりもさらに詳しい内容が記載されている参考書です。東大の論述問題では教科書レベルを超えた知識が必要になることもあり、この参考書がその補完として非常に有効です。
詳説世界史研究の最大の特徴は、歴史学の研究成果を取り入れながら、各事件の背景や影響について多角的に説明している点です。例えば宗教改革について、神学的な側面だけでなく、経済的・政治的・社会的な背景まで詳しく解説されています。
この参考書は通史を一通り終えた後、論述演習と並行して使用することをおすすめします。特に600字の大論述で深い理解が必要なテーマについては、この参考書で背景知識を補強することで説得力のある答案が書けるようになります。毎日1時間程度、論述問題で出題されたテーマについてこの参考書で調べる習慣をつけましょう。
時代と流れで覚える世界史用語
文英堂から出ている時代と流れで覚える世界史用語は、歴史用語を時代の流れの中で理解するための問題集です。東大の論述では単に用語を知っているだけでなく、その用語が歴史の中でどのような意味を持つかを理解していることが求められます。
この問題集の特徴は、バラバラに用語を覚えるのではなく、一つの事件や時代に関連する複数の用語をセットで学習できる点です。また解説が充実しており、なぜその用語が重要なのか、他の事件とどう関連するのかが分かりやすく説明されています。
通史学習の1周目から並行して使用し、1日30分程度のペースで進めることをおすすめします。講義本で学んだ範囲をこの問題集で確認し、用語の理解を深めていきましょう。特に論述問題を書く際に使える用語かどうかを意識しながら学習することが重要です。
世界史論述練習帳
駿台文庫から出ている世界史論述練習帳は、100字から300字程度の論述問題が豊富に収録されている問題集です。東大の論述対策として、この問題集で基礎的な論述力を養うことが非常に効果的です。
この問題集の特徴は、テーマ別に問題が整理されており、段階的に論述力を高められる構成になっている点です。また模範解答だけでなく、答案作成のポイントや採点基準も示されているため、独学でも論述力を伸ばすことができます。
通史を2周終えた段階からこの問題集に取り組み始め、1日2問のペースで進めることをおすすめします。最初は模範解答を見ながら答案の型を学び、徐々に自力で書けるようにしていきましょう。特に因果関係を明確に書く練習を重ねることで、東大レベルの論述力が身につきます。
東大の世界史25カ年
教学社から出ている東大の世界史25カ年は、過去25年分の東大世界史の過去問と詳しい解説が収録されている問題集です。東大世界史の対策において、この問題集は必須の教材となります。
この問題集の特徴は、単に模範解答を示すだけでなく、出題の意図や答案作成のポイントが丁寧に解説されている点です。また年度ごとの傾向分析も掲載されており、東大世界史の出題パターンを理解する上で非常に役立ちます。
論述演習を3ヶ月程度行った後、本格的な過去問演習に入る際に使用します。最初は古い年度から始め、1日1年分のペースで解いていきましょう。解いた後は必ず模範解答と自分の解答を比較し、どこが足りなかったかを分析することが重要です。この作業を20年分以上繰り返すことで、東大世界史の合格答案が書けるようになります。
まとめ
今回は東大に合格するための世界史の勉強法について、基礎から過去問演習までの流れを解説しました。
東大世界史の勉強法についてのまとめは以下のようになります。