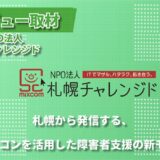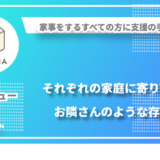「ボランティアは社会貢献だけでなく、自己実現の機会でもある」
この言葉は、『NPO法人 おりがみ』の理事長である都築則彦(つづき のりひこ)氏の活動理念を端的に表しています。同法人は、約450名の学生メンバー、若手社会人が主体となり、独自のボランティアマネジメントを展開。従来の「支援する側・される側」という固定的な関係性を超え、参加者全員が成長できる場の創出を目指しています。
特筆すべきは、その活動の多様性です。障害のある方との大規模な旅行企画「パラ旅応援団」、地域の伝統を復活させる「上野ハレノヒ計画」、そして中高生の地域参加を促す「習志野市地域わかもの会議(ちいわか)」など、独創的な取り組みを次々と生み出しています。
今回は都築氏に、団体設立の経緯から今後の展望まで、詳しくお話を伺いました。東日本大震災をきっかけに人生が大きく変わり、ボランティア活動に身を投じることになった氏の経験には、現代社会における「新しいボランティアの形」のヒントが詰まっています。
NPO法人おりがみの概要 – ボランティアを通じた社会課題解決と自己実現の両立
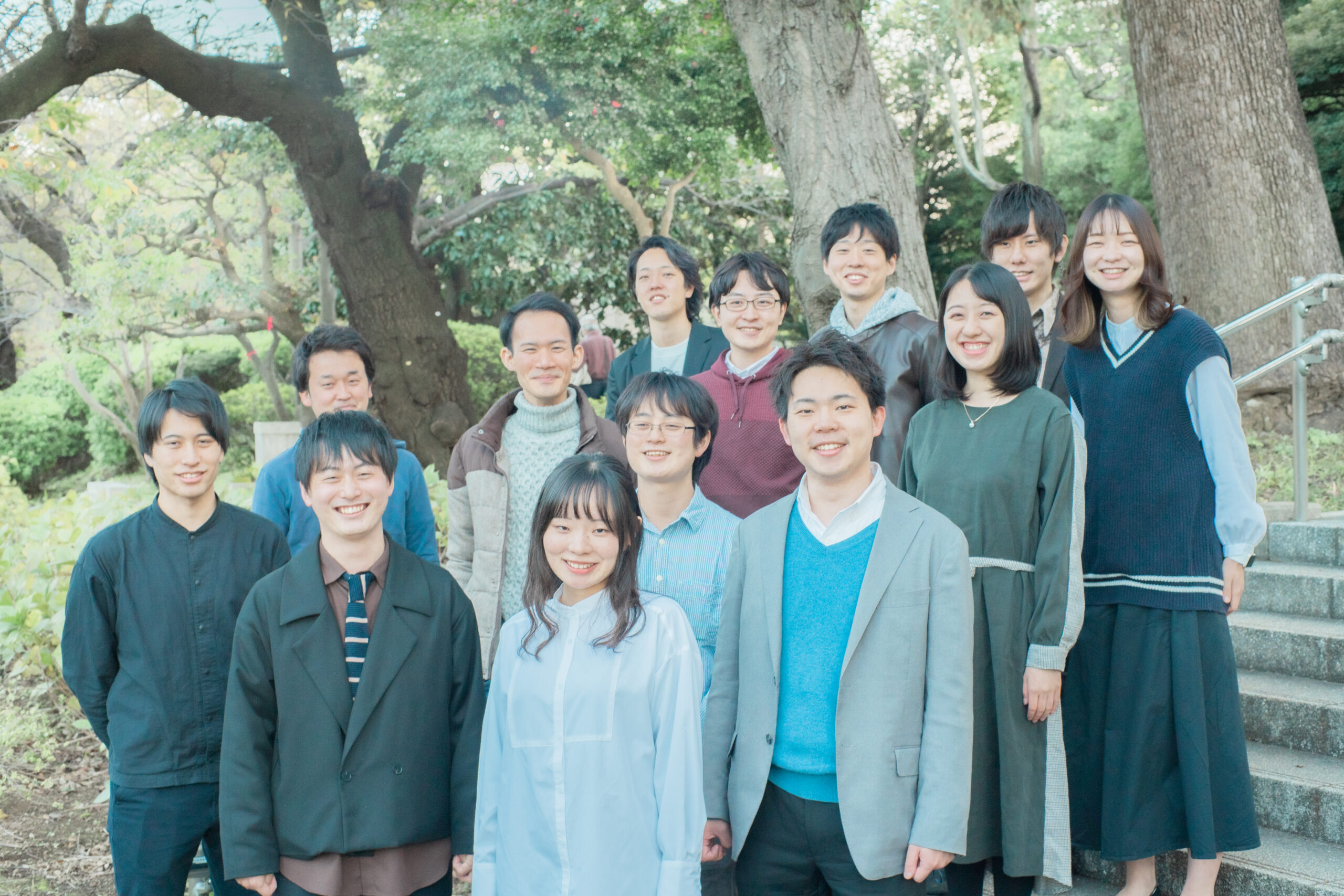
ー都築さま、本日はどうぞよろしくお願いいたします!まずは、『NPO法人おりがみ』の活動概要についてお聞かせください。
都築 則彦理事長(以下敬称略):NPO法人おりがみは、ボランティアのマネジメントを専門とするNPO法人です。私たちは、ボランティアを単なる社会貢献の手段としてではなく、参加者自身の自己実現の機会としても捉えています。現在、約450名の学生メンバーと若手社会人が在籍し、各々がボランティアプログラムの企画・運営に携わっています。
メンバーとして所属している学生は大学生のみですが、個別の事業では中学生や高校生もボランティアとして参加することがあります。彼らは主に受益者として私たちの活動に関わっていますが、時にはボランティアとして一緒に活動することもあります。
例えば、私たちの拠点がある習志野市では、高齢化が進む町会自治会の課題と、文化祭が実施されていない中学校の現状に着目し、地域と学校を結ぶ取り組みを展開しています。これにより、中学生の体験機会を創出すると同時に、地域コミュニティの活性化も図っています。
設立の経緯 – 東日本大震災がもたらした人生の転機
ー都築さまが『NPO法人おりがみ』を立ち上げた経緯について、お聞かせください。
都築:当団体の起源は、オリンピック・パラリンピックに関連した学生団体「おりがみ」にさかのぼります。私個人の経緯としては、家業である牛乳配達業を継ぐ予定だった人生が、東日本大震災を機に大きく変わったことが始まりでした。
私の家庭は経済的に厳しい状況にあり、本来であれば中学校卒業後に就職する予定でした。小学校4年生の頃から、深夜1時に起きて母の運転する車の助手席で牛乳配達を手伝い、朝6時に帰宅して学校に行き、放課後は友達と遊んで夜8時には就寝するという生活を送っていました。
高校には特待生として進学できましたが、大学進学は諦めていました。しかし、震災で家が大規模半壊し、保険金が下りたことで、思いがけず大学進学の機会を得ることができました。両親は家の修繕費用をローンで賄い、保険金を私の大学進学費用に充ててくれたのです。
この経験から、震災による人生の変化を社会にどう還元できるかを考えるようになりました。震災で苦しんだ人もいれば、私のように人生が良い方向に変わった人もいます。そんな中、東京オリンピック・パラリンピックの招致が決定し、この機会に社会に貢献できる何かを始めたいと考えたのです。
その後、多くのネットワークが形成され、様々なプロジェクトが生まれていきました。 オリンピック・パラリンピックという大きな目標に向かって活動する中で、私たちは思い描いていた夢がやがて実現していきました。
しかし、これらの活動をより持続的なものにし、社会により大きなインパクトを与えていくためには、大学卒業後もボランティアをできる仕組みの必要性を感じました。学生団体『おりがみ』に加え、NPO法人『おりがみ』を設立し、新たなスタートを切ることを決意したのです。
現在は、NPO法人の活動と並行して、家業も引き継いでいます。『おりがみ』の活動を通じて夢を実現し、理想とする人生を手に入れた今、両親への恩返しとして家業の経営に携わっています。就任から3期目を終え、ようやく黒字化を達成することができました。まだ道のりは長いですが、『おりがみ』での経験とネットワークを活かしながら、家業の発展にも尽力しています。
ユニークな特徴 – クリエイティブで参加しやすいボランティア活動
ー『NPO法人おりがみ』の特徴的な点について教えてください。
都築:最大の特徴は、ボランティアをクリエイティブに展開している点です。社会貢献活動は往々にして事業化が進み、少人数での専門的な取り組みになりがちですが、私たちは「誰もが参加できる」という要素を大切にしています。
例えば、宇宙開発プロジェクト「アースライトプロジェクト(Earth Light Project)」では、参加希望者を選考せず、興味のある人なら誰でも参加できるようにしています。オリンピックの聖火リレーをモチーフに、炎を成層圏で点灯し、世界平和のメッセージを発信する取り組みとして展開しました。
また、障害者支援の取り組み「パラ旅応援団」でも、高校生から大学生まで幅広い層が参加できる仕組みを整えています。支援する側とされる側という固定的な関係ではなく、共に楽しみながら活動できる場を創出することを心がけています。
活動を支える原動力 – 先輩への憧れが生み出す好循環
ー実際に参加されている450名ほどの方々は、どのような思いで活動されているのでしょうか?
都築:基本的には「先輩への憧れ」が大きな動機づけになっています。特に学生団体としての側面では、Instagramなどでの発信に力を入れており、「こんな素敵な活動をやってみたい」「大学生活を充実させながら意味のある活動がしたい」という思いを持つ学生が集まってきます。
かつては「この会社の社員になりたい」「この車を持ちたい」といったカテゴリーへの憧れが主流でしたが、現代では価値観が細分化され、何に憧れればよいのか分からない状況があります。そんな中、私たちの活動には様々なロールモデルが存在し、「この人のようになりたい」という個人への憧れを醸成しています。
私たちは10年を超える活動を通じて、特にオリンピック・パラリンピックという機会の中で、学生が憧れるようなモデル事業を数多く生み出してきました。これらの実績が「種」となり、新たに参加する学生たちの「自分もこんな大きなことをやってみたい」という意欲につながっています。今後は、こうした個人のロールモデルをNPO法人として対外的にも発信していきたいと考えています。
組織の理念 – 共生社会の実現に向けて
ー『NPO法人おりがみ』が特に大事にしている方針や理念があれば教えてください。
都築:最も重視しているのは「共生社会」の理念です。多様なメンバーが参加する中で、時には「あの人は足を引っ張っている」といった声が上がることもあります。しかし、私たちは相手を排除するのではなく、むしろ共に活動していく方法を模索することを大切にしています。
気を抜くと能力主義的な価値観に傾きがちで、「この人は仕事ができる」「この人は仕事ができない」といった分断が生まれやすくなります。しかし、私たちが目指すのは、「誰とでも協力できる」「多様なメンバーと活動できる」といった温かさを持った人材を育てることです。
特に教育関連の事業では、中学生や高校生の意見が十分に言語化されていない場合でも、それを待つ姿勢が重要です。お互いを理解し合い、認め合える関係性を築くことが、教育事業の根幹であり、大学生メンバーにもこの考え方を浸透させるよう心がけています。
特徴的な3つの事業 – 多様な活動展開
ー『NPO法人おりがみ』として特徴的な活動を、いくつか教えていただけますでしょうか?
都築:1つ目は「パラ旅応援団」です。昨年は障害のある方と学生ボランティア合わせて208名で大規模な旅行を実施しました。障害のある方々は、福祉施設での生活を通じて交流範囲が限定されがちです。その結果、世界が徐々に狭くなっていく傾向にあります。
この状況は、一見うまくいっているように見えても、何か問題が発生した際に対応が難しくなる可能性があります。また、家族が全ての負担を背負わなければならないという課題もあります。そこで私たちは、学生ボランティアとの旅行を通じて、新しい出会いと思い出を作る機会を提供しています。今年は牧場への旅行を予定しており、支援する側とされる側という関係性を超えた、友人としての関係づくりを目指しています。
2つ目は「上野ハレノヒ計画」です。上野の商店街で様々なお祭りを企画・運営しています。学生メンバーが地域を歩き、歴史や文化、面白いお店などを発掘し、それらを活かした企画を立ち上げています。その集大成として、50年前に途絶えた盆踊り大会を復活させました。この取り組みはオリンピックの公式文化プログラムにも選ばれています。
3つ目は「習志野市地域若者会議ちいわか」です。約10年前に文化祭が中止になった地域の中学校の課題に着目し、新たな交流の場を創出する事業を展開しています。コロナ禍で一時中断を余儀なくされましたが、大学生がファシリテーターとなって中学生・高校生と地域住民をつなぎ、共に事業を立ち上げていく取り組みを行っています。これは市の補助事業として実施されています。
今後の展望 – ボランティアマネジメントの体系化を目指して
ー今後、特に注力したい取り組みについて教えてください。
都築:最も力を入れたいのは、ボランティアマネジメントのスキルを体系化し、「ボランティアマネージャー」という職業を確立することです。その際、特に中学生・高校生の地域参加をフレームの一つとして組み込んでいきたいと考えています。
日本のボランティア支援は従来、「仲介型」が主流でした。つまり、ボランティアを求める側とボランティアをしたい側を単につなぐ形式です。しかし、これでは支援団体や個人の自発性に完全に依存してしまい、活動が嚙み合わなかったり、衰退したりする可能性があります。
そこで私たちは、より積極的に地域資源を活用し、新しい活動を立ち上げていく「介入型」の支援を目指しています。地域の様々な団体に働きかけ、新しい企画を提案し、そこに参加の場を作っていくという支援のあり方を、日本の標準にしていきたいと考えています。
さらに、「パラ旅応援団」については、活動地域を広げ、より多くの大学と連携していく展開も検討しています。これらの取り組みを通じて、ボランティア活動の新しい形を提示していきたいと考えています。
参加希望者へのメッセージ – ボランティアを人生の軸に
ー最後に、『NPO法人おりがみ』への参画を考えている方々へメッセージをお願いします!
都築:日本では「所属が終われば活動も終わる」という文化が根強くあります。高校卒業、大学卒業、引っ越し、子どもの卒業など、所属や肩書きの変更と共にボランティア活動を辞めてしまう傾向があります。
しかし、私がロンドンでボランティアを学んだ際、「ボランティアは人生をかけた旅(ボランティアジャーニー)だ」と教わりました。この考え方は、私の価値観を大きく変えました。
仕事や家庭だけに人生の全てを求めると、それが重荷となって辛くなることもあります。ボランティアを人生の重要な軸の一つとして位置づけることで、自己実現の場や居場所、新たな仲間との出会いなど、より豊かな人生を送ることができるのではないでしょうか。
私たちは世代を問わず、共に活動できる仲間を募集しています。中学生・高校生はプロジェクトへの参加が可能です。特に20代、30代の若手社会人の方々は大歓迎です。40代以上の方々も、ご一緒に活動できることを心より楽しみにしています。ボランティアを通じて、共に成長し、社会に貢献していける仲間との出会いを心からお待ちしています。