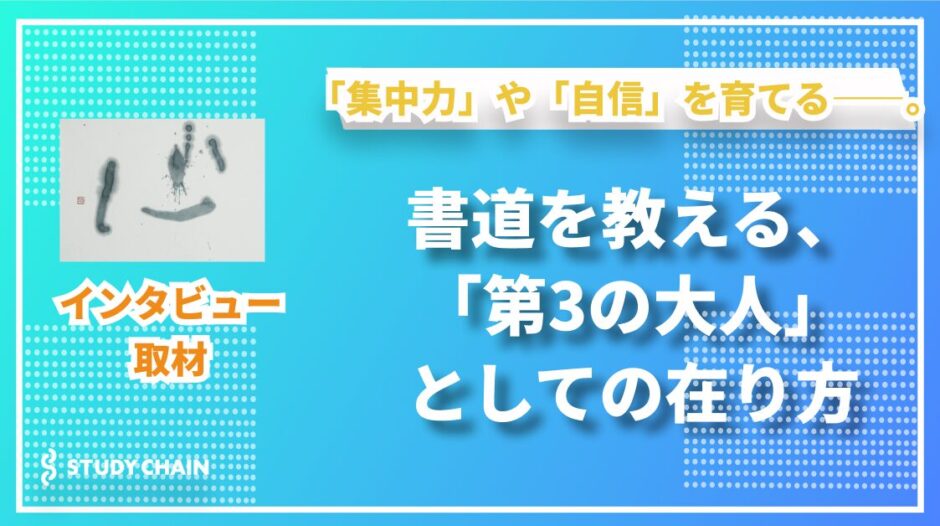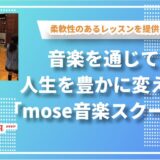元教育コンサルタントという異色の経歴を持つ荒木游莫先生が運営する、ふたば書道会游莫支部。ここは単なる「習い事の場」ではありません。学校や家庭とは異なる価値観を持つ“第3の大人”として、子どもたち一人ひとりに寄り添いながら、書道を通じて「集中力」「継続力」「自己肯定感」まで育てる独自の指導を実践しています。
子供クラスの最大の特徴は90分のレッスン。決して短くはない時間ですが、子どもたちは少しずつ慣れ、静かに筆と向き合う時間を楽しむように。そこには、細やかな声かけやスモールステップの工夫、個々の感覚に合わせた伝え方など、豊富な指導経験に裏打ちされたノウハウが活かされています。
さらに、大人クラス(120分レッスン)では道具の貸出や振替制度など、忙しい日常の中でも通いやすい仕組みが整えられており、初心者でも安心して通える書道教室となっています。この記事では、游莫先生が教室運営に込める思いや、今後の展望、書道の枠を超えた“人生の学び”について、たっぷりと語っていただきました。
ー教室にはどんな方が通っているんでしょうか?

ふたば書道会游莫支部講師 荒木さん:お子さんと大人の書道教室でして、子どもは小学生・中学生が中心です。大人のクラスは高校生から社会人、上は年齢制限はありません。たまにですけど、ご兄弟で一緒にいらっしゃる幼稚園の子もいたりしますね。ご心配な保護者の方もいらっしゃいますが、まずは体験時にきちんと座っていられれば、ご入会いただいております。
ー書道教室を始められた経緯、ぜひ詳しく教えてください!
荒木さん:僕自身、子どもの頃に書道を習ってたんですよ。でもその先生が中学に上がる前に亡くなられてしまって、そこから離れてしまい、、、、。しばらく間が空いて、大人になってから「もう一回やってみようかな」と。
独立前は、学習塾の先生をしていた時期があり、そのあと転職して、教育機関専門のコンサルタントをやってました。学校とか学習塾に対して、集客とか授業のやり方を教える、けっこう尖った内容のコンサルですね。
40過ぎて、「自分で何かやりたいな」って思った時に、好きだった書道を人に教えることが自分にとって自然だったんですよね。教えるのが得意っていうか、ずっとそういう仕事してきたんで。好きなことと得意なことが重なったのが、この書道教室だったんです。
ーなるほど、背景を聞くと今の教室がすごく腑に落ちますね。ちなみに、離れていた間も書道には触れていたんですか?
荒木さん:いえ、自己流でしたね(笑)。詩人になりたくて、自分で言葉をつくって、それを書いていたんですけど、まぁ下手くそで。「これはダメだな」と思って、ちゃんとやり直そうと。それが再開のきっかけですね。
ー書道教室としてのアピールポイントや、他の教室との違いはありますか?
荒木さん:子供クラスで言えば、一番は「1回90分」の指導時間だと思います。たぶん他の教室さんは、60分が多いと思うんですけど、正直それだと準備して片付けして、もう終わり、みたいな感じになっちゃうんですよ。
でも90分あると、学校でいうと授業2コマ分。ちゃんと座って、落ち着いて書くってことができる。もちろん長く感じる子もいますけど、みんなけっこう集中して書けてます。
あと、うちはお手本をただ見て書くだけじゃなくて、僕が指導する時のポイントなどを自分でお手本に写してもらったりもします。「こういうふうに注意するんだよ」って言ったことを、鉛筆でメモさせたり。これ、塾の先生時代の名残かもしれないですけど(笑)、教わるだけじゃなくて、「自分で吸収する」ってことも大事にしてます。
ー子どもたちにとっては、字だけじゃなくて、集中力や学ぶ姿勢も育ちそうですね。
荒木さん:そうなんですよ。僕自身が、学校の先生とかお父さんお母さんとか、そういう「身近な大人」とはちょっと違う、いわば「第3の大人」みたいな面白い存在になれたらいいなと思いながら指導しています。
ー90分のレッスンって、お子さんには大変じゃないですか?最初から座っていられるんでしょうか?
荒木さん:最初はもちろん難しいですよ。でも、少しずつ慣れていきますね。子供クラスは、硬筆と毛筆を切り替えながらやっていくので、生徒たちはそこまで⾧く感じていないように思います。
それに、「あと10分がんばろう」とか「あと3枚書こう」とか、時間とか枚数などの「数字」で区切ってあげると、子どもたちも「もうちょっとやってみようかな」ってなるんですよ。細かく区切ってあげると、目標が見えるんですよね。スモールステップってやつですね。
で、大体3ヶ月くらいやると、みんなちゃんと座って書けるようになってきます。あとはね、ご家庭のしつけがちゃんとしてる方が多いので、本当に助かってます。
ー指導の中で、特に大切にされていることはありますか?
荒木さん:ささいな一言を逃さないことですかね。「太くなっちゃうんです」とか「バランス取りにくい」とか、ふと漏れる言葉に、ヒントがたくさんあるんですよ。
あとは、人によって「見て覚える人」「話を聞いて理解する人」「一緒にやって身体で覚える人」というように理解の仕方にタイプがあるんです。その人に合ったやり方を探して、なるべく合う方法で伝えるようにしてます。見て覚えろ、っていうのももちろん大事だけど、それだけじゃ伝わらない人もいますからね。
ー現在、提供されているコースやプランについても教えてください!
荒木さん:コースは大きく分けて3つです。
まず、小中学生対象の子どもクラスです。ふたば書道会のお手本を使って、硬筆と毛筆の両方を練習するスタイルです。次に大人のクラスです。ふたば書道会のお手本と私の書いた独自の手本を用いてレッスンしています。
もうひとつが、「デザイン書道クラス」。これは完全にお手本を使わないで、自分でデザインして書いていくコースです。古典的な書道を踏まえて、映画タイトルやパッケージの筆文字ロゴなどで用いるような商業的なデザイン書道を指導しています。
大人は120分のクラスです。デザイン書道クラスは月2回、1回150分のレッスンです。
ー今後、さらに力を入れていきたい取り組みがあれば教えてください!
荒木さん:今考えているのは、将来的に「書道教室を開きたい」とか「自分も教えてみたい」っていう人に向けて、指導法とか教室運営のノウハウを伝えられる仕組みができたらいいなと思っています。
ー最後に、通おうか迷っている方や保護者の方に向けて、メッセージをお願いします!
荒木さん:お子さんにとっては、字が上手くなるだけじゃなくて、「90分ちゃんと座って集中する」っていうことが、他の習い事や学校生活でも生きてくると思ってるんです。
書道の時間に「上手いね!」って言われると、それが自信になって、学校でもちょっと誇れるようになってくるみたいで。実際にそういう声、けっこう聞くんですよ。書道を通じて元気になったお子さんを見て、お父さんお母さんも嬉しそうだったりして。そういうの、すごく良いなって思いますね。
大人の方に関しては、今後AIがロゴもなんでも自動でやってくれる時代になると思ってるんです。だからこそ、「筆を持って、自分の手で書く」っていう時間そのものに、意味があると思ってます。
「どうやって書くか」より、「どうやって向き合うか」っていうことに価値が出てくるんじゃないかなと。なので、過程や体験に喜びを感じてもらえるような場にしていきたいです。
昔ながらの「怖い先生がいて、見て覚えろ!」みたいな教室じゃなくて、寄り添いながら、一人ひとりに合った教え方をしていく、そんな教室でありたいですね。