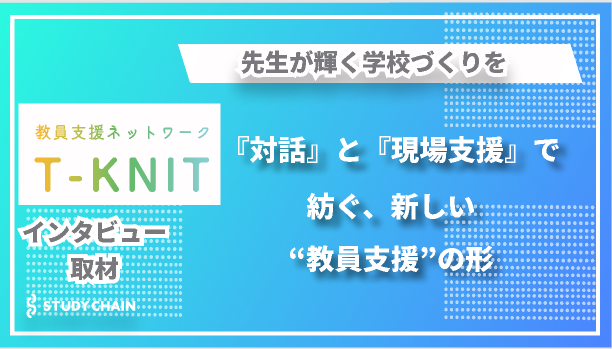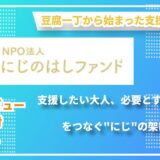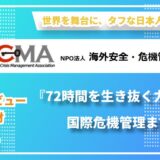教育現場における教員支援のあり方が問われる今、独自のアプローチで注目を集めているのが、『特定非営利活動法人 教員支援ネットワーク T-KNIT(ティニット)』。従来の事務作業支援とは一線を画し、「教師の本質的な負担軽減」を目指す同団体の活動は、教育関係者から高い関心を集めています。今回は代表の塩畑様に、活動への想いや教育現場の課題、そして今後の展望について詳しく伺いました。
教員支援への想い―プログラマーから教育支援へ

ーまずは貴団体の活動概要について詳しく教えていただけますでしょうか?
塩畑様:私たちは「教員支援」という、一般的にはまだ珍しい活動を展開しています。多くの教員支援は事務作業の代行や業務の肩代わりが中心となっていますが、私たちはより本質的なアプローチを心がけています。具体的には、教師の方々の負担を根本から取り除くための方法を模索し、実践しています。
現在、主に2つの事業を展開しています。1つは「対話事業」です。これは「先生を変えられるのは先生自身しかいない」という考えに基づいています。先生方に自身の価値観や将来の展望について深く考えていただく機会を提供し、内発的な変化を促進しています。
もう1つは「学校応援事業」です。この事業では、「教育は学校だけのものではない」という理念のもと、地域全体で教育を支える仕組みづくりを行っています。茨城県を中心に、近隣地域での実地支援や研修、講演活動を展開する一方、対話事業ではオンラインを活用し、全国の教育者とつながっています。
ーそのような教員支援に特化した活動を始められたきっかけについて、より詳しくお聞かせください。
塩畑様:私の前職はプログラマーでした。当時は深夜まで働き、家に帰っては寝るだけという生活を送っていました。体調を崩して退職を余儀なくされた後、次のキャリアを模索する中で、学校でのICT支援員という仕事に出会いました。
そこで目にしたのは、想像以上に多くの課題を抱える教育現場でした。特に印象的だったのは、ある日のできごとです。期限の迫ったWebアンケートで困っている先生を手伝っていた時、システムの制約で3時間以上かかる作業に直面しました。その最中、ある生徒が深刻な表情で相談に来たのですが、先生は期限に追われ、「明日話を聞くからね」と返すしかありませんでした。
その生徒の表情が忘れられません。おそらく家に帰って保護者に話を伝え、それが新たなクレームとなって学校に戻ってくる。そしてまた新たな調査やアンケートが発生する。この負のサイクルをどこかで断ち切らなければならないと強く感じました。
教員支援がもたらす社会的価値
ー教員支援を通じて、どのような社会の実現を目指されているのでしょうか?
塩畑様:教員は、子どもたちにとって家庭以外で出会う最も重要な大人のロールモデルです。その影響力の大きさを考えると、教員が疲弊していたり、責任を押し付け合っているような姿を子どもたちに見せることは、決して良い影響を与えません。
私たちが目指しているのは、先生が生き生きと働き、その姿を見た子どもたちが「早く大人になりたい」と思えるような環境づくりです。そして、それは単に学校内だけの話ではありません。地域の大人たちも協力的で、子どもたちの成長を皆で支えている。そんな姿を子どもたちに見せることで、彼らも将来、自分が育った地域や社会に貢献したいという想いを持つようになるはずです。
教育の質は、結局のところ教員の状態に大きく左右されます。小学校以上になると、子どもたちが学校で過ごす時間は非常に長くなります。その時間を共に過ごす教員が充実感を持って働けているかどうかは、子どもたちの将来に大きな影響を与えるのです。
現場で見える教員の課題
ー現在、塩畑様がお感じになっている『先生方が直面している特に重要な課題』について、具体的にお聞かせください。
塩畑様:私が考える最も大きな課題の1つは、「考える時間の不足」です。目の前の業務に追われるあまり、そもそもなぜその活動が必要なのか、本質的な目的を考える余裕がない状況が続いています。
例えば、宿題一つとっても「なぜ出すのか」「全員一律である必要があるのか」という根本的な問いを立てる機会が少ないのです。新しい教育内容は次々と追加されていきますが、既存の業務を見直したり、場合によっては廃止するという判断はほとんど行われません。
もう1つ大きな課題は、地域との協力体制構築です。実は多くの保護者や地域の方々は協力的で、「困ったことがあれば言ってね」と声をかけてくださる方が大勢いらっしゃいます。しかし、一部の教育熱心な保護者からの要望に応えることに追われ、そうした支援の手を十分に活かしきれていないのが現状です。
例えば、下校時の見守り活動一つとっても、本来は地域と協力して行えることなのに、教員が時間を作って巡回せざるを得ない状況が生まれています。保護者からの声に過剰に反応し、結果として教員の負担を増やしてしまうケースも少なくありません。
具体的な支援の成果
ー実際の支援を通じて、どのような変化が見られていますか?
塩畑様:学校応援事業では、特に『コミュニティ・スクール』を活用した取り組みで大きな成果が出ています。従来、学校の課題解決は校長の判断に委ねられ、時として「なぜそういう決定をしたのか」という疑問の声が上がることもありました。
しかし、私たちが推進している『コミュニティ・スクール』の考え方では、地域の方々、保護者、子どもたち、そして教員が一緒になって課題解決に取り組みます。例えば、「自分で進んで学習するにはどうしたらいいか」という課題に対して、皆で対話を重ね、解決策を見出していった事例があります。このように、皆で決めた方針だからこそ、実行段階での協力も得やすく、持続的な改善につながっているのです。
対話事業では、より個人的なレベルでの変化が見られています。対話を重ねることで、「自分は本当は何がしたかったのか」「今やっていることは何に繋がっているのか」を考える機会が生まれ、教員としての自分の在り方を見つめ直すきっかけとなっています。
その結果、「学校に行く意味が見出せた」「周りの人ともっと協力していきたい」という前向きな声が増えています。数値化しにくい成果ではありますが、教員一人一人の意識変化が、確実に学校全体の雰囲気を変えていっているのを実感しています。
今後の展望―教員支援のネットワーク構築へ

ー今後の活動について、特に注力されたい部分をお聞かせください。
塩畑様:現在、特に強化したい部分が2つあります。1つは、今まさに深い悩みを抱えていらっしゃる先生方へのサポート体制の構築です。学校応援事業で学校全体の変革を、対話事業で教員個人の意識変革を支援できていますが、精神面で大きな負荷を抱え、苦しんでいる先生方へのアプローチが十分ではありません。
実際、そうした先生方から電話で相談を受けることも増えていますが、現状では適切な支援につなげられていない状況です。カウンセラーなどとの連携も考えられますが、「教員支援」という枠組みでの予算確保が難しく、実現に至っていません。
そこで、私たちが目指しているのは、総合的な窓口としての機能強化です。各種支援団体や組織、行政との連携を深め、必要な支援に確実につなげられる体制を作りたいと考えています。
もう1つは、政策レベルでの働きかけです。現場での支援だけでは解決できない課題も多くあります。そのため、研究活動や署名活動なども視野に入れ、より根本的な解決を目指していきたいと考えています。
ー最後に、この記事をご覧になる方へメッセージをお願いできますでしょうか?
塩畑様:「子どもたちのために大人が変わっていくべき」という想いに共感してくださる方々に、ぜひ私たちの活動を知っていただきたいと思います。教育は学校だけの問題ではありません。子どもたちの未来のために、共に考え、行動できる仲間を募集しています。説明会などを定期的に開催していますので、興味をお持ちの方はぜひご参加ください。
教員一人一人が生き生きと働ける環境づくりは、子どもたちの未来を明るくする第一歩です。私たちと一緒に、より良い教育環境の実現を目指しませんか。