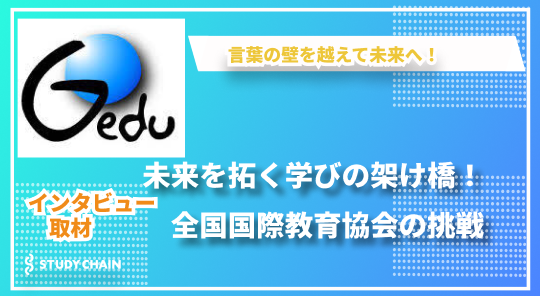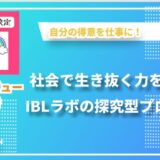全国国際教育協会は、多文化共生を目的に、日本の子どもたちには、グローバル教育によって、世界に目を向けさせるとともに、外国ルーツの子どもたちが平等に教育を受けられる環境を提供するための支援活動を行っています。進学支援や情報提供、学習サポート、やさしい日本語指導、教材開発を通じて、日本社会での自立を目指す子どもたちをサポートしています。
活動の概要について教えてください。
日本に定住する外国人が300万人を超えるいま、日本の学校には、多くの外国にルーツを持つ子供たちが通っています。ところが、教員も、学校も、その子たちへの指導は追いつかず、わずかの取り出し授業で、日本語支援を行っているにすぎません。そのため、孤立や、ドロップアウトが起こっています。学校からのお知らせさえ、理解できない子供たちにとって、複雑な都立高校入試などには、支援が必要なのです。
そこで、日本語が不自由なために情報を得ることが困難な外国ルーツの子どもたちを対象に、都立高校への進学を支援するガイダンスを実施しています。これにより、彼らが経済的負担を抑えながら、日本社会で働いていくための教育を受けられる環境を整えています。また、保護者も含めた説明会や進路相談の機会も設けており、家庭単位での支援を強化しています。働く外国人が日本に来ることは、その家族である子どもたちの支援も必要なのです。
加えて、進学後のフォローアップ支援にも注力しており、教育機関との連携を通じて、持続的なサポート体制を整えています。さらに、教育機関や地域の支援団体と協力し、社会全体で外国ルーツの子どもたちを支える仕組み作りにも積極的に取り組んでいます。
立ち上げたきっかけや背景についてお聞かせください。
私は長年、教員として教育の現場に携わってきました。その間、青年海外協力隊の一員としてアフリカで技術支援を行った経験があります。現地では、言語や文化の違いに苦労しましたが、地元の人々に助けられることで、国際的な相互支援の重要性を痛感しました。この経験が、現在の活動に繋がっています。
もともとこの協会の生い立ちは、戦後、海外移住が再開され、農業青年の移住が盛んになった時期に、当時の移住事業団(現国際協力機構:JICA)とともに、海外移住の正しい理解と発展を促すため、主に農業高校の先生たちによって活動が始まりました。しかし、時代と共に日本の経済は飛躍的な発展を遂げ、海外に出る人々だけでなく、逆に日本に戻ってくる移住者の子どもたちが増えてきました。彼らは日本語の壁や経済的な問題で進学や就職に苦しんでいます。こうした背景から、彼らを支援するために、現在のような活動へとシフトしてきました。
特に、私が教育現場で目の当たりにしたのは、日本語が十分に話せないことで学校生活に適応できず、自信を失ってしまう子どもたちの姿でした。教育の機会が平等に提供されるべきであるにも関わらず、言語の壁が原因で十分な学びの場を得られない現状に直面し、強い危機感を抱きました。これが、協会の活動に本格的に関わるきっかけとなりました。
特徴・強みはどんなところでしょうか。
当協会の強みは、教育分野における幅広い専門知識と経験を持つメンバーが多数在籍していることです。校長経験者や教育管理職の方々が多く、学校運営に関する深い知見を持っています。また、青年海外協力隊として海外で活動してきたメンバーも多く、多様な文化に対する理解と対応力があります。
特に、異なる国の文化や価値観を理解した上で、日本での生活をサポートする点が特徴です。海外経験のあるスタッフが多いため、外国ルーツの子どもたちが直面する問題に対して、日本的な考え方にとどまらず、柔軟な対応が可能です。
さらに、全国の教育機関と連携し、学校現場に即した支援を提供できる点も強みの一つです。日本の教育制度に精通しているメンバーが、外国ルーツの子どもたちがスムーズに適応できるよう、カリキュラムの調整や学習サポートを行っています。
活動・指導方針についてお聞かせください。
当協会では、情報弱者になりがちな外国ルーツの子どもたちに対し、丁寧でわかりやすい情報提供を心がけています。特に、日本語が不自由な家庭のために「やさしい日本語」を使って説明し、進学や就職に関するサポートを行っています。各教科の教員資格を持つ日本語教師や、やさしい日本語リーダーもいます。
また、学校だけでなく、地域社会との連携も重要視しています。子どもたちが孤立しないように、学校外での支援ネットワークを構築し、コミュニティとのつながりを強めています。具体的には、進学ガイダンスの開催や個別相談会を定期的に実施し、子どもたちが安心して学べる環境を提供しています。
指導の際には、子どもたちの個々の状況に合わせたアプローチを取り入れており、学習支援だけでなく、精神的なサポートも大切にしています。家庭環境や文化的背景を考慮した個別対応を行いながら、子どもたちが自信を持って学べるようサポートしています。
今後の展望についてお聞かせください。
現在の活動は東京都を中心に展開していますが、将来的には全国各地で同様の支援を行いたいと考えています。地方でも外国ルーツの子どもたちは増えており、彼らが平等な教育を受けられる環境を整えることが課題です。
また、オンラインを活用した支援体制の強化も検討しています。情報が届きにくい地域の子どもたちにも進学や就職のサポートが行き届くよう、Web上での相談窓口や学習支援のプログラムを拡充していきたいと考えています。
さらに、行政や民間企業との連携を強化し、より包括的なサポート体制を整備する予定です。奨学金制度の拡充や職業訓練の機会提供など、教育だけにとどまらない包括的な支援を目指しています。
メッセージ
外国ルーツの子どもたちは、日本社会の中で言語や文化の壁に直面し、多くの困難を抱えています。しかし、適切な支援があれば、彼らは日本で十分に活躍できる可能性を持っています。それだけではなく、この支援は、外国にルーツをもつ子どもたちだけの利益ではありません。彼らとの交流が、日本の子どもたちには、グローバルで多様な文化に気づき、「ともに生きる」力をあたえるのです。
私たちは、そうした子どもたちが安心して教育を受け、将来の可能性を広げる手助けをするために活動を続けています。情報を得る手段が限られている彼らに対し、やさしい日本語で伝えること、コミュニティとのつながりを強めることを大切にしています。
これからも、情報発信と実際の支援を組み合わせながら、彼らが安心して学び、成長できる環境づくりに取り組んでいきます。少しでも興味を持たれた方は、ぜひ私たちの活動にご協力ください。