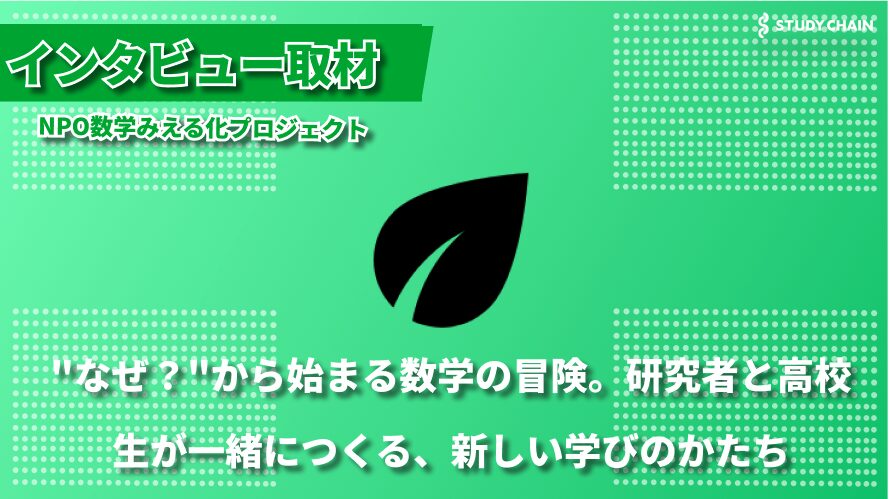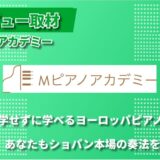数学は難しい、数学は苦手—。そんな声をよく耳にします。しかし、数学を「体験する」ことで、その本質的な面白さに気づくことができるのではないでしょうか。NPO数学みえる化プロジェクトは、数学の概念を視覚的・体験的に学べる展示やワークショップを全国で展開しています。今回は、代表の正宗淳氏に、数学の新しい学び方についてお話を伺いました。
数学の概念を体験的に学ぶ、独自の教育活動
ー まずはNPO数学みえる化プロジェクトの活動内容について教えてください。
正宗氏:私たちは、数学の面白さや実社会での役割を広く伝えることを目的とした非営利団体です。数学の抽象的な概念を視覚的・直感的に捉えやすい形で表現し、学問としての数学だけでなく、その楽しさや応用を多くの人に伝えることを目指しています。
具体的には、小学生から一般市民まで幅広い層を対象に、数学の概念を体験的に学べる展示の開催や、年に3回程度、ワークショップを実施しています。また、YouTubeでの動画配信や書籍の発行なども行っています。
これ以外の活動として、週1~2回開催している「寺子屋」では、高校生や大学生を対象に大学数学を分かりやすく講義しています。
活動のきっかけと広がり
— 活動を始められたきっかけについて教えてください。
正宗氏:数学は社会のあらゆる場面で重要な役割を果たしているにも関わらず、多くの人にとっては難解で遠い存在と感じられがちです。私は高校の先生方と交流する中で、通常のカリキュラムだけでは数学の面白さが十分には伝わりにくいという課題を共有していました。そこで、まずはそのギャップを埋めるための勉強会を2018年に開始しました。
大きな転機となったのは、2022年に北海道大学で開催した数学展示でした。当初は高校生を主な対象として想定していましたが、実際にはお子さんからお年寄りまで、4万人を超える来場者が訪れ、予想以上の反響がありました。一方、都市部からの来場者は多かったものの、遠方の村や町の子どもたちはなかなか来られないという現実にも気がつきました。
そこで、私たちが出向いていくことを考え、平時は北海道大学に機材を保管していただき、興味を持ってくれる地域へトラックで機材を運んで展示やワークショップを行う、いわば「数学のサーカス」のような活動を展開することにして、NPOを設立しました。
数学みえる化プロジェクトの特徴
— 数学みえる化プロジェクトの特徴的な点について教えてください。
正宗氏:数学は抽象的な概念を積み上げていく学問であり、好き嫌いがはっきりしやすい分野です。学校では、公式を覚えて応用することが重視されがちで、「なぜそのようなことを考えるに至ったか」「実社会でどのように活用されているのか」「どのようなことが問題になっているか」は伝わりにくいと感じています。
しかし実際には、スマホやコンピューター、原子炉の設計、経営戦略、ファイナンス、宇宙の形の決定など、数学は現代社会の重要な場面で不可欠です。また、研究者によって日々数学は深化していて、社会に大きなインパクトを与えています。私たちは、こうした実例の基礎にある数学やそれがどのように発展しているかを紹介することで、科学や数学、算数への興味を持ってもらうことに力を入れています。
子どもたちと関わる際に意識していること
— 子どもたちとの関わり方で意識されていることはありますか?
正宗氏:大切にしているのは、参加者と一緒に楽しんで何かを作るという姿勢です。例えば小学生が対象のワークショップの場合、作る過程で小学生が参加すると、プレゼンテーションが格段に良くなることが期待されます。これは私たちにとっても大きな学びとなっています。
また、出版した本も高校生に査読してもらい、意見を参考にしながら推敲しました。一方的な教育ではなく、一緒に新しいものを作っていくという意識を大切にしています。これは私たちの活動の根幹となる考え方です。
数学の魅力を伝える書籍の出版
— 出版されている書籍について教えてください。
正宗氏:『感じる数学』という本を共立出版から出版しています。この本は、一般的な数学の教科書とは異なり、ガリレイからポアンカレに至るまでの数学発展の物語をやさしく紹介しています。著者たちを感動させてきた数学の魅力を伝えることを心がけています。
— この書籍や関連するYouTubeチャンネル「感じる数学Tangible Math」などの活動が評価され、2025年3月、NPO数学みえる化プロジェクトは「2025年度日本数学会出版賞」を受賞されました。
正宗氏:はい、受賞は大変光栄であり、これまでの活動が認められたことを嬉しく思います。これを励みに、今後も数学の魅力を多くの人に伝える活動を続けていきたいと考えています。
今後の展望
— 課題や今後の活動についてお聞かせください。
正宗氏:課題としては、展示やワークショップの運営資金の確保、活動の認知度向上、人材確保、教育現場との連携などが挙げられます。
今後も、地域に出向き、その土地の特徴を活かしたワークショップを地元の先生方と一緒に作っていきたいと考えています。特に、従来の数学の枠におさまらない数学を見つけたいですね。また、若い人の提案を中心に、数学の専門家だけでなく、ボランティアの方々も交え、20分程度の「みえる化トーク」を配信することも検討してもらっています。
記事を読んでいる方に向けたメッセージ
— 最後に、活動に興味を持たれた方へメッセージをお願いします。
正宗氏:数学はすべての人に開かれた知の世界です。公式を覚えることだけが数学ではなく、「なぜ、そんなことを考えるか」「どのように活用できるのか」を考え、一見異なる現象の間の共通項を抽象化することで、この世界の本質を発見することができます。
新しいアイデアやコラボレーションは、いつでも歓迎です。ワークショップの依頼も全国どこからでも受け付けています。数学の楽しさを、より多くの人と共有できることを楽しみにしています。