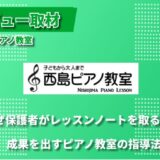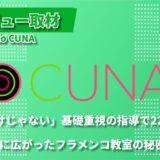従来の書道教室では見られない「すみあそび」という活動を通じて、子どもから大人まで、誰もが自由に表現を楽しめる場を提供している生涯発達支援塾TANE/書道塾tane。特別支援教育の経験を活かし、教育・福祉・芸術の領域を横断する新しい取り組みを行っています。代表の育子さんに、活動に込めた思いと、目指す未来について話を聞きました。

サービス概要
ー生涯発達支援塾TANE/書道塾taneではどのような活動をされているのでしょうか?
育子さん:生涯発達支援塾TANEは、心理・発達・教育・福祉・文化芸術の領域を横断しながら活動を展開しています。主に、障害があると言われている方々や、人間関係や社会に違和感を持つ方々との「つなぎめ」のコーディネートを行っています。
活動は大きく3つの柱があります。1つ目は組織のコーディネート、2つ目は支援者のコーディネート、そして3つ目が個人のコーディネートです。例えば、放課後デイサービスなどの施設で専門家が不在の場合、職員への支援や情報提供、研修なども実施しています。現在は主に個人のコーディネートとして、社会の中に多様な参加が可能な場を創る活動をしています。
設立の経緯
ーTANEを立ち上げられた経緯について教えていただけますか?
育子さん:私は以前、特別支援学校の教員として働いていました。その中で、インクルーシブな社会を目指すと言いながら、実際には分断が生じている現状に気づきました。障害のある方々は社会で過ごす時間の方が長いにもかかわらず、交流や学びの場が非常に限られているのです。
具体的なきっかけは、18歳の自閉症の男子生徒との出会いでした。卒業後、家と施設の往復だけの生活に対して、生徒の母親から「こんな人生では寂しい」という声があがりました。
書道を教えてほしいという要望をいただいたのですが、従来の書道指導では文字を正確に書くことが求められ、自閉症のある生徒には難しい面がありました。そこで、お手本にとらわれず、筆で自由に表現を楽しむ活動を始めたところ、予想以上に生徒が楽しんでくれたのです。
この経験から、障害の有無に関係なく、誰もが自由に表現できる場所を作りたいと考えました。心理・発達・教育・福祉・文化芸術など、様々な分野を横断的に取り入れることで、より多くの方が参加できる環境を目指しています。
特徴とアピールポイント
ーTANEならではの特徴について教えてください。
育子さん:最大の特徴は「すみあそび」という独自のワークショップです。これは、お手本のない書道活動で、年齢制限もなく、誰でも気軽に参加できます。用具を持参する必要もなく、手ぶらで参加可能です。
通常の書道では、お手本があるために「下手」「上手」という評価が生まれてしまいます。しかし、私たちの活動では、柔らかい筆を使って自由に創作することを重視しています。これにより、小さな子どもからお年寄りまで、障害の有無に関係なく、誰もが楽しめる場となっています。
指導理念
ー「すみあそび」を通じて大切にされていることは何でしょうか?
育子さん:私たちが最も大切にしているのは「比べない」という考え方です。世の中で生きていく中で、人と比べないということは非常に難しいものです。しかし、この活動を通じて、そのような体験をしていただき、自分自身の魅力に気づくきっかけを作っています。
特に興味深いのは、子どもと大人の反応の違いです。子どもたちは迷わずに表現できますが、大人は「お手本がないのか」と戸惑うことが多いのです。これは実は、自分がいかに枠にとらわれていたかに気づくきっかけとなります。
料金・開催情報
ー開催場所や料金について教えてください。
育子さん:現在、宮城県の石巻と塩釜を中心に、各地で移動開催をしています。料金は1回2,500円から3,000円程度で、90分程度のワークショップとなっています。参加者は好きな時間に来て、満足するまで創作を楽しむことができます。
オンラインでの参加も可能で、その場合は家庭にある筆ペンや割り箸、さらにコーヒーなど身近な材料を使って活動を行います。開催情報は主に公式LINEで発信しています。
今後の展望
ー今後の活動についてのビジョンをお聞かせください。
育子さん:現在力を入れているのが、「はみだすラボ」という大人向けのオンラインコミュニティです。子どもたちの支援には、まず大人自身が固定観念から解放される必要があると考えています。すみあそびを通じて、大人たちが自分の感情や行動を見つめ直すことで、子どもたちの個性も自然に受け入れられるようになっていきます。
また、私たちが提唱している「フリーランス教育者」という考え方も広めていきたいと思っています。必ずしも教員免許やカウンセラーの資格がなくても、身近な大人として子どもたちを見守り、支援できる人はたくさんいるはずです。例えば、隣に住むおじさんが、困っている子どもの良き理解者になるかもしれません。そういった地域の中での自然な支援の輪を広げていきたいと考えています。
このように、専門家だけでなく、地域の大人たち一人ひとりが子どもたちの個性を受け入れ、見守れる社会を目指しています。
メッセージ
ー最後に、記事を読んでいる方へメッセージをお願いします。
育子さん:自分と他の人が違うことは当たり前であり、その違いはいずれ必ず魅力となっていきます。「はみ出す」ということがもっと自由にできる社会になってほしい。そのための「自由な表現」の機会を、私たちは提供していきたいと考えています。