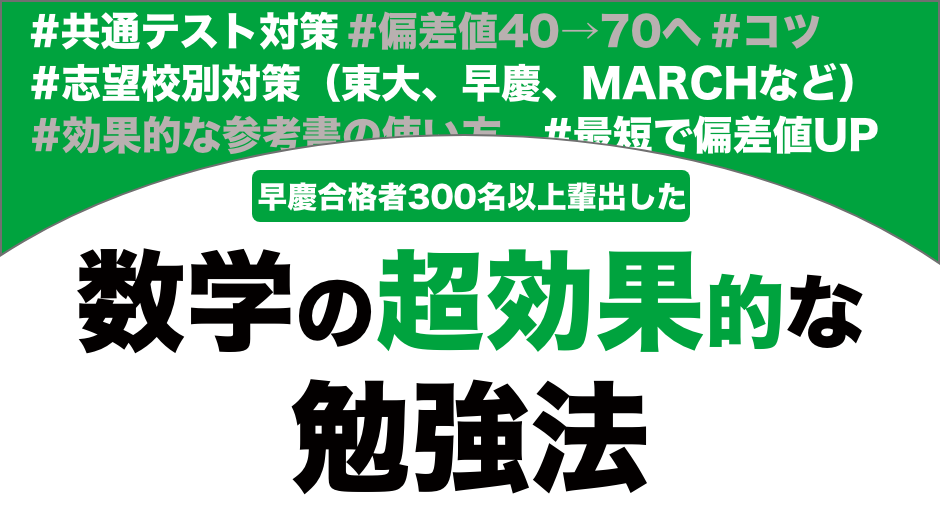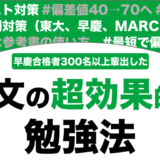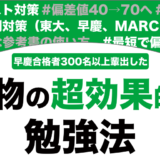本サイトの表記には、一部プロモーションを含みます
数学の大学受験対策におすすめの勉強法を完全解説します。数学の共通テスト対策におすすめの勉強法から東大・早稲田・慶應・MARCH志望まで志望校別対策、数学IA・IIB・III・C、確率・微積分・ベクトルなど分野別勉強法、定期テスト対策、ゼロから偏差値を伸ばす学習順序まで網羅的に紹介します。

【この記事の監修者:逆転合格特化塾塾長「竹本明弘」
これまで逆転合格特化塾の塾長として早慶に現役生および浪人生を含めて合計で300人以上の合格者を輩出してきました。その中で共通テストの数学で9割以上を取った生徒もたくさんおり、実際に指導する中でゼロからでも数学の偏差値70まで到達した大学受験対策の数学の勉強法や使ってよかった参考書およびおすすめの数学の勉強の順番を解説したいと思います。
いきなり最終結論!ゼロから東大に受かる数学の勉強法を徹底解説!
結論として、数学の偏差値を6ヶ月で40から70にする勉強法としては以下のようになります。勉強時間の目安は1日2時間の勉強時間の前提で計画や参考書を選んでいます。
→基礎的な例題にて解法のレパートリーを増やしていく。(学校で使用している参考書もしくは基礎問題精講もしくは黄色チャートなど)
- 学校で使用している数学の参考書の解説が自分の中でわかりやすいと感じているのであれば、その参考書を活用して大丈夫です。ただ、東大に年間何十人と輩出するような学校ではない限り、ほとんどの場合で学校の数学の参考書は解説がわかりづらく、授業の終わりなどに学校の先生に聞いたり、授業を通して理解するような形になっているので、おすすめは「入門問題精講および基礎問題精講」や「黄色チャート」や「FocusGold」を使用するのがおすすめです。
- また黄色チャートやFocusGoldなどを進めていく中での注意点としては、学校の数学の授業を聞いていなかったという人はわからない問題がでた場合においては、必ずtry itもしくはスタディサプリにて映像授業を見ながら進めることをおすすめします。例えば、数学1・Aの確率がわからなかったという場合には、その範囲の映像授業を視聴して、理解していくことがおすすめです。
- はじめの段階で数学が苦手な人にはとにかく解説がわかりやすい参考書を選ぶことが何よりも重要です。特に数学が苦手という人は「はじめから始める数学シリーズ」の1・Aからはじめるのもおすすめです。
→基礎の徹底強化期間として数学1・Aおよび2・Bの例題に出てくる解法は8割程度暗記できる状態にする。
- 基礎問題精講およびFocusgoldもしくは青チャートを1冊完璧にできるのが理想ではありますが、青チャートは量が多すぎる参考書なので、基礎問題精講を解いて苦手だったセクションのみ、青チャートを解くような形で進めていきましょう。
- 数学は特にFocusGoldや基礎問題精講を1冊完璧にできたかどうかが非常に重要です。その後の数学の偏差値がどれだけ伸びるかに繋がってくるので、できれば3周はしたいです。1周目は特に解けることには拘らずに、きちんと理解して、2回目に解いた時に何も見ずに解けるように自分なりの要点整理を大事にしましょう。メモ書きでも良いので、解き方のポイントを自分の言葉で整理するイメージです。
- 最後に受験に差がつくポイントとしては、自分の苦手な分野を把握しているかどうかです。そのため、ただ毎日何ページやるという目標よりも何日までに確率の単元を全て終わらせるというような形で取り組むことをおすすめします。そうすると確率の漸化式だけはなかなかできないなあなどと苦手分野が見えてきやすくなります。
→応用力強化期間としてどの解法を使うべきかの判断力を特に強化できるようにする。そのための演習を重視。
- 数学の標準問題精講や文系の数学の実践力向上編を使って、この問題の場合どの解法を使うべきかについてこれまで覚えてきた解法のレパートリーの中から解法を選んで解けるようにしていきましょう。そのためには初見の問題を解いた回数が非常に重要になってきます。数学は基礎固めについては「苦手分野を埋めること」が大事ですが、基礎が固まったら、初見の問題をとにかく解き続けることが重要です。
- もし数学の問題の解き方の考え方を習得したいというかたでまだ時間があるという人は「入試問題を解くための発想力を伸ばす 解法のエウレカ」は非常におすすめの参考書です。そして、この参考書を使って良いのは「基礎問題精講」や「青チャート」や「Focus Gold」を3周以上取り組んでおり、基本的に見た瞬間例題の解法は思いつく状態になっている人限定です。なぜなら、解法のレパートリーがない中で考え方だけ見についても仕方がないからです。
→過去問演習も含めて志望校合格に必要な分析と最後の応用レベル強化。苦手の分析と志望校の頻出分野の両方が重なる部分は特になくす。
- 文系数学の良問プラチカや理系数学の良問プラチカなどが必要かどうかは正直、残りの勉強時間および勉強期間がどれだけあるかによって大きく変わってきます。解法暗記の期間が終わり、問題を分析した上でどの解法で解くかどうかの判断力を鍛える上では初見の難易度の高い問題を解く回数を上げることが一番効きます。だからこそ、時間がある人はたくさん難易度の高い問題を解供解くようにしていきましょう。
- 早慶以下のレベルの人についてはこの時点でもう過去問に入って、過去問の頻出分野を見つけることと過去問を解いていく上で自分の苦手な傾向の強い単元を見つけていきましょう。10~15年分はどの志望校を目指すにしろ必ず解くことをおすすめします。
▽数学のおすすめの参考書一覧はこちら

共通テストで9割取れる数学の勉強法
共通テストの数学で9割を達成するための勉強法を段階的に解説します。
- 最初の1ヶ月間は基礎固めと理解の定着をテーマに、教科書レベルの基礎を徹底的に理解することから始めます。全範囲をざっと通してなぜその解法になるのかを理解することを重視します。
- 使用する参考書ははじめからはじめる数学シリーズや入門問題精講がおすすめです。 数学が苦手な人は映像授業で理解を深めるのが効果的なので、Try ITやスタディサプリなどを活用してわからない単元をすぐに補強します。この期間の目標は基礎レベルの例題を読めば理解できる状態にすることです。
- 共通テスト数学は典型問題を素早く正確に処理できる力が問われるため、基礎問題精講や黄色チャートを使って各単元の基本問題を繰り返し解いていきます。
- 1日2時間のうち30分を解法の復習に充て、残り90分を問題演習に使うのが理想的な配分です。
- この時期からは共通テスト本番を意識した時間配分の練習を始め、Focus Gold数学や基礎問題精講を活用して特に苦手な単元を優先的に潰していきます。
- この時期の数学の勉強法のコツは1問を丁寧に解き、なぜそう解けるのかを自分の言葉で説明できるようにすることです。
- 共通テスト過去問研究を使用して年度ごとに通しで解き、1日90分のうち60分で演習、30分で解説確認を行って間違えた問題の原因を分析します。
- 得点戦略としては難問に固執せず確実に取れる問題を落とさないことが9割達成の鍵になります。
- 共通テスト本番を想定した実戦演習を繰り返し、共通テスト実戦模試や共通テスト総合問題集を活用して実際の試験と同じ80分で解く練習を積みます。間違えた問題は計算ミス、時間不足、理解不足のどれかを明確にして原因を分類します。
実際にやってよかった短期間で数学の偏差値が伸びる勉強法3選
短期間で数学の偏差値を伸ばすために実際に効果があった勉強法を3つ紹介します。
やってよかった勉強法①解法パターンの徹底暗記
数学のやってよかった勉強法の1つ目は解法パターンの徹底暗記です。
数学の偏差値を短期間で上げるためには基礎的な解法パターンを頭に入れることが最も効率的な方法です。
基礎問題精講や黄色チャートの例題を1冊完璧にすることで、数学の基礎力が飛躍的に向上します。 ポイントは1周目で解けることにこだわらず、きちんと理解して2回目に解いた時に何も見ずに解けるように自分なりの要点整理をすることです。メモ書きでも良いので解き方のポイントを自分の言葉で整理するイメージで進めます。
やってよかった勉強法②苦手分野の集中的な克服
数学のやってよかった勉強法の2つ目は苦手分野の集中的な克服です。 短期間で偏差値を伸ばすためには自分の苦手な分野を正確に把握して、その分野に集中的に取り組むことが重要です。ただ毎日何ページやるという目標よりも何日までに確率の単元を全て終わらせるという形で取り組むと苦手分野が見えやすくなります。
苦手分野が明確になったら、その分野の映像授業を見たり問題集を追加で解いたりして徹底的に理解を深めます。
確率の漸化式だけはなかなかできないといった具体的な弱点が分かれば、そこを重点的に補強することで効率的に偏差値を上げられます。
やってよかった勉強法③初見問題への演習量を増やす
3つ目は初見問題への挑戦回数を増やすことです。
基礎が固まったら初見の問題をとにかく解き続けることが偏差値アップの鍵になります。
標準問題精講や文系数学の実践力向上編を使って、この問題の場合どの解法を使うべきかについてこれまで覚えてきた解法の中から適切なものを選んで解く練習を積みます。初見の問題を解いた回数が多いほど本番での対応力が高まります。
分野別におすすめの大学受験対策の数学の勉強法
分野別におすすめの大学受験対策の数学の勉強法を解説します。
数学1・Aの大学受験対策におすすめの勉強法
数学1・Aは大学受験数学の基礎となる最も重要な分野です。
特に二次関数、確率、図形と計量、整数の性質は入試頻出分野なので重点的に学習する必要があります。
数学1・Aの勉強法としてはまず入門問題精講や黄色チャートで基本的な解法パターンを身につけることから始めます。
二次関数では最大値・最小値問題やグラフの平行移動、場合の数と確率では確率の基本性質や条件付き確率を確実に理解します。
図形と計量では正弦定理や余弦定理の使い分け、整数の性質ではユークリッドの互除法や不定方程式の解法を習得します。基礎が固まったら基礎問題精講やFocusGoldで演習量を増やしていきます。
数学1・Aは他の分野の土台になるため、この段階で曖昧な理解を残さないことが重要です。
特に確率は数学Bの数列との融合問題として出題されることも多いので、基本的な考え方を完全に理解しておく必要があります。苦手な単元がある場合はスタディサプリなどの映像授業を活用して理解を深めましょう。
数学2・Bの大学受験対策におすすめの勉強法
数学2・Bは数学1・Aの知識を前提として応用的な内容を扱う分野です。 特に微分積分、数列、ベクトルは入試での配点が高く、確実に得点できるようにする必要があります。数学2・Bの勉強法としては数学1・Aの内容を理解していることを前提に進めていきます。
微分では接線の方程式や関数の増減・極値、積分では面積計算や体積計算の基本をマスターします。
数列では等差数列・等比数列の一般項や和の公式、漸化式の解法パターンを習得し、ベクトルでは平面ベクトルと空間ベクトルの計算や内積の利用を理解します。これらは基礎問題精講で基本を固めた後、標準問題精講で応用力を養います。
数学2・Bは計算量が多い分野なので、計算ミスを減らすための工夫も重要です。 途中式を丁寧に書く習慣をつけ、検算の方法も身につけておきましょう。また数列とベクトルは数学3・Cでも使う重要な道具なので、この段階で完全に理解しておくことが後の学習を楽にします。
数学3・Cの大学受験対策におすすめの勉強法
数学3・Cは理系受験生にとって最も重要かつ難易度の高い分野です。 極限、微分積分、複素数平面、式と曲線、ベクトル、行列などの高度な内容が含まれ、演習時間も十分に確保する必要があります。数学3・Cの勉強法としては数学1・A、2・Bの内容が完全に理解できていることが前提条件になります。
極限では数列の極限や関数の極限の基本性質を理解し、微分積分では複雑な関数の計算や面積・体積の応用問題に取り組みます。 複素数平面では複素数の計算や図形への応用、式と曲線では媒介変数表示や極座標の扱い方を習得します。
数学3・Cは計算力と思考力の両方が試される分野なので、日々の演習で両方をバランスよく鍛える必要があります。
文系数学の大学受験対策におすすめの勉強法
文系数学の大学受験対策におすすめの勉強法を解説します。
文系数学の基礎固めは入門問題精講または黄色チャートを使って1日2時間のペースで典型問題の解法を暗記していきます。
文系数学ではこの時期に解けることよりも解法の理由を理解することを優先し、わからない単元はスタディサプリで映像授業を見ながら進めます。文系数学の入試で頻出の二次関数、確率、数列の基本パターンは特に丁寧に学習します。
文系数学の基礎を徹底的に固めるため、基礎問題精講を最低3周は繰り返します。 文系数学の勉強法として、1周目は解説を読みながら理解し、2周目は自力で解き、3周目は時間を計って解くという流れで進めます。特に文系数学で頻出の確率、数列、ベクトル、二次関数の微積分は1日1単元ずつ集中的に取り組みます。
文系数学の問題で苦手な単元が見つかったら、問題集の該当ページを2周追加で解いて弱点を克服します。 文系数学では確率と数列の融合問題がよく出題されるため、両方の単元を関連づけて理解することが重要です。この時期に文系数学の基本問題は8割以上正解できる状態を目指します。
文系数学の応用力を養うため、文系数学の良問プラチカまたは文系数学の実践力向上編を使います。 文系数学のこの段階では1日2時間のうち90分を初見問題の演習に充て、30分を復習に使います。文系数学の問題を見たら5分間は何も見ずに考え、どの解法を使うべきかの判断力を鍛えます。
文系数学の応用問題では複数の単元を組み合わせた問題が出題されるため、単元ごとの知識を統合する練習が必要です。 文系数学の標準レベルの問題集を1日5問から7問のペースで解き、間違えた問題は必ずノートに解法のポイントをまとめます。文系数学の得点力を高めるには、この時期の演習量が非常に重要になります。
文系数学の総仕上げとして志望校の過去問を10年分から15年分解いていきます。早慶レベルの文系数学であれば確率と数列の融合問題、微積分の面積計算問題を中心に対策し、MARCHレベルの文系数学であれば基本から標準レベルの問題を確実に得点する練習を重ねます。文系数学の答案作成では論理的な記述が求められるため、解答プロセスを丁寧に書く訓練も行います。
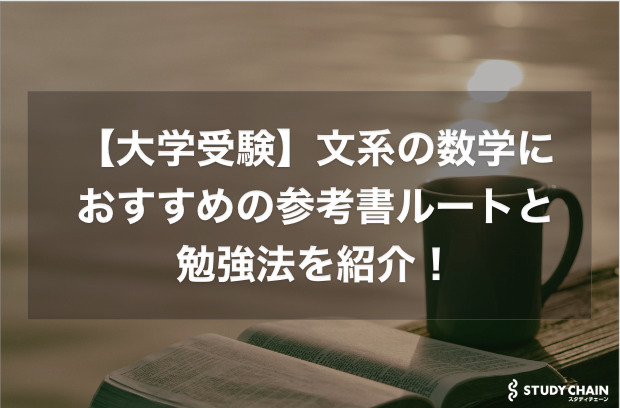 【大学受験】文系の数学におすすめの参考書ルートと進め方を徹底解説!
【大学受験】文系の数学におすすめの参考書ルートと進め方を徹底解説! 理系数学の大学受験対策におすすめの勉強法
理系数学の大学受験対策におすすめの勉強法を解説します。
理系数学の基礎固めは入門問題精講または黄色チャートを使って数学1・A、2・Bの全範囲を1日3時間のペースで進めます。
理系数学は範囲が広いため、1日あたり10問から15問の例題を解き、わからない単元は必ずTry ITやスタディサプリで映像授業を視聴します。理系数学の土台となる数学1・A、2・Bをこの時期に確実に理解することが後の学習効率を大きく左右します。
理系数学の本格的な学習として数学3・Cの基礎学習と数学1・A、2・Bの強化を並行して行います。 理系数学では午前中の2時間を数学3・Cの新規学習に充て、午後の1時間を数学1・A、2・Bの復習に使うという配分で進めます。理系数学の重要分野である基礎問題精講またはFocusGoldを使って、数学3の極限、微分積分、数学Cの複素数平面、式と曲線、ベクトルの基本問題を3周繰り返します。
理系数学の数学3・Cは計算量が多いため、毎日計算練習を欠かさず行うことが重要です。 理系数学では特に微分積分の計算スピードが合否を分けるため、積分計算は1日10問以上解いて習熟度を高めます。理系数学の基礎が固まったかどうかは、基本問題を見た瞬間に解法が思い浮かぶかどうかで判断します。
理系数学の応用力を養うため、理系数学の良問プラチカまたは標準問題精講を使います。 理系数学のこの段階では1日3時間のうち2時間を初見問題の演習に充て、1時間を間違えた問題の復習と解法の整理に使います。理系数学で差がつく微積分の計算は毎日10問以上解いて計算スピードを上げ、複素数平面やベクトルでは図形的な意味を理解しながら解く練習を積みます。
理系数学の応用問題では複数の分野を融合した問題が頻出するため、単元横断的な思考力を養います。 理系数学の演習では時間を計って解くことで本番を想定した訓練を行い、1問あたりにかけられる時間配分の感覚を身につけます。理系数学の偏差値を65以上に引き上げるには、この時期に難問にも積極的に挑戦する姿勢が重要です。
理系数学の総仕上げとして過去問演習と最終調整を行います。 東大や京大などの難関大学の理系数学を目指す場合は15年分から20年分の過去問を解き、志望校の頻出分野を徹底的に分析します。東大の理系数学であれば整数問題や確率漸化式、京大の理系数学であれば極限や複素数平面の難問が頻出なので、その分野を集中的に対策します。
理系数学の過去問演習では1日4時間のうち3時間を過去問演習に充て、1時間を苦手分野の補強に使います。 理系数学の本番では時間が足りなくなることが多いため、解ける問題から確実に得点する戦略を身につけます。理系数学の配点は非常に高いため、ここで安定して得点できるかどうかが合格を大きく左右します。
▽分野別におすすめの数学の参考書の一覧表
| 期間 | 勉強内容 | 使用する数学の参考書 |
|---|---|---|
| 1〜2ヶ月目 | 基礎例題で解法理解 | 「入門問題精講」「基礎問題精講」(旺文社)/「黄色チャート」「Focus Gold」(数研出版)/「はじめから始める数学」(東進ブックス) |
| 3〜4ヶ月目 | 解法暗記・苦手補強 | 「基礎問題精講」3周/「青チャート」(数研出版)/映像授業(Try IT・スタディサプリ) |
| 5〜6ヶ月目 | 標準問題で思考訓練 | 「標準問題精講」(旺文社)/「文系数学 実践力向上編」(河合出版)/「解法のエウレカ」(Z会)※上級者 |
| 7〜8ヶ月目 | 志望校別演習・頻出分野対策 | 「良問プラチカ」(河合出版)/「志望校別過去問」 |
▽もっとおすすめの数学の参考書を知りたいという方はこちら
 数学のおすすめの参考書ランキング20選を徹底解説!【大学受験】
数学のおすすめの参考書ランキング20選を徹底解説!【大学受験】 大学受験対策のノートを使った数学の勉強法
結論から述べると、数学のノートは予習用と復習用の2冊に分けることで成績が大きく伸びます。
予習用は授業内容のインプットと不明点の明確化に使い、復習用は要点整理とアウトプットに使います。
数学の予習用ノートと復習用ノートに分けることで苦手分野が見やすくなり、能動的な学習ができるようになります。
ノートには必ず日付、ページ数、ワーク名、単元名を書きましょう。いつの時点でどの問題ができているか、どの部分を間違えているかの記録がないと改善が困難です。 取り組んだ日付とワーク名は毎回必ず書くことが重要です。
間違えた問題を赤ペンで写して終わりにしないことが最も大切です。解説を読んだ後に本を閉じて、自力で一から解き直します。 ミスノートを別に作り、なぜ間違えたのか、どういう計算ミスをしたのかを記録しておくと、模試前に見返すことでケアレスミスが減らせます。
数式を左詰めで書かず、イコールごとに改行して縦に揃えて書くと計算ミスが減ります。
方眼ノートを使うと式を揃えやすく、分数も自由に書けるためおすすめです。 間違いは消さずに残しておき、正しい解法と比較できるようにしておきましょう。
志望校別におすすめの大学受験の数学の勉強法
志望校別におすすめの大学受験の数学の勉強法を解説します。
東大志望の大学受験生におすすめの数学の勉強法
東大数学の最大の特徴は、複数分野を組み合わせた融合問題が出題されることです。文系は100分で4問80点、理系は150分で6問120点の配点で、1問あたり20点の重みがあります。 解答用紙は大問ごとに区切られた大きなスペースのみで、小問ごとの区切り線がない全問記述式です。
何度も操作を繰り返すとどうなるかという問題が確率、漸化式、整数に多く出題されます。文系では数学的帰納法の習熟が重要で、理系では数学3の微積が2題出題され得点源となります。 東大の採点は答えに至るロジックを重視するため、完答できなくても解答方針が正しければ部分点を取れることが特徴です。
勉強法としては青チャートでレベル3までは完璧に、レベル4から5は8割解ける状態を目指します。その後1対1対応の演習や東大数学で1点でも多く取る方法で演習を重ねます。 過去問演習では論理的一貫性を意識した答案作りを心がけ、10年分以上解いて出題パターンに慣れることが合格への近道です。
慶應義塾大学志望の大学受験生におすすめの数学の勉強法
慶應数学は学部によって難易度と出題形式が大きく異なることが特徴です。理工学部は試験時間120分で大問5題、配点150点でマークシートと記述の併用形式となっています。 問題レベルは標準的ですが試験時間に対して問題数が多く、解答スピードを上げて全ての問題を解き切ることが求められます。
理工学部では微分積分、空間ベクトル、確率が頻出分野で、計算量が非常に多いことが特徴です。複雑な処理が必要になる場合があり、計算ミスで得点を落とさない工夫が重要です。
商学部は標準からやや難レベルの問題が目立ち、時間配分や問題選択に注意が必要です。総合政策学部は全てマーク式で、問題集では見たことのないような独自の問題が出題される傾向があります。
勉強法としては基礎問題精講やFocusGoldで典型問題を網羅した後、理系数学の良問プラチカで演習を積みます。慶應は難問を解くよりも、標準問題を確実に素早く解く力が合格につながります。 過去問10年分以上を時間を測って解き、頻出分野と自分の苦手分野をノートに整理して重点的に対策しましょう。
早稲田大学志望の大学受験生におすすめの数学の勉強法
早稲田数学は学部によって出題形式や難易度が大きく異なり、学部ごとに特化した対策が必要です。理工学部の数学は試験時間120分で大問5題の全問記述式で、年度によっては最難関国公立レベルに匹敵する難易度となります。 抽象度が高く計算量が多い問題が出題され、高い思考力と正確な計算力の両方が求められることが特徴です。
理工学部では微分積分が例年2題以上出題される最重要分野です。確率、数列、極限も頻出で、小問による誘導問題が設けられているため流れに沿って前の問題の解答を利用しながら解き進めます。 商学部の数学は90分で60点満点の文系数学としては最難関レベルで、例年平均点が10点前後、約16%程度を推移しています。半分正解するだけでも大きなアドバンテージとなります。
勉強法としては高校2年が終わるまでに全範囲を終わらせることが最重要です。基礎問題精講やFocusGoldを3周以上取り組み、見た瞬間に例題の解法が思いつく状態にします。 証明問題対策として数学的帰納法や背理法を完璧に使えるようにし、過去問10年分以上を解いて小問の誘導に沿って解く練習をノートで繰り返すことが合格への鍵です。
| ▽おすすめの数学の勉強法をもっと知りたい方はこちら |
| 定期テスト対策におすすめの数学の勉強法 |
| 共通テストの数学のおすすめの勉強法 |
| 大学受験向け数学のおすすめの勉強法 |
定期テスト対策におすすめの数学の勉強法
定期テスト対策におすすめの数学の勉強法を解説します。
高校生におすすめの数学の定期テスト対策の勉強法
数学の定期テストで高得点を取るためには、試験の2週間前から計画的に勉強を始めることが重要です。 最初に取り組むべきことは、出題範囲の確認と自分の苦手分野の洗い出しです。 授業ノートや配布プリントを見直して、どの単元が試験範囲なのかを明確にします。
2週間前の段階では、教科書や学校で配られた問題集の例題を全て解くことを目標にします。 解けなかった問題は必ず解説を読んで理解し、分からない部分はその日のうちに解決することが大切です。 教科書の解説だけでは理解が難しい場合は、教科書ガイドや映像授業サービスを活用します。
1週間前からは演習中心の勉強法に切り替えます。 1周目で間違えた問題を解説なしで解き直し、どこでつまずいたのかを分析します。 2回以上間違えた問題には印をつけて、試験直前に見返せるようにノートにまとめておくと効果的です。
高校生の数学の定期テストの前日の一夜漬けにおすすめの勉強法
試験前日は新しい問題に手を出さず、これまで解いた問題の総点検に集中します。 公式や定理の使い分けを素早く判断できるかを確認し、間違えやすいポイントを短時間でチェックします。 ただ読むだけでなく、実際に数問を手で解いて感覚を取り戻すことが重要です。
一夜漬けで勉強する場合は、試験範囲全体を網羅することは難しいため、出題頻度の高い単元に絞ります。 教科書の例題レベルの問題を確実に解けるようにすることを最優先にします。
学年別に高校生におすすめの数学の勉強法
学年別に高校生におすすめの数学の勉強法を解説します。
高校3年生におすすめの数学の勉強法
高校3年生は大学受験に向けた総仕上げの時期です。 春から夏にかけては基礎固めを徹底し、秋以降は志望校の過去問演習に集中します。 数学1A、2Bの基本的な解法パターンは、見た瞬間に思い出せるレベルまで定着させることが必要です。
基礎固めには基礎問題精講やフォーカスゴールドなどの参考書を使い、例題を3周以上解きます。 1周目は理解を重視し、2周目以降は何も見ずに解けることを目標にします。 基礎が固まったら、標準問題精講などで応用力を鍛え、秋以降は志望校の過去問を10年分から15年分解きます。
高校2年生におすすめの数学の勉強法
高校2年生は数学2Bの内容が本格化し、難易度が大きく上がる時期です。 微分積分やベクトルは大学受験でも頻出分野であるため、授業の段階でしっかり理解することが大切です。 予習よりも復習に重点を置き、授業で習った内容はその日のうちに復習します。
定期テストごとに学んだ内容を確実に定着させることが、受験勉強の基盤となります。 黄色チャートやフォーカスゴールドなどの参考書を使い、例題レベルの問題を繰り返し解きます。 2年生の後半からは、1年生で学んだ数学1Aの内容も並行して復習を始めることをおすすめします。
高校1年生におすすめの数学の勉強法
高校1年生はこの時期に数学への苦手意識を持たないことが、とても大事です。 授業についていけないと感じたら、早めに基礎レベルの参考書で復習することが重要です。
数学が苦手な場合は、はじめから始める数学シリーズのような解説が丁寧な参考書から始めます。 教科書の例題を確実に理解し、同じレベルの問題を繰り返し解いて基礎を固めてください。
中学生におすすめの数学の勉強法
中学数学は高校数学の土台となる重要な内容です。 方程式や関数、図形の性質といった基本概念をしっかり理解することが、高校での学習をスムーズにします。 分からない部分を放置せず、その都度解決する姿勢が大切です。
毎日30分でも良いので、教科書の問題や学校のワークを継続的に解きます。 計算ミスを減らすために、途中式を丁寧に書く習慣をつけます。 定期テストの2週間前からは集中的に勉強時間を増やし、試験範囲を2周以上復習します。
まとめ
数学の大学受験対策におすすめの勉強法を解説しました。
以下が今回のまとめおよび要点になります。