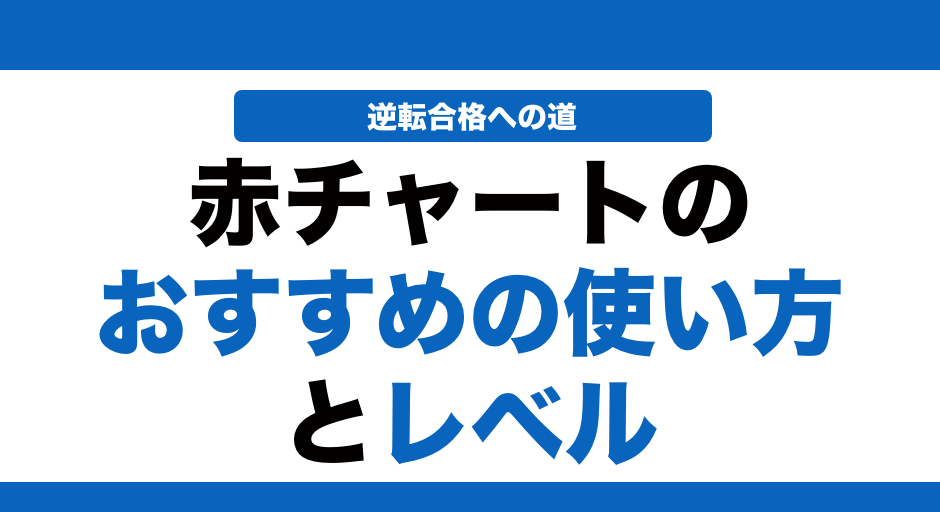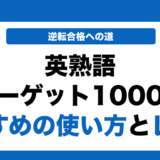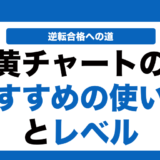本サイトの表記には、一部プロモーションを含みます
赤チャートのおすすめの使い方と勉強法を徹底解説します。
赤チャートのレベルや難易度についても具体的に解説します。また実際にやってみておすすめの赤チャートの参考書としての進め方や順番についても紹介します。

【この記事の監修者:逆転合格特化塾塾長竹本明弘】
これまで個別指導塾の塾長として早慶に現役生および浪人生を含めて合計で300人以上の合格者を輩出してきました。参考書の使い方や各教科の勉強法について紹介しているのでぜひ参考にしてみてください。
赤チャートのレベル
赤チャートのレベルを解説します。
赤チャートのレベルと難易度
赤チャートは入試標準から難レベルまでを一冊で網羅する上位者向け問題集です。例題と練習でコンパス3を素早く解ける段階で偏差値60台に乗りやすく、コンパス4と5を8割以上即答できれば偏差値67.5〜70が現実的になります。共通テスト対策にとどまらず旧帝大や早慶の二次記述に直結する解法運用力を鍛えられます。

【この記事の監修者:逆転合格特化塾塾長竹本明弘】
赤チャートは偏差値65以上を狙う受験生の主軸教材です。例題の理解直後に練習で確認し、日を空けて周回し、瞬時に手が動くかで進捗を判定すること。コンパス5を8割即答できる状態が東大京大志望の実戦到達目安です。
赤チャートの習熟度別のレベル
赤チャートは段階的に習得することで、確実に実力をつけることができます。
各レベルの到達目標を明確にしておくことで、受験生の皆さんは自分の現在地を把握しながら学習を進めることができます。
レベル1は、コンパス2までの例と例題が8割以上、手を止めずに解ける状態です。この段階では赤チャートの基礎部分を理解し始めた状態と言えます。
レベル2では、コンパス2までの練習問題が8割以上、手を止めずに解けるようになります。このレベルに到達すると偏差値55程度が期待できます。赤チャートを使い始めた受験生がまず目指すべき地点です。
レベル3は、コンパス3までの例と例題が8割以上、手を止めずに解ける段階です。難関大学入試の標準問題に対応できる基礎力が身につき始めます。
レベル4になると、コンパス3までの練習問題が8割以上、手を止めずに解けるようになります。この段階で偏差値65に到達し、東京大学や京都大学といった最難関大学の受験に必要な実力が備わってきます。
レベル5は、コンパス5までの例と例題が8割以上、手を止めずに解ける状態です。赤チャートの例題部分をほぼ完璧にマスターした段階と言えます。
レベ6では、コンパス5までの練習問題が8割以上、手を止めずに解けます。このレベルに達すると偏差値67.5程度となり、最難関大学でも数学を得点源にできる力がつきます。
レベル7は演習問題が5割以上、手を止めずに解ける段階です。赤チャートの最高難度の問題にも取り組める実力がついています。
レベル8では演習問題が8割以上、手を止めずに解けるようになり、偏差値70に到達します。この段階まで到達すれば、どの大学の入試でも数学で高得点を狙える実力が身についています。
▽赤チャートと他の数学の参考書のレベルを比較

▽数学のおすすめの参考書をもっと知りたいという方はこちら
 数学のおすすめの参考書ランキング20選を徹底解説!【大学受験】
数学のおすすめの参考書ランキング20選を徹底解説!【大学受験】 赤チャートのおすすめの使い方
赤チャートを効果的に使うためには、段階的な学習方法を実践することが重要です。ここでは3つの段階に分けて、赤チャートの使い方を解説します。
赤チャートを使い始める受験生は、まず例題に取り組むことから始めます。例題を見たら、まず自力で解けるかどうかを試してみましょう。解き方がわからない場合は、すぐにバツマークをつけて解説を読みます。
ここで重要なのは、長時間考え込まないことです。赤チャートを使う目的は新しい解法や考え方を身につけることなので、知識がない状態で悩み続けるのは効率が悪いのです。
解説を読む際には、指針やチャートの部分に特に注目しましょう。これらの箇所には、その問題を解くための重要なポイントが明確に書かれています。ただ漫然と読むのではなく、こういう式や条件があったらこう解く、というパターンを意識しながら読むと応用力が高まります。重要な部分には印をつけたり、書き込みをしたりすることで理解が深まります。
例題の解説を読んだ後は、解き直しをせずにすぐ下の練習問題に移ります。例題で学んだ解法が本当に身についているかを確認するためです。例題が解けなくても練習は解けることが多く、その場合は例題にバツ、練習にマルをつけます。このマーク付けによって、次回以降は例題だけ復習すればよいことがわかり、復習効率が格段に向上します。
赤チャートの使い方で特に重要なのが、マルバツマークを活用した復習管理です。受験生の皆さんは必ずマルバツマークをつけながら学習を進めてください。解けた問題にはマル、解けなかった問題にはバツを機械的につけていきます。
マルバツマークは累積させることがポイントです。バツマークが何個もついた後にマルがついた問題は、習得に時間がかかった問題であり、優先的に復習すべき問題だとひと目でわかります。マルバツマークを消して上書きしてしまうと、この貴重な情報が失われてしまいます。
ただし、マルバツマークをつけるのは3日以上あけて復習した場合に限るというルールを守ってください。短期的な復習で解けてもそれは短期記憶に過ぎず、マルバツマークの信頼性が下がってしまいます。この厳格なルールで運用することで、長期記憶に定着した問題としていない問題を正確に把握できます。
赤チャートを使った学習では、既習範囲を最初から最後までやり、再び最初に戻ってくるサイクルで勉強します。この分散学習によって、自動的に適切な期間をあけて復習することができ、長期記憶への定着が促進されます。
赤チャートの習得において最も重要なのは、問題を瞬殺できる状態を目指すことです。マルをつける基準は、時間をかけずにスムーズに解けるかどうかです。時間がかかったり途中で詰まったりした場合は、まだ瞬殺レベルに達していないと判断してください。
1テーマあたり30分を目安に学習を進めます。例題がわからなければすぐに解説を読み、15分ほどかけて理解し、残りの15分で練習問題に取り組みます。例題が解ける場合は20分ほどで完答し、10分で解答を確認します。ただし1周目は慣れない部分もあるため、多少時間がかかっても構いません。2周目以降は1テーマ30分以内で進められるようになります。
例題が解けた場合、練習問題はスキップして構いません。練習問題は例題とほぼ同じ内容なので、例題が瞬殺できれば練習も解けるからです。ただし苦手意識のあるテーマは練習問題も解いておくとよいでしょう。
赤チャートの使い方では、忘れてから思い出すという分散学習が原則です。短期的に復習を繰り返すと短期記憶にしかならず、すぐに忘れてしまいます。時間をあけて復習することで徐々に長期記憶に定着させていきましょう。

赤チャートの習得にかかる時間
赤チャートの習得に必要な時間を把握しておくことは、受験生の皆さんが学習計画を立てる上で非常に重要です。ここでは具体的な時間の目安をお伝えします。
赤チャートでは、1テーマ、つまり1つの例題と1つの練習問題をセットにして約30分が標準的な学習時間となります。もちろん問題によって難易度は異なるため、実際にかかる時間は変動しますが、平均するとこの程度の時間になります。この時間を基準に学習計画を立てると、大きく見積もりを誤ることがありません。
演習問題については、1問あたり20分程度を目安としてください。演習問題は例題よりも難易度が高く、思考力が求められる問題が多いため、例題よりも時間がかかります。
赤チャートの数学1Aには、例と例題を合わせて364問、練習問題が229問あります。数学2には例と例題が263問、練習問題が187問です。これらすべてを習得しようとすると相当な時間が必要になりますが、レベルに応じて取り組む範囲を調整することで、効率的に学習を進めることができます。
例えばコンパス3までを完璧にすることを目標とする場合、それより上のコンパスの問題は後回しにできます。このように自分の目標レベルに応じて学習範囲を絞り込むことで、赤チャートの使い方はより効率的になります。
また、2周目以降はマルバツマークによって復習すべき問題が明確になっているため、1周目の半分程度の時間で復習を終えることができます。特に例題にバツ、練習にマルがついている問題は例題だけ復習すればよいので、大幅に時間を短縮できます。
赤チャートを使う時の注意点
赤チャートを使って学習する際には、いくつか重要な注意点があります。これらを守ることで、赤チャートを最大限に活用することができます。
まず最も重要なのは、瞬殺できる状態を目指すということです。マルをつける際の判断基準として、手を止めずにスムーズに解けているかを厳しく評価してください。時間がかかったり途中で詰まったりした場合、たとえ最終的に正解できたとしても、それは瞬殺レベルとは言えません。瞬殺できていないのにマルをつけてしまうと、習得レベルが上がっているのに期待する偏差値が出ず、自信を失う原因になってしまいます。赤チャートをやったという状態は、瞬殺できるようになったという状態と同義なのです。
次に、例題の後すぐに練習問題に入るという流れを守りましょう。例題の解答を見た後に練習を解くのはもったいないと感じるかもしれませんが、例題にバツ、練習にマルがつく問題を増やすことのメリットは非常に大きいのです。この状態は、例題の解き方さえ定着すれば練習は解けることを意味しており、次回以降の復習では練習をスキップできるため、復習時間が大幅に短縮されます。
1テーマに30分以上かけないという時間管理も重要です。例題がわからなければすぐに解答を読み、それでもわからない問題は次の周回に回したほうが効率的です。1周目で完璧を目指す必要はありません。分散学習を繰り返すことで徐々に定着させていくほうが、結果的に早く習得できます。
分散学習の原則を守ることも大切です。忘れるのが怖くて短期的に復習してしまうと、短期記憶にしかならず、またすぐに忘れてしまいます。この負のスパイラルに陥ると、勉強時間をかけても成績が伸びません。3日以上あけて復習し、忘れてから思い出すという学習を基本としてください。
赤チャートの演習問題については、すべて解く必要はありません。演習問題の中には難易度が高すぎたり、出題傾向的に優先度が低かったりする問題も含まれています。自分の目標レベルに応じて、取り組む範囲を選択することが賢い赤チャートの使い方です。
赤チャートの特徴
赤チャートには、他の参考書にはない独自の特徴があります。ここでは受験生の皆さんが知っておくべき赤チャートの特徴を解説します。
第一の特徴は、例題を通して典型問題からやや発展的な問題まで学べることです。
青チャートではエクササイズで扱われていたような問題が、赤チャートでは例題として取り上げられています。逆に、青チャートで例題として扱われていたあまり典型的とは言えない問題は、赤チャートの例題からは除外されています。このように、より重要度の高い問題が厳選されて例題に配置されており、偏差値70を目指す受験生にとっては青チャートよりも赤チャートのほうが効率的に学習を進められます。
第二の特徴は、ポイントが明確に書かれていることです。指針やチャートというコンテンツが例題の解説に掲載されており、その問題のテーマにおける重要なポイントが非常にわかりやすく説明されています。これらの部分を意識して読むことで、問題の本質的な考え方を理解することができます。赤チャートの使い方として、この指針とチャートの部分を重点的に学習することは非常に効果的です。
第三の特徴は、チェック問題で簡単な計算問題を確認できることです。各セクションの最初にチェック問題が配置されており、基本的な計算力を確認してから例題に取り組むことができます。これにより、受験生は段階的に難易度を上げながら学習を進めることができ、スムーズに赤チャートの内容に入っていくことができます。
第四の特徴として、解説が本質的で詳しいという点が挙げられます。青チャートが問題の解き方のプロセスを中心に解説しているのに対し、赤チャートは数学的な本質により重きを置いて解説されています。数学が得意で、表面的な知識より本質的なことを理解したい受験生にとっては、赤チャートの解説のほうが適しています。
赤チャートのメリット
赤チャートを使用することには多くのメリットがあります。
偏差値60から70に到達できる
最大のメリットは、偏差値70まで到達できる実力が身につくことです。赤チャートは東京大学、京都大学、大阪大学などの最難関大学の入試に対応できる内容となっており、本書のみで難関大学合格に必要な数学力を養成することができます。特に数学を得点源にしたい受験生にとって、赤チャートは理想的な参考書と言えます。
マルバツマークによる復習管理ができることも大きなメリットです。赤チャートの使い方として推奨されているマルバツマーク方式を実践すると、2周目以降の復習すべき問題数が大幅に減少します。
特に例題にバツ、練習にマルがついている問題は例題だけ復習すればよいため、1周目の半分程度の時間で2周目を完了できます。また、マルバツマークを累積することで、優先的に復習すべき問題がひと目でわかり、効率的な学習が可能になります。
難問かつ良問が数多く掲載
問題の厳選度が高いこともメリットです。赤チャートに掲載されている問題は、入試で出題される可能性が高い重要な問題が中心となっており、無駄な問題に時間を費やすことがありません。特に医学部や最難関大学を目指す受験生にとって、必要十分な問題が揃っているため、赤チャート1冊を完璧にすれば他の問題集に手を広げる必要が少なくなります。
解説の質の高さもメリットの一つです。赤チャートは難易度が高い参考書でありながら、解説は非常に詳しく丁寧に書かれています。数学の本質的な理解を促す解説となっているため、単なる解法の暗記ではなく、応用力のある真の数学力を身につけることができます。このような質の高い解説により、受験生は独学でも赤チャートを使いこなすことが可能です。
赤チャートのデメリット
赤チャートには優れた特徴が多い一方で、いくつかのデメリットも存在します。
最も大きなデメリットは、簡単な問題が例題ではなく例として扱われていることです。青チャートのコンパス1や2に相当する基本的な問題が、赤チャートでは例という形式で掲載されており、問題の下に解説が載っていません。
別冊解説を見る必要があるため、基本問題の習得がやや面倒になります。数学の基礎に不安がある受験生にとっては、この点が赤チャートの使いづらさにつながる可能性があります。
演習問題の中に解かなくてもよい問題が多いこともデメリットです。赤チャートの演習問題には、難易度が高すぎたり、問題の質的に優先度が低かったりするものが含まれています。そのため、演習問題に手をつける場合は、すべてを解くのではなく一部に絞る必要があります。どの問題を解くべきか判断する必要があるため、受験生にとっては負担になる場合があります。
採用校が少ない点にやや不安が残ることも挙げられます。医学部や最難関大学を目指す受験生の多くが青チャートやフォーカスゴールドを使用しており、赤チャートを使用している受験生は相対的に少数です。受験は相対評価であるため、多数派が使っている参考書を使わないことに不安を感じる受験生もいるでしょう。ただし、赤チャートの問題ラインナップは必要十分であり、内容的には全く問題ありません。
難易度が高いため、数学の基礎が固まっていない段階で取り組むと挫折しやすいこともデメリットです。赤チャートは教科書レベルの理解が前提となっているため、基礎が不十分な状態で始めると理解が追いつかず、効率的に学習を進められません。すでに青チャートを持っている場合は、無理に赤チャートに乗り換える必要はなく、青チャートを完璧にするほうが効率的です。
学習に時間がかかることもデメリットの一つです。赤チャートは問題数が多く、すべてを習得するには相当な時間が必要です。受験生の中には、赤チャートに時間をかけすぎて他の科目の学習や過去問演習に十分な時間を割けなくなってしまうケースもあります。自分の受験までの残り時間を考慮し、赤チャートの使い方を計画的に決めることが重要です。
赤チャートに関するよくある質問
赤チャートに関するよくある質問を紹介します。
- 赤チャートの後に取り組むべき問題集はありますか
- 赤チャートを完璧にマスターした後は、志望大学の過去問演習に進むのが最も効果的です。赤チャートのレベルまで習得していれば、ほとんどの大学の過去問に対応できる実力がついています。さらにレベルアップを目指す場合は、大学への数学シリーズの上級問題精講や、志望大学別の対策問題集に取り組むとよいでしょう。ただし、多くの受験生にとって、赤チャートと過去問だけで十分な対策ができます。新しい問題集に手を広げるよりも、赤チャートを何度も復習して完璧にすることのほうが重要です。
- 赤チャートは何周すればよいですか
- 赤チャートは最低でも3周することを推奨します。1周目はほとんどの問題ができないのが普通で、新しい解法を身につけることが目的です。2周目では復習すべき問題が明確になっており、1周目の半分程度の時間で終えることができます。3周目以降は、マルバツマークでバツが多くついている問題を中心に復習します。瞬殺できる状態になるまで周回を重ねることが重要で、人によっては4周、5周と繰り返す必要があります。赤チャートの使い方として、周回数よりも各問題を瞬殺できる状態になることを目標にしてください。
- 赤チャート1冊で大学受験は十分ですか
- 赤チャートのみで偏差値70まで到達可能であり、多くの難関大学の入試に対応できます。東京大学や京都大学、医学部などの最難関大学を受験する場合でも、赤チャートを完璧にマスターすれば、数学で合格点を取るための実力は十分に身につきます。ただし、志望大学の過去問演習は別途必要です。また、特定の分野や形式に特化した対策が必要な場合は、赤チャートに加えて過去問や大学別対策問題集を使用するとよいでしょう。
- 赤チャートの演習問題はすべて解くべきですか
- 赤チャートの演習問題はすべて解く必要はありません。演習問題の中には難易度が非常に高いものや、入試での出題頻度が低いものも含まれています。偏差値65から67.5を目指す場合は、コンパス5までの例題と練習を完璧にすることを優先し、演習問題は余裕があれば取り組む程度でよいでしょう。偏差値70を目指す場合でも、演習問題は5割から8割程度解ければ十分です。赤チャートの使い方として、自分の目標レベルに応じて取り組む範囲を調整することが効率的です。
- 赤チャートと青チャートはどちらを選ぶべきですか
- すでに青チャートを持っている場合は、青チャートを継続して使用することをおすすめします。青チャートも赤チャートも、どちらも偏差値67.5から70まで到達できる優れた参考書です。途中で参考書を変更すると、その分学習時間が無駄になってしまいます。これから新しく購入する場合は、より問題が厳選されていて効率的に学習できる赤チャートを選ぶのもよいでしょう。赤チャートは青チャートと例題の重複が多いものの、より発展的な問題が例題として扱われているため、最難関大学を目指す受験生には適しています。
- 赤チャートは初学者でも使えますか
- 赤チャートは初学者にも使用可能ですが、教科書レベルの基礎がある程度身についていることが望ましいです。新課程版の赤チャートは以前よりも基礎問題が充実しており、例やチェック問題で基本的な内容から学べるようになっています。ただし、数学に苦手意識がある場合や、教科書の内容がまだ十分に理解できていない場合は、まず白チャートや黄チャートから始めることをおすすめします。赤チャートの使い方として、教科書の例題レベルが解ける状態になってから取り組むと、スムーズに学習を進めることができます。