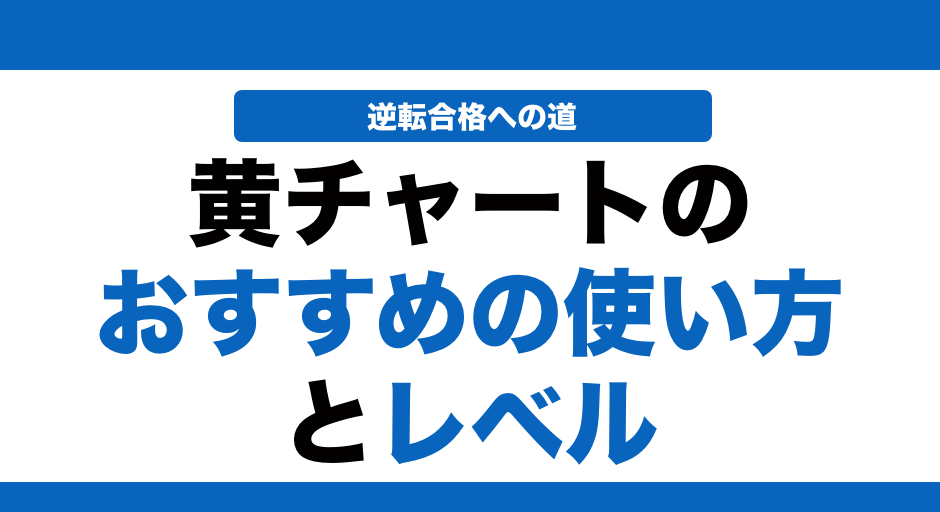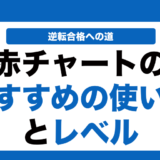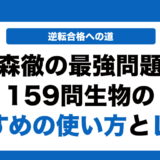本サイトの表記には、一部プロモーションを含みます
数学の黄チャートのおすすめの使い方と勉強法を徹底解説します。
数学の黄チャートのレベルや難易度についても具体的に解説します。また実際にやってみておすすめの数学の黄チャートの参考書としての進め方や順番についても紹介します。

【この記事の監修者:逆転合格特化塾塾長竹本明弘】
これまで個別指導塾の塾長として早慶に現役生および浪人生を含めて合計で300人以上の合格者を輩出してきました。参考書の使い方や各教科の勉強法について紹介しているのでぜひ参考にしてみてください。
黄チャートのレベル
黄チャートのレベルを解説します。
黄チャートのレベルと難易度
黄チャート(チャート式 解法と演習数学)は、共通テスト〜国公立・難関私大レベルまで対応した標準〜やや難レベルの参考書です。例題のみで偏差値65、Exerciseまでやり切れば偏差値67.5に到達でき、青チャートよりも分量が少なく最後まで完走しやすい構成です。
必要十分な典型問題が厳選されており、CHART & SOLUTIONの解説も丁寧で、どの問題にどの解法を使うかが明確に整理されています。基礎から応用まで体系的に身につくため、最初の1冊としても、共通テスト対策やMARCH・早慶・国公立上位校対策にも最適な問題集です。

【この記事の監修者:逆転合格特化塾塾長竹本明弘】
青チャートは分量が多く挫折しやすいですが、黄チャートは必要十分なレベルに絞られており、やり切れば数学の基礎力と標準問題の瞬殺力が確実に身につきます。最初の1冊としても仕上げ用としても非常に優れています。
黄チャートの習熟度別のレベル
黄チャートのレベルを段階的に解説します。
黄チャートは6つの習得レベルに分かれており、受験生の到達度を明確に測ることができます。
レベル1では、コンパス2までの例題が8割以上手を止めずに解ける状態を目指します。
レベル2になると、コンパス2までの練習問題が8割以上スムーズに解けるようになり、偏差値55相当の実力がつきます。
レベル3では、コンパス5までの例題が8割以上手を止めずに解ける状態となります。
レベル4まで到達すると、コンパス5までの練習問題が8割以上解けるようになり、偏差値65相当の実力を獲得できます。
レベル5では、Exercisesの問題が5割以上手を止めずに解ける状態を目指します。
最高レベルのレベル6では、Exercisesが8割以上スムーズに解けるようになり、偏差値67.5に到達します。この段階まで黄チャートのレベルを上げれば、東京大学や京都大学などの最難関大学の入試にも対応できる実力がつきます。
| レベル | 到達基準 | 偏差値目安 |
|---|---|---|
| レベル1 | コンパス2までの例題が8割以上、手を止めずに解ける | – |
| レベル2 | コンパス2までの練習が8割以上、手を止めずに解ける | 偏差値55 |
| レベル3 | コンパス5までの例題が8割以上、手を止めずに解ける | – |
| レベル4 | コンパス5までの練習が8割以上、手を止めずに解ける | 偏差値60 |
| レベル5 | Exercisesが5割以上、手を止めずに解ける | – |
| レベル6 | Exercisesが8割以上、手を止めずに解ける | 偏差値62.5 |
▽黄チャートと他の数学の参考書のレベルを比較

▽数学のおすすめの参考書をもっと知りたいという方はこちら
 数学のおすすめの参考書ランキング20選を徹底解説!【大学受験】
数学のおすすめの参考書ランキング20選を徹底解説!【大学受験】 黄チャートのおすすめの使い方
黄チャートのおすすめの使い方を段階的に解説します。
黄チャートの使い方として、まず例題に挑戦してみることから始めます。解法がわからない場合は、すぐにバツマークをつけて解説を読みましょう。知識がない状態で長時間考え込むよりも、すぐに解説を読んで新しい解法を学ぶ方が効率的です。解説を読む際は、この式があったらこう解くというパターンで理解することが大切です。考え方やCHART&SOLUTION、CHART&THINKINGに書かれた内容を重点的に読み込みましょう。例題の解説を読んだ後は、すぐに練習問題に取り組みます。例題が解けなくても、練習問題は解けることが多いです。なぜなら練習問題は例題とほぼ同じ内容だからです。練習問題が解けたらマルマークをつけます。このように例題にバツマーク、練習問題にマルマークがつく問題は、次回以降例題だけ復習すればよいので効率が良くなります。黄チャートのレベルを上げるには、この使い方を徹底することが重要です。
黄チャートの使い方の第2段階として、マーキングシステムを確立します。マルバツマークは累積していき、決して消さないようにします。バツマークが複数ついた後にマルマークがついた問題は、優先的に復習すべき問題だからです。マークをつける際のルールとして、3日以上間隔を空けて復習した場合のみマークをつけるようにしましょう。短期的な復習でマークをつけると、マークの意味が薄れてしまいます。1テーマあたり30分を目安に進めます。例題がわからなければ15分で解説を読み、残り15分で練習問題に取り組みます。例題が解ける場合は20分で完答し、10分で解答確認をします。分散学習を基本とし、既習範囲を最初から最後まで進めてから再び最初に戻るサイクルで学習します。この黄チャートの使い方により、長期記憶への定着が促進されます。
黄チャートの使い方の第3段階は、全ての問題を瞬殺できるレベルまで仕上げることです。マルマークをつける基準は、問題を見た瞬間に解法が浮かび、手を止めずに最後まで解ききれる状態です。この基準に達していない状態でマルマークをつけてしまうと、模試で点数が取れず黄チャートのレベルが上がっているのに結果が出ないという状況に陥ります。例題が瞬殺できるようになったら、練習問題はスキップして構いません。2周目以降はバツマークがついた問題のみを集中的に復習するため、1周目の半分以下の時間で済みます。Exercisesまで取り組む受験生は、コンパス5までの問題が瞬殺できるようになってから挑戦しましょう。この黄チャートの使い方を徹底すれば、偏差値67.5レベルまで到達可能です。
黄チャートの習得にかかる時間
黄チャートの習得にかかる時間を解説します。
黄チャートは1テーマあたり30分、Exercisesは1問あたり20分が目安となります。
数学1の例題は157問あり、練習問題も同数なので合計314問です。これだけで約157時間かかります。
数学Aは例題138問と練習問題138問で276問、約138時間です。
数学2は例題225問と練習問題225問で450問、約225時間となります。数学Bは例題80問と練習問題80問で160問、約80時間です。
数学3は例題181問と練習問題181問で362問、約181時間かかります。
数学Cは例題150問と練習問題150問で300問、約150時間です。ただし2周目以降はバツマークがついた問題のみの復習となるため、所要時間は1周目の半分程度に短縮されます。毎日2時間学習すれば、1冊を約2か月で1周できる計算です。受験生の理解度により時間は前後しますが、この目安で計画を立てると大きくずれることはありません。

黄チャートを使う時の注意点
黄チャートを使う時の注意点を解説します。
最も重要な注意点は、瞬殺できる状態を基準にマルマークをつけることです。
何となく解けた程度でマルマークをつけてしまうと、黄チャートのレベルが上がっているはずなのに模試で点数が取れないという事態になります。問題集をやったという状態は、瞬殺できるようになったという状態と同じ意味です。
次に、例題が解けなかった場合は必ずすぐに練習問題に取り組みましょう。例題の解説を読んだ後に練習問題を解くのはもったいないと思うかもしれませんが、例題の解法が定着すれば練習問題は解けることを確認できるため、次回以降の復習効率が大幅に向上します。分散学習の原則を守ることも大切です。
短期的な復習を繰り返すと短期記憶にしかならず、すぐに忘れてしまいます。忘れてから思い出すことで長期記憶に定着させましょう。3日以内の復習ではマルマークをつけないというルールを厳守してください。
黄チャートの特徴
黄チャートの特徴をいくつか解説します。
黄チャートの最大の特徴は、必要十分な問題が厳選されている点です。青チャートと比べると、難しすぎてやる必要のない問題が含まれておらず、一方で偏差値67.5まで到達できる十分な問題量が確保されています。
受験生が本当に身につけるべき典型問題に絞り込まれているため、無駄のない学習が可能です。CHART&SOLUTIONというコンテンツも充実しており、各単元のポイントが明確に記載されています。
青チャートにも同様のコンテンツはありますが、黄チャートの方がより詳しく丁寧に書かれています。コンパスマークによる難易度表示も特徴的で、コンパスマーク1は教科書の例レベル、2は教科書の例題レベル、3は教科書の節末章末レベル、4は入試の基本から標準レベル、5は入試の標準からやや難レベルとなっています。
受験生は自分の現在のレベルと目標レベルを把握しやすく、計画的に学習を進められます。
黄チャートのメリット
黄チャートのメリットをいくつか解説します。
復習効率が飛躍的に向上する
黄チャートのメリットとして、マルバツマークによる復習効率の向上が挙げられます。例題にバツマーク、練習問題にマルマークという組み合わせが多くなるため、2周目以降は例題のみを復習すればよく、1周目の5割の時間で2周目を完了できます。解ける問題に時間をかけず、解けない問題に集中できるため、学習効率が格段に上がります。
優先順位が明確になる
マークを累積することで、バツマークが複数ついた後にマルマークがついた問題が優先的に復習すべき問題だとひと目でわかります。解けるようになるまで時間がかかった問題ほど忘れやすいため、このシステムは非常に合理的です。受験生は限られた時間の中で効率的に復習できます。
学校指定で追加購入不要なケースが多い
黄チャートは多くの高校で指定教材として採用されているため、すでに持っている受験生が多いです。新たに参考書を購入する必要がなく、経済的負担も少なくて済みます。医学部や難関大学合格者も黄チャートを使用しており、実績も十分です。
黄チャートのデメリット
黄チャートのデメリットをいくつか解説します。
典型問題の一部がExercisesに配置されている
黄チャートのデメリットとして、本来例題で扱うべき典型問題の一部がExercisesに掲載されている点があります。例題だけでは偏差値65までしか到達できず、偏差値67.5を目指すにはExercisesまで取り組む必要があります。受験生によっては負担に感じるかもしれません。
採用校が限られることへの不安
医学部や難関大学を目指す受験生の多くがFocus Goldや青チャートを使用しているため、黄チャートを使うことに不安を感じる受験生もいます。受験は相対評価なので、周りと同じ参考書を使いたいという心理は理解できます。ただし黄チャートの問題選定は必要十分であり、実際には十分対応可能です。
最高レベルまでは到達しにくい
偏差値70近くを最終目標とする受験生にとっては、黄チャートだけでは物足りない可能性があります。最初からFocus Goldや青チャートを選んだ方が効率的なケースもあります。ただし偏差値67.5まで到達できれば多くの難関大学に合格できるため、受験生の目標次第といえます。
黄チャートに関するよくある質問
黄チャートの使い方や選び方に関するよくある質問を紹介します。
- 黄チャートの前後に他の問題集は必要ですか?
- 黄チャートの前に取り組むべき問題集は特にありません。1冊目として使用できます。黄チャートの後についても、偏差値67.5まで到達可能なので、多くの受験生は市販教材としては黄チャートのみで十分です。目指す偏差値や志望校によって判断しましょう。黄チャートのレベルと使い方を徹底すれば、難関大学にも対応できる実力が身につきます。
- 黄チャートとニューアクションレジェンドの違いは何ですか?
- 両者はレベルが近く、どちらも偏差値65から67.5を目指せる問題集です。すでにどちらかを持っている場合は、わざわざ変更する必要はありません。黄チャートの使い方をマスターすれば、十分な実力がつきます。
- 黄色チャートは何周する必要がありますか?
- 全ての問題が瞬殺できるようになるまで繰り返すのが理想ですが、一般的には3周から5周で十分な受験生が多いです。マルバツマークをつけながら進めれば、2周目以降は復習すべき問題が絞られます。黄チャートのレベルを上げるには、バツマークが多い問題を重点的に復習することが大切です。
- 黄チャートは1日どのくらい勉強すればよいですか?
- 毎日2時間程度取り組めば、1冊を約2か月で1周できます。部活動で忙しい受験生は1日1時間から始め、徐々に増やしていきましょう。重要なのは継続することです。黄チャートの使い方として、短時間でも毎日取り組むことが効果的です。
- 黄チャートと青チャートはどちらを選ぶべきですか?
- すでに学校で黄チャートが配られている受験生は、そのまま黄チャートを使い続けることをおすすめします。黄チャートだけで偏差値67.5まで到達でき、東京大学や京都大学などの難関大学にも対応可能です。これから購入する受験生で偏差値70を目指す場合は、青チャートやFocus Goldを選ぶとよいでしょう。黄チャートのレベルと使い方を理解すれば、十分な結果を出せます。