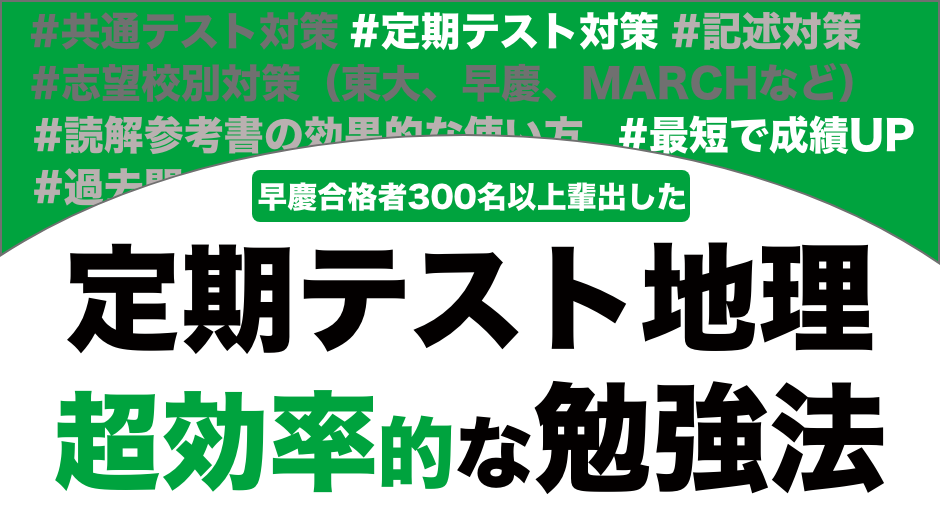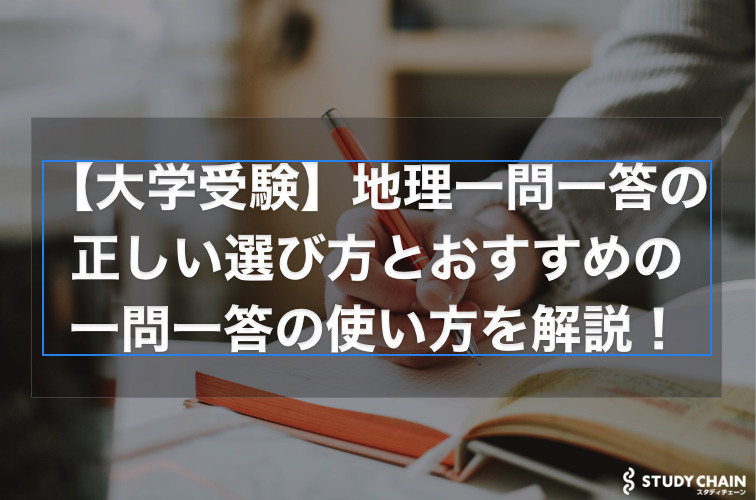本サイトの表記には、一部プロモーションを含みます
地理の定期テストで高得点(9割)を取るための勉強法と定期テスト対策の勉強のスケジュールを徹底解説します。
地理のレベル別に定期テスト対策及び文野別に解説をしています。
地理の定期テストを受験勉強の偏差値UPにつなげるためにもぜひご覧ください。

【この記事の監修者:逆転合格特化塾塾長竹本明弘】
定期テストの地理対策で重要なことは2週間を半分に分けた時に、最初の1週間でしっかりと前提知識や細かい背景知識を暗記し、その後問題を解くなどアウトプットの量を増やしながら、問題の考え方や応用問題の解き方をマスターしていくことが重要です。
定期テストの地理で9割を取る勉強法
定期テストの地理で9割が取れる勉強法を解説します。
- 最初の1週間は、地理の定期テストに向けた基礎固めの期間です。この時期に一番大切なことは、1週間前までにテスト範囲の7割を理解し、説明できる状態を作ることです。地理の定期テストで高得点を狙うためには、暗記よりも理解を重視した勉強法が必要です。地理は思考力を問う問題が多く、丸暗記の勉強では応用が効かないためです。だからこそ、2週間前からの勉強が勝負になります。
- まず、1日60分から90分の勉強時間を確保してください。この段階では、教科書、授業ノート、地図帳を使いながら、「なぜそうなるのか」を丁寧に考えることがポイントです。例えば、中東に石油が多いのはなぜか、日本の気候が地域によって違うのはなぜか、ヨーロッパの都市が川沿いに多いのはなぜか。こうした疑問をその日のうちに教科書を使って解決していきましょう。教科書は学校によっては理解しづらい解説が多い教科書もあるので、山岡の地理B教室を使って理解を進めていくこともおすすめですう。これを毎日続けることで、知識が一つひとつつながり、定期テストの地理問題で問われる因果関係を理解できるようになります。
- また、地理の定期テストの学習を進める上で地図帳は必ず毎日使いましょう。地理の定期テストでは地名や国名をただ覚えるのではなく、その位置をイメージできていることが大切です。指で位置を確認しながら、気候や産業などの特徴を関連付けて覚えると、記憶が深く定着します。資料問題に対応できるように、分布図や統計表を読む練習も少しずつ始めましょう。地理は図や表を理解できるかどうかが得点のカギを握ります。この1週間で、テスト範囲の7割は説明できるように仕上げることを目標にしてください。
- 2週目の前半は、地理の定期テストで得点を伸ばすための演習期間です。ここからは理解した内容を使って解く練習を重ね、アウトプット中心の勉強法に切り替えましょう。授業プリントやワーク、過去の定期テスト問題を使って演習を行うことで、出題の傾向をつかむことができます。先生が授業中に「ここは大事」と言っていた部分は最優先で復習してください。
- 資料問題の演習も必須です。地理の定期テストでは、雨温図、統計グラフ、地形図などを使った問題が頻出です。たとえば、雨温図を見て気候帯を特定する、統計グラフを読んで産業構造を分析する、地形図を見て地形の特徴を答えるなど、さまざまな形式で出題されます。こうした資料問題は暗記では対応できないため、毎日15分程度の演習時間を取って慣れておきましょう。
- さらに、地図帳を教科書と照らし合わせながら使うことが重要です。単純な暗記ではなく、国や地域の関係を理解することが、定期テストの地理勉強法で特に大切な部分です。例えば、工業が発達している国はどんな資源を持っているのか、その国の気候はどんな特徴があるのか、といったように知識を線で結ぶ練習をしてください。加えて、自分で一問一答を作るのも効果的です。自作問題を作ることで、理解の浅い部分を洗い出せます。友達と問題を出し合えば、楽しみながら記憶を定着させられるでしょう。
- この時期は、弱点補強と総仕上げに集中します。新しいことを覚えるよりも、これまで勉強してきた内容を整理して、確実に得点できる状態に仕上げることが大切です。間違えた問題をまとめたノートを見直し、なぜ間違えたのかを分析しましょう。理解不足なのか、ケアレスミスなのかを明確にし、再度教科書で確認することで弱点が消えていきます。
- 地理の定期テストでは資料問題の得点配分も高いので、統計や雨温図の確認を欠かさないようにしましょう。短時間でもいいので、毎日繰り返し見ることで記憶が安定します。この時期には、60分程度の模擬テスト形式で全範囲を一気に復習するのも効果的です。時間を計りながら全体を通しで解くことで、本番での時間配分の感覚をつかむことができます。
- 地理の定期テスト前日は、詰め込みではなく整理が中心です。一夜漬けで暗記しようとしても、地理の定期テストでは思考力を問う問題に対応できません。むしろ、眠気や焦りで集中力を欠き、ミスを増やしてしまうことが多いです。だからこそ、前日は自分の理解を整理し、全体の流れを確認する時間に使いましょう。
- 気候から産業、産業から貿易、貿易から文化というように、知識を物語のようにつなげて説明できるようにしておくと、問題を見た瞬間に流れが頭に浮かびます。最後に地図帳を開き、重要な国や都市、地域の特徴を軽く確認しておくと安心です。位置や関係性をイメージできれば、テスト中の思考力問題にも落ち着いて対応できます。十分な睡眠を取り、万全の状態で定期テストに臨みましょう。
定期テストの地理で高得点を狙うための勉強法
地理の定期テストで高得点を取るために効果的な勉強法を紹介していきます。
演習と解説の往復を繰り返す勉強法
定期テストの地理を勉強を進めていく上で知識を定着させるには、アウトプットが欠かせません。
学校のワークや授業プリントを解いたあと、間違えた問題はすぐに山岡の地理B教室で該当箇所を読み直し、なぜ間違えたのかを確認します。
この共通テスト対策におすすめの勉強法である解いて山岡の地理B教室で確認して理解してまた再度解いてみるの流れを繰り返すことで、知識が点ではなく線としてつながり、応用力がつきます。
さらに、雨温図や統計グラフなどの資料問題を毎日少しずつ解くと、思考力が鍛えられ、どんな出題にも対応できるようになります。
理解重視で読む勉強
地理の定期テストで高得点を取るために一番効果があったのは、暗記ではなく「なぜそうなるのか」を考えながら勉強する方法です。山岡の地理B教室は、地理の背景や理由を筋道立てて説明してくれるので、読んでいくだけで理解が深まります。
読むときは、教科書とノートを横に置き、「中東に石油が多い理由」「ヨーロッパに都市が集中する理由」などを自分の言葉で言えるか確認します。理解して説明できる状態を作ることで、思考問題にも対応できるようになります。
地図帳を使った位置と因果の整理
定期テストの地理の勉強法では、地図帳を使った学習がとても効果的でした。地名や国名を丸暗記するのではなく、位置を指で確認しながら「この地域はどんな気候で、どんな産業が発達しているのか」と関連付けて覚えると、記憶が長く残ります。
地図帳を開くたびに、教科書や講義本で学んだ内容を実際の場所と結びつける習慣をつけることで、テスト中も自然にイメージが浮かび、資料問題にも強くなりました。
日頃から「なんで?」を無くそう!
日頃の授業の中で自然と疑問は出てくると思います。「石油産出国で中東が多いのはなんで?」「なんで時差がうまれるの?」など、ふとした時に気になる疑問があると思います。
その疑問をその日のうちに解決できればより知識は定着し定期テスト前になっても、因果関係を理解できているのですぐに思い出せると思います。
テスト勉強は2週間前に始めよう!
テスト対策に必要なのは、何よりもテスト勉強の時間を確保すること。
一番いいのは、2週間前から始めるのが効果的です。テスト対策としてやるべきことを考えると少なくとも2週間は必要です。
実際に中間テスト、期末テストで確実に高得点をとる成績のいい人の多くは、テスト勉強に2週間かけています。。
しかし、部活動が、活動停止になるのは1週間前や、なかには3日だけという部活もあります。そういう人はテスト勉強と部活動の期間が重なってしまうことになりますが、それを不利だと考えるのも、困難だからこそ絶対やってやるぞ、と考えるのでは結果も変わってきます。
早めに知識習得をして問題演習で点数を伸ばすこと
地理には思わず見逃してしまうような落とし穴が存在します。
それは、他の社会科目と比べ地理という科目は暗記量がすくないことです。
なぜ暗記量が少ないかというと「常識」でわかってしまう範囲が多いためです。たとえば、人口が最も多い国が中国で二番目に多い国がインドであることは誰でも知っているし、石油の生産がサウジアラビアなどの中東で多いことも誰でも知っているのです。
その代わり、地理では思考力が問われます。
思考力が問われるということは、暗記をする量が減るという反面その場その場での対応力、元から持っている知識の量、柔軟な考え方が試されるというわけです。
そのため一夜漬けをした状態でテストに臨み、眠気で頭が回らず思考力を試されている問題が解けないなんてこともあるかもしれません。それは一番避けたいことです。
▽地理の勉強法をもっと詳しく知りたいという人はこちら
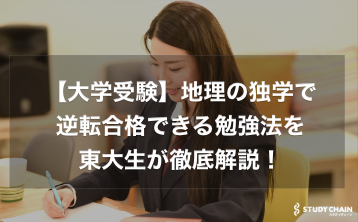 【大学受験】地理の超効率的な勉強法を徹底解説!
【大学受験】地理の超効率的な勉強法を徹底解説! 地理の定期テストの際によくある質問と解決策
逆転合格特化塾でも地理の定期テストについての質問を多くいただきます。
その中でも特に多かった地理の定期テストについての質問を紹介し、その解決策についても詳しく説明していきます!
Q1 地理の予習・復習はどれくらいやればいいの?
多くの地理選択の高校生がこの質問を抱きながら過ごしているでしょう。
結果を先に言うと全く必要ありません。というのも、地理は用語を暗記することに関してはとても少なく、しかしその用語を他の用語や背景知識を理解していないと全くテストには使えないのです。
ですので、授業中やその日中に理解していれば予習や復習は一切必要ありません。
逆を言うと、地理はいくら用語を暗記したからと言って点数が伸びるわけではないのでその点は定期テストや受験に役立てていただきたいです。
Q2 地理の定期テスト前日はどのように過ごせばいいですか?
この質問も非常に多くいただいております。地理の定期テストの前日に暗記事項を詰め込むのか、それとも流れだけ確認して終えるか迷いますよね。
地理の定期テストの多くは穴埋め形式を採用しているので、地理の定期テストだけを意識するのなら前日に地理の用語を詰めるのも悪くないと思います。
しかし、せっかく地理を選択した皆さんには是非受験につなげてほしいと思っているので地理の用語を暗記するのではなく、穴埋め問題の前後で予測できる程度になってほしいと思います。
ですので地理の定期テストの前日は地理の用語を暗記をするのではなく、大まかな流れと背景知識を確認するのが最適です。
Q3 地理の定期テストは一夜漬けで高得点は狙えますか?
厳しいことを言いますが勉強法において最も効率が低いのが“一夜漬け”なのです。
定期テストの一夜漬けのデメリットは下記のようなことが挙げられます
・全部が暗記できるわけではない
・他の教科の定期テストに悪影響が出る
・一日で忘れてしまう など様々
このように一夜漬けをすることはデメリットのほうが大きく、絶対にやめてほしい勉強法です。
しかし地理の定期テストだけについて考えれば、前述したように穴埋め形式の問題は用語さえ知っていれば簡単に埋めることができてしまうので高得点を狙うことは可能なのです。
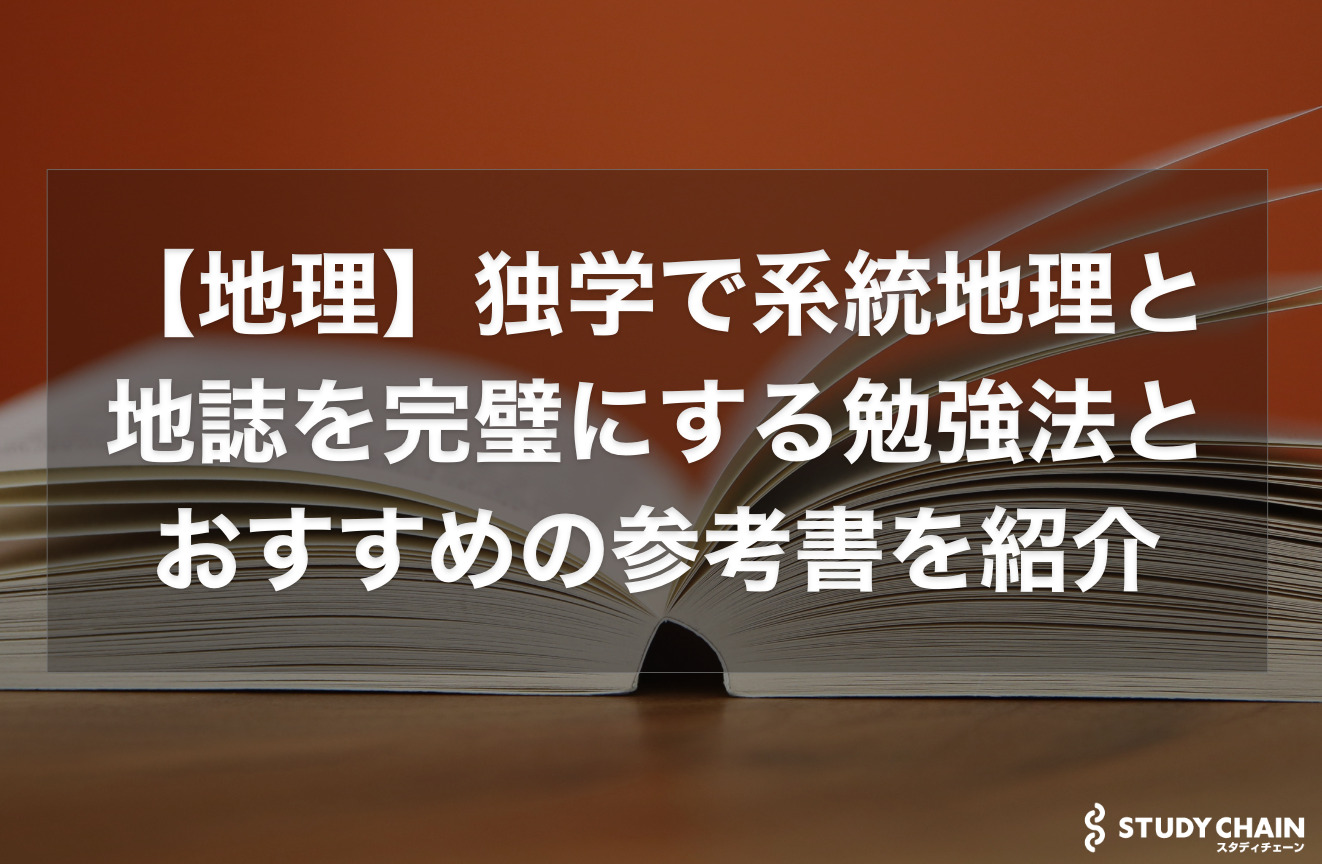 【地理】独学で系統地理と地誌の勉強法とおすすめの参考書を紹介!
【地理】独学で系統地理と地誌の勉強法とおすすめの参考書を紹介! 地理の定期テストで高得点を取るための勉強法4選
地理の定期テストで高得点を取るための勉強法を4つ紹介します。
①試験に直結する情報をあらゆる角度から集める
まずは定期テストの試験に直結する情報を徹底的に集めましょう!
試験についてなにも知らなければ、なにをどれくらい勉強すればいいか、どこが出題されるのかなど具体的な部分がわかりませんよね。
そこで試験に関する情報を集めると、自分がやるべきことが具体的になります。
「ここテストで出す」と先生が言っている場所があるならそこは絶対にやるべきですし、ここは出題しないと言っていたならそこまで重点的にやる必要はないでしょう。
②教科書やプリントの「資料」を忘れないように!
教科書やプリントには、どのページにも写真・分布図・統計グラフ・地形図などがたくさん載っています。これらを資料といいますが、実は「資料」に重要事項が凝縮されているのです。
略図から地形の名称を問われたり、雨温図を見て気候区分を問われたりする問題は決して少なくありません。
各地域の特徴や様子、貿易や経済の状況などを資料から読み取れるよう、日頃から資料に慣れておきましょう。
③地理の定期テスト対策で絶対やってはいけないのは地図帳の存在を軽視すること
また、地理では地図帳も重要な資料です。教科書に出てくる地名は必ず地図上で位置を確認したり、統計の上位3か国の位置を押さえたりと、活用法はいくらでもあります。
定期テスト対策としては、教科書・地図帳・授業ノートのすべてを照らし合わせながら、学習内容を丹念にチェックしていくのが効果的です。
[s_ad]④テスト本番の時間配分では思考力が試される問題があることを意識する
上記で述べたように、地理の定期考査では思考力を試してくる問題が出る場合があります。
その形の問題が出題されるかどうかは、テストを作成する先生が前もって教えてくれたり、過去のその先生の作成したテストをみるとわかったりします。
もし、思考力を試される問題が出されているのであれば当然のことながらその問題を念頭に置きながらテストの時間配分を整えるべきです。問題によりけりですが、最低でも10~15分は残しておくと時間に対する焦りがなくスムーズに問題を解くことができるかと思います。
地理の定期テストの勉強を受験勉強につなげよう
どうせ定期テストで高得点を狙うなら大学受験の勉強と並行して行いたいですよね!受験勉強に直結させるために意識して欲しい3点をまとめて紹介します。これを意識すれば立派な受験生です!
暗記ではなく理解を大事にしよう
ついつい定期テストの勉強は暗記がメインになってしまい理解が疎かになってしまいがちですよね。暗記がメインになってしまうと、テストの一時間後には忘れてしまいます。
ですので暗記をメインにしてはどうでしょうか?上で述べたように、その日のうち疑問は解決ししっかりとした知識を定着させましょう。
参考書を併用して点数アップ!
受験の時には地理では必須アイテムとなる参考書を併用してみてはいかがでしょうか。
参考書を用いると授業の中では説明されないような深い内容であったり、より分かりやすく解説がされているので授業の予習、復習にも役立つし受験で使える知識も身につきます。詳しい使い方に関しては下の記事やスタディチェーンの地理の記事を参考にしてください!
自分だけの問題をつくる
東進ブックスの地理の一問一答の最後のページには自ら作成した問題を書き込んスペースがあります。知識が増えていくと、自然と自分の苦手な分野も出てくると思います。
そこを補強できれば定期テストだけでなく受験勉強も自信をもって取り組めるでしょう。作った問題を友達同士で交換すればゲーム感覚で楽しく覚えられるでしょう。
地理のおすすめの参考書の使い方
高校生活の中で部活と勉強の両立は誰もが一度は突き当たる壁です。部活などで忙しく定期テストまで時間がない人、受験に向けて定期テストも頑張りたい人などレベル別に詳しく解説!
部活で時間がない人の参考書の使い方
定期テストまで残り3日しかない!という人でも効率よく点数を上げる方法はあります。
大雑把に言うと学校の一回の授業で習う内容は地理の参考書を用いて自学自習をすると20分程度で終わってしまいます。
地理の講義形式の参考書だと本当の授業のような書かれ方をしているので最初から理解できることができるし、他の人に追いつくことも十分可能です。
学校に出発する前の朝の20分を地理の勉強に費やすだけで簡単に部活と両立できてしまいます。
受験勉強に向けて定期テストを頑張りたい人の参考書の使い方
受験を見越して定期テストを頑張りたい人は定期テストを受験本番と捉えて勉強することをお勧めします。定期テストは狭い範囲から満遍なく出題されるので毎回を完璧にしていけば自然と全範囲が完璧になります
。狭い範囲で万点近く狙うにはその範囲の参考書に満遍なく目を通し人に説明できるぐらい何度もアウトプットを行うことが重要になります。講義形式の参考書を自分が説明するように読み進めるとまた違った視点で理解が深まると思います。
地理に大学受験についてや地理の参考書、勉強法については下の記事で徹底解説しています。
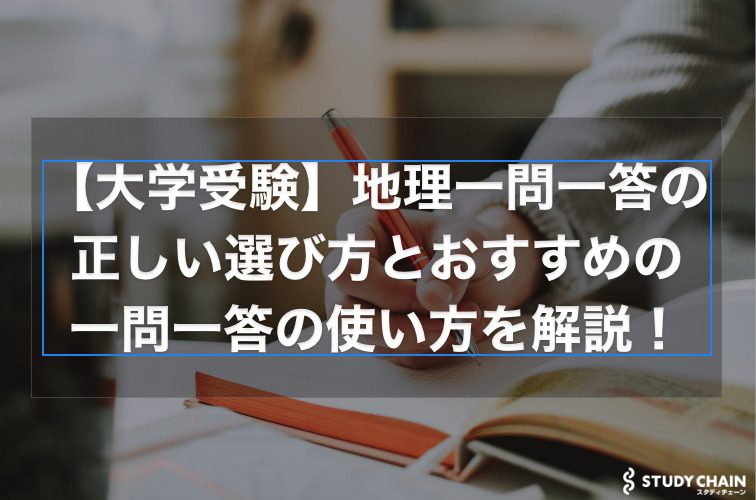 【大学受験】地理のおすすめの一問一答を解説!使い方も徹底解説
【大学受験】地理のおすすめの一問一答を解説!使い方も徹底解説 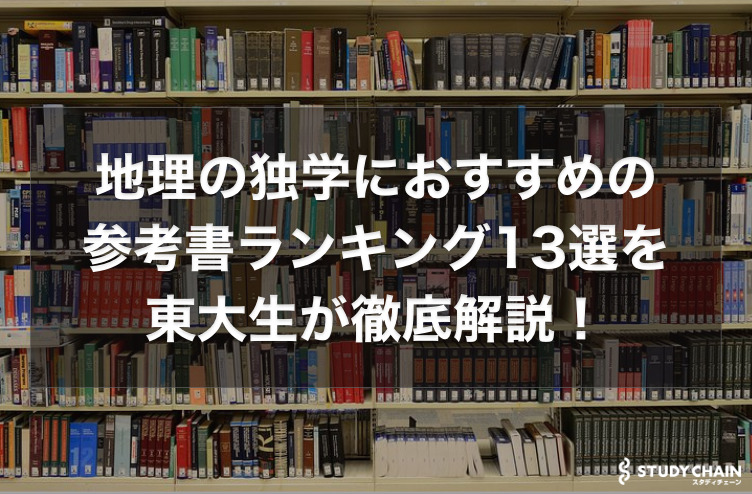 地理のおすすめの参考書ランキング13選を東大生が徹底解説!【大学受験】
地理のおすすめの参考書ランキング13選を東大生が徹底解説!【大学受験】 ▽定期テスト対策向けの勉強法が知りたい方はこちらもぜひ参考にしてみてください。