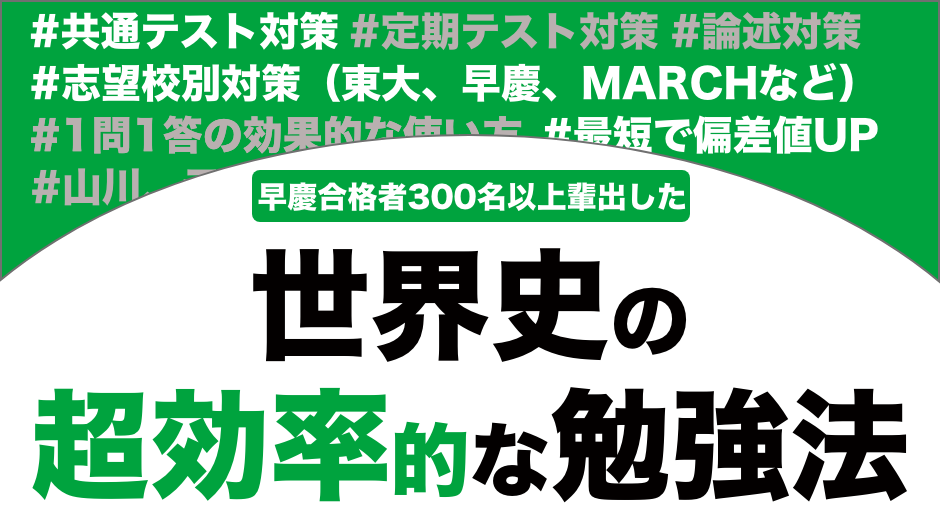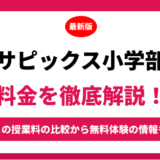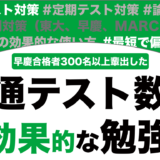本サイトの表記には、一部プロモーションを含みます
大学受験の世界史対策におすすめの効率的な勉強法を志望校別の対策から共通テスト対策や定期テスト対策など目的別の対策までそれぞれ具体的に解説します。
また、実際に自分がやってみてよかった世界史の勉強法やこれまで個別指導で早慶に300名以上合格させてきた中で使ってよかった世界史の参考書ややってよかった論述対策や1問1答や教科書の使い方も含めてそれぞれ解説していきたいと思います。
短期間で世界史の成績を伸ばせる勉強法を具体的に紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

【この記事の監修者:逆転合格特化塾塾長「竹本明弘」
これまで早慶に現役生および浪人生を含めて合計で300人以上合格者を輩出してきました。その中で世界史選択の合格者もたくさんおり、実際に指導する中でゼロからでも偏差値70まで到達した世界史の勉強法や使ってよかった参考書およびおすすめの世界史の勉強の順番を解説したいと思います。
この記事でわかること
- ゼロからでも共通テストの世界史で9割取れる勉強法
- 実際にどういう勉強のスケジュールをこなせば世界史の偏差値が70になるのか
いきなり結論!最短で伸びる期間別の大学受験の世界史の勉強法
世界史の大学受験対策のおすすめの勉強法を受験本番まで6ヶ月,8ヶ月,1年のそれぞれに分けて期間別に解説します。
6ヶ月で大学受験の世界史の偏差値を40から70にする勉強法
世界史の偏差値を伸ばすためには「年号」「用語」を他の人よりも効率的に覚えることがまず大切です。
なぜなら、年号と用語をしっかりと覚えることでタテの流れの理解と暗記が格段とやりやすくなります。

上記の3点セット「講義本(教科書」「一問一答」「年代サーキットトレーニング」を最も効率的な勉強法でできるかどうかが世界史の成績UPの鍵です。
その次に必ず知っておくべきこととして世界史は偏差値40から60の壁と60から70の壁があります。
大学受験の世界史の偏差値40から60については、重要となってくるのは「年号・用語(人物、事件など)」を通してタテの流れをしっかりと把握して暗記できているかどうかで、60から70の壁についてはさらにヨコの流れや細かい用語や文化史や地図まで覚えきれているかどうかが重要になってきます。
早慶以下の大学を志望していて、偏差値70まで伸ばす必要がないという方は最後の1,2ヶ月の部分を省略していただくと目標偏差値に届く形になります。
結論として、大学受験の世界史の偏差値を6ヶ月で40から70にする勉強法としては以下のようになります。(目安:1日2時間の勉強時間)
→特に年号と用語を重視しながら通史を1通り理解する(1日40分:講義本→30分:時代と流れで覚える→30分:1問1答→最後復習)
- まず世界史については最初は可能な限りシンプルに1周目を進めていきましょう。定期テストなどで世界史は得意もしくは苦手意識がないという人は最初から世界史探究(KADOKAWA出版)もしくは山川を使って、通史を進めるやり方がおすすめです。ただし、定期テストでも赤点ばっかりや学校の授業を全く聞いていなかった方は「マンガで世界史が面白いほどわかる本」から進めましょう。一通り読み終わったら世界史探究にうつるのがおすすめです。
- 1日40分世界史探究を読んで、その範囲を「時代と流れで覚える」を解いて、覚えて、最後に全体的な用語を星2以上のみ一問一答で覚えていきましょう。星0はまず覚えなくてよく、星1はまだ覚えなくて大丈夫です。
- 個人差はありますが、世界史探究の1周が終わるまでに毎日2時間時間が取れれば2ヶ月程度で終わります。
→年号の強化を軸にタテの流れを覚えることをメインに通史を進める。(1日40分:講義本→30分:サーキットトレーニング→30分:1問1答→最後復習)
- 「超効率!世界史年代サーキットトレーニング」を使って、年号をメインにタテの時代の流れをしっかりと覚えていきましょう。1周目に1問1答や時代と流れで覚えるで覚えた用語が「なぜ起きたのか」をより深掘りながら、タテの流れをどんどん覚えていくイメージです。
- 2周目は1周目よりも早いペースで通史を終わらせられると思いますが、ここで年号を覚えているかどうかでかなり大きく変わってくるので、1つ1つ地道ですが覚えていきましょう。
- サーキットトレーニングが終わったら、世界史の基礎問題精講を解きつつ、自分が暗記できていない分野をどんどん洗い出していきましょう。
→アウトプット量を少しずつ増やしつつもより細かい知識の習得+苦手の穴を埋める暗記(1日30分:講義本→45分:基礎問題精講→30分:1問1答→最後復習※用語集も活用)
- ここからは細かい用語を覚えつつも覚えてきた年号を活かして地図も覚えて、ヨコの流れを中心に覚えていきましょう。そのためには、年表や地図を見るのももちろん大事ですが、用語集や資料集を活用して、問題集で間違えた分野を復習するなどして、その時代その時代ごとに何がどういう流れで起きたのかを把握することが重要です。もし覚え辛いという方には「世界史一問一答地図」もおすすめですが、おすすめの勉強法としては、白紙に各時代の地図を書いてみるというのは確実に覚えられるので非常におすすめです。
- この時点で世界史の1問1答完全版(東進)は星2までをしっかりと覚えきることを目標にしていきたいので、まだ全然覚えれていないという人は少し基礎問題精講にかける時間を減らして、1問1答に時間を割く形で、講義本に45分、1問1答に45分かけて、年号のサーキットトレーニングの復習もしながらインプット中心で構いません。世界史は焦っても特に得をする科目ではないので、インプットばかりになっていてもそこまで焦る必要はないです。
→共通テスト対策をしつつ、徹底的な苦手克服に向けた分析と学習の繰り返し(1日30分:講義本→45分:共通テスト問題集→45分:1問1答→最後復習※用語集も活用)
- 「きめる!共通テスト世界史」や「共通テストの過去問集」を活用しながら、何も見ずにこれまで習得したような用語や年号や流れの知識を活用して解きましょう。そして、成績の分析表を作って、時代ごとにどこで自分は間違えやすいのか?いつの時代のインド史なのか?それともある時代の中国史なのか?などを分析して、その分野をこれまで使ってきた講義本や参考書を使って確認するという作業を繰り返しましょう。
- 目安としては10年〜15年分共通テストおよびセンター試験の過去問を活用して対策を進めることをおすすめします。実際に解く時間はアウトプットの問題としてはやはり共通テストやセンター試験はスラスラ解きやすいので、自分が覚えていたと思ったいた分野が実はできていなかったというのを見つけるのに適してます。
→特に現代史の細かいタテの流れや頻出テーマの地図、タテの流れ、横の流れの把握(1日30分:講義本→45分:攻略世界史→45分:1問1答→最後復習※用語集も活用)
- 早慶以上の難関大志望の受験生は特に最後攻略世界史を使って、意外と把握していないような特に近現代史における細かいなぜこの法律ができたのかやなぜこの事件が起きたのかなどのタテの流れや用語を把握していきましょう。Z会の出している攻略世界史の各国史と近・現代史をやるのがおすすめです。ただし、まだ時間に余裕があるという方はHISTORIAという参考書にも難問と呼ばれるような問題とわかりやすい解説があるので取り組むのもおすすめです。そしてその後志望する大学の過去問を解きつつ、間違えた問題などは講義本や資料集や用語集でしっかりと確認するということを繰り返していきましょう。世界史の過去問演習は何年分やったかも大事ですが、どれだけ復習を念入りにやったかの方が非常に重要です。
- それ以下の大学を志望する受験生は使う参考書は増やさずにこれまでの復習をより重点的に行うもしくは過去問演習に入っていきましょう。


8ヶ月で大学受験の世界史の偏差値を40から70にする勉強法
ただ暗記するだけでは大学受験の世界史の偏差値は伸びません。正しい順序で「通史→タテの流れ→ヨコの流れ→演習」と積み上げていくことで、偏差値40から70まで一気に伸ばすことができます。
私、竹本がこれまで早慶に300名以上を合格させてきた中で指導する上で「やってよかった」と実感しているのが、シンプルに世界史の通史の1周目を進める→縦の流れを徹底→横の流れを定着→過去問で総仕上げという勉強の流れです。
▽世界史のおすすめの参考書ルート
.jpg)
ここでは 8ヶ月の期間で1日2時間の勉強で世界史の偏差値を40から70にするスケジュール を紹介します。使う参考書は「山川世界史探究」「時代と流れで覚える!」「東進一問一答」「世界史年代サーキットトレーニング」「基礎問題精講」「きめる!共通テスト世界史」「攻略世界史」「HISTORIA」「志望校の過去問集」です。
結論として、世界史の偏差値を8ヶ月で40から70にする勉強法としては以下のようになります。(目安:1日2時間の勉強時間)
テーマ:通史をシンプルに1周し、基礎用語を定着
勉強内容:(1日40分:山川世界史探究 → 30分:時代と流れで覚える!世界史用語 → 30分:東進一問一答完全版 → 最後復習)
まずは世界史の通史全体の流れをざっくりと掴むことを最優先にしましょう。定期テストである程度世界史を理解していた人は、最初から「世界史探究」を使って問題ありません。一方で学校の授業をほとんど聞いていなかった人は「マンガで世界史が面白いほどわかる本」から始めて、読み終わったら世界史探究(KADOKAWA)に移行するのがおすすめです。ここでは星2以上の用語を中心に一問一答で暗記を進めましょう。
テーマ:年号とタテの流れの強化
勉強内容:(1日40分:山川世界史探究 → 30分:世界史年代サーキットトレーニング → 30分:東進一問一答完全版 → 最後復習)
ここからはタテの流れを重視します。「なぜその出来事が起こったのか」を意識して、1周目よりも速いペースで通史を回しましょう。サーキットトレーニングで年号を叩き込みつつ、苦手分野は「基礎問題精講」を使ってアウトプットして見つけて、復習のタイミングで講義本を使って確実に補強するのが効果的です。
テーマ:ヨコの流れと知識の精緻化
勉強内容:(1日30分:講義本 → 45分:基礎問題精講 → 30分:一問一答 → 最後復習+用語集)
この段階では地図や資料集を使いながら、ヨコの流れも定着させていきましょう。自分で白紙に地図を書き、国名や出来事を埋める勉強法は特におすすめです。星2の用語を完璧に仕上げることを意識してください。
テーマ:共通テストレベルの演習開始
勉強内容:(1日30分:講義本 → 45分:きめる!共通テスト世界史 or 共通テスト過去問集 → 45分:一問一答 → 最後復習)
共通テスト過去問を使い、時代ごとの弱点を徹底的に洗い出します。間違えた分野は必ず「探究」「用語集」「資料集」に戻って補強し、弱点分析シートを作ると効果的な世界史の勉強法です。
テーマ:志望校過去問と近現代史の仕上げ
勉強内容:(45分:Z会攻略世界史(近現代史・各国史)or HISTORIA → 45分:志望校の過去問 → 30分:用語集・年表復習)
最後は過去問演習に徹底的に取り組みます。特に近現代史は盲点になりやすいので、「攻略世界史」でタテの流れを深く理解しましょう。復習を最優先にして、曖昧な知識を確実に得点源に変えていくことが合格への決め手となります。
1年で大学受験の世界史の偏差値を40から70にする勉強法
「平日は部活や学校が忙しくて、90分くらいしか勉強時間が取れない…」や「まだ受験本番まで残り時間があるけど、他の苦手科目に時間をかけないといけない..」そんな人でも、正しいやり方で世界史の知識を積み上げれば世界史の偏差値を70まで伸ばすことは可能です。
私、竹本がこれまで早慶に300名以上を合格させてきた中で、世界史の勉強法を指導していく中で一番効果を実感したのは、平日でインプット&アウトプットを積み重ね、土日で重点的に復習を行う勉強法です。

参考書は「山川世界史探究」「時代と流れで覚える!」「東進一問一答」「世界史年代サーキットトレーニング」「基礎問題精講」「きめる!共通テスト世界史」「攻略世界史」「HISTORIA」「志望校の過去問集」に絞っています。
結論として、世界史の偏差値を1年で40から70にする勉強法としては以下のようになります。(平日90分・土日2時間)
テーマ:通史の基礎固め
勉強内容(平日90分:40分探究 → 25分:時代と流れで覚える!世界史用語 → 25分:一問一答/土日2時間:探究+一問一答+復習)
まずは通史をゆっくり理解し、世界史一問一答における星2以上の基本用語を固めます。平日は少しずつ、土日はまとめて時間を取り、必ず毎週復習時間を確保してください。
テーマ:タテの流れと年号暗記の徹底
勉強内容(平日90分:30分探究 → 30分サーキットトレーニング → 30分一問一答/土日2時間:探究+基礎問題精講+復習)
「なぜ起きたか」を意識しながら年号と縦軸の流れを定着させます。土日には基礎問題精講を解き、インプットとアウトプットをバランス良く進めましょう。
テーマ:ヨコの流れと地図・資料を活用
勉強内容(平日90分:30分講義本 → 30分基礎問題精講 → 30分一問一答/土日2時間:講義本+一問一答+地図復習)
地図や年表を見ながら、地域ごとのつながりを整理します。白紙地図に書き込む学習は平日はできなくても、土日にまとめて行うのが効果的です。
テーマ:共通テストレベルでの総合演習
勉強内容(平日90分:30分講義本 → 30分共通テスト問題集 → 30分一問一答/土日2時間:共通テスト過去問+復習)
10〜15年分の共通テスト・センター過去問を解いて、弱点を徹底的に分析。土日にまとめて復習し、平日は弱点克服に時間を当てましょう。
テーマ:過去問演習と近現代史の最終仕上げ
勉強内容(平日90分:30分攻略世界史(近現代史・各国史) → 30分過去問 → 30分復習/土日2時間:HISTORIA or 志望校過去問+復習)
最後の1ヶ月は過去問中心で実戦力を養成します。特に近現代史は細かい出来事の因果関係を問われるので「攻略世界史」で徹底的に潰しましょう。復習を重ね、曖昧な部分を残さず入試に挑むことが重要です。
分野別に世界史の大学受験のおすすめの勉強法
大学受験の世界史の勉強法をそれぞれ「世界史の一問一答の使い方」「教科書や講義本を使った世界史の勉強法」など参考書ごとの使い方から論述対策や文化史対策や試験当日の対策まで解説します。
世界史の1問1答を使った大学受験の勉強法

世界史の一問一答を使う上でおすすめの使い方としては、必ず講義本と年号の世界史のサーキットトレーニングもしくは元祖世界史の年代暗記法の2冊と併用して使う使い方です。
その理由としては、世界史の一問一答の単独で使ってもタテの流れやヨコの流れの学習に全く繋がらなくなってしまうからです。
ただシンプルに、合わせて年号を覚えるだけでもタテの流れにつながりやすくなり、写真や地図や講義本やそこにある年表と合わせて使うことでヨコの流れの理解や暗記にもつながります。
だからこそ、たとえば2時間世界史の勉強時間を取れるのであれば最初の1時間はその日に学習する範囲の講義本を読み込むことに使って、その範囲の年号をしっかりとサーキットトレーニングを使って学習しましょう。
世界史年号サーキットトレーニングの図解は下記のようになります。

これまで東大京大や早慶をはじめ世界史選択の合格者を輩出してきましたが、その学習の中で気づいたこととしては、上記のような年号が覚えられる参考書と合わせて一問一答を活用すると一気に偏差値の上がりやすくなります。
▽おすすめの世界史の一問一答が知りたい方はこちら
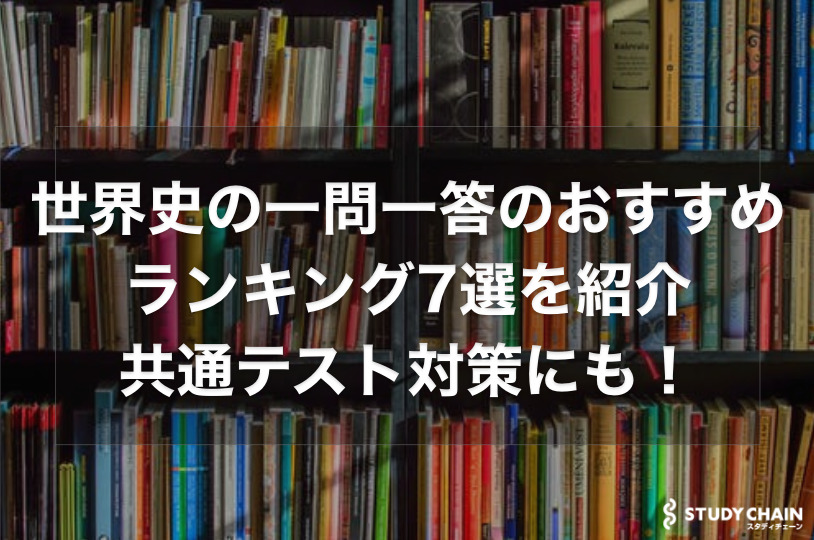 世界史の一問一答のおすすめランキング7選を解説!定期テスト対策にも!【大学受験】
世界史の一問一答のおすすめランキング7選を解説!定期テスト対策にも!【大学受験】 世界史の教科書や講義本を使った大学受験の勉強法
世界史の山川の参考書や実況中継や世界史探究など下記の3つがありますが、短期間で世界史の成績を伸ばしたい人におすすめの教科書および講義本としては「山川の世界史探究」もしくは「世界史探究※KADOKAWA出版」です。

時間がある人でかつ実況中継を使ってみて、これしか読みやすい参考書がないと感じた人にのみ実況中継をおすすめします。
その理由としては、まず世界史の教科書や講義本のおすすめの勉強法としては、ただ読むだけで良いのではなく、1問1答や用語集や年号の参考書で得た情報をどんどん教科書や講義本に書き込んでいく方が頭に入りやすく実際合格した受験生も非常に多いです。
特に同じ時代のヨコの流れを理解する上では、年号、事件、人物、地図などをまとめて覚えないといけないので、読んで覚えるというよりは書いたりアウトプットしながら覚えるのがヨコの流れを理解する上で一番最短であり効率的です。
その上で世界史の実況中継は非常にページ数が多く、書き込んでもなかなか復習する際に確認するのに時間がかかるという難点があるため、何周もできる時間があるという方のみ使うことをおすすめします。
世界史の論述対策におすすめの勉強法
世界史の論述対策としては、まずはこれまで説明したような年号と一問一答と講義本もしくは教科書をしっかりとインプットした上で論述対策の参考書に取り組むことが一番大切です。
これまで実際に世界史選択で大学受験に挑む受験生を指導してきた中で論述が一番できない原因は明らかな「流れ」を暗記できていないことです。
たとえば近現代の用語暗記はそれぞれ一問一答形式で覚えていたとしても、「なぜその事件が起きたのか?」や「なぜその法律が制定されたのか?」などまでタテの流れを年号などと合わせて理解できていないと記述には対応できません。
だからこそ、下記のようにインプットとアウトプットを両立しながら、年号、用語、地図を同時並行して覚えていくことが最も世界史の論述対策においては一番効果的な勉強法です。

インプットがしっかりとできた受験生は「攻略世界史 各国史」「攻略世界史 近・現代史」「世界史 論述トレーニング」の3つの世界史の論述対策の参考書をこなして、間違えたら、さらにその範囲を講義本や用語集を通して確認するということを繰り返し行うのがおすすめの勉強法になります。
▽世界史の論述対策の勉強法をもっと詳しく知りたいという方はこちら
 世界史の論述の勉強法と書き方とおすすめの参考書を解説【大学受験】
世界史の論述の勉強法と書き方とおすすめの参考書を解説【大学受験】 世界史の文化史対策のおすすめの勉強法
世界史の文化史対策には専用の参考書を使うよりも「作品・内容・時代・地域をセットで理解すること」と「文化史対策はアウトプットの回数も重要」という2つの大事な要点を押さえた勉強法の実践が非常に重要です。
まず世界史の文化史の対策をする上で、著者や作品名だけでなく、「どんな内容か・どの時代か・どの地域か」を一緒に覚えるのがポイントです。
例えば「グーテンベルクが活版印刷術を発明したのは15世紀ドイツであり、宗教改革やルネサンスの拡大に大きな影響を与えた」と押さえておけば、単なる名前暗記では解けない問題にも対応できます。
美術や建築は資料集を活用して写真・図版から名称を答えられるようにしておくとより効果的な世界史の文化史対策になります。
世界史の文化史の問題は「時代・地域・作品の特徴」をヒントに解かせる形式が多いので、アウトプットの練習と世界史図録などの資料集を組み合わせる勉強法が非常に効果的です。

ただし、世界史の文化史の注意点としては、文化史専用の問題集をやり切っても文化史は完璧にはなりません。必ず上記の世界史図録などの資料集にある文化史に関する写真や用語を確実に覚えきることをおすすめします。
世界史の用語集を使ったおすすめの勉強法
世界史の用語集ですが、用語集を使って世界史を学習するのは早慶以上の大学を志望する大学受験生のみに推奨します。
なぜかというと、用語集を使って世界史を勉強するよりもまずしっかりと一問一答の星2の部分および星3の部分や年号を覚えて、世界史の基礎を固めることの方が非常に大切です。
世界史の用語集のメリットは、それぞれの用語に関する解説が細かいことと用語集でしか解説されていないような事項がたくさんあるという点です。一方で世界史の用語集のデメリットは細かすぎるので、時間がかかりすぎる可能性があるということです。
だからこそ、早慶以上を志望する受験生には一問一答の星2以上の部分と年号を8割程度覚え切った後は世界史の用語集を活用して、暗記を進めるのがおすすめの勉強法です。
早慶以上を志望する大学受験生にこそ山川など世界史の講義本1冊と一問一答1冊と用語集1冊と資料集の4点セットを通して、「年号」「タテの流れ」「ヨコの流れ」「地図」「文化史」の5つを暗記し続けるのが一番おすすめの勉強法です。
世界史の試験当日にやると効果的な勉強法
世界史の試験当日にやると効果的な勉強法としては「自分の苦手な分野を把握する分析シートを作成しておくこと」と「世界史の年表の活用」と「自分オリジナルの苦手部分まとめノートを作っておくこと」の3つです。
1つ目の、自分の苦手な分野は共通テストやセンター試験の世界史の過去問を解いたら、必ず時代✖️大陸ごとにどこが間違えたかを表にまとめていきましょう。縦軸に2022年や2024年などの年数をかいて、横軸に時代✖️大陸を書きましょう。
10年分の世界史の過去問をやってみると、わかりやすく自分がどこが苦手でどこが得意なのか判断することができるようになります。
そうすると試験当日は特にその自分が苦手な世界史の範囲を重点的に取り組むことができるようになり、試験当日や前日にみた部分が試験に出やすい可能性がどんどん高くなるかと思います。
また試験当日には世界史の年表をみるとわかりやすくタテの流れもヨコの流れも理解できるようになるというのと自分オリジナルでノートに苦手な単元の年表を作ってそれを試験当日に確認できると最も効果的な試験当日の世界史の勉強法ができるようになります。
共通テスト対策の世界史の超効果的な勉強法
共通テスト対策の世界史の勉強法としておすすめは、「共通テストおよびセンター試験の過去問を解いて分析シートを作成し、それをもとにインプット対策を徹底的にやり直す」という勉強法と「復習のやり方を共通テスト対策専用のものにする」という勉強法の2つです。
1つ目には、下記のような形で共通テストやセンター試験の過去問演習の記録として表を作りましょう。

そして、❌がたくさんある分野に一番世界史の勉強時間を割けるようにすることが世界史の偏差値UPのカギになります。
また、復習する際は特に世界史年表や年代のサーキットトレーニングで広く年号を確認したり、間違えた問題部分のみ復習するのではなく、タテの流れもヨコの流れも両方をまとめてインプットすることが非常に大切です。
特に1周目の共通テスト対策の過去問演習は表をつけながらや復習をしながらだと時間がかかりますが、そこを根気強くやり抜くのが世界史の共通テスト対策におけるカギです。
▽共通テスト対策の世界史の勉強法を詳しく知りたいという方はこちら
 世界史の共通テストの勉強法を徹底解説!【大学受験】
世界史の共通テストの勉強法を徹底解説!【大学受験】 世界史の勉強法の実践におすすめの参考書一覧

大学受験の世界史のおすすめの参考書として特に4つ実際に使ってみてよかった参考書および早慶合格者が特に使ってよかったという参考書を厳選してピックアップしたので紹介したいと思います。
世界史の勉強法の実践におすすめの参考書①世界史年代サーキットトレーニング

世界史年代サーキットトレーニングは実際に使ってみた時の使いやすさとしても実際に指導する際に使った時の生徒の評判としても非常におすすめできる世界史の参考書の1つです。
特に年代のシンプルに高速で覚えられる参考書になっているので、用語暗記の一問一答などと並行して取り組むとより効果が発揮される参考書になっています。
世界史の勉強を始めたばかりという人にも初めからでも使えるような参考書の構成になっているので、ぜひ早いかなと悩むことはなく世界史の大学受験の勉強をする全ての受験生におすすめの参考書です。
世界史の勉強法の実践におすすめの参考書②ビジュアル世界史問題集

ビジュアル世界史問題集は、地図問題が苦手な大学受験生やなかなか地図が覚えられないような大学受験生におすすめの世界史の参考書です。
白紙に地図をかけるかどうかが大事と世界史の勉強法でよく言われますが、大事なのはただ地図を書けることではなく、どういう経緯でどういうことが起きてその地図になっていったのかなど流れの把握が重要です。
地図はもちろん通史の勉強や資料集の学習を中心に行うことが重要ではありますが、さらなる補強としてビジュアル世界史問題集を活用するのは非常におすすめの世界史の勉強法です。
世界史の勉強法の実践におすすめの参考書③マンガで世界史が面白いほどわかる本

マンガで世界史が面白いほどわかる本は学校で世界史の授業を全く聞いていなかった高校生やまだこれから世界史の勉強を始めるが、やり方も含めて全てよくわからないという人がゼロから始める時におすすめの世界史の漫画形式の参考書です。
おすすめの理由としては、年表付きの漫画になっているので、大まかに世界史のタテの流れをそれぞれ把握することができる点です。
ぜひゼロから世界史に取り組むという高校生の方はこのマンガで世界史が面白いほどわかる本から始めて、次に山川の世界史探究や世界史探究(KADOKAWA)にうつっていくのがおすすめの参考書ルートです。
▽世界史をゼロから勉強するという高校生や受験生向けに世界史の漫画が知りたいならこちら
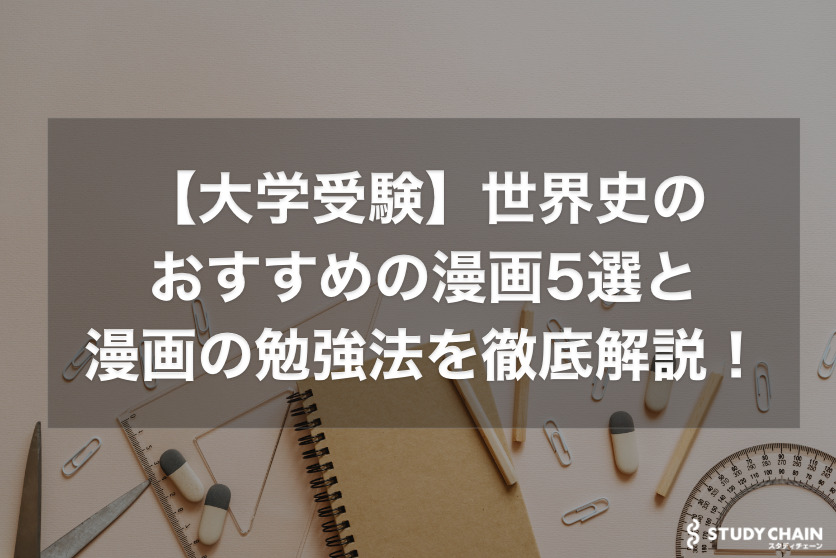 【大学受験】世界史のおすすめの漫画4選と漫画の勉強法を徹底解説!
【大学受験】世界史のおすすめの漫画4選と漫画の勉強法を徹底解説! 世界史の勉強法の実践におすすめの参考書④攻略世界史

共通テストもセンター試験の世界史の過去の点数を分析してみても、明らかに現代史が出た際に平均点が下がる傾向にあります。現代史は確かに他の年代と比較してみたときに、細かい部分が出題されるケースが非常に多いです。
だからこそ、細かいタテの流れの把握が特に求められる世界史の中でも難易度の高い年代が現代史です。
そこで大学受験生の中でも世界史の差がつく部分になる現代史の対策におすすめなのがこの「攻略世界史の近現代史」です。
これまで早慶合格者を300名輩出し、その中で3割程度世界史選択の受験生がいましたが、ほとんど全ての指導した生徒にこの「攻略世界史の近現代史」を解いてもらったので、自信を持っておすすめできる大学受験対策の世界史の参考書です。
▽もっと世界史の参考書が知りたいという方は下記の記事もぜひ参考してみてください。
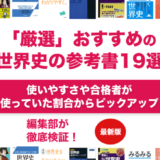 世界史のおすすめの参考書ランキング19選を東大生が徹底解説!【大学受験】
世界史のおすすめの参考書ランキング19選を東大生が徹底解説!【大学受験】 志望校別におすすめの大学受験の世界史の勉強法
志望校別におすすめの大学受験の世界史の勉強法を紹介します。
東大志望におすすめの大学受験の世界史の勉強法
東京大学の世界史は大論述が中心で、歴史の因果関係を理解し、自分の言葉で説明できる力が問われます。まずは『山川 世界史探究』で通史を徹底的に押さえ、白紙年表ノートを作って縦と横の流れを整理しましょう。
加えて『HISTORIA』やZ会の『攻略世界史(各国史/近現代史)』を活用し、制度や事件が「なぜ起きたのか」を論理的に語れるようにしておくことが重要です。最終段階では東大の過去問を用いて論述練習を繰り返し、添削を通じて表現力を磨くことが合格への近道となります。
 東京大学に合格する世界史の勉強法を解説!【大学受験】
東京大学に合格する世界史の勉強法を解説!【大学受験】 早稲田大学志望におすすめの大学受験の世界史の勉強法
早稲田大学の世界史は知識量勝負で、文化史や地域史の細部まで問われ、時間内に大量の問題を処理するスピードも必要です。
そこで効果的だったのが、『東進 世界史一問一答 完全版』を星3〜星1まで徹底的に仕上げつつも、資料集と用語集を中心に復習を繰り返していく勉強法です。
実際にこれまで早稲田志望の受験生を指導した中で良かったのは、模試や過去問演習の中で間違えた細かい知識を専用の一問一答ノートにまとめ、直前期にそのノートを何度も回して完成度を高めた方法でした。
知識を積み重ねながら過去問でアウトプットを繰り返すことで、限られた時間でも高得点を安定して取れるようになりました。
 早稲田に合格する世界史の勉強法を徹底解説!【大学受験】
早稲田に合格する世界史の勉強法を徹底解説!【大学受験】 慶應義塾大学志望におすすめの世界史の勉強法
慶應義塾大学志望におすすめの世界史の勉強法としては、これまで紹介した世界史の勉強法に加えて資料問題への対応力を鍛える勉強法です。
慶應の世界史は学部ごとに傾向が異なりますが、特に経済学部・商学部では資料や史料を使った問題が多いのが特徴です。そのため通史理解を土台にしつつ、『攻略世界史』や資料集を使ってグラフ・地図・史料の読解に慣れておく必要があります。
実際に慶應志望の受験生を指導した中で効果があったのは、過去問の資料問題を解いた後に、必ず教科書や用語集で背景を調べ直し「答えに至るプロセス」を自分のノートにまとめさせる勉強法でした。これにより単なる暗記ではなく「設問意図を理解して答える力」がつき、慶應独自の思考力問題に対応できるようになりました。
 慶應義塾に合格する世界史の勉強法を解説!【大学受験】
慶應義塾に合格する世界史の勉強法を解説!【大学受験】 目的別におすすめの世界史の勉強法
目的別におすすめの世界史の勉強法を紹介します。
高校生の定期テスト対策におすすめの世界史の勉強法
高校生の世界史の定期テスト対策に効果的な勉強法としては「定期テスト当日に復習できる苦手まとめリストを作ること」と「試験当日の1週間前までにはその範囲のスピードマスター世界史という問題集を7割は解けるようにしておくこと」です。
特におすすめできる自分が高校生の時に世界史の定期テストで高得点を取れた勉強法としては、その試験範囲の学習を定期テスト2週間前から山川で大事な用語に青でマーカーを引いて、赤シートで隠すという覚え方を繰り返して取り組みつつ、スピードマスター世界史という問題集で7割を取れるようにコツコツ年号や用語をしっかりと覚えていくという勉強法です。
▽もっと詳しく定期テスト対策の世界史の勉強法が知りたいという方はぜひ下記を参考にしてみてください。
 世界史の定期テストの勉強法を徹底解説!ノートの作り方も紹介!
世界史の定期テストの勉強法を徹底解説!ノートの作り方も紹介! 世界史の一夜漬けの定期テスト対策におすすめの勉強法
世界史の一夜漬けの定期テスト対策向けの勉強法としては、世界史の資料集についているような年表と世界史の一問一答もしくは教科書を掛け合わせで覚えることです。
特に白紙の紙に世界史の年表は定期テストの範囲であれば一夜漬けでも書けるようになると思います。
下記が世界史の資料集についている世界史の年表になるので、ぜひ高校生の方は定期テスト前日にゼロから対策したいという方にもぜひやってみてください。

年表を白紙に書けるようになるためには年号と用語をまとめて一気に覚える必要があるので、定期テスト前日の一夜漬けにぴったりの勉強として非常におすすめです。
期間別におすすめの世界史の大学受験の勉強法
夏休みと冬休みに分けて期間別におすすめの世界史の大学受験の勉強法を解説します。
夏休みにおすすめの世界史の大学受験対策の勉強法
夏休みは時間が取りやすく、一気に「世界史を何周もできる」という貴重な大学受験対策ができる期間です。まずは山川『世界史探究』で通史の流れを押さえ、その範囲を『時代と流れで覚える!世界史用語』で演習します。
そこで出てきた用語を一問一答で確認し、星2以上から優先的に暗記しましょう。最後に用語集を使いながら、今日やった範囲をざっと復習して定着させます。
目安としては夏休み2ヶ月で通史を1周終えることを目標にしてください。ここでの完成度が高いほど、秋以降の演習がスムーズに進みます。
冬休みにおすすめの世界史の大学受験対策の勉強法
冬休みは本番直前なので、アウトプットを中心に据えます。
まずは「きめる!共通テスト世界史」やセンター・共通テストの過去問を解いてみましょう。解き終わったら必ず表にまとめ、どの地域・時代で間違えやすいかを分析します。
例えば「近代インド史が弱い」「中世ヨーロッパで用語が曖昧」などを洗い出し、その分野を山川『世界史探究』や用語集で即座に確認。
さらに世界史の一問一答で星2以上を徹底的に潰していきましょう。冬は新しい参考書を増やす必要はなく、これまでやってきた教材の総復習に力を入れるのが鉄則です。
早慶など難関大志望の場合は、Z会『攻略世界史(近・現代史/各国史)』や『HISTORIA』で細かいテーマを補強し、大学別の過去問に取り組むのも効果的です。
世界史の効果的なノートを使った勉強法
世界史のノートの使い方としておすすめの勉強法は、一問一答で覚えらない単語をノートにまとめていく勉強法と白紙年表ノートを作るという世界史の勉強法です。
一問一答ノートを活用した世界史の勉強法
世界史の勉強法として特に効果的なのが、一問一答ノートを作る方法です。『東進 世界史一問一答 完全版』を解きながら間違えた用語だけをノートに書き出し、自分専用の弱点辞書を作り上げます。模試や過去問で出た苦手分野も同じノートに追記すれば、総復習の効率が格段に上がります。
世界史においてしっかりと成績が伸びるのに当たり前にできそうだがみんなやらない勉強法は、覚えていないことだけをまとめることです。
だからこそぜひこの一問一答ノートを活用した世界史の勉強法は取り組んでみてください。
白紙年表ノートを活用した世界史の勉強法
もう一つ有効なのが、白紙に自分で作る年表ノートを活用した勉強法です。私は早慶合格者を300名以上輩出した中で、この年表ノートを必ず作らせてきました。西暦の目盛りを引いて出来事を書き込み、縦の流れと横の流れを同時に整理していきます。例えば「1492年 コロンブス新大陸到達|同時期のヨーロッパ:レコンキスタ完了」と記すことで、世界史全体をつなげて理解でき、応用問題に強くなります。
学年別におすすめの世界史の勉強法
高校生の学年別に高校3年生、高校2年生、高校1年生のそれぞれに合わせたおすすめの世界史の勉強法を解説します。
高校3年生向けの世界史の勉強法
高校3年生におすすめの世界史の勉強法は、まず受験で必要な範囲を逆算しながら通史を短期間で一気に仕上げることです。夏までに『山川 世界史探究』や『時代と流れで覚える!世界史用語』を使って全体像を固め、秋以降は『東進 世界史一問一答 完全版』で細かい用語を徹底的に暗記していきましょう。
並行して『世界史年代サーキットトレーニング』で年号と縦の流れを仕上げておくと、入試本番での得点力が安定します。冬は過去問演習を軸に、間違えた分野を参考書や用語集で即座に復習するサイクルを繰り返すことが最重要です。
高校2年生向けの世界史の勉強法
高校2年生は世界史対策をする上で、まずは通史を早めに1周終えて「歴史の流れ」を頭に入れることが大切です。その際、用語をただ暗記するのではなく、年号と一緒に押さえて縦の流れを意識しましょう。
特に『世界史年代サーキットトレーニング』を使って早いうちから年代暗記を習慣化しておくと、受験学年での伸びが格段に違います。また2年生のうちに『東進 世界史一問一答 完全版』の星2レベルまで固めておけば、3年生での演習に余裕を持てます。
高校1年生向けの世界史の勉強法
高校1年生には時間があるので、理解しづらい部分はスタディサプリやTry ITなどの映像授業を活用し、まずは大きな流れをイメージできるようにしましょう。最初から完璧に暗記する必要はなく、「どの時代にどんな出来事があったのか」をざっくり把握することを優先してください。
余裕があれば『山川 世界史探究』を読み進めながら、『時代と流れで覚える!世界史用語』で確認する習慣をつけると効果的です。
まとめ
世界史の勉強法について大学受験の共通テスト対策から志望校別の対策から定期テスト対策までそれぞれ具体的に解説してきました。
世界史は覚えるべき用語が非常に多い科目ですが、ただ用語を覚えたから世界史の大学受験の偏差値が上がるのではなく、しっかりと教科書と一問一答と年号の参考書や資料集を並行しながら、知識を増やしていくことが非常に重要でうs。
今回の世界史の勉強法を解説した内容としてマスターしてほしかったことは、以下の3つになります。
- 世界史の偏差値UPのためには用語暗記だけでなく「年号」「タテの流れ」「ヨコの流れ」「地図」「文化史」の5つを同時に習得していくことが必要不可欠
- 世界史の大学受験対策にはアウトプット重視よりもアウトプットしつつも、自分で白紙に年表を書いたり、問題を解いたりなど本当に自分が覚えているかを確認することが重要。
- 1時間世界史の勉強をするにしろ、2時間世界史の勉強をするにしろインプットとアウトプットを両方やりこむことと一番効果的な世界史の参考書(例:世界史年代サーキットトレーニングなど)をとにかく徹底的にやりこむことが重要。