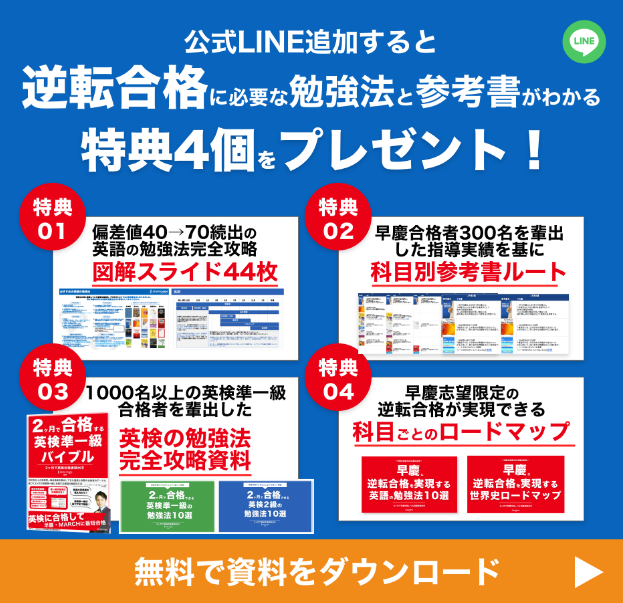本サイトの表記には、一部プロモーションを含みます
「独学で大学受験する人ってどれくらいいるの?」「私立高校に通っていて、塾に行くか迷っている・・・」
こんな疑問・不安を持つ方は必見!
この記事では、実際に塾・予備校なしで大学受験する人の割合と合わせて、医学部や難関大学に合格するための独学のノウハウを解説します。
独学で受験する人向けのおすすめ参考書も紹介するので、ぜひ参考にしてください。

【この記事の監修者:塾比較ドットコム編集長あき先生】
これま高校生の参考書選びに合計2500名以上携わってきました。塾なしで志望校合格を目指す高校生向けに、独学のノウハウやおすすめの参考書を徹底的に解説していきたいと思います。
結論!塾なし・独学で大学受験をする人の割合は?
結論として高校3年生のうち塾なしで大学受験に挑戦する人の割合は5割以上です。
そのうち塾なしで大学に合格する人の割合は約4割だと考えられますが、有名国公立大学や難関私大を目指す場合はさらに厳しく、塾なしで合格できるのは1~3割程度でしょう。
データだけで判断すると、塾なしで大学合格を勝ち取る人は少数派であり、塾や予備校を活用するほうが大学受験に有利だということが言えます。
ただ、塾なしが必ずしも独学だとは限らず、中には通信教育や家庭教師を利用している人もいるので、完全独学で大学に合格する人の割合はかなり少ないと考えられるでしょう。
塾なし・独学で大学に合格するのは簡単ではない
塾や予備校に通わず、独学で大学に合格するのはとても難しいということがわかりました。
その理由について詳しく説明していきます。
勉強計画や進路決定をすべて自分で行わないといけない
大学受験はただ必要科目の学習をするだけではありません。
- 大学の情報を集める
- 大学の出題傾向を知る
- 進路の選択と決定をする
- 勉強の計画を立てる
- 出願に関する書類を作成、提出する
など、勉強以外の面でも大切な過程がたくさんあります。
塾などのサポートがない場合、学校の先生がある程度は相談に乗ってくれると思いますが、最終的にはすべて自分で管理し行うことになります。
特に学習計画については漠然としたものではなく、
「○月○日までに、参考書の△△ページまで完璧にマスターする」
というように具体的で細かに立てることがとても重要です。
学校以外で学習を指導・サポートしてもらえない
大学受験対策は学校の授業でだけでは十分な対応ができません。
進学校に通っている場合は学校で長期休みに集中して補習が行われたりすることもありますが、一人一人の苦手部分に焦点を当てたり、大学別の特徴に合わせた授業を受けることは難しいでしょう。
大学合格には各大学の出題傾向に合わせた対策が必要となるため、学校以外の学習がとても重要になります。
家庭学習の習慣を身につけ、受験スケジュールと自分の弱点を見通した学習計画の作成と実行を自分一人で行っていく必要があります。
塾のテキストがないため、自分で参考書を選ぶ
塾なしで大学受験をする場合、学校の教科書だけでは不十分なので、自分で参考書を選ぶ必要があります。
そのためには志望校の出題傾向などの情報をできるだけ多く集め、自分の弱点や向き不向きなども把握しなければなりません。
その点塾には、大学受験に特化し長年の研究結果やノウハウが詰め込まれたテキストが用意されていることがほとんどです。
また、塾生の現状や目的に合わせたテキストを選ぶところからサポートしてもらえます。
私立の中高一貫校は塾に行かなくても大丈夫?
私立の中高一貫校に通っている人は、塾に行かなくても大学受験に対応できるのでしょうか。
そんな疑問にお答えします。
高校が通塾をおすすめしないこともしばしば
私立の中高一貫校では、学校側が通塾をおすすめしないことが多いです。
なぜなら、中高一貫校では中3から高2にかけて高校のカリキュラムを修了する「先取り学習」を取り入れている学校がほとんどで、高3になると大学受験対策に集中して取り組むからです。
また、定期テストも大学受験を見据えた内容で、一般的な学校に比べると難易度が高くなっています。
そのため、中高一貫校は大学受験に有利だとも言われていますし、学校も大学受験対策に力を入れているので通塾は必要ないという考え方が多いのです。
私立の中高一貫校は受験サポートが充実している場合もある
私立の中高一貫校の場合、もともと中学受験を突破して入学してくる生徒の学力レベルが、公立校の生徒に比べると高いです。
学校の授業も最初から高いレベルに合わせているので、公立校の生徒より高い学力が身につくという点で大学受験に非常に有利です。
また、系列大学の指定校や推薦枠を多く持っているため、推薦入試に強くそのための受験サポートは充実しています。
推薦できる大学も1校や2校ではなく、複数あるのが一般的です。
公立校に比べると先生の移動がほぼないので、入学から卒業まで手厚く指導してもらえたり、設備や施設の充実度など様々な面から見ても大学受験のサポート体制が整っている学校が多いと言えるでしょう。
塾・予備校に行けばさらなる学力向上が見込めることも事実
私立の中高一貫校は公立校に比べると大学受験に有利な点が多いですが、塾や予備校に通うとさらに高い学力を身につけられます。
実際、中高一貫校生の通塾率は中1の段階で約5割、つまり2人に1人は塾に通っています。
中高一貫校生で塾に通っている人は、学校の授業について行けず補習目的で通う人もいますが、難関校への合格を目指してよりハイレベルな塾に通う人の割合も多いです。
大学受験対策に特化した塾では、学力向上はもちろん、学習計画や進路指導なども学校よりきめ細かく対応してくれる場合が多いので、安心して勉強に集中できるでしょう。
大学受験対策で塾に行くメリット・デメリット
大学受験対策で塾に行った方がいいのかどうか、悩んでいる方も多いと思います。
ここでは、大学受験対策で塾に行くメリットとデメリットについて詳しく解説していきます。
塾・予備校に行くメリット
高校より先取りでカリキュラムを学べる
よりハイレベルな学力を身につけて難関校を目指す生徒にとっては、学校の授業だけでは物足りないと感じる場合があります。
塾や予備校では自分のレベルに合ったクラスや内容で学ぶことができるので、上を目指したい人は高校より先取りしてカリキュラムを終わらせることができます。
残った時間で弱点強化をしたり復習や実践に十分な時間を注げるなど、思い通りに学習を進められることと、自信と余裕をもって大学受験本番に臨めるのが大きなメリットの一つでしょう。
大学受験に特化した講師の講義を受けられる
大学受験対策の塾や予備校には、大学受験を知り尽くした指導力の高い講師から講義を受けることができます。
学校の先生も塾講師もどちらも勉強を教える仕事ではありますが、学校の先生は学習指導要領に沿ったカリキュラムで授業を進め、その他にも生徒指導などを通して人格の形成を行うことを目的としています。
一方、塾の講師は塾生の学力を上げることが大きな目的です。大学受験専門の塾講師は、各大学の出題傾向や特徴などの情報やデータを豊富に持っており、合格するためのノウハウを研究しているプロが揃っています。
進路相談・志望校選びのアドバイスを受けられる
大学受験対策の塾や予備校では、学力アップだけではなく進路相談や志望校選びについてもきめ細やかなアドバイスを受けられます。
授業を行う講師の他に、進路相談などを専門に行うアドバイザーが常駐している塾もあり、塾生だけではなく保護者の相談や悩みに乗ってもらえることもあります。
ただ、塾によっては個別面談などを行う進路相談が可能なところと、総合的な対応しか行っていないところに分かれます。
充実した進路相談を希望するのであれば、事前にしっかり調べて確認してから塾を選びましょう。
塾・予備校に行くデメリット
安くはない授業料がかかる
塾や予備校に通うとなると、授業料だけではなく入塾金や教材費、家から遠い場合は通塾のための交通費など、塾によってばらつきはあるものの様々な費用がかかります。
大学受験に特化した塾といっても様々な指導形態がありますが、一般的には個別指導の方が集団指導よりも高い傾向にあります。
特に少人数グループよりもマンツーマン指導の塾ではさらに高くなるでしょう。
また、講師の指導力や受講するコマ数によっても費用に差が出てくるので、総合的に考えた通塾の計画や塾選びをすることが大事です。
学校の勉強で手一杯の人には逆効果
学校の勉強についていくので精一杯の人は、塾や予備校に通うことが逆効果になることもあります。
進学校や中高一貫校では学校の授業もハイレベルでスピードが速く、学校の宿題で手一杯なうえに定期テスト対策も重なると、かなりの負担となります。
そのような状態で塾に通ったとしても、塾の宿題と学校の宿題が両立できずにどちらも中途半端になってしまう可能性が高いです。
塾が必要かどうか悩んでいるなら「何を目的にするのか」、「何を優先すべきか」をはっきりさせることが大事です。
塾なし・独学で大学受験するには参考書選びが大切!
塾なし、独学で大学受験に挑む場合は、参考書選びがとても重要です。
ここでは国公立、私立、理系文系別に参考書選びのポイントについて解説していきます。
国公立・理系を受験するための参考書ポイント
全科目共通・解説の詳しい参考書を選ぶ
参考書選びのポイントで重要なのは、解説がきちんと理解できるかどうかです。
同じような問題の解説でも、参考書によって微妙なニュアンスや言い回しが違っていたり、図解があるかどうかなど様々です。
どれが良いかは「自分が理解できるか」によって人それぞれなので、先生やクラスメイトに勧められたからといって安易に選ぶのは良くありません。
できれば書店で複数の参考書を実際に見て、解説をしっかり読んでから自分が最も理解しやすいものを選ぶようにしましょう。
数学は二次試験の内容を網羅する参考書を選ぶ
国公立理系の大学を受験する場合、数学の参考書は二次試験の内容を網羅しているかどうかをチェックしましょう。
数学にあまり自信がないという人は、基本問題をクリアしてから応用問題に進めるようなステップバイステップ形式のものがおすすめです。
学校の授業にはついていけてるけど試験の時間が足りないという人は演習不足なので、問題数が多いもので数をこなしてみましょう。
数学が得意で得点源とできる人は、基本を抑えたうえで上位大学を狙えるハイレベルなものを選ぶのが良いでしょう。
じっくりと考える思考力が身に付くような丁寧な解説がされているものがおすすめです。
国語・社会は口コミや評判を見て効率的に学習できるものを選ぶ
国語や社会はそこまで時間を割けない人が多いと思いますので、口コミや評判を調べできるだけ短時間で結果を出せるような、効率的に学習できるものを選ぶようにしましょう。
そのためにも自分の現状をしっかり把握することが大事です。
例えば国語なら現代文、古文、漢文の中でどこが弱点なのかを理解し、自分と同じようなレベルの人で同じ志望校へ合格した人が実際に使った参考書はどれなのか。
また、どんな順番で、どの項目を重点的に学習したのかも参考にすると良いです。
国公立・文系を受験するための参考書ポイント
英語は語彙の量・単語レベルがともに中級以上の参考書を使う
まず、共通テスト対策に関しては「共通テストレベル」と書かれてある参考書を選びましょう。
共通テストは文章量が多いので、早めに多くの問題を解いて慣れておくのが重要です。
国公立文系の二次試験対策は、アウトプット重視です。大学によってレベルが異なりますが、迷ったら語彙量、単語レベルともに中級以上の参考書を選ぶのがおすすめです。
ちなみに、長文に含まれる単語数は多いほど難易度が上がります。
共通テスト対策だったら1文あたり300語以上、難関大を目指すなら500語以上が目安となります。
国語は解説ができるだけ詳しい参考書を選ぶ
国語は暗記科目ではないうえにジャンルごとで対策が異なりますが、現代文の長文読解や記述対策で悩む人が多いのではないでしょうか。
読解力や記述力を鍛えるにはただ問題をこなすだけではなく、コツやテクニックも必要となるので、解き方や考え方が詳しく解説されている参考書を選びましょう。
図解が豊富なものは視覚的にも理解しやすいですし、採点基準がとても詳しく解説されているものは、自分の解答と照らし合わせながら特典につながるコツも理解できます。
数学は二次試験にも対応した難易度の参考書を選ぶ
文系志望の人は理系と違って数学にあまり多くの時間を割けないと思いますので、二次試験にも対応した難易度の参考書を選ぶようにしましょう。
大学にもよりますが、文系の二次試験の数学は思考力が問われる問題が多い傾向にあります。
まずは志望校の出題傾向や難易度を把握し、自分の苦手な分野が入っている場合は、高校数学全体を網羅したような参考書よりも、単元特化の参考書を使う方が良いです。
難関大を目指す場合は、文系でも理系と変わらないレベルの問題が出題されますので、より専門的でレベルの高いものを選びましょう。
私立・文系を受験するための参考書ポイント
英語は二次試験に対応した語彙・単語レベルの参考書を選ぶ
英語の入試問題は大学の偏差値や学部によって大きな差があります。
志望校のレベルを把握し、それに合った参考書を選ぶことが重要です。
志望校によって基礎的な問題を重視するのか、長文読解だけは難易度が高いなど、それぞれに応じて必要な練習量も変わってきます。
独学で進める場合は解説が詳しいもの、英語が得意なら演習問題の量が多いものなど、自分の実力や弱点も考慮する必要があります。
参考書の種類が多すぎて選べない場合は、同じ志望校に合格した先輩やネット上の口コミを参考にして選ぶのがおすすめです。
社会は内容を完璧に網羅した参考書を選ぶ
社会は科目が多いですが、多くの方は「日本史または世界史+その他1科目」という選択をするのではないでしょうか。
正直なところ、社会の参考書はどれを選んでもそこまで大差はありませんので、内容を完璧に網羅した参考書を1冊選べばOKです。
内容が講義調で読みやすいとか、図解が多い、時事問題にも対応しているなど、自分に合うかどうか好みによるところも大きいので、先輩の声やネット上の評判・レビューなどを参考にしながら選ぶのが良いでしょう。
全科目共通・科目が少ない分参考書をたくさん回す!
私立文系の大学入試科目は英語、国語の他に社会や数学から1科目選択といった3教科型が主流ですが、中には2教科や1教科で受験できる大学もあります。
受験科目が少ない分、苦手科目があるとその分を他で取り戻すのがとても難しくなります。
例えば合格ラインが7割であれば、3科目どれでも7割以上を目指すのがおすすめです。
そのためには、たくさんの参考書をこなすよりも、各教科1冊ずつに絞って完璧になるまで何度も回すことが重要です。
できるだけ高3の夏休み前に全体の学習を終え、夏以降は過去問を中心に弱点克服に力を注げれば順調と言えるでしょう。
【国公立・理系】独学で受験をする高校生におすすめの参考書5選
国公立大学の理系を独学で受験する高校生におすすめの参考書を5つご紹介します。
青チャート数学Ⅰ+A、Ⅱ+B

大学入学共通テスト対策で王道と言われているおすめの参考書は、青チャート数学Ⅰ+AとⅡ+Bです。
基礎から応用まで幅広く対応し、答えにたどり着くまでの考え方が詳しく解説されています。
- メリット
- 解き方や考え方の解説が詳しいので自学自習がしやすい
- 思考力や判断力を高めるのに効果的
- 基礎から応用まで幅広い問題が掲載されている
- デメリット
- 分量が多くボリュームが大きい
- 基礎を復習したい人にとっては難しい
- 答えをすぐに見る癖がつく場合もある
大学への数学 1対1シリーズ
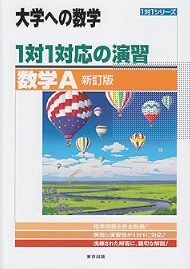
厳選された良問が単元ごとに2問程度で進められる構成になっています。
基礎から受験対策まで包括的に数学が学べる演習中心の参考書です。
- メリット
- 解説がとても丁寧
- 例題と演習問題が1対1で対応している
- 教科書にはない解き方もたくさん掲載されている
- デメリット
- 問題数が少ない
- 確率分野がない
- 問題は標準的だけど解法レベルが高い
大学入試 最短でマスターする数学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・A・B・C (赤本プラス)
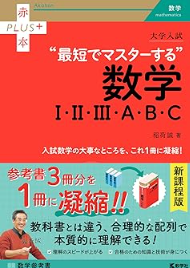
高校数学全般(数学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・A・B・C)から入試対策の大事な部分までを凝縮した1冊です。
難関大学合格のための知識とスキルが身に付きます。
- メリット
- 3ステップで独学でも進めやすい
- 高校数学全般を網羅している
- ポイントを抑えた解説がわかりやすい
- デメリット
- 例題と演習問題が少ない
- ハイレベルな人には物足りない
- 初中級レベルの人には難しい
大学受験Doシリーズ 鎌田の理論化学の講義 改訂版
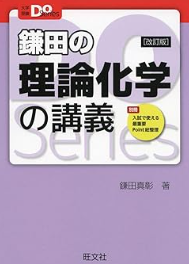
大学入試に必要な知識を効率よく身につけられる参考書です。
評判の良かった説明をさらにわかりやすく加筆修正した改訂版で、多くの受験生に選ばれています。
- メリット
- トップクラスの大学も狙える内容
- 暗記事項がまとめられた別冊がついている
- 講義形式の解説がわかりやすい
- デメリット
- 基礎から復習したい人には合わない
- 説明が独特だと感じる部分もある
- ある程度化学ができる人向け
大学入試 漆原晃の 物理基礎・物理が面白いほどわかる本
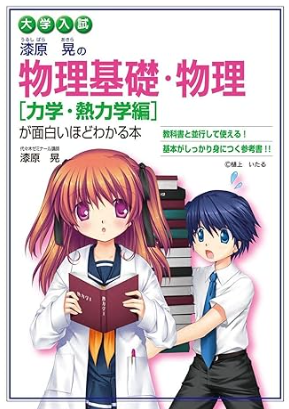
新課程に対応した改訂版で、力学と熱力学分野がわかりやすく学習できる参考書です。
他にも「電磁気編」、「波動・原子編」などのシリーズがあります。
- メリット
- ストーリーとイラストでイメージしやすい
- 対話形式の説明がわかりやすい
- 大事な部分が厳選されている
- デメリット
- 基礎からやり直したい人には向かない
- ボリュームがかなり大きい
- 上級者には物足りない部分もある
【国公立・文系】独学で受験をする高校生におすすめの参考書5選
独学で国公立文系大学の受験をする高校生におすすめの参考書を5つご紹介します。
Next Stage 英文法・語法問題[4th EDITION]
![Next Stage 英文法・語法問題[4th EDITION]](https://site.studychain.jp/wp-content/uploads/2024/05/スクリーンショット-2024-05-22-120119.png)
大学入試の頻出項目を効率よく身につけられると好評の参考書です。
大学合格を勝ち取るために必要な知識が1冊にまとめられています
- メリット
- 問題と解説が見開き2ページでまとまっていて読みやすい
- 情報が整理されていて理解すべきことと覚えることが明確になる
- 英作文問題で必要な情報が一目でわかる
- デメリット
- 基礎部分の復習をしたい人には向かない
- 上級者には物足りないと感じる部分がある
- 文法の説明がさらっとしている
やっておきたい英語長文500 (河合塾シリーズ)
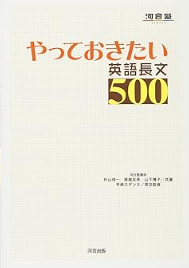
基礎固めからハイレベル大学まで幅広く対応した参考書です。
他にも同シリーズで「700」や「1000」があり、難関大の受験生は使っている人がかなり多いです。
- メリット
- 中堅以上レベル大学の二次試験で合格できる力を身につけられる
- 記述形式の問題が多く、国公立対策に向いている
- 本文の解説がかなり詳しい
- デメリット
- レイアウトが多少見づらい
- 日本語訳が微妙な部分がある
- 設問の解説に物足りなさを感じる場合もある
船口のゼロから読み解く最強の現代文 (大学受験Nシリーズ)
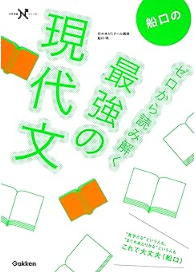
代々木ゼミナールで人気の現代文講師、船口先生の語り口で話題の参考書です。
正しい基本の読解法を徹底的にトレーニングすることができます。
- メリット
- 正攻法の読解トレーニングができる
- 文章の構造が一目でわかる図解
- 共通テストから二次試験対策まで可能
- デメリット
- 標準解答時間が全体的に短い
- 漢字問題についての解説がない
- 初心者にはやや難しい部分もある
漢文早覚え速答法 共通テスト対応版 (大学受験VBOOKS)
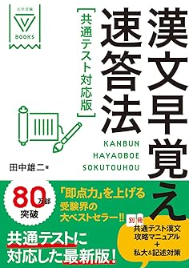
暗記を最小限にし「漢文に慣れること」を重視した内容で、漢文の受験参考書ではナンバー1と言われています。
別冊に共通テストの試行調査を徹底分析した「共通テスト漢文攻略マニュアル+私大&記述対策」がついています。
- メリット
- 「いがよみ」=「漢字以外の読み」を覚える10の公式がわかりやすい
- 受験に不要な内容をハッキリ述べている
- 覚え方の後に練習問題がついているので振り返りしやすい
- デメリット
- 超基礎のレ点や一二点などの説明はない
- 基礎がわかっていないと1ページ目からまったくわからない
- 簡潔にまとめすぎている部分もある
石川晶康 日本史B講義の実況中継(1)原始~古代 (実況中継シリーズ)
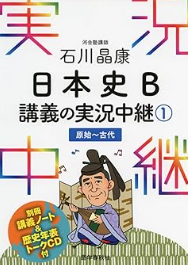
改訂に伴い全4巻のシリーズとなっている日本史の参考書で、予備校の講義を元にしています。
講義ノート、日本史年表、語呂合わせで覚えられる年表トークCDつきです。
- メリット
- すべての史料に現代語訳とルビがついている
- 定期テストから二次試験の論述まですべてのテストの前提となる基本的な内容
- 難関大を狙う受験生にとっても痒い所に手が届く内容
- デメリット
- 初めて日本史に手を付ける人には向かない
- 若干無理な語呂合わせもある
- 時間がない受験生には量が多すぎる
【私立・文系】独学で受験をする高校生におすすめの参考書5選
私立文系大学を独学で目指す高校生におすすめの参考書を5つご紹介します。
大学入試問題集 関正生の英語長文ポラリス
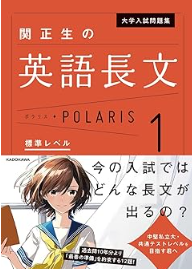
英語界で多くの受験生から指示されている関正先生が選び抜いた、大学入試の最前線を走る英文がわかる参考書です。
12のテーマを把握すれば、どのレベルの大学入試にも幅広く対応できます。
- メリット
- 長文の解説がとても丁寧で詳しい
- ネイティブによる音声もダウンロードでき、リスニング力も鍛えられる
- 頻出テーマ、最新テーマの英文を扱っている
- デメリット
- たまに直訳で不自然なところがある
- 中級者以上レベルでないと難しい
- 文法の解説はほぼない
英語長文問題solution1
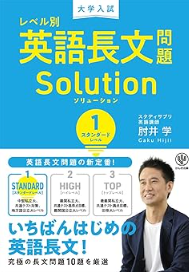
中堅私大、地方国公立レベルの長文問題10問が厳選されています。
あらゆる角度から英語力を向上させる4つのポイントで、理解力が高まります。
- メリット
- 音読用白文とデータもあり復習がしやすい
- 構文解釈と問題演習が1冊で完結
- 構成がシンプルで使いやすい
- デメリット
- 10問が物足りないと感じる人もいる
- 中級レベル以上の人にはさらに上位シリーズがおすすめ
- たまに誤訳がある
入試現代文へのアクセス (完成編) (河合塾シリーズ)
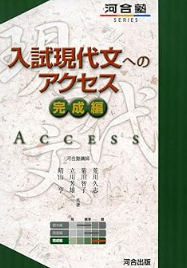
関関同立MARCHレベルの私大を目指す人におすすめの現代文の参考書です。
現代文がわりと得意で得点源にしたいという人に合っています。
- メリット
- 記述問題の対策ができる
- 高度な問題にもチャレンジできる
- 本文の読解方法や設問の解き方がわかりやすく解説
- デメリット
- 随筆が1問しか掲載されていない
- 解説を徹底的に読み込まないと成績アップにつながらない
- 問題と答えを切り離しづらい
首都圏「難関」私大古文演習 (河合塾シリーズ)
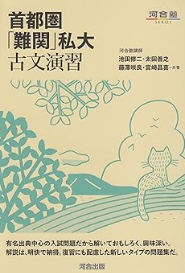
MARCHから早慶レベルの首都圏の難関私大を目指す方におすすめの古文の参考書です。
ハイレベルな問題が20問掲載されています。
- メリット
- レベルの高い古文読解の力がつく
- 解説がとても丁寧でわかりやすい
- 制限時間や特典配分など本番を意識した内容も掲載
- デメリット
- 中堅私大を狙う人には難しい
- 2012年出版なので古い問題も多い
- 文字装飾が見づらい部分がある
時代と流れで覚える! 世界史B用語

入試で頻出される世界史用語を3ステップでチェックできる参考書です。
170ページとコンパクトながら約3000語が掲載されています。
- メリット
- 地図や図解もわかりやすく解説されている
- 内容も数も程よく基礎固めにぴったり
- 覚えるべき事項が流れで理解できる
- デメリット
- 右ページにふり仮名がないのが不便
- まとめすぎて理解しづらい部分もある
- 難関校対策には足りない
まとめ
本記事では、塾なし独学で大学受験をする人の割合や、独学で受験する人向けのおすすめ参考書を紹介しました。
塾なし、独学で大学受験をする人は少数派ではあるものの、参考書をうまく使いこなして合格をつかみ取っている方もいます。
独学で大学受験に挑戦したい方は志望校を早めに決め、自分の現時点での実力や弱点、志望校の出題傾向などを把握したうえで、口コミなども参考にしながら自分に合う参考書を選びましょう。
塾に行くかどうか悩んでいる方は、通塾や独学に関するメリットとデメリットを参考にしながら比較検討してください。