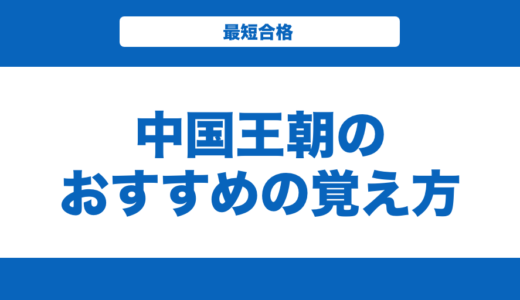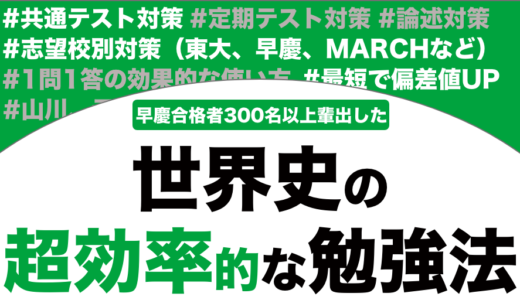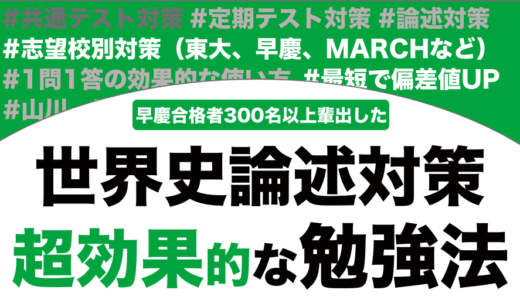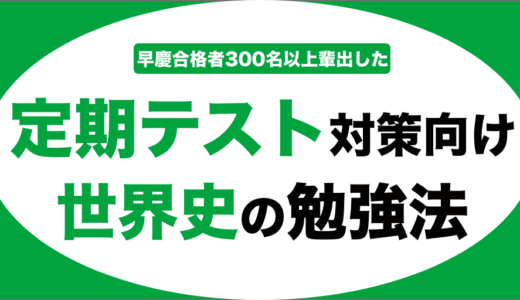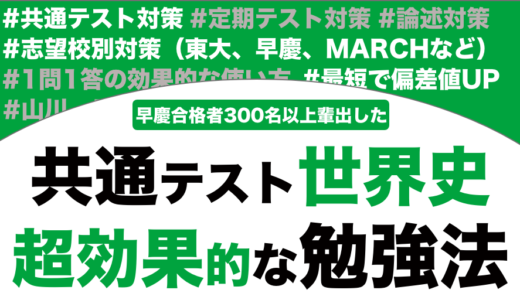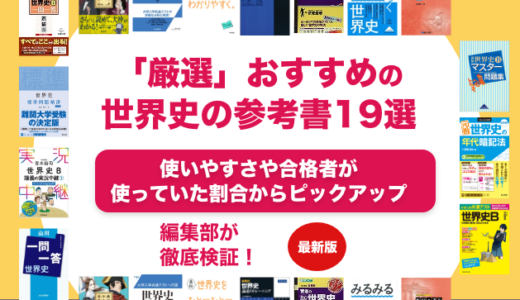世界史の大学受験対策に向けた志望校別の勉強法から共通テスト対策向けの勉強法からゼロから東大志望や早慶志望やMARCH志望の合格できる勉強のロードマップも合わせて解説します。
また、世界史の定期テストの勉強法から高校生向けに学年別におすすめの世界史の勉強法も解説します。

【この記事の監修者:逆転合格特化塾塾長「竹本明弘」
世界史の効果的な勉強法を大学受験対策向けと高校生向けに分けて2種類紹介します。大学受験対策向けの世界史の勉強法はこれまで世界史選択で早慶に100名以上合格させてきた中で使ってよかった参考書と合わせてやって良かった世界史の勉強法も解説します。大学受験対策をしている世界史選択の受験生はぜひ参考にしてみてください。
ゼロからでも短期間で世界史の偏差値を伸ばせる大学受験の勉強法をこれから解説していくので、ぜひ参考にしてみてください。
この記事でわかること
- ゼロからでも共通テストの世界史で9割取れる勉強法と使うべき参考書一覧
- 実例付きで実際にどういう勉強のスケジュールをこなせば世界史の偏差値が70になるか
いきなり最終結論!ゼロから東大早慶レベルに受かる世界史の勉強法を徹底解説!
結論として、ゼロからでも世界史の偏差値を6ヶ月で40から70にする勉強法としてこれまで100人以上の受験生が実践して、東京大学から京都大学から早稲田大学や慶應義塾大学などの難関大学に合格した方法は下記の通りです。(目安:1日2時間の勉強時間)
→特に世界史の基礎作りにおいては年号と用語を重視しながら通史を1通り理解する
勉強時間の時間配分の目安=1日40分:講義本→30分:時代と流れで覚える→30分:1問1答→最後復習
- まず世界史については最初は可能な限りシンプルに通史の1周目を進めていきましょう。定期テストなどで世界史は得意もしくは苦手意識がないという人は最初から世界史探究もしくは山川を使って、通史を進めるやり方がおすすめです。ただし、定期テストでも赤点ばっかりや学校の授業を全く聞いていなかった方は「マンガで世界史が面白いほどわかる本」から進めましょう。一通り読み終わったら世界史探究にうつるのがおすすめです。
- 1日40分世界史探究を読んで、その範囲を「時代と流れで覚える!世界史用語」を解いて、覚えて、最後に全体的な用語を星2以上のみ「世界史一問一答完全版(東進)」で覚えていきましょう。星0はまず覚えなくてよく、星1はまだ覚えなくて大丈夫です。
- 個人差はありますが、世界史探究の1周が終わるまでに毎日2時間時間が取れれば2ヶ月程度で終わります。
使用する世界史の参考書:「マンガで世界史が面白いほどわかる本(初心者のみ)」、「山川世界史探究」or「世界史探究(KADOKAWA)」、「時代と流れで覚える!世界史用語」、「世界史一問一答完全版(東進)」
→年号の強化を軸にタテの流れを覚えることをメインに通史を進める。
勉強時間の時間配分の目安=1日40分:講義本→30分:サーキットトレーニング→30分:1問1答→最後復習)
- 「超効率!世界史年代サーキットトレーニング」を使って、年号をメインにタテの時代の流れをしっかりと覚えていきましょう。1周目に1問1答や時代と流れで覚えるで覚えた用語が「なぜ起きたのか」をより深掘りながら、タテの流れをどんどん覚えていくイメージです。
- 2周目は1周目よりも早いペースで通史を終わらせられると思いますが、ここで年号を覚えているかどうかでかなり大きく変わってくるので、1つ1つ地道ですが覚えていきましょう。
- サーキットトレーニングが終わったら、早慶以上を志望する受験生は世界史の基礎問題精講を解きつつ、自分が暗記できていない分野をどんどん洗い出していきましょう。早慶以下を志望する受験生は世界史の決める!共通テスト世界史を解きましょう。
使用する世界史の参考書:「超効率!世界史年代サーキットトレーニング」、「世界史 基礎問題精講」or「決める!共通テスト世界史」、「世界史一問一答完全版(東進)」
→アウトプット量を少しずつ増やしつつもより細かい知識の習得+苦手の穴を埋める暗記
勉強時間の時間配分の目安=1日30分:講義本→45分:基礎問題精講→30分:1問1答→最後復習※用語集も活用)
- ここからは細かい用語を覚えつつも覚えてきた年号を活かして地図も覚えて、ヨコの流れを中心に覚えていきましょう。そのためには、年表や地図を見るのももちろん大事ですが、用語集や資料集を活用して、問題集で間違えた分野を復習するなどして、その時代その時代ごとに何がどういう流れで起きたのかを把握することが重要です。もし覚え辛いという方には「世界史一問一答地図」もしくは「世界史ビジュアル問題集」もおすすめですが、おすすめの勉強法としては、白紙に各時代の地図を書いてみるというのは確実に覚えられるので非常におすすめです。無難な地図対策におすすめの世界史の参考書は世界史ビジュアル問題集です。
- この時点で1問1答は星2までをしっかりと覚えきることを目標にしていきたいので、まだ全然覚えれていないという人は少し基礎問題精講にかける時間を減らして、1問1答に時間を割く形で、講義本に45分、1問1答に45分かけて、年号のサーキットトレーニングの復習もしながらインプット中心で構いません。世界史は焦っても特に得をする科目ではないので、インプットばかりになっていてもそこまで焦る必要はないです。
使用する世界史の参考書:「山川世界史用語集」「世界史図録など資料集」「世界史一問一答地図」「世界史ビジュアル問題集」「世界史一問一答完全版(東進)」「超効率!世界史年代サーキットトレーニング」
→共通テスト対策をしつつ、徹底的な苦手克服に向けた分析と学習の繰り返し
勉強時間の時間配分の目安=1日30分:講義本→45分:共通テスト問題集→45分:1問1答→最後復習※用語集も活用
- 「きめる!共通テスト世界史」や「共通テストの過去問集」を活用しながら、何も見ずにこれまで習得したような用語や年号や流れの知識を活用して解きましょう。そして、表を作って、時代ごとにどこで自分は間違えやすいのか?いつの時代のインド史なのか?それともある時代の中国史なのか?などを分析して、その分野をこれまで使ってきた講義本や参考書を使って確認するという作業を繰り返しましょう。
- 目安としては10年〜15年分共通テストおよびセンター試験の過去問を活用して対策を進めることをおすすめします。実際に解く時間はアウトプットの問題としてはやはり共通テストやセンター試験はスラスラ解きやすいので、自分が覚えていたと思ったいた分野が実はできていなかったというのを見つけるのに適してます。
使用する世界史の参考書:「きめる!共通テスト世界史」、「共通テストの過去問集」「世界史一問一答完全版(東進)」
→特に現代史の細かいタテの流れや頻出テーマの地図、タテの流れ、横の流れの把握
勉強時間の時間配分の目安=45分:攻略世界史or45分過去問→75分:講義本&1問1答&年表&用語集&資料集
- 早慶以上の難関大志望の受験生は特に最後攻略世界史を使って、意外と把握していないような特に近現代史における細かいなぜこの法律ができたのかやなぜこの事件が起きたのかなどのタテの流れや用語を把握していきましょう。Z会の出している攻略世界史の各国史と近・現代史をやるのがおすすめです。ただし、まだ時間に余裕があるという方はHISTORIAという参考書にも難問と呼ばれるような問題とわかりやすい解説があるので取り組むのもおすすめです。そしてその後志望する大学の過去問を解きつつ、間違えた問題などは講義本や資料集や用語集でしっかりと確認するということを繰り返していきましょう。世界史の過去問演習は何年分やったかも大事ですが、どれだけ復習を念入りにやったかの方が非常に重要です。
- それ以下の大学を志望する受験生は使う世界史の参考書は増やさずにこれまでの復習をより重点的に行うもしくは過去問演習に入っていきましょう。
使用する世界史の参考書:「HISTORIA」「攻略世界史の各国史(Z会)」「攻略世界史の近・現代史(Z会)」「志望校の過去問」


▽大学受験の世界史の勉強法についてまとめたので、受験生の方はぜひ下記の記事を参考にしてみてください。
 【大学受験】世界史の超効率的な勉強法を徹底解説!
【大学受験】世界史の超効率的な勉強法を徹底解説! ▽世界史の勉強法の実践におすすめの参考書比較表

共通テストで9割取れる世界史の勉強法
共通テスト対策で9割取るために重要なとしては、用語と年号と地図と文化史の4つをどれだけ積み上げられるかが非常に重要になってきます。
そのため、共通テスト対策で高得点を取るためにおすすめの世界史の勉強法は、まずは用語と年号をしっかりと覚えるために、通史を世界史の山川の教科書もしくは世界史探究(KADOKAWA)で進めつつ、元祖世界史の年代暗記法という参考書か世界史年代サーキットトレーニングという参考書のどちらかを使って、確実に年号を覚えながら、用語を世界史一問一答(東進)で覚えていくことになります。
共通テストで9割取れる世界史の勉強法①年号を最優先してタテの流れを確実に覚える
これまで早慶に300名以上受験生を合格せてきた中で世界史の共通テストで9割以上取った生徒は150名以上輩出してきました。その中で同じ勉強時間でも世界史の共通テストで点数が取れる子の特徴としては、「年号を軸にタテの流れを時間をかけてでも覚えていること」です。
だからこそ、共通テストで9割取りたいと考えている受験生はまずは年号を特に重視しながら、通史を進めて、タテの流れをしっかりと把握して、暗記していくことがおすすめの勉強法です。
共通テストで9割取れる世界史の勉強法②講義本とアウトプットの問題集を必ず両方行う
まず共通テスト対策におすすめの世界史の参考書としては、下記のような講義本が挙げられます。

個人的には左側の2つの「詳説山川の世界史探究」もしくは「大学入試ストーリーでわかる世界史探究」がおすすめの講義本です。
そして、通史対策は「30日完成スピードマスター世界史問題集」もしくは「時代と流れで覚える!世界史用語」で基礎的なレベルにおいては対策を行い、応用レベルまできたら「世界史 基礎問題精講」で行い、地図対策は「ビジュアル世界史問題集」で行うことをおすすめします。
世界史の勉強のイメージとしては、1時間あったら前半は講義本を読み込んで、後半はその範囲を解いて、最後の復習は講義本を読み込みながら行うような形でインプットして、アウトプットして、最後またインプットするのがおすすめの勉強法です。

世界史の問題集や過去問を解く時には常にこのインプットして、アウトプットして、インプットするの3段階を必ず取り入れることをおすすめします。
1年間や半年間でもこの勉強法を続けた時に単なる覚えている用語の数が増えるだけでなく、「なんでその事件を起きたのか?」や「なんでそんな王政になったのか?」などがどんどん詳しくなってくるので、タテの流れの理解がどんどん深まり、結果的に世界史の共通テストの正答率がどんどん上がっていきます。
共通テストで9割取れる世界史の勉強法③講義本と一問一答と年号の参考書の3つを並行して使う
共通テスト対策の世界史の勉強法としては、用語と年号と地図の3つを同時に覚えていくことが一番最短の方法です。

その上では、上記のような世界史の王道3点セットを使って、共通テスト対策の学習を常に行うことが一番やってよかった勉強法です。
世界史の一問一答星3と星2を覚え切っても共通テストの世界史では点数が取れないケースがあります。その原因は、特に年号と合わせて覚えられていなかったり、文化史や地図を関連づけて覚えられていないことがほとんどです。
だからこそ、世界史の共通テスト対策の勉強法としては1冊の参考書で完結させるのではなく、年号はこの世界史の参考書で覚えつつも用語を一問一答で確実に覚えていくということをベースに写真は資料集を活用して、地図はビジュアル世界史問題集や地図一問一答を活用して覚えていきましょう。
▽世界史の共通テスト対策におすすめの勉強法は詳しくはこちら
 世界史の共通テストの勉強法を徹底解説!【大学受験】
世界史の共通テストの勉強法を徹底解説!【大学受験】 
【この記事の監修者:逆転合格特化塾塾長竹本明弘】
▽実際にやってよかった世界史の勉強法10選を厳選して解説しました。
短期間で世界史の偏差値が伸びる勉強法3選
短期間でも世界史の偏差値が伸びる勉強法を3つ紹介します。
世界史全体の苦手分野を明確にして重点復習する「分析シート法」
過去10年分の共通テスト・センター試験の世界史を解き、時代×大陸で間違えた箇所を表にまとめましょう。
世界史全体におけるどの時代・地域が苦手なのか一目で分かり、当日はその範囲だけを集中的に復習できます。「古代ヨーロッパ」「近代アジア」など、自分の弱点を色分けしておくのも効果的です。
世界史の試験直前はこのシートを見るだけで、効率よく得点力を最大化できます。
縦と横の流れを整理して知識を定着させる「年表復習法」
試験当日は新しい暗記よりも、年表を使って世界史全体の流れを確認することが重要です。大陸ごとに色分けした自作年表を見ながら、「この出来事の前後関係」や「同時代の他地域の動き」を整理しましょう。
文化史や近現代史も年表に組み込むと、忘れやすい知識を時代の流れでつなげて思い出せます。直前に流れを俯瞰することで、本番の問題にもスムーズに対応できます。
自分の間違えた問題をまとめる「オリジナルまとめノート法」
世界史の一問一答や世界史の過去問で間違えた問題を、なぜ間違えたのか・正しい答えは何かをセットでノートに整理しましょう。10ページ以内に苦手な範囲だけをまとめると、試験当日でもすぐに見返せます。
自分が忘れやすい世界史の用語や因果関係を簡潔にメモしておくのがポイントです。最後の30分はこのノートだけを確認し、直前まで知識を定着させましょう。
世界史の論述対策におすすめの勉強法
実際に世界史の論述対策で効果があったおすすめの勉強法を解説します。
具体的に3ヶ月で世界史の論述力をつけるためにおすすめの勉強法は下記になります。
使用する参考書:『みるみる論述力がつく世界史』
- まずは論述の「型」を理解する。
- 問題を解く際は必ず ①設問分析 → ②要素の抽出 → ③答案の骨格づくり → ④文章化 の流れを意識。
- 各章を解いたら、模範解答を「なぜその表現になるのか」まで分析して自分の答案に赤入れする。
ポイント:最終戦は世界史の論述の書き方を覚えることなので、この時期は「短くても論理的に書ける」ことを優先し、字数を埋めようとしすぎない。
「攻略世界史」や「詳説世界史探究」など自分の普段使っている講義本の参考書で 各国史(フランス史・中国史・イスラーム史など)や近現代史(国際関係史・戦後史) を深掘りしていきましょう。論述で頻出テーマを整理し、「因果関係・時代背景・結果」を必ずメモ化しておく。それと並行して「世界史論述トレーニング」を制限時間を区切って答案を書き、添削をするというのを繰り返しましょう。
ポイント:知識を詰め込みすぎず、「設問に必要な部分を抽出して書く」訓練を徹底するようにしましょう。
使う参考書:『世界史論述トレーニング』反復+志望校の過去問演習
世界史論述トレーニングを2周目に入り、答案の完成度を高める。世界史の過去問演習では「時間配分」を意識。設問ごとに「構成メモ」を2分で作れる練習をする。世界史の過去問を解き終わった後は模範解答と比較し、①抜けていた要素は何か②不要に書いてしまった要素は何か③論理の流れに無理はないかを必ず確認しましょう。必要に応じて普段自分の使っている世界史の講義本に戻り、知識不足を補強する。
▽世界史の論述対策の勉強法はぜひ下記の記事を参考にしてみてください。
 世界史の論述の勉強法と書き方とおすすめの参考書を解説【大学受験】
世界史の論述の勉強法と書き方とおすすめの参考書を解説【大学受験】 定期テスト対策におすすめの世界史の勉強法
定期テスト対策におすすめの世界史の勉強法を解説します。
高校生におすすめの世界史の定期テスト対策の勉強法
高校生向けの定期テスト対策の勉強法としては、ノートの使い方がカギになってくるのと教科書をコピーして教科書自体をオリジナルのテキストとして使うのがおすすめです。
まず世界史の定期テスト対策でおすすめなのは、教科書をそのまま「自作テキスト」に変える方法です。範囲のページをコピーして余白に授業の板書やプリントの要点を書き込み、段落ごとに一行でまとめを添えることで、自分だけの定期テスト対策の世界史の参考書が完成します。
ノートは本文の要約を書いた後に疑問形式で整理し、最後に結論を短くまとめる形にすると理解が深まります。
さらに、コピーの要約部分を隠して声に出して説明し、言えなかった部分だけを重点的に復習すれば効率よく覚えられます。
図版や地図は「作品名・時代・地域」の三点を必ず押さえるのが世界史の定期テスト対策における効果的な勉強法のコツです。
高校生の世界史の定期テストの前日の一夜漬けにおすすめの勉強法
世界史の定期テストの前日におすすめの勉強法としては、白紙のノートに年表を書く練習をすることをおすすめします。

前日の勉強では、まず範囲を象徴する年表や地図を一枚決め、机に広げて軸にしましょう。その上で白紙に横長の年表を書き、出来事・人物・制度・戦争・条約を色分けして整理し、因果関係は矢印で必ず結びます。
最後に寝る前に白紙の年表を頭の中で再現できれば、定期テスト当日は一問目からスムーズに得点を積み上げられます。
▽世界史の定期テストに役立つ勉強法はこちら
 世界史の定期テストの勉強法を徹底解説!ノートの作り方も紹介!
世界史の定期テストの勉強法を徹底解説!ノートの作り方も紹介! 志望校別におすすめの大学受験の世界史の勉強法
大学受験において志望校別におすすめの世界史の勉強法を解説します。
東大志望の大学受験生向けの世界史の勉強法
東大志望者にとって世界史の勉強法の核心は、大論述対策にあります。東大の世界史では単なる知識の羅列ではなく、歴史の因果関係を深く理解し、自分の言葉で筋道立てて説明する力が求められるため、世界史勉強法も通常とは異なるアプローチが必要になります。
まず基礎となる世界史勉強法として、「山川 世界史探究」を使って通史をしっかり押さえることから始めましょう。このとき効果的な世界史勉強法は、白紙に年表ノートを作成し、縦の時代の流れと横の地域間の関係を整理していくことです。この世界史勉強法により、東大が求める俯瞰的な歴史理解が身につきます。
次の段階の世界史勉強法では、「HISTORIA」やZ会の「攻略世界史(各国史/近現代史)」を活用し、制度や事件がなぜ起きたのかを論理的に説明できるように仕上げていきます。東大合格のための世界史勉強法の仕上げ段階では、過去問を繰り返し解き、添削を受けながら論述の表現力を磨いていくことが、最も確実な世界史勉強法となります。
 東京大学に合格する世界史の勉強法を解説!【大学受験】
東京大学に合格する世界史の勉強法を解説!【大学受験】 慶應義塾大学志望の大学受験生向けの世界史の勉強法
慶應義塾大学の世界史の勉強法は学部ごとの傾向を踏まえる必要がありますが、特に慶應義塾大学の経済学部や商学部では資料や史料を使った問題が多いという特徴があります。
そのため慶應合格のための世界史勉強法では、通史理解をベースにしつつ、資料読解力を養うことが欠かせません。
慶應対策の世界史勉強法として、「攻略世界史」や資料集を使ってグラフ・地図・史料の読解に慣れておくことが重要です。実際に慶應志望の生徒に世界史勉強法を指導した際に効果があったのは、過去問の資料問題を解いた後に必ず教科書や用語集で背景を調べ直し、答えに至るプロセスを自分のノートにまとめさせるという世界史勉強法でした。
この世界史勉強法を継続することで、単なる暗記ではなく設問の意図を正しく読み取って答える力が身につきます。慶應独自の思考力を問う問題に対応するための世界史の勉強法は、知識と思考力を同時に鍛えることで完成するのです。それぞれの大学が求める力を理解し、適切な世界史の勉強法を選択することが、志望校合格への最短ルートとなります。
▽実際に慶應合格者が使った世界史の参考書ルート

 慶應義塾に合格する世界史の勉強法を解説!【大学受験】
慶應義塾に合格する世界史の勉強法を解説!【大学受験】 早稲田大学志望の大学受験生向けの世界史の勉強法
早稲田大学の世界史は知識量勝負で、文化史や地域史の細かい部分まで出題されます。限られた時間の中で大量の問題を処理するスピードも必要です。
効果的なのは、「東進 世界史一問一答 完全版」を星3から星1まで徹底的に仕上げ、さらに資料集や用語集を使って繰り返し復習していく方法です。私がこれまで早稲田志望の生徒を指導していて良かったのは、模試や過去問で間違えた知識を専用の一問一答ノートにまとめ、直前期にそのノートを何度も回すやり方でした。
早稲田大学志望の受験生はこうして知識を積み重ね、過去問でアウトプットを繰り返すことで、短時間でも安定して高得点を取れるようになります。
 早稲田に合格する世界史の勉強法を徹底解説!【大学受験】
早稲田に合格する世界史の勉強法を徹底解説!【大学受験】 目的別におすすめの大学受験対策の世界史の勉強法
大学受験対策の世界史の勉強法を目的別に解説します。
世界史のタテの流れを覚えるための勉強法
世界史の勉強法でタテの流れを覚えるには、白紙のノートに年表を作って出来事を時系列で整理するのが効果的です。
年号と出来事を結びつけながら因果関係を矢印で示すことで、バラバラだった知識が筋道として理解できます。自分で白紙に年表を作るのは少し難しいという方は元祖世界史の年代暗記法などを使いながら写す形で作成する形でも十分効果がある勉強法です。
特に同じ国や地域の出来事を縦につなげると、制度や戦争の背景が一気に見えてきます。
世界史の勉強法としては、まずタテの流れを土台にすると論述や共通テスト対策にも強くなります。
世界史の横のつながりを覚えるための勉強法
世界史の勉強法で横のつながりを覚えるには、同じ時代に世界の各地で何が起きていたかを地図や表で比較するのがおすすめです。例えば16世紀ならヨーロッパの宗教改革と同時期のオスマン帝国や明の動きを並べてみると理解が深まります。
世界史の横のつながりを覚えるためには、地図や年表に同じ世紀ごとの出来事を横一列に書くと、地域ごとの影響関係が見やすくなります。
世界史の勉強法ではヨコの流れを押さえることで、複雑な国際関係史も得点源に変わります。
世界史が苦手な人向けの勉強法
世界史が苦手な人におすすめの世界史の勉強法は、まず教科書や漫画形式の参考書で大まかな流れをつかむことです。細かい用語にこだわらず、時代のストーリーとして理解することから始めましょう。
そのうえで一問一答や年表ノートを活用して、少しずつ知識を積み重ねていくと苦手意識が消えていきます。世界史の勉強法は「理解→暗記→アウトプット」の順で進めるのが効率的です。
世界史の文化史を覚えたい人におすすめの勉強法
世界史の文化史を覚える勉強法としては、人物・作品・時代・地域を必ずセットで整理することが大切です。
単なる名前や用語の暗記ではなく、「誰が・どこで・いつ・何を残したのか」を表やカードにまとめると定着しやすくなります。資料集を活用して建築や絵画を目で見て覚えるのも文化史対策には有効です。
世界史の勉強法として文化史を計画的に進めれば、差がつきやすい分野を得点源にできます。
世界史の勉強法の実践におすすめの参考書6選

世界史の勉強法の実践におすすめの参考書①大学入試ストーリーでわかる世界史探究(KADOKAWA)

大学受験対策の世界史の講義本形式のおすすめの参考書としては、大学入試ストーリーでわかる世界史探究(KADOKAWA)です。
最大の特徴は教科書とは違って口語体で書かれているため楽しくスラスラと読み進めることができる点です。
人の動きと歴史の流れをつかむことが大切というコンセプトのもと、因果関係を論理的に理解できる詳しい解説が掲載されています。
各テーマの最初には時代のテーマを大づかみできるページがあり、重要事項は時系列に沿ってクローズアップにまとめられているため、流れを意識しながら学習を進めることが可能です。
比較したい内容は表や図でスッキリと整理されており、ビジュアル面でも理解を助ける工夫が施されています。
また、近現代日本へのアプローチというコラムが随所に掲載されているため歴史総合の対策にも対応しており、可能な限り最新の現代史まで盛り込まれているため独学で世界史の勉強をしようと思っている受験生にもおすすめです。
世界史の勉強法の実践におすすめの参考書②超効率!世界史年代サーキットトレーニング

大学受験の世界史の偏差値を短期間で上げる上でおすすめの参考書は、超効率!世界史年代サーキットトレーニングです。
「世界史年代サーキットトレーニング」(KADOKAWA)は、年代をテンポよく覚えられる構成になっており、世界史の勉強法として一問一答と並行して取り組むと暗記効率が格段に上がります。
用語の意味は理解しているけれど年号があやふやという受験生には特におすすめで、シンプルに年号を高速で定着させることができます。世界史の勉強を始めたばかりの人でも無理なく使える構成になっているため、早すぎると感じる必要はありません。
大学受験で世界史を選択するすべての受験生におすすめできる参考書です。
世界史の勉強法の実践におすすめの参考書③攻略世界史 近・現代史(Z会)

特に難関大志望の大学受験対策の世界史の参考書は攻略世界史の近現代史です。
「攻略世界史 近現代史」(Z会)は、大学受験における世界史の現代史対策に特化した勉強法を実践できる参考書です。共通テストやセンター試験の傾向を見ても現代史は平均点が下がりやすく、細かいタテの流れや因果関係を正確に把握する必要があります。
この世界史の参考書は、なぜ出来事が起こったのか、どのように歴史がつながっているのかを丁寧に整理しており、早慶レベルにも対応できる深い理解が得られます。これまで早慶合格者を数多く指導してきた中でも、特に世界史選択の生徒にはこの一冊をできる限り取り入れてきました。
現代史で得点差をつけたい早慶以上を志望する受験生におすすめできるZ会の世界史参考書です。
世界史の勉強法の実践におすすめの参考書④ビジュアル世界史問題集

大学受験で頻出分野の地図の理解やヨコの流れを理解するために大事になってくる地図を覚えるためにおすすめの世界史の参考書はビジュアル世界史問題集です。
ビジュアル世界史問題集は駿台文庫から出版されている地図問題に完全特化した問題集です。世界史学習で最も差がつきやすい地図知識を視覚的にインプットすることをコンセプトに作られており、31のテーマで構成された見開きの書き込み式となっています。地図上で出来事や人物を関連付けて覚えることができるため、一見すると地名だとわからないような用語でも場所と結びつけて記憶することが可能です。
基礎から標準レベルの問題が中心となっており、やや難しい問題には星印がついているため自分のレベルに合わせて取り組むことができます。全体のボリュームは少なめですが入試で重要となるエリアが厳選されているため、短期間で何周も繰り返して知識を定着させることができます。教科書や講義本で通史の流れを一通り学んだ後に取り組むことで、覚えた知識を地図上で整理し直すことができるため、世界史の立体的な理解につながります。
世界史の勉強法の実践におすすめの参考書⑤世界史一問一答(東進ブックス)

大学受験対策の世界史の一問一答形式の参考書の中で一番おすすめは世界史一問一答完全版(東進ブックス)です。
最大の特徴は各問題の頻出度が星の数で4段階に分けられており、学習の優先順位をつけやすくなっている点です。世界史探究と歴史総合に対応しており、単なる用語の羅列ではなく世界史のなぜという因果関係と流れがわかりやすいように問題文が配列されています。
星3つレベルの問題には朗読音声が付属しているため、通学時間や隙間時間に耳からも知識をインプットすることが可能です。共通テストレベルから早慶上智などの難関私大レベルまで幅広く対応しており、国公立大学の論述対策にも活用できる圧倒的な単語数を誇ります。
通史のインプット学習と並行して演習を行うことで効果を最大化できるため、講義本や教科書で流れを理解しながらこの一問一答で用語を定着させていくという使い方がおすすめです。チェックボックスがついているため全問正解するまで繰り返し取り組むことができ、この一冊を完璧にすれば世界史の用語暗記に関しては十分な力がつきます。
▽世界史のおすすめの一問一答が知りたいという方はこちら
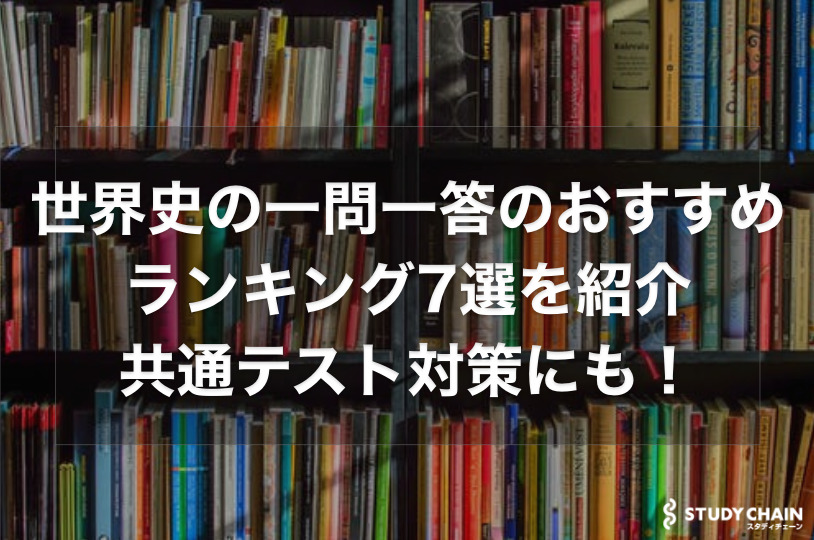 世界史の一問一答のおすすめランキング7選を解説!定期テスト対策にも!【大学受験】
世界史の一問一答のおすすめランキング7選を解説!定期テスト対策にも!【大学受験】 世界史の勉強法の実践におすすめの漫画の参考書⑥マンガで世界史が面白いほどわかる本

大学受験対策の世界史の参考書の中でもまだ世界史の勉強を始めたばかりの人や世界史の勉強がどうしても苦手という人におすすめがマンガで世界史が面白いほどわかる本です。
「マンガで世界史が面白いほどわかる本」(KADOKAWA)は、世界史の勉強法をゼロから始めたい高校生に最適な漫画形式の参考書です。
学校の授業を聞いていなかった人や、世界史の流れが全く分からない人でも、マンガと年表の両方を通してストーリーのように理解できます。
年表付きの構成になっているため、世界史のタテの流れを自然に把握でき、後の通史学習にもスムーズに進めます。
まずこの参考書で全体像をつかみ、その後に「山川世界史探究」(山川出版社)や「世界史探究」(KADOKAWA)へ進む学習ルートがおすすめです。
読むだけで世界史の全体像をつかめる入門書として、初心者が最初に手に取るべき世界史の参考書です。
▽世界史の勉強におすすめの漫画の参考書を知りたい方はこちら
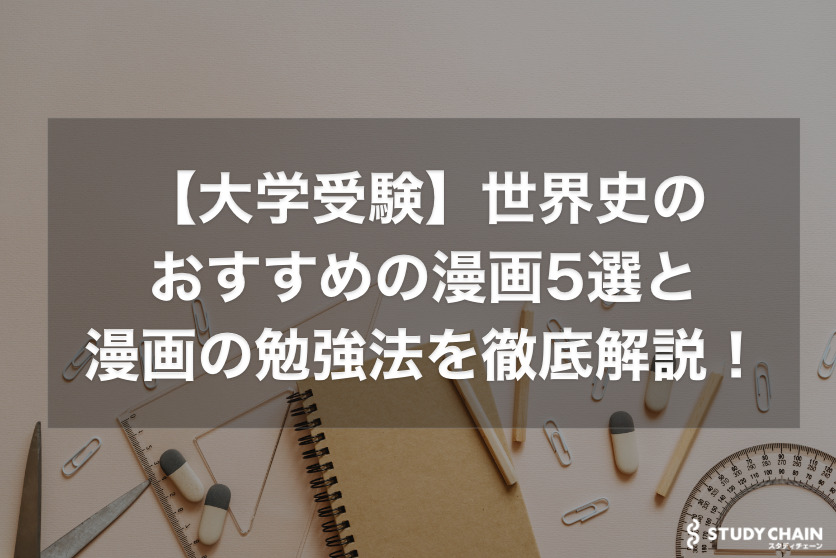 【大学受験】世界史のおすすめの漫画4選と漫画の勉強法を徹底解説!
【大学受験】世界史のおすすめの漫画4選と漫画の勉強法を徹底解説! 世界史の大学受験対策におすすめの参考書ルート
世界史の大学受験対策におすすめの参考書ルートを紹介します。
流れとしては、通史の基礎理解にしっかりと時間をかけて丁寧に行なった上で、年号+タテの流れ強化から横の流れ+地図理解など徐々にタテからヨコの流れまで全体の理解していけるようにしていくことが大学受験の世界史の偏差値UPの鍵です。
世界史の大学受験対策におすすめの参考書ルートは下記になります。
| 月 | 勉強内容 | 使用参考書(出版社) |
|---|---|---|
| 1〜2ヶ月目 | 通史の基礎理解(年号+用語中心) | 「世界史探究」(山川出版社 or KADOKAWA)/「時代と流れで覚える!世界史用語」(東進ブックス)/「東進 世界史一問一答 完全版」(東進ブックス)/初心者は「マンガで世界史が面白いほどわかる本」(KADOKAWA) |
| 3ヶ月目 | 年号+タテの流れ強化 | 「世界史年代サーキットトレーニング」(KADOKAWA)/「基礎問題精講」(旺文社) |
| 4ヶ月目 | 横の流れ+地図理解 | 「世界史一問一答地図」(東進ブックス)/「資料集」(山川) |
| 5ヶ月目 | 共通テスト過去問分析 | 「きめる!共通テスト世界史」(学研プラス)/「共通テスト過去問集」 |
| 6ヶ月目 | 現代史+難関大対策 | 「攻略世界史 近現代史・各国史」(Z会)/「HISTORIA」(Z会)/「志望校別過去問」 |
▽世界史のおすすめの参考書ランキングを知りたいという方はこちら
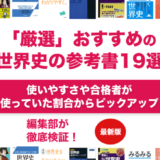 世界史のおすすめの参考書ランキング19選を東大生が徹底解説!【大学受験】
世界史のおすすめの参考書ランキング19選を東大生が徹底解説!【大学受験】 世界史のノートを使ったおすすめの勉強法
世界史のノートを使ったおすすめの勉強法を紹介します。
世界史の流れをつかむなら「年表ノート勉強法」
世界史の勉強法で流れを整理するなら、年表を自分で作るノート学習が最も効果的です。
世界史の参考書は「山川世界史探究」や「超効率!世界史年代サーキットトレーニング」を使い、タテの流れ(前後関係)とヨコの流れ(同時期の他地域)を1枚の年表ノートにまとめましょう。
例えば「フランス革命」と同時期に「産業革命」や「アメリカ独立戦争」がどう関係していたかを線で結ぶと、因果関係が明確になります。
この世界史ノートは試験直前の総復習にも使えるため、「読む→書く→見返す」のサイクルで記憶が定着する勉強法です。
世界史の理解を深めるなら「白地図ノート勉強法」
世界史の勉強法の中でも、地図を書いて整理するノート学習は特に効果的です。
「世界史一問一答(東進)」や「世界史 基礎問題精講」を使い、学習した範囲の地図を白紙ノートに自分の手で描き、国名・出来事・勢力範囲を書き込んでいきましょう。
例えば「ローマ帝国の領土」や「大航海時代の航路」など、地理と時代の対応関係を自分のノートにまとめることで、ヨコの流れと空間的な理解が一気に深まります。
ノートに地図としてアウトプットすることで、視覚的に記憶が定着するだけでなく理解度もかなり上がります。世界史の試験で地図問題が出ても迷わず解答できるようになります。
学年別に高校生におすすめの世界史の勉強法
学年別におすすめの世界史の勉強法を解説します。
高校3年生におすすめの世界史の勉強法
高校3年生が大学受験に向けて世界史を効率よく仕上げるには、まず通史を短期間で完成させることが最優先です。夏までに「山川 世界史探究」(山川出版社)や「時代と流れで覚える!世界史用語」(東進ブックス)を使い、世界史全体の流れを早めに固めましょう。
秋以降は「東進 世界史一問一答 完全版」(東進ブックス)で細かい用語や頻出語句を徹底的に暗記します。並行して「世界史年代サーキットトレーニング」(KADOKAWA)を使い、年号とタテの流れを整理しておくことで、入試本番での安定感が増します。
冬は過去問演習を中心に、間違えた問題をすぐに講義本や用語集で復習するサイクルを繰り返すことが合格への近道です。
高校2年生におすすめの世界史の勉強法
高校2年生のうちに取り組むべき世界史の勉強法は、早い段階で通史を1周し、歴史の流れを理解することです。この時期は暗記よりも、出来事の因果関係を意識しながら「なぜ起きたのか」を理解する勉強法が効果的です。
「山川 世界史探究」(山川出版社)で通史を進めながら、「世界史年代サーキットトレーニング」(KADOKAWA)で年号を少しずつ覚える習慣をつけておきましょう。また「東進 世界史一問一答 完全版」(東進ブックス)の星2レベルを早めに固めておくと、受験学年での演習に余裕が生まれます。
高校2年生のうちに基礎を固めておくことで、3年生からは問題演習と過去問対策にスムーズに移行できます。
高校1年生におすすめの世界史の勉強法
高校1年生は、世界史の基礎となる「全体の流れ」を早めにイメージできるようにすることが大切です。スタディサプリやTry ITなどの映像授業を活用し、まずは時代ごとのストーリーを理解する勉強法を取り入れましょう。この段階では完璧に暗記する必要はなく、「どの時代にどんな出来事があったか」を大まかに把握すれば十分です。
余裕がある場合は「山川 世界史探究」(山川出版社)を読み進めながら、「時代と流れで覚える!世界史用語」(東進ブックス)で復習するのがおすすめです。基礎理解と興味を育てる学習を積み重ねることで、2年生以降の本格的な暗記・演習にスムーズに入れます。
中学生におすすめの世界史の勉強法
中学生におすすめの世界史の勉強法としては、ヨコの流れよりもタテの流れが正確に覚えられているかで差がつくのが中学生だからこそ、ノートをフル活用して、試験範囲の年表を教科書などを読みながら、作成してみることをおすすめします。
実際に自分の手でノートに年表を作ることでこれまで気づけていなかったタテの流れを把握できるだけでなく、なぜその事件が起きたのかやその人物はどういう思想や目的を持っていたのかなどを理解できるようになります。
大学受験の勉強法を他の教科ももっと詳しく知りたいという方はぜひ下記を参考にしてみてください。

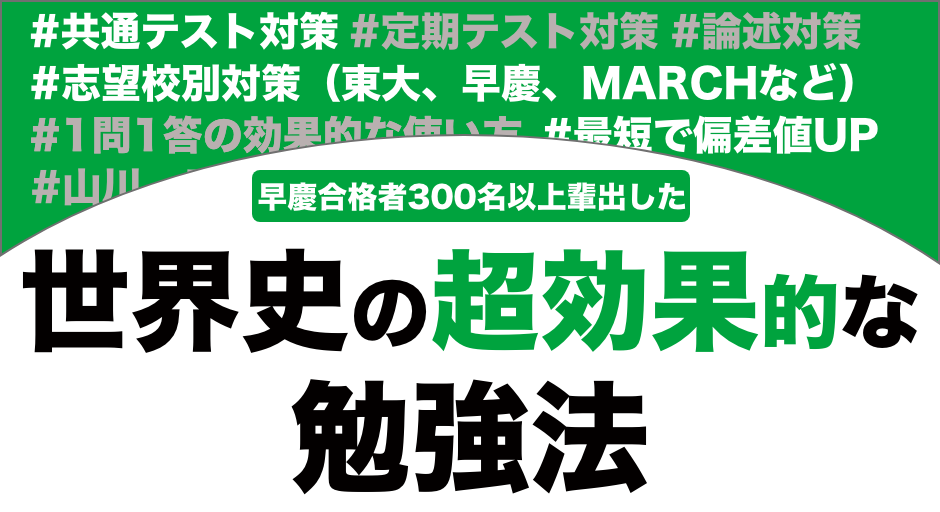

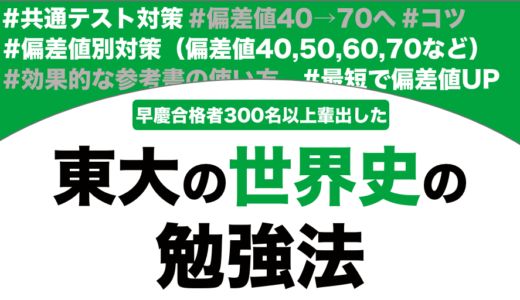
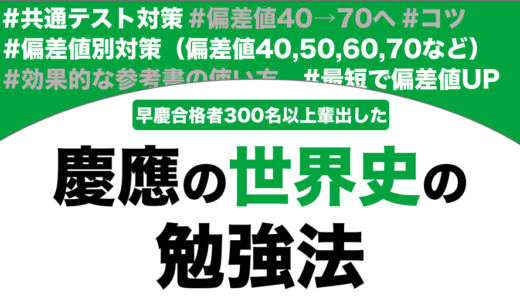
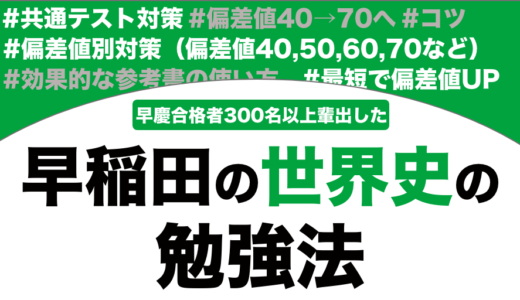
-520x300.png)