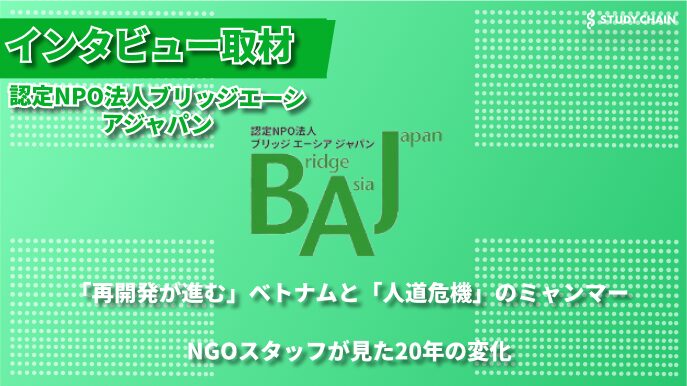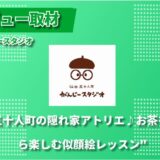貧困地域の子どもたちを支援することから始まり、今では環境教育を中心とした活動へと発展しているベトナム。一方で、2021年のクーデター以降、深刻な人道危機に直面し、支援すら届きにくい状況が続くミャンマー。1993年の設立以来、両国で支援活動を続けている認定NPO法人ブリッジ エーシア ジャパンの新石さんに、現地の様子や支援における課題についてお伺いしました。

20年以上に渡るベトナムでの環境教育支援活動
ーまずは御社の活動内容について教えていただけますでしょうか?
新石さん:私たちは国際協力を行うNGOとして1993年に設立され、今年で31年目を迎えます。主な活動地域はベトナムとミャンマーです。教育関連の事業については、特にベトナムで長年取り組んでいます。
ベトナムでは環境教育事業を20年以上継続しています。2000年代初頭、活動を開始した当時のベトナムでは、都市部の周縁に貧困地区が形成されていました。職を求めて地方から人々が流入し、不法居住地域が形成される状況でした。特に世界遺産のある街フエでは、城壁沿いや水上で生活する人々も多く存在していました。
貧困地域の子どもたちへの教育支援から環境教育へ
ー具体的にはどのような活動を行ってきたのでしょうか?
新石さん:当時、そうした地域の子どもたちの教育状況に関心を持ち、調査を進めたのがきっかけです。貧困地域の子どもたちは、親が早く働くことを望むため、十分な教育を受けられない状況にありました。また、学校で差別を受けることもあり、ドロップアウトする子どもも多かったのです。
そこで私たちは、これらの子どもたちを対象に、就学支援と環境教育を組み合わせた活動を展開しました。例えば、子どもたち自身がゴミ問題について調査し、リサイクル活動を行い、その収益で地域の水道設備や街灯を整備するといった取り組みです。この活動を通じて、子どもたちは自信をつけ、地域の環境改善にも貢献することができました。
時代とともに変化する支援の形
ーベトナムの発展に伴い、支援の形も変化したのでしょうか?
新石さん:2010年代に入ると、ベトナムは大きく変化しました。具体的には国際的なスポーツイベントなどを契機に再開発が進み、かつての貧困地区は次々と整備されていきました。不法居住者たちにも正式な住所が与えられ、私たちが支援していたコミュニティ自体が解消されていったのです。
そして嬉しいことにそれまでの私たちの活動を評価した現地の教育関係者から、学校での環境教育実施の要請を受けるようになり、現在は3つの小中学校で月1回程度、環境教育の授業を実施しています。
以前は船上生活者の子どもたちを対象としていた活動が、今では一般の教室で環境教育を行うというように形を変えて続いているのです。
新たな課題:オンライン教育と学びの定着
ー現在の環境教育における課題は何でしょうか?
新石さん:現在の課題の一つは、環境教育の内容をいかに子どもたちに定着させるかということです。インターネットの普及により、環境教育に関する情報へのアクセスは容易になりましたが、それが本当の意味での学びにつながっているかという課題があります。
特にコロナ禍でオンライン授業を実施した際、この課題が顕在化しました。私たちは工夫を重ねてオンライン授業を行いましたが、後日の調査で子どもたちの印象に残っていたのは、むしろコロナ前の体験型の授業でした。知識を効果的に定着させ、深い学びにつなげていくことの難しさを実感しています。
ミャンマーの現状:深刻な人道危機
ーミャンマーの現状についてお聞かせください。
新石さん:現在のミャンマーは非常に厳しい状況にあります。最近の調査では、世界で最も深刻な人道危機に直面している国のワースト3位に挙げられました。2021年のクーデター以降、国内の紛争が激化し、現在では350万人以上の国内避難民が発生しています。
ミャンマーは135もの民族が暮らす多民族国家です。2011年に軍事政権から民主化を果たし、「奇跡の10年」と呼ばれる平和な期間がありました。しかし、2021年の選挙結果を巡る対立がクーデターに発展し、それまで抑制されていた民族間の対立が表面化してしまいました。
支援活動の困難さと私たちにできること
ー私たちにできる支援はありますか?
新石さん:まず、ミャンマーの状況を忘れないでいただきたいと思います。NGOや国際機関は様々なルートを駆使して活動を続けています。そうした団体の情報発信に注目し、活動を支援していただければと思います。
また、多くのNGO・NPOは常にファンドレイジングに苦心しています。少額であっても、継続的な支援は団体の活動を支える大きな力となります。加えて私たちの場合、ウェブサイトやSNS、年に1回程度のクラウドファンディングで情報を発信しています。月2回発行しているメールマガジンでは、より詳しい現地の状況をお伝えしていますのでぜひ活動に注目して頂けますと幸いです。
今後の展望:教育を通じた持続可能な社会づくり
ー今後、特に注力して取り組んでいきたいことについて教えてください。
新石さん:ベトナムについては、日本の教育現場との交流を深めながら、より質の高い環境教育プログラムの開発を目指しています。子どもたちが生き生きと学べる環境教育の在り方を、現地の教育関係者と共に模索していきたいと考えています。
ミャンマーについては、現在の困難な状況の中で粘り強く活動を継続していくことが重要だと考えています。特に、支援を必要としている人々に確実に援助を届けられる方法を模索し続けていきます。
そして両国に共通する課題として、持続可能な社会づくりのために必要な教育とは何かを考え、実践していくことを大切にしています。皆様からのアイデアやご意見もいただきながら、より良い活動を展開していければと思います。
読者の皆様へのメッセージ
ー最後に、記事を読んでいる方へメッセージをお願いします。
新石さん:本日は、ベトナムとミャンマー、二つの国における私たちの活動についてお話しさせていただきました。発展を遂げ、環境教育に力を入れるベトナムと、深刻な人道危機に直面するミャンマーでは、現状や課題が大きく異なります。
読者の皆様にはそれぞれの国の状況に関心を持っていただき、共感できる部分から関わっていただければ幸いです。ベトナムでは、より良い環境教育の実現に向けて、皆様のアイデアやご意見を歓迎しています。ミャンマーについては、現地の状況を心に留めていただき、できる範囲での支援をご検討いただければと思います。
私たちは月2回のメールマガジンで現地の詳しい状況を発信しています。より深く活動を知っていただき、共に国際協力の輪を広げていければ幸いです。小さな一歩でも、継続的な関心と支援が、確実に現地の人々の力になっていきます。