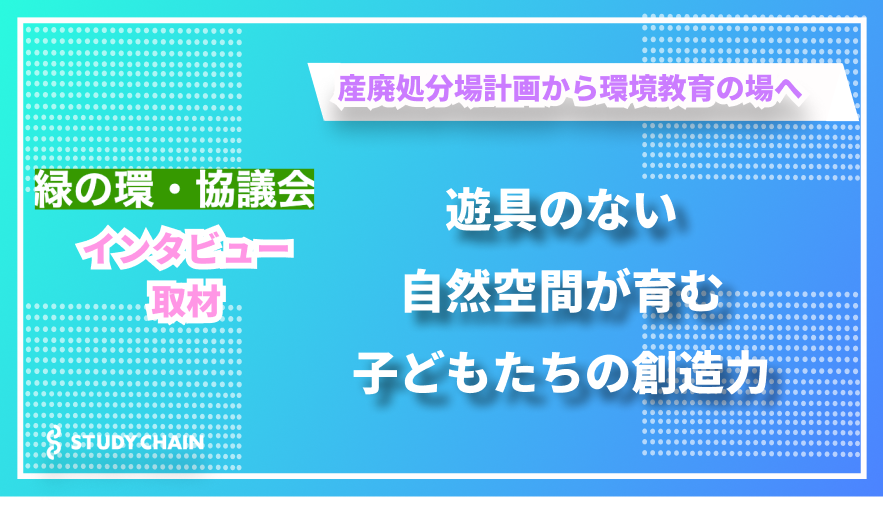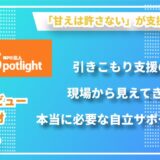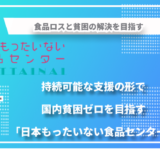山砂の違法山砂採取により荒廃した土地を、地域住民の手で元の水源涵養林に戻す活動を行う「特定非営利活動法人緑の環・協議会」。
20年近い活動の中で自然環境の保護・再生と共に、子どもたちの自然体験や環境教育の場として発展してきた取り組みについて、金井さんにお話を伺いました。
違法山砂採取跡地の再生から始まった環境保護活動

ー団体の概要と主な活動内容について教えてください。
金井:私どもの活動の中心は、違法山砂採取により荒廃した土地を元の水源涵養林に戻すことです。2006年頃から活動を開始し、自然保護活動と共に、自然の中でさまざまな体験ができる場を提供しています。
子どもの自然体験や環境教育の場としても活用され、保護者の方々と一緒に植林活動を行うなど、多くの方々にご参加いただいています。
参加者は子どもに限らず、自然保護活動に興味のある大人の方も多く、むしろそちらがメインとなっています。活動を通じて、世代を超えた交流も生まれています。
地域住民の反対運動から環境再生へ
ー活動を始められたきっかけについて教えてください。
金井:この場所は建設用の山砂を違法に採取され、大きな穴が開いた状態で放置されていました。その後、産業廃棄物処分場として利用する計画が持ち上がりましたが、地域住民による反対運動の結果、地元の組合が競売で土地を取得しました。
反対運動に携わった私たちは、この荒廃地をどうにかしなければと考え植林活動を始めました。現在までに約3,000本の苗木を植え、10年以上が経過した木々は人の背丈を超えるまでに成長しています。
もし、そのまま放置していれば不法投棄の温床となる可能性があったため、地域の環境保全のためにも私たちの活動は重要な意味を持っています。
自然と共に成長する環境教育
ー子どもたちの参加を募った経緯についてお聞かせください。
金井:この場所はプレイパークの考え方に基づき、子どもたちが自由に遊べる自然空間としても活用しています。遊具などは特に設置せず、自然の中で子どもたち自身が遊び方を見つけられる環境を大切にしています。
例えば、どんぐりから苗木を育てる「千の苗プロジェクト」では、近くの公園に出かけ親子が競争でドングリを拾いました。
苗ポットにセットしたドングリを各家庭に持ち帰ってもらい、子どもたちが家庭で苗木を育て、成長を楽しみにしながら水やりを続けました。
翌年の春にポットから植えつけられた苗木の数は1,000本を優に超えましたが、自然の中ではさまざまな要因で育たないものも多く、その過程自体も大切な学びとなっています。
また、被爆アオギリ2世の苗木を育てる活動も行っています。広島の原爆投下で被害を受けながらも翌年に芽吹いた被爆アオギリの種から育てた苗木は、現在では27本ほどが成長し、平和への祈りと復興のシンボルとして大切に育てられています。
私達は何も無くなったこの場所で、苗木を育てるのとともに子どもたちも育てているのです。
自然との直接的な触れ合いを重視
ー他の環境教育を行う団体との違いや、独自の取り組みがあれば教えてください。
金井:私たちの特徴は、あえて特別な道具や設備を用意せず、自然そのものと触れ合える場所を提供していることです。子どもたちは自分たちで秘密基地を作ったり、虫を観察したりと、自由に遊びを見つけています。
バッタやセミ、カブトムシなどの昆虫や、時にはウサギの姿も見られ、子どもたちは自然の中で多様な生き物との出会いを体験できます。私たちスタッフは必要以上に介入せず、子どもたちが自然と向き合い、自ら考え遊び方を見つけていく過程を大切にしています。
未来に向けた自然保護活動の展望
ー今後の展望についてお聞かせください。
金井:生物多様性の回復を目指し、トレイルカメラの設置など、夜間に訪れる動物たちの観察も始めています。
また、活動をより充実させるため、手押しポンプ付きの井戸を掘る工事も進めています。現在は水道も電気もない環境ですが、井戸が完成すれば、より多様な活動が可能になると期待しています。
ー最後に、読者の方へメッセージをお願いします。
金井:この活動は小さな取り組みかもしれませんが、世界中で同じような活動が行われることで、未来の世代に豊かな自然を残すことができます。
私が大学を卒業した頃と比べて、世界の人口は80億人と2倍になり森林は急速に減少しています。人口増加や環境破壊が進む中、たとえ2ヘクタールという小さな面積でも、自然を守り再生させる活動を続けていくことが重要です。
私たちの活動地では、GoogleMapの航空写真で見ると、活動開始当初と比べて森林が明らかに回復していることがわかります。このように、一歩一歩着実に自然を再生させていく取り組みを、次世代へとつなげていきたいと考えています。