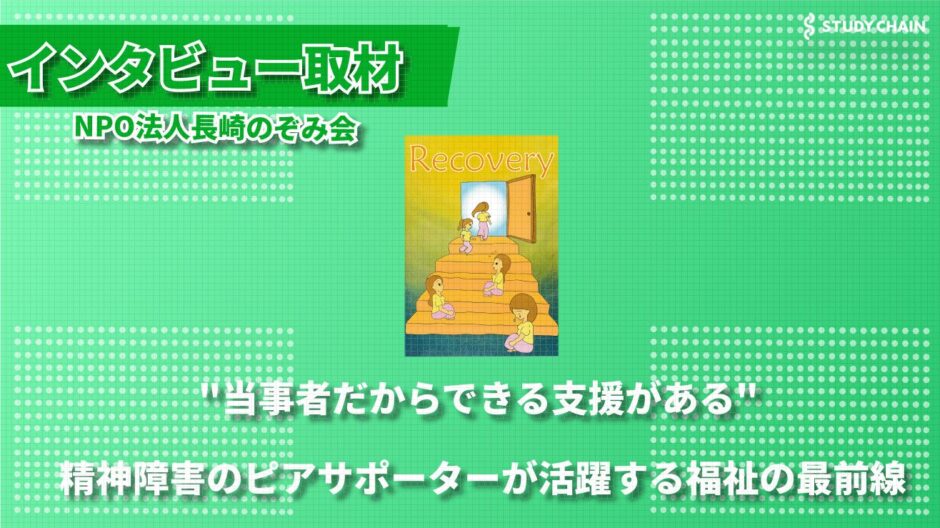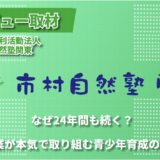支援する側と支援される側という従来の枠組みを超えて、精神障害を抱える当事者がピアサポーターとして活躍する場を作り上げてきたNPO法人長崎のぞみ会。医療、福祉、そして一般社会をつなぎ、誰もが自分らしく生きられる社会の実現を目指している理事長の河野さんにインタビューしました!

地域に根差した精神障害者支援の拠点として
ーNPO法人長崎のぞみ会の活動内容について教えてください。
河野さん:基本的には地域に住まわれている精神障害を抱える方の通所支援が中心です。就労を目指している方もいれば、居場所としてこられている方など、様々な目的を持った方が利用されています。
年齢層も20代から70代まで幅広く、現在約60名の方が登録されている状況です。プログラムを中心とした活動を展開しており、一人一人の目標や状況に合わせた支援を心がけています。
設立からの歩みと現在の支援内容
ー共同作業所としての活動内容と、その変遷について教えてください。
河野さん:当施設は長い歴史を持っており、設立当初は障害のある方が商品を作って販売する作業活動が中心でした。しかし、現在はそういった収入が発生する作業はほぼなくなりつつあり、支援の形も大きく変化してきています。
現在特に力を入れているのが、就労を目指す方への準備段階としての支援です。生活リズムを整えることや、人とのコミュニケーションを取る練習など、社会参加に向けた基礎的なスキルの習得を重視しています。来年からは施設の名称も変更を予定しており、より現在の支援内容に即した形への転換を図っています。
河野さんの参画経緯と想い
ー河野さんがNPO法人長崎のぞみ会に携わるようになったきっかけを教えていただけますか?
河野さん:現在、理事長として運営に携わって8年目になります。きっかけは大学院生時代にボランティアとして参加したことでした。当時、精神科領域での活動を志していた私は、病院での勤務を考えていましたが、指導教授からの勧めで地域支援の現場を知る機会を得ました。
約半年間のボランティア活動を通じて、地域での支援に大きな可能性を感じたと同時に、前任の方から引継ぎの打診を頂いたのです。卒業したばかりで経験も浅く、不安もありましたが、新しいことへの挑戦という気持ちと、地域支援への強い想いから、団体の運営を引き継がせていただくことを決意しました。
ピアサポーターの活用による特徴的な支援体制
ー長崎のぞみ会様の特徴的な部分やアピールポイントを教えてください。
河野さん:当法人の大きな特徴は、昨年度まで長崎市の委託事業として精神障害者ピアサポーターの養成に取り組んできたことです。現在は、支援スタッフの半数以上が精神障害を抱えながら支援現場で活躍するピアサポーターとなっています。
私は専門職という立場ですが、当事者の方々と共に支援を行うことで、より深い理解と効果的な支援が可能となっています。現在は、精神科病院などの医療機関にもはたらきかけ、医療現場でもピアサポーターの方が活躍できる環境づくりを進めているところです。
利用者に寄り添う支援の姿勢
ー利用者様とのコミュニケーションで特に意識されていることはありますか?
河野さん:基本的には利用者様を尊重する姿勢を何よりも大切にしています。完璧な言葉遣いというのは難しい部分もありますが、常に対等な関係性を意識しています。
また私自身、「もし自分が利用する立場になったとしても心から頼りたいと思える施設でありたい」というイメージを持ちながら日々の活動に取り組んでいます。利用者の平均年齢は40代前半で、30代から50代の方が中心となっていますが、それぞれの年代に応じた適切なコミュニケーションを心がけています。
利用方法と今後の展望
ー利用を希望される方への案内と、今後の展望についてお聞かせください。
河野さん:利用にあたっては所定の手続きが必要です。条件として、精神科の病院またはクリニックに通院されていることが必要となります。まずは面談を通じて、その方の状況や目的をお伺いし、当施設での支援が適切かどうかを慎重に判断させていただいています。
今後の展望としては、現在の福祉領域での活動に加えて、医療機関との連携も強化していきたいと考えています。最終的には、福祉、医療、一般社会が密接につながり、精神障害を抱える方の就労を含めた社会参加が当たり前となる社会づくりに貢献していきたいですね。また、差別や偏見のない、誰もが互いを理解し合える社会の実現に向けて、啓発活動にも力を入れていきたいと思います。
精神障害を抱える方々へのメッセージ
記事を読んでいる方に向けたメッセージをお願いします。
河野さん:精神障害を抱えると、周囲の理解を得ることが難しく、様々な苦労があることと思います。当施設では、前向きに捉え直すことが出来る様々な機会を提供したいと考えています。
また、ピアサポーターとして活動することに興味がある方には、研修の案内や経験の機会も提供しています。現在は直接的なピアサポーター養成は行っていませんが、連携している機関を通じて、必要な研修や情報提供を行うことができます。皆様の「経験」を「強み」に変えていける場所として、お気軽にご相談いただければと思います。