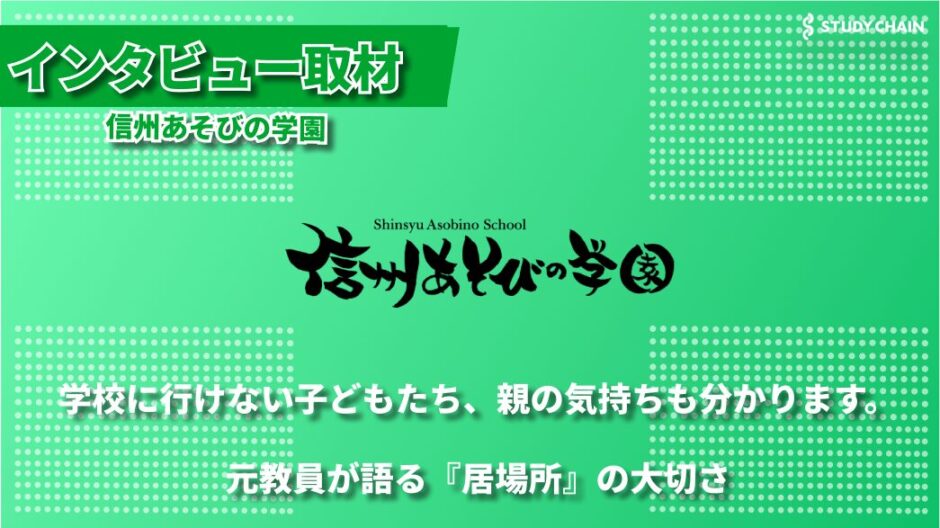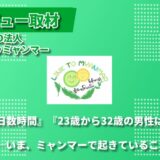不登校の子どもたちやその保護者が安心できる居場所を目指して設立された信州あそびの学園。代表の駒村さんは、15年の活動を通じて、一人ひとりに寄り添った支援を続けてきました。今回は、自然豊かな環境の中で行われる独自の取り組みについて代表の駒村さんにインタビューしました!

サービス概要
ー信州あそびの学園のサービス内容について詳しく教えていただけますでしょうか。
駒村さん:当学園は、不登校の生徒さんやその保護者の方々をはじめ、心の居場所を求めているすべての方に門戸を開いているフリースクールです。学校への通学の有無は問いません。何より大切にしているのは、一人ひとりが自分らしさを見つけられる環境づくりです。
活動は3つのフィールドを展開しております。一つ目は、個々の状況に合わせた学習指導。二つ目は、整備した森での自然体験活動。そして三つ目が、マインクラフト教育版を活用したオンラインでの活動です。これらのフィールドは独立しており、生徒さんの希望や状況に応じて自由な選択が可能です。
開所時間は月曜日から金曜日の午前9時から午後4時までを基本としています。ただし、生徒さんの状況に応じて柔軟な対応を心がけています。
例えば小学生は週1回1時間通っており、中学時代に毎週通っていた生徒さんは高校中退後、現在は2週間に1回2時間参加しています。水曜日の開放日は、オンラインスクール会員は誰でも参加して自由に楽しめる時間ですが、アカウントやプライバシー保護の観点から「会員以外は参加不可」です。
なお、オンラインスクールへの入会前に体験を希望される方もいますが、こちらも会員のプライバシー保護の観点から入会前はお断りしています。オンラインスクールの活動は、Youtubeのあそびの学園のチャンネルで動画を公開しているので、そちらを見ていただくようにしています。
こちらがチャンネルです。
https://www.youtube.com/@asobinogakuen
設立の経緯
ー信州あそびの学園を立ち上げられたきっかけを詳しく教えていただけますでしょうか。
駒村さん:私は音楽教師として教壇に立っていた時期に、クラスに馴染めない生徒さんの増加を目の当たりにしました。音楽の授業は比較的受け入れやすい環境でしたが、専科教員という立場上、保護者との関わりが限られており、十分なサポートができない状況に課題を感じていました。
その後、私自身のうつ病の経験や、実子の不登校など、様々な経験を重ねることとなり、特に印象的だったのは、病弱養護学校での勤務経験です。自然に囲まれた環境の中で、生徒たちが見せる穏やかな表情との出会いが、大きな転機となりました。現代社会では、外遊びや自然との触れ合いの機会が減少している中で、このような環境での居場所づくりの必要性を強く実感し、このサービスを開始することを決意しました。
教室としての特徴
ー信州あそびの学園の特徴について教えていただけますでしょうか。
駒村さん:最大の特徴は、私自身が教員、保護者、そして心の不調を経験した者として、多面的な視点からサポートできることです。実際に教員時代に息子が不登校になるという複雑な経験もしました。周囲の先生方からは、教員でありながら自分の子どもが不登校になったことについて、様々な見方をされました。
そのため生徒さんや保護者の方、心の不調を抱える方々の相談に対して、その立場に立って寄り添うことができます。また、長年の教員としての経験を活かした学習指導も当学園の強みです。
生徒と関わる際に気をつけていること
ー生徒さんや保護者の方との関わりで特に気をつけていることはございますか。
駒村さん:最も大切にしているのは、相手を否定しないという姿勢です。例えば、妄想的な思考に囚われている方であっても、その人にとってはそれが紛れもない現実です。その世界観を否定せずに受け止めながら、私たちの立場からの見方も丁寧に伝えるようにしています。
特に自然の中での活動では、それぞれがありのままでいられる環境づくりを心がけています。様々な状態があって当たり前で、それぞれの状態を受け入れる—そんな世界を大切にしています。
今後の展望や取り組みについて
ー今後の展望についてお聞かせいただけますでしょうか。
駒村さん:2008年に学校を退職してから約15年、不登校への理解を求めて活動を続けてきましたが、長野県では昨年からフリースクール認定制度がスタートし、私たちは第1回の認定をいただくことができました。ここまでの道のりは決して平坦ではありませんでしたが、ようやく社会的な認知が進んできた実感があります。
しかしながら、学校や公的機関、社会全体の理解はまだまだ十分とは言えない状況です。残念ながら、自死率も依然として高い水準にあります。私たちは、より多くの方々に届く場所となることはもちろん、この活動を通じて、一人ひとりが自分の居場所を見つけられる機会が増えていく社会の実現を目指しています。
記事を読んでいる方に向けたメッセージ
ー最後に、支援を求めている方々へメッセージをお願いいたします。
駒村さん:辛い時は「自分だけが」という気持ちに囚われがちです。特に不登校の場合、親は子どもを心配し、子どもは親を心配する—そんな状況の中で、お互いへの気遣いから本音を言えなくなってしまうことが少なくありません。
どうか、遠慮なく相談してください。最初は辛い気持ちを吐き出すだけでも構いません。「こんなことを言ったら恥ずかしい」「駄目な人間だと思われる」という気持ちがあるかもしれませんが、誰かに話すことで必ず心が軽くなります。
私たちは、そうした思いを受け止める場所の一つとして存在しています。気軽な世間話でも構いません。メールや手紙など、どんな形でも、あなたの声を待っています。必ず、どこかで受け止めてくれる人がいることを、どうか忘れないでください。