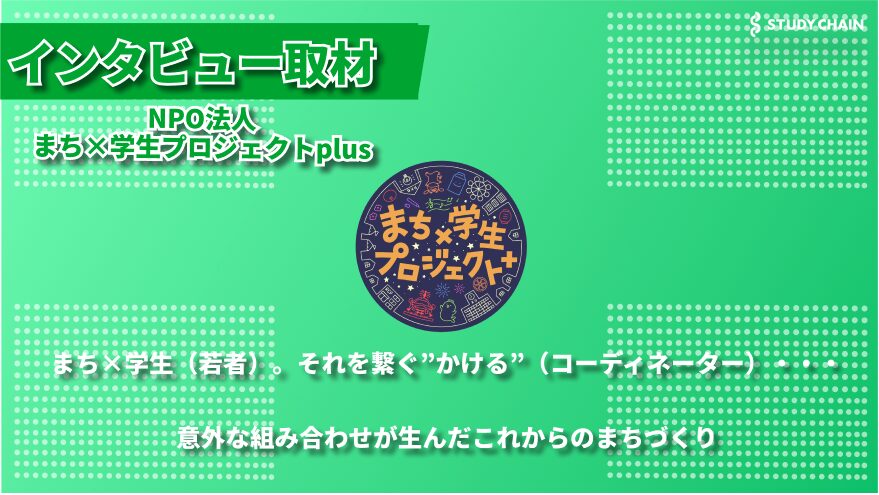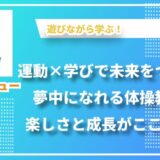「学生はまちの活気を生む存在」。この発見から始まったNPO法人まち×学生プロジェクトplusは、横浜市神奈川区を拠点に独自のまちづくり活動を展開しています。発足した2016年当初は六角橋の地域住民や神奈川大学の学生などで行われていた活動は、今や地域も年齢も超えて広がりを見せています。住民と若者をつなぎ、活動を通して「世代を超えて想いをつなぐ『まち』づくり」を実現する取り組みに迫ります。

NPO法人まち×学生プロジェクトplusの概要
ー御社の活動内容について教えていただけますか?
小倉さん:私たちの団体名は、その名の通り「まち」と「かける(コーディネーター)」と学生が協働するという意味を持っています。その中で、年齢や時間軸の価値観が異なる複数の主体を調整する、「かける(コーディネーター)」という存在に名前をつけて、意識している点も特徴です。。2016年に任意団体として活動を開始し、コロナ禍を経て、想いで繋がる組織として法人化を決意しました。
活動の中心となるのは学生ですが、実際には若者全般を指しています。私自身も社会人5年目ですが、地域住民からすれば学生も若手社会人も同じ若者として見られているかもしれません。特徴的なのは、自治体や企業だけでなく、自治会と密接に連携して活動を行っている点です。
基本的には学生や若者とまちが協働し、その間に立つ「かける」というコーディネーターが存在します。この3者が連携することで、まちづくりというテーマに取り組んでいます。
主要な活動内容:オレンジプロジェクトとキャンドルナイト
ー具体的にどのような活動をされているのでしょうか。
小倉さん:現在、主力となっている活動が「オレンジプロジェクト」と「キャンドルナイト」です。コロナ禍以前は年間4つの大きな企画を実施していましたが、現在はこの2つが中心となっています。
オレンジプロジェクトは認知症啓発活動です。活動拠点である横浜市神奈川区六角橋の商店街を舞台に、オレンジ色(認知症見守りのテーマカラー)を用いた啓発活動を展開しています。具体的には、認知症サポーター養成講座の実施や、飲食店でのコースター・ランチョンマットを活用した啓発(健康維持のための)など、誰もが住み続けたいと思えるまちづくりを目指しています。
キャンドルナイトは7年目を迎える大規模イベントです。特徴的なのは、牛乳パックを使用してキャンドルホルダーを作る点です。牛乳パックは組み立てると家の形になり、それが集まることで「一日限りのまち」が創出され、「近所」や「みまもり」といった「まちづくり」に関わる要素をイメージしています。小さな子どもから大人まで、誰もが参加できる形でまちづくりについて考えるきっかけとなっています。
その他にも、横浜市内や藤沢市などの行政・団体とコラボした取り組みなども最近は増えてきています。
活動のきっかけと歩み
ー活動を始められたきっかけを教えていただけますか?
小倉さん:活動は神奈川大学周辺地域から始まりました。大学は住宅街の中心に位置し、約2万人の学生が通う総合大学です。当初は学生と地域住民との間にトラブルもあり、学生たちは地域との関わりを避ける傾向にありました。
しかし、地域のケアプラザのコーディネーターである原島さんの提案で、学生と地域住民が一堂に会する機会が設けられたのですが、そこで、学生の存在が防犯やまちの活気づけに貢献しているという、予想外の評価を得ることができたのです。これをきっかけに、若者の力を必要としている地域と、活動の場を求める学生とのマッチング、本プロジェクトが始まりました。
イベントの開催日時
ーキャンドルナイトはいつ開催されているのでしょうか?
小倉さん:キャンドルナイトは毎年11月末に開催しています。2024年で7回目を迎え、年々参加団体も増えています。地域の幼稚園から一般企業まで、様々な団体が参加して六角橋のまちを照らしています。特に注目すべきは、牛乳パックで作るキャンドルホルダーを使用する点です。最終日の金曜日にキャンドルナイト参加団体の多くが集まる神奈川大学横浜キャンパスにおける「一斉点灯」は圧巻です。
7年目となる現在では、参加団体それぞれが工夫を凝らし、より精巧な作品を制作するようになりました。
また、オレンジプロジェクトは年間を通して実施しており、特に春から夏にかけては認知症サポーター養成講座や、商店街での啓発活動を積極的に展開しています。六角橋商店街の各店舗と協力して、コースターやランチョンマットを活用した継続的な啓発活動を行っています。
団体の特徴やアピールポイント
ー他の地域活動団体とは異なる特徴について教えてください。
小倉さん:最大の特徴は、自治会との密接な連携です。多くの地域活動団体が企業との協働を中心としている中、私たちは地域住民との直接的な関係構築を重視しています。特に六角橋地区の自治連合会長を務められた森さん(現理事長)の「まちづくりは住んでいる人間が自分のまちをこうしていきたいと思って作っていくもの」という言葉が、私たちの活動の根幹にもなっています。
また、参加する若者の年齢や所属を限定せず、「思い」で繋がることを大切にしている点も特徴です。神奈川大学の学生だけでなく、横浜市内の様々な大学の学生が参加するようになり、活動の輪は藤沢や千葉の柏にまで広がっています。さらに、社会人になったOBも運営に関わり続けるなど、持続可能な活動基盤を築いています。
活動でさまざまな人と関わる際に意識していること
ー活動に参加される方々と関わる際に、特に意識されていることはありますか?
小倉さん:私は大学1年生からこの活動に参加し様々な経験をさせていただきましたが、まちづくりの活動において最も大切にしているのは、本気で取り組む姿勢です。正直なところ、まちの人々が学生を受け入れてくれるのは少数派だと思います。地域の定例会に突然学生が参加することに対して、「2、3年したらいなくなる」と最初は理解されないこともあったと聞いています。
しかし、自治連合会長だった森さんをはじめとしたまちの理解や、コーディネーターの原島さんのサポートもあり、今ではこの活動を応援してくださる人もとても多いです。この活動を続けることで、「子育ての時など、いつかこのまちに戻ってきたい」と思ってもらえるようになりました。
就職活動などを考えると実質の活動期間は2年ほどしかない学生も多く、イベントやメディア掲載などで終わらせたい気持ちもあるかもしれませんが、まちの人々にとっては、ここで暮らし続けていく場所なのです。
現在は事務局長として、様々な団体と関わる立場になりました。特にキャンドルナイトでは、幼稚園から企業まで多くの方々が時間を割いて参加してくださっています。社会人として仕事と両立しながらの活動ですが、それを言い訳にはできません。この気持ちは学生たちにも伝えていきたいと考えています。
今後の展望
ー今後、どのような活動を展開していきたいとお考えですか?
小倉さん:神奈川大学の周辺から始まった活動は、現在、横浜市内の様々な大学の学生が参加するようになり、活動範囲も藤沢や千葉の柏にまで広がっています。この広がりは非常に良い流れだと感じています。
次のステージとして注目しているのは、世代を超えた循環の創出です。例えば、キャンドルナイトでは、かつて幼稚園生として参加していた子どもたちが中学生になり、実行委員として運営に関わるようになったりというのが、来年で10年目を迎えるこの活動の次のステージだと思っています。また、卒業したOBが理事として運営に携わるなど、様々な立場での関わり方が生まれています。
このように、年齢や立場を超えて活動に関わることのできる仕組みを、さらに充実させていきたいと考えています。それぞれの経験や視点を活かしながら、より良いまちづくりを実現できる、そんな循環を作っていきたいと思います。
参加・支援を考えている方々へのメッセージ
小倉さん:私たちは「想いで繋がる」ことを大切にしています。距離や所属に関係なく、やりたいという想いがある方々との協働を歓迎しています。特に、私個人の経験からですが、若手社会人の方々にとってこの活動は人生を豊かにする機会になると考えています。ここでしか出会えない人々、ここでしか得られない経験があります。
活動に関する情報は主にFacebookで発信しており、今後はInstagramなども活用していく予定です。興味を持たれた方は、ぜひご連絡ください。一緒に活動できることを楽しみにしています。
公式ホームページ:https://www.matikake.yokohama/
公式Facebook:https://www.facebook.com/matikake.plus/
公式Instagram:https://www.instagram.com/mati.gakusei.plus/
キャンドルナイトInstagram:https://www.instagram.com/candle_matikake/