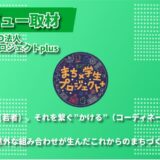海の生き物たちを守るには、実は陸の環境も大切です。特定非営利活動法人海の環境教育NPO bridgeは、海の自然を切り口に、地球環境全体への理解を深める教育活動を展開しています。無料で提供される教材、都心での体験学習、最新の学習方法など、次世代に向けた新しい環境教育のあり方を模索する同法人の活動に迫ります。

海の環境教育を通じて、持続可能な社会の実現を目指す
ー環境教育の中で「海」を選んだ理由を教えてください。
伊東さん:特定非営利活動法人海の環境教育NPO bridgeは、海の自然、持続可能な社会に向けたアクションに繋がる学びをサポートする環境教育団体です。なぜ「海」を通じた環境教育なのか。その理由は、海の生態系が持つ特徴にあります。
海の生態系は、シャチや白熊などの大型捕食者から、イルカ、タコ、魚、そして植物まで、陸上の生態系と同様のピラミッド構造を持っています。しかしその大きな違いは、海の生態系を支える基盤となる植物の栄養が、森や陸上の様々な場所から供給されている点です。森で作られる腐葉土や、岩石の間を水が通ることで栄養が流れ出し、海の生態系を支えているのです。
このことは、海の環境保護の特徴的な側面を示しています。例えば、クジラなど特定の海洋生物を守りたいと考えた時、餌となる生物や、その餌の餌となる生物の生息環境、つまり植物の生息環境の保全が必要となり、最終的には陸上の環境全体を考える必要が出てくるのです。このような観点から海は地球全体の「人間活動と自然」の相互関係に深く関わりがあると考え、環境教育の中で「海」を選択しました。
「LAB to CLASS」プロジェクト―教材開発の革新的アプローチ
ーLAB to CLASSプロジェクトについて詳しく教えてください。
伊東さん:当団体の主な活動は、環境教育教材の制作・普及、環境学習・探究学習のプログラムの企画指導、企業・自治体向けの研修やイベントの実施です。特に注力しているのが「LAB to CLASS」プロジェクトです。
このプロジェクトは、海辺の環境教育フォーラムという、全国の海をフィールドとした環境教育実践者、水族館学芸員、大学研究者、学校教員などによる緩やかなネットワークから生まれました。それぞれの現場で開発された優れた教材を集め、より多くの人々が活用できるよう再編集して提供しています。現在、ウェブサイトでは31の教材を無料でダウンロードできます。
「LAB to CLASS」という名称には、フィールドや研究室(ラボ)での発見、知見を教室などの学習の場(クラス)に届けたいという思いが込められています。研究者やフィールドワーカーとの対話の中で感じる発見の喜びや環境問題の緊迫感を、そのまま学習の場に持ち込むことを目指しています。
革新的な教材開発―体験を通じた学びの実現
ー具体的にどのような教材を開発されているのでしょうか。
伊東さん:開発された教材の代表例の一つに、サンゴ礁や干潟の大型ジグソーパズルがあります。海を見ると、どこまでも続く変化の乏しい「水面」にしか見えませんが、海の中には驚くほど多様な生物の世界が広がっています。このパズルを協力して組み立てることで、身近な海の生態系の豊かさを実感できる仕掛けになっています。
また、「餌の餌の餌は何?」という食物連鎖を学ぶカードゲームも開発しました。日本の様々な海域の食物連鎖を10種類用意し、サンゴ礁から北方の海まで日本の海の生物多様性を学べるようになっています。このゲームを通じて、マイクロプラスチックが食物連鎖を通じて生物や人体に与える仕組みについても理解を深めることができるでしょう。
さらに、「森と海のつながり」を学ぶ大型すごろくも制作しました。教室に広げて生徒自身が駒となって進む体験型の教材で、森と海と人間関係の密接な関係を体感的に学ぶことができます。
教育格差の解消を目指して
ー教材を無料で提供されている理由を教えてください。
伊東さん:これらの教材をすべて無料で提供している理由は、海の環境教育における教育格差の解消を目指しているからです。海での体験学習には、地理的な制約、交通費や安全確保のための費用など、様々な障壁が存在します。
結果として、保護者が海好きで経済的に余裕のある家庭の子どもたちだけが海の環境教育を受けられる状況が生まれています。この状況を変えるため、学校や公民館などの公共施設でも気軽に海の環境教育が実施できるよう、全ての教材を無料で提供する方針を採用しています。
都市部における環境教育の可能性―盤洲干潟プロジェクト
ー都市部での環境教育の取り組みについて教えてください。
伊東さん:現在特に注力している取り組みが、盤洲干潟での探究学習プログラムです。盤洲干潟は、東京湾アクアライン千葉側の橋のたもとにある、東京ドーム330個分という広大な自然干潟です。干潮時には、岸から最大1.2キロメートルにわたって干潟が現れ、多様な生物が生息しています。
この場所は、東京湾の歴史的な変遷を理解する上で重要な意味を持っています。かつての東京湾は、沿岸のほとんどが干潟や湿地という浅瀬の海で、「芝エビ」や「浅草のり」の名前の由来となるほど生物が豊かでした。現在は大部分が埋め立てられていますが、盤洲干潟には昔ながらの東京湾の姿が残されています。
2025年4月からは、この干潟を舞台に、地域の方々のご協力を得ながら新しい探究学習プログラムを開始する予定です。単なる生物調査だけでなく、港湾開発、水質保全と下水処理方法、第一産業の衰退、都市生活と自然の共存など、様々な社会課題を学べる場にしていきたいと思っています。
時代に即した教材開発の課題と展望
ー現在直面している課題について教えてください。
伊東さん:2017年の教材公開から約7年が経過し、新たな課題も見えてきています。気候変動の加速や環境意識の高まり、ICT教育や探究学習の普及など、教育を取り巻く環境は大きく変化しています。
特に、「地球温暖化」から「気候危機」へと認識が変わる中、ブルーカーボンや磯焼け、持続可能な漁業など、時代に即した新しいテーマの教材開発が求められています。また、VR・ARなどの新技術を活用した教材開発も検討課題となっています。
ただし、これらの教材開発には資金面での課題があります。教育格差解消のための無料提供という方針を維持しながら、いかに新しい教材開発を進めていくか。現在、企業や自治体との連携を模索しているところです。
日本の海が持つ世界有数の価値と課題
ー日本の海の特徴について教えてください。
伊東さん:多くの人々は「大自然」と聞くと、アマゾンやアフリカのサバンナなどの風景を思い浮かべるかもしれません。しかし実は、日本の海は世界有数の生物多様性を誇っています。地球全海域のわずか1.5%しかない日本の海域に、世界の海洋生物の14.6%が生息しているのです。
同時に、海は環境破壊の影響を最も早く受ける場所でもあります。熱やCO2の吸収、海洋プラスチックごみなど、様々な環境負荷が海に集中しています。その影響が、すでに陸にも現れ始めています。2024年の能登半島地震後の豪雨災害も、海水温が平年よりも3-5度高かったことが一因とされています。
未来に向けた取り組みと読者へのメッセージ
ー最後に、読者の方々へメッセージをお願いします。
伊東さん:陸に暮らす人間には「目に見えない」という特性から、海の環境問題は危機感を持ちにくい課題です。しかし、私たちの生活は海と密接に結びついており、海の健全性は地球全体の環境を左右します。
そのためより多くの方々に海への関心を持っていただき、「良い意味での使命感」を持った次世代の担い手を育てていきたいと考えています。東京の目の前、湘南の海にも驚くほど豊かな生物の世界が広がっているとともに、急速な環境破壊が起きています。まずは海に関心を持ち、実際に足を運ぶ機会を提供していきたいです。
同時に、海から遠い内陸部でも環境教育を通じて、楽しみながら海の生物や環境問題について考える機会を提供していきたいと考えています。当団体の活動に賛同いただける方は、ホームページの「寄付・協賛について」のページで、個人・法人それぞれの支援方法をご確認ください。みなさまのご協力を心よりお待ち申し上げております。
特非)海の環境教育NPO bridge https://www.npo-bridge.org
海洋学習サイト「LAB to CLASS」 https://lab2c.net/