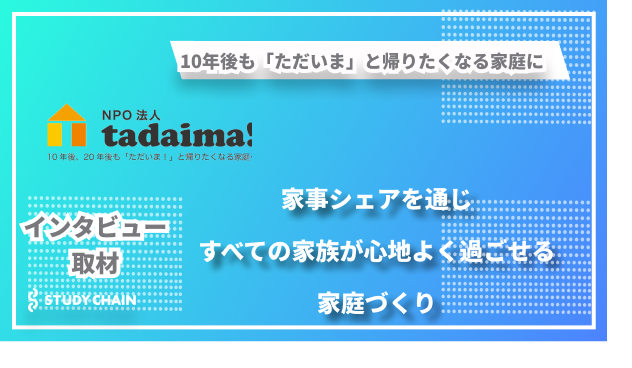家事は「女性の仕事」という固定観念が薄れ、パートナー同士で分担することが当たり前になりつつある今、具体的な実践方法が課題となっています。
家事シェアを通じて、すべての家族が心地よく過ごせる家庭づくりを支援するNPO法人ただいまの代表・三木智有さんに、活動内容や家事シェアが秘める可能性について伺いました。
「ただいま」と帰りたくなる家庭づくりをビジョンに

ーどのような方を対象にどういった支援をされていますか?
三木さん: NPO法人tadaima!のビジョンは「10年後20年後もただいまって帰りたくなる家庭にしよう」というものです。
このビジョンのもと、主に家事シェアを広める活動と、子育て家庭のためのインテリアコーディネートを行っています。
特に家事シェアの普及に関しては、講演や講座の開催、メディアでの情報発信、さらには企業や自治体との連携など、様々な形で取り組んでいます。
ー 具体的な家事シェアの内容について教えてください。
三木さん:シンプルに言えば、夫婦やお子さんを含めた家族全員で家事や育児を助け合っていくことです。
活動を始めた15年前は、まずその重要性を伝えることから始めました。
今では家事シェアの大切さは徐々に認識されるようになってきましたので、具体的な方法論やパパ向けの講座など、実践的なアプローチに重点を置いています。
インテリアの専門家として気付いた、パパたちの居場所の問題
ーこの活動を始められたきっかけについて教えてください。
三木さん:この活動を始める前は、インテリアコーディネーターとして活動していました。
その中で、家に居場所がないと感じているパパさんの姿をよく目にしていました。
自分自身も結婚を控えていた時期で、そうなりたくないという思いが強くありました。
そこで100人のパパ・ママにヒアリングを実施したところ、家事や育児の協力が家庭の居心地の良さに大きく影響していることが分かりました。

当時、パパの育児参加は注目され始めていましたが、まだ子どもがいなかった私は、まず家事シェアという考え方を広めることから始めようと決意しました。
現代の家事シェアが抱える課題と解決への糸口
ーこの活動を続けていく中で、気付きはありましたか?
三木さん:今は「パパも家事をしよう」という雰囲気は確実に広まっています。
しかし、その必要性は理解していても、実践の場面で様々な課題に直面している家庭が多いのが現状です。
やり方が違うと指摘されたり、かえって邪魔になってしまうと感じたり、時間が足りないといった声をパパさんたちからよく聞きます。
私たちは、家事のスキルレベルに関係なく、限られた時間の中でもできることはたくさんあることを伝えています。
そして何より大切なのは、どうやったら家族が協力し合えるのか、その方法を具体的に提案していくことです。
各地で広がる家事シェア講演活動

ー どのような場で講演活動をされているのでしょうか?
三木さん:主に各地の男女共同参画センターからご依頼をいただくことが多いですね。
また、企業研修や、子育て団体、保育園、幼稚園、小学校などでも講演の機会をいただいています。
特に意識しているのは、ビジネスの文脈に置き換えた説明方法です。
例えば、家族の家事シェアのスタイルを組織図のような形で提案したり、チームビルディングの観点から説明したりすることで、男性にとっても理解しやすい形で伝えるよう工夫しています。
価値観の浸透から実践へ、次のステージへ

ー今後のビジョンについてお聞かせください。
三木さん:家事シェアという言葉は確実に広まり、多くの企業でも使われるようになってきました。
しかし、実際の家事育児時間は依然として女性に大きく偏っているのが現状です。
ここからは、浸透してきた価値観をいかに実践に移していくかが重要になってきます。
ただし、単純に男性の家事時間を増やせばいいという問題ではありません。
男性の多くは既に時間的な制約を抱えており、仕事に費やす時間が多いものの、家庭に使える時間はほぼすべて使っているという調査結果もあります。
そのため、これからは「ワークインライフ」という考え方のもと、働き方自体を見直し、仕事と家庭生活全体のバランスを考えていく必要があります。
家族との暮らしを取り戻す権利
三木さん:現代のパパたちは、家事も育児も仕事も、すべてを一生懸命頑張っている方が多いです。
私たちの親世代は仕事に全力を注ぎ、その代償として家族との暮らしが犠牲になってきた面がありました。
一方で、女性たちは長年、働く権利を取り戻す戦いを続けてきました。
これからは、男性自身が家族との暮らしを営む権利を取り戻していく番だと考えています。
やらなければならないから、あるいは配偶者に怒られるからという消極的な理由ではなく、家族との暮らしを企業や社会から取り戻していく。
そして企業や社会も、それを支えながら成果を上げる方法を模索していく。
そんな社会を目指して、これからも活動を続けていきたいと思います。