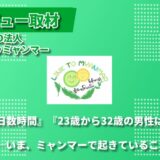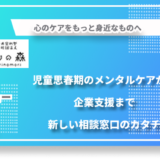離岸流の危険がある幕張の浜で、人々の命を守りたいという思いから始まったビーチクリーン活動。NPO法人Aqua Dream Projectは、環境保護とともに地域の安全を守る活動を続けています。ゴミアートの制作や企業との連携など、活動の幅を広げながら、持続可能な環境保護の実現を目指す同社の取り組みについて代表の小亀さんにインタビューしました!
設立の経緯と活動内容
ー NPO法人Aqua Dream Projectの活動内容と対象について教えてください。
小亀さん:私たちは千葉県千葉市の幕張の浜を拠点に、環境保護と地域の安全を両立させる活動を展開しているNPO法人です。活動の原点は、幕張の浜で発生していた深刻な人身事故の防止にあります。ZOZOマリンスタジアムや幕張メッセに近接する当エリアは、観光客や若者が多く訪れる場所でありながら、人工海浜の特性でもある離岸流により、数年連続で人身事故が発生していました。
この状況を改善するため、私たちはまずビーチクリーン活動を開始。当初は基本的なインフラも整っておらず、ゴミ箱すらない状況でした。千葉県と協力してゴミ箱の設置を実現し、定期的な清掃活動を通じて、人々が安心して訪れることができる海辺づくりを目指してきました。
組織の特徴と運営方針
ー 御社の特徴について教えてください。
小亀さん:私たちの団体の最大の特徴は、「エンターテインメント性のある環境保護活動」という新しいアプローチです。単なるビーチクリーン活動ではなく、参加者一人ひとりが楽しみながら環境保護について考えられる場を創出しています。
例えば、トゥクトゥク体験や、馬との触れ合い体験、シャボン玉アーティストによるパフォーマンス等、様々なエンターテインメント要素を取り入れています。さらに、幕張の浜のオリジナルソングを作って皆で歌うなど、参加者の思い出に残る仕掛けも用意しています。
運営面での特徴的な点は、メンバーの3分の1から半分を大学生が占めていることです。特に、オリンピック・パラリンピック時に結成された環境を考え行動する学生団体が中心となって、司会進行から企画運営まで担っています。若い世代に主体的に関わってもらうことで、新しい視点やアイデアが生まれ、活動が活性化されています。
また、活動の持続可能性を重視し、法人化によって安定した運営基盤を確立しています。これにより、企業や地域社会との連携も円滑に進められ、より大規模な環境保護活動が可能となっています。現在では、企業向けのチームビルディングプログラムの提供や、拾ったゴミを活用したアート作品の制作など、活動の幅を広げています。
このように、エンターテインメント性、若者の主体的参加、そして持続可能な運営体制という3つの柱を軸に、従来の環境保護団体とは一線を画す新しい形のNPO法人として活動を展開しています。
活動場所の特徴
ー 幕張の浜の特徴について詳しく教えていただけますか?
小亀さん:幕張の浜は、千葉市の代表的な観光スポットであるZOZOマリンスタジアムや幕張メッセに隣接する、人工の埋立地です。この場所は、ビジネスと観光の両面で多くの人が訪れる千葉市の重要なエリアとなっています。
しかし、この浜には大きな課題が存在していました。一つは、防風林によって囲まれているため、陸側から海がほとんど見えない構造となっていることです。これは津波対策として設置された防風林が、結果として海辺を人々の目が届きにくい場所にしてしまっているのです。
もう一つの重要な特徴は、離岸流が非常に強い海域だということです。人工海浜の特性から予測が難しい強い離岸流が発生しやすく、遊泳には危険が伴います。
このような環境要因が重なり、以前は人身事故が相次ぐ危険な場所として認識されていたので、私たちは、この状況を改善するため、人々の目が行き届く、安全で楽しい海辺づくりを目指して活動を始めました。現在では、定期的なビーチクリーン活動により、多くの人が集まる明るい空間へと変わりつつあります。
環境教育の取り組み
ー 環境問題への啓発活動についてお聞かせください。
小亀さん:環境教育において私たちが最も大切にしているのは、「自分事として環境問題を捉えてもらう」というアプローチです。単にゴミを拾うだけでなく、その過程で海洋環境や地域の自然について考えるきっかけを提供しています。
具体的な取り組みとして、特に注力しているのが「ゴミアート」の制作です。ビーチクリーンで回収したゴミを使って作品を制作することで、海洋ゴミ問題を視覚的に伝える試みを行っています。これは単なる啓発活動を超えて、環境問題を芸術的な視点から考える機会を提供しています。
また、企業向けには独自のチームビルディングプログラムを展開しています。このプログラムでは、ビーチクリーン活動を通じて環境問題への理解を深めるだけでなく、組織の一体感を醸成する効果も期待できます。参加企業からは、「社員の環境意識が向上した」「チームワークの強化につながった」といった声をいただいています。
若い世代への教育も重要な柱となっています。大学生が運営の中心を担うことで、同世代への訴求力が高まっているのが特徴です。環境を考え行動する学生団体のメンバーたちは、SNSを活用した情報発信や、若者向けのイベント企画など、独自の視点で環境教育活動を展開しています。
さらに、2024年からは「資源循環」をテーマに、新たな取り組みも始めています。回収したゴミを単に廃棄するのではなく、再生可能な形での活用を模索しています。これは、環境問題に対する「気づき」から「行動」へと、参加者の意識を変えていく試みでもあります。
このように、アート、企業研修、若者主体の活動、資源循環など、多角的なアプローチで環境教育を実践しています。私たちは、これらの活動を通じて、環境保護の重要性を楽しみながら学べる場を提供し続けていきたいと考えています。
今後のビジョン
ー 今後の取り組みについて教えてください。
小亀さん:私たちは2024年を「資源循環元年」と位置づけ、ビーチクリーン活動で回収したゴミの新しい活用方法を模索してきましたが2025年度は「調和」をテーマに掲げ、より広範な活動展開を計画しています。
この「調和」には二つの意味が込められています。一つは地域社会との調和です。地域のイベントにより積極的に参加し、私たちの活動やコンテンツを通じて地域の環境保護活動をサポートしていきます。
もう一つは企業との調和です。企業にとって意義のあるビーチクリーン活動の機会を提供することで、環境問題に対する企業の主体的な関わりを促進したいと考えています。特に、企業のSDGs活動やCSR活動との連携を強化し、環境保護活動の社会的インパクトを高めていく予定です。
メッセージ
ー 最後に、記事を読まれる方へメッセージをお願いします。
小亀さん:日本では、まだまだボランティア活動が特別なものとして捉えられがちです。「時間がない」「やり方が分からない」「自分にできるのか不安」といった声をよく耳にします。しかし、私自身の経験からお伝えできることは、環境保護活動は決して敷居の高いものではないということです。
私たちの活動に参加される方々を見ていると、最初は「ボランティア活動」という意識で来られる方がほとんどです。ところが、実際に活動に参加し、同じ志を持つ仲間と出会い、海辺の環境が少しずつ改善されていく様子を目の当たりにすると、その意識は大きく変わっていきます。
ビーチクリーン活動を通じて、参加者の方々は環境問題を「自分事」として捉えるようになります。そこから、「次は何ができるだろう」「もっと多くの人に知ってもらいたい」という思いが自然と生まれ、視野が広がっていくのです。この「気づき」から「行動」への変化こそ、私たちの活動の真の価値だと考えています。
特に若い世代の方々には、ぜひ一度活動に参加していただきたいと思います。私たちの運営メンバーの多くを占める大学生たちも、最初は「試しに参加してみよう」という軽い気持ちでスタートしました。それが今では、運営の中心として活躍し、独自のアイデアで活動を盛り上げてくれています。
企業の方々にとっても、私たちの活動は新しい可能性を提供できると考えています。チームビルディングの場として、また、実践的なSDGs活動の一環として、様々な形で活用していただければと思います。
環境問題は、一朝一夕には解決できない大きな課題です。しかし、一人ひとりの小さな行動が、確実に変化を生み出していくことを、私たちは幕張の浜で実証してきました。まずは気軽な気持ちで、私たちの活動に足を運んでみてください。きっと、新しい発見や仲間との出会いが待っているはずです。
皆さまのご参加を、心よりお待ちしています。