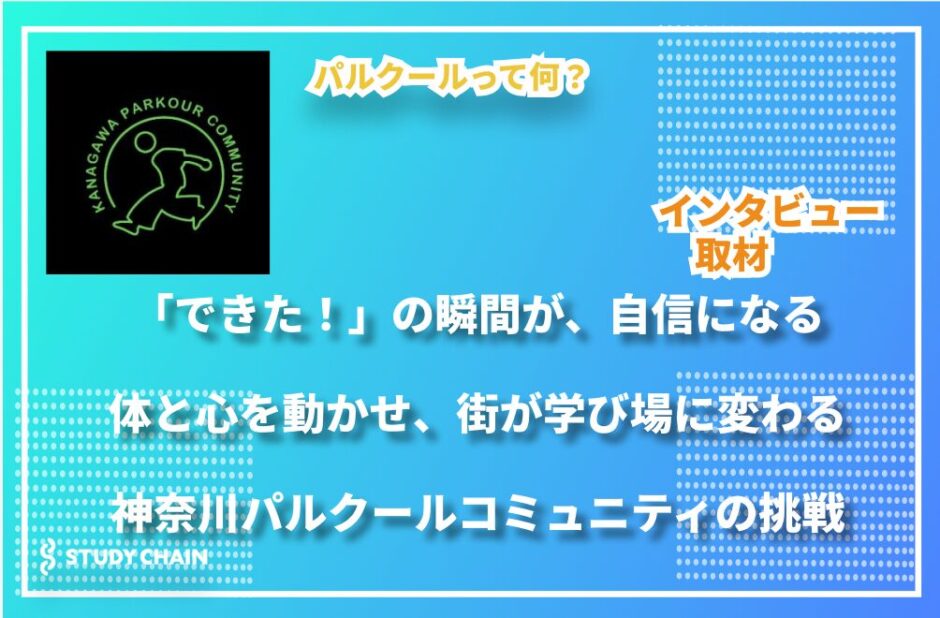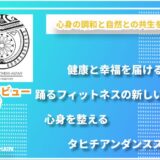神奈川パルクールコミュニティ 代表・佐藤さんにお話を伺いました。
都市の中で、壁を跳び越え、段差を登り、自由自在に動き回る──。
そんな映像で見かける“パルクール”という言葉には、どこかアクロバティックで遠い世界のイメージを抱く方もいるかもしれません。
けれど神奈川県で活動する「神奈川パルクールコミュニティ」は、そのパルクールを通じて、子どもたちや大人が“自分らしく生きる力”を身につけるための、温かな学びの場を提供しています。
今回は、コミュニティ代表の佐藤さんに、活動のきっかけや教室の方針、そしてパルクールに込めた想いをじっくりとお伺いしました。
私自身が伝えたいのは、“技術”だけでなく“生き方”としてのパルクール
私が運営している「神奈川パルクールコミュニティ」は、神奈川県横浜市を拠点に、パルクールというまだ日本では馴染みの薄いスポーツの普及を目的に立ち上げた団体です。
「走る」「跳ぶ」「登る」──このような本能的な身体の動きを軸に、自分の体と心に向き合いながら、挑戦と創造を繰り返していく。それが、パルクールというスポーツの本質だと、私は考えています。
活動エリアは、主に横浜市泉区・金沢区など。対象年齢は特に設けていませんが、現在は小学生から高校生までの子どもたちが多く、大人の方も少数ながら参加してくださっています。
この教室では、技術の習得だけにとどまらず、パルクールの歴史や文化、価値観までを共有し、スポーツを通じて“人としての成長”を目指す指導を行っています。
この教室が生まれた背景には、スポーツを“正しく”伝えたいという思いがありました
私自身がパルクールに惹かれたのは、身体を動かす喜びと同時に、それが人生に通じる“哲学”を含んでいると感じたからです。
もともとパルクールは屋外で行われることの多いスポーツでした。日本でも公園や街中で行う愛好者が増える一方で、マナーの問題やトラブルが発生することもありました。
「このままでは、正しい理解がされないまま広まってしまうのではないか」。
そんな危機感を抱き、私はパルクール専用のトレーニング場をつくり、誰もが安心して楽しめる環境と、文化的な側面まで伝えられる場を用意したいと考えるようになりました。
そして、それを実現する手段として、コミュニティを立ち上げるに至りました。
私たちは“教える場”ではなく、“育ち合う場”をつくっています
この教室では、「ただ技を教える」だけではなく、「どう人として育つか」に重きを置いています。
例えば、レッスンでは順番を守ること、仲間と空間を共有すること、どんな風に周囲と関わるかといった“社会性”も大切にしています。
もちろん、技術的な指導も行いますが、それ以上に大切にしているのは、自分で考えて、自分の意思で動く“自律性”や“創造性”です。
私自身、指導者として手本を示すことはしますが、生徒のやりたいことや目指したい姿を聞きながら、一人ひとりに合わせたアプローチをしています。
親御さんともじっくり話し合いながら、それぞれの個性に寄り添い、単なる習い事を超えた“人生の一部”として、ここでの時間を育んでいただきたいと思っています。
生徒の“できた”の笑顔に、私自身も励まされています
この仕事をしていて、最もやりがいを感じる瞬間は、やはり子どもたちが自分の限界を乗り越えた時の笑顔を見るときです。
最初は怖がってできなかった技や、高い壁のように感じていた課題も、仲間と励まし合い、練習を積み重ね、ある日ふと乗り越える。
そのときの「できた!」という声と表情は、私にとっても忘れがたい瞬間であり、この活動を続ける原動力になっています。
将来は“パルクールで生きていける社会”をつくりたい
今後の展望としては、より多くの方にパルクールの魅力を知っていただくため、外部イベントへの参加や制度面の整備も進めていきたいと考えています。
私自身の最終的なビジョンは、パルクールを“本業”として生きていけるような社会の構築です。
「パルクールが好き」という気持ちを、ただの趣味で終わらせず、それが職業として成立する。そんな世界を、日本でも実現していきたいと思っています。
パルクールは、自分を知るきっかけになります
最後に、これから参加を検討される方や、少しでも興味を持ってくださった方へ、私からお伝えしたいことがあります。
パルクールは、単なるアクロバットな運動ではありません。
むしろ、自分と静かに向き合い、「自分は何をしたいのか」「どんな風に生きたいのか」といった本質的な問いを考えるきっかけになります。
もしも今、自分に自信が持てなかったり、何か新しいことを始めたいと考えていたりする方がいたら、ぜひ一度、私たちのコミュニティをのぞいてみてください。
きっと、あなた自身の中に眠っている“可能性”と出会えるはずです。