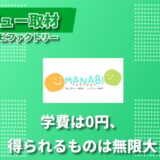外国籍の子どもたち、外国にルーツを持つ子どもたち。彼らの発達支援には、言語や文化の違いを超えた専門的なアプローチが必要です。NPO法人 HATI JAPAN多文化多言語の子ども発達支援(以下HATI JAPAN)は、そんな子どもたちとその家族に寄り添い続けています。個別カウンセリングから地域コミュニティの形成まで、多角的な支援を展開する同法人の取り組みについて、代表理事の東谷さんにインタビューしました!

外国とつながる子どもたちの発達支援に特化したNPO法人
ー御社の事業概要について教えてください。
東谷さん:私たちの活動の中心は、外国につながる子どもたちの発達支援です。「外国につながる」とは、外国籍を持つ子どもや、日本国籍でも両親や片親が外国出身の子ども、また日本人の両親から生まれても海外で育った帰国子女などを指します。そういった子どもたちの発達障害への対応や、言葉の遅れ、行動上の問題などについて支援を行っています。
3つの柱で構成される支援活動
ー具体的にどのような支援を行っているのでしょうか。
東谷さん:主に3つの活動を展開しています。1つ目は個別の発達支援です。完全予約制で、1回1時間のカウンセリングを行います。実際にお会いして検査を実施したり、保護者の方の相談に応じたりしています。
2つ目は地域の居場所づくりです。2カ所で月2回ずつ、合計月4回開催しています。予約不要で、近隣にお住まいの子どもたちやお母さんが気軽に立ち寄れる場所として、遊びや運動、学習など様々な活動を2時間程度行っています。
3つ目は、支援者向けのオンラインセミナーです。年に4~6回ほど開催しており、外国につながる子どもたちの支援に携わる日本語指導員や特別支援学級の先生方を対象に、日本語教育と特別支援教育の両面からアプローチする内容を提供しています。
海外での経験と日本の課題から生まれた支援への想い
ー設立のきっかけについて教えてください。
東谷さん:2019年7月の設立に至った理由は大きく2つあります。1つは私自身のインドネシア・バリ島でのボランティア経験です。心理士として現地で発達支援を行う中で、多文化環境における子どもたちの支援の重要性を実感しました。
もう1つは、日本国内での課題認識です。私は臨床心理士として20年以上の経験がありますが、その中で外国につながる子どもたちが増える一方、学校や保育園、発達支援センターなどの現場で、その支援に苦慮している状況を目の当たりにしてきました。
特に日本では、外国につながる子どもたちへの支援というと、まず日本語教育が中心となります。日本語教室は全国にたくさんありますが、同じように教えても、習得に個人差が大きいのが現状です。その背景には、一人ひとりの発達特性が関係していることも少なくありません。そこで、日本語教育と発達支援の両面からアプローチできる支援体制の必要性を感じ、NPO法人の設立を決意しました。
高い専門性と丁寧な支援体制が強み
ー御社の特徴的な部分について教えてください。
東谷さん:当法人の強みは、高い専門性を持つスタッフが揃っていることです。教諭、日本語教師、心理士、社会福祉士、行政書士など、様々な専門家が在籍しており、多角的な視点から子どもたちを支援できる体制を整えています。
また、スタッフ同士の連携を重視し、一人ひとりの子どもを丁寧に観察し、情報共有を行っています。例えば、居場所に来た子どもの様子や変化について話し合い、支援方法を検討するなど、チームとしての支援力を大切にしています。
子どもたち一人ひとりに寄り添う姿勢
ー支援にあたって特に意識されていることはありますか。
東谷さん:私自身もスタッフにも常に伝えているのは、「子どもたちを優しい目で見る」ということです。外国につながる子どもたちは、日本社会の中でマイノリティとして困難に直面することも多いだろうと思います。
そのため、「外国人だから」という目で見るのではなく、一人の人として大切に接することを心がけています。子どもたちが「日本にも自分の居場所があり、大切にされている」と実感できるような関わりを目指しています。
今後の展望:インクルーシブな地域づくりへ
ー今後の取り組みについてお聞かせください。
東谷さん:これからは、支援の対象を外国につながる子どもたちに限定せず、地域全体で支援の受け皿を作っていくことが重要だと考えています。子どもたちだけでなく、地域の高齢者や保護者など、様々な立場の人々が集える居場所づくりを目指しています。
また、個別支援においても、発達や心理の側面だけでなく、様々な観点から子どもを理解する包括的・多角的なアプローチを大切にしています。「インクルーシブ」という考え方をキーワードに、誰もが安心して過ごせる地域づくりを進めていきたいと考えています。
お子さまとご家族に寄り添う、長期的な支援を目指して
ー最後に、読者へのメッセージをお願いします。
東谷さん:一人ひとりの子どもたちは、かけがえのない存在です。お子さまやご家族の願い、感じている課題に丁寧に耳を傾け、それぞれに合った支援を心がけています。
支援は1回で終わることはほとんどなく、最短でも2~3回、長い方では2年以上継続的に関わらせていただくケースもあります。例えば、当初は日本語学習を目的に来られたお子さまが、学習を重ねる中で学校での友人関係に課題を感じるようになった場合は、自然とコミュニケーション面のサポートにシフトするなど、その時々の課題に応じて柔軟に対応しています。
まずはお電話でご相談ください。経済的なご事情がある場合も、ご相談に応じて料金を調整させていただいております。また、地域の居場所づくり活動は無料で参加いただけます。お子さまとご家族の思いをお聞かせいただき、私たちと一緒によりよい支援の方法を探していければと思います。