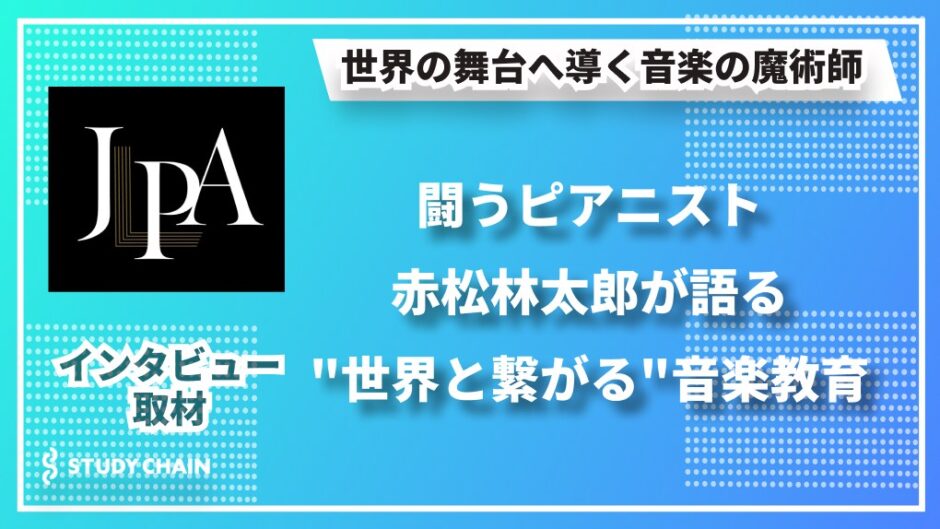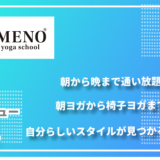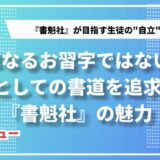国際的なピアニストとして世界の舞台で活躍し、現在は大阪音楽大学や洗足学園音楽大学などで教鞭を執る赤松林太郎氏。そのキャリアは5歳でのテレビ出演から始まり、ヨーロッパでの長い留学生活を経て、今では日本の音楽教育の最前線に立っています。しかし、彼が芸術監督を務める『Japan Liszt Piano Academy』は一般的なピアノ教室とは一線を画しています。コロナ禍をきっかけに始まったこの取り組みは、いまや国内外から多くの音楽家や生徒が集まる場となっています。
今回のインタビューでは、このユニークな音楽教育の場の成り立ち、指導哲学、そして日本の音楽教育が直面する課題と未来について、赤松氏に率直に語っていただきました。ヨーロッパの伝統とアジアの活力を融合させた新たな音楽教育の形とは—。

第44回全日本学生音楽コンクール第1位、第3回クララ・シューマン国際ピアノコンクール第3位。神戸大学を卒業後、パリ・エコール・ノルマル音楽院にてピアノ・室内楽共に高等演奏家課程ディプロムを審査員満場一致で取得。
現職は、大阪音楽大学准授、洗足学園音楽大学客員教授、宇都宮短期大学客員教授、平成音楽大学客員教授、カシオ計算機株式会社アンバサダー。
ハンガリーのダヌビア・タレンツ国際音楽コンクールで審査員長を歴任し、近年はヨーロッパやアジア各地で公演のみならず、国際コンクールやマスタークラスにも多数招聘。キングインターナショナルより8枚のアルバムをリリース、新聞や雑誌への執筆も多く、エッセイや教則本を多数出版。
ピアノ教室の概念を超えた『Japan Liszt Piano Academy』
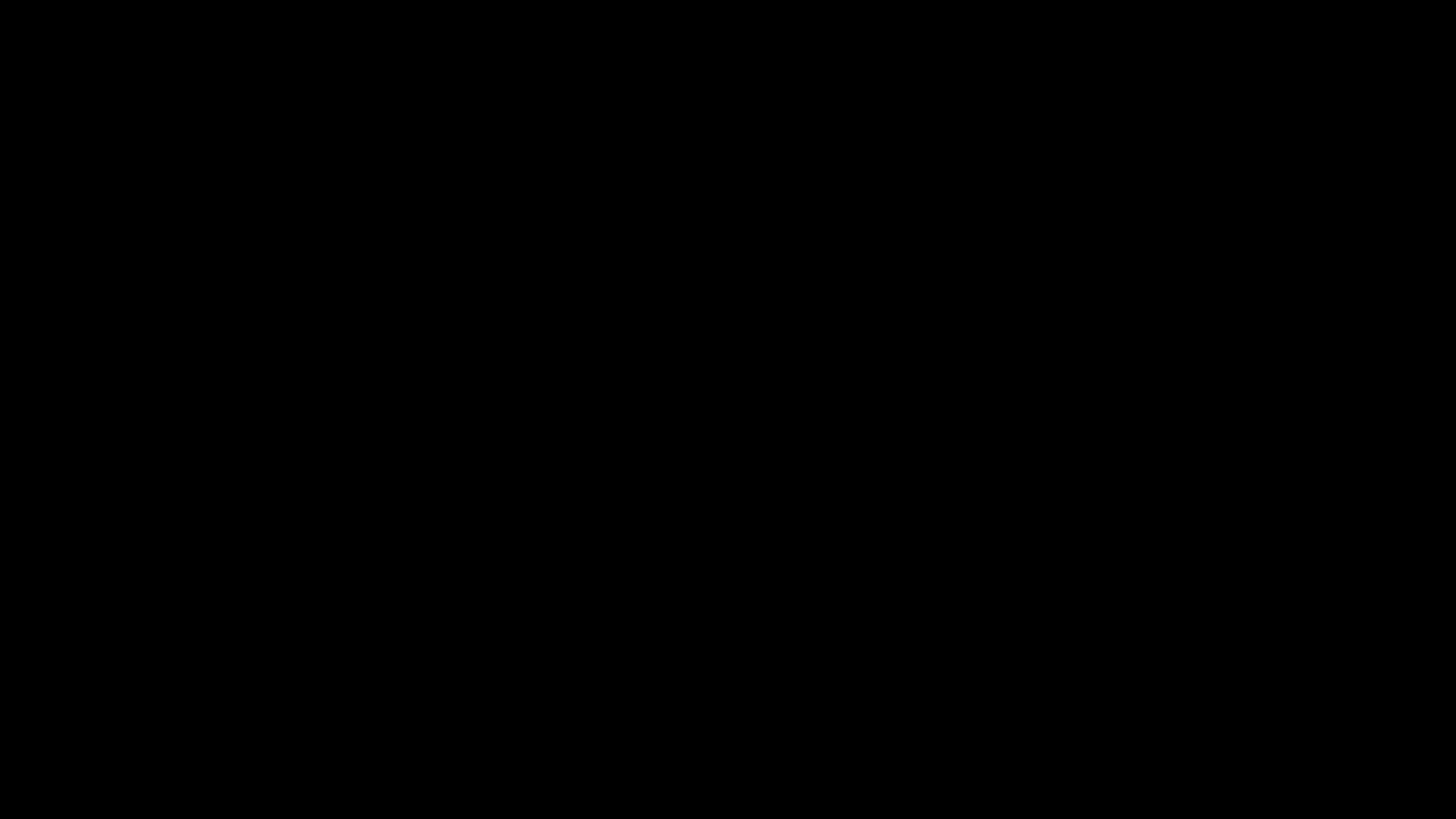
ー 赤松先生、本日はどうぞよろしくお願いいたします!まずは簡単に、どういった方を対象にしているのか、そしてどういった指導を行っているのか、Japan Liszt Piano Academyの概要をお聞かせいただけますでしょうか?
赤松林太郎 芸術監督(以下敬称略):基本的には「来るものを拒まず」という姿勢でレッスンを提供していますが、実際には多くの生徒さんが自分でレベルを見極めて来られるか、他の先生からの紹介で来られることが多いですね。
小学校低学年のお子さんも時々いらっしゃいますが、そういった方々は既に全国レベルの大会に出場するような子どもたちや、早くから海外を志向される方たちです。中学生や高校生は主に音楽大学受験を目指している方が中心で、東京藝大をはじめ、音楽大学への進学希望者が多いです。
大学生の場合は、私の所属していない大学からセカンドオピニオンを求めて来られることが多いですね。また、意外かもしれませんが、生徒さんの3〜4割は大人の方々です。プロのピアノ講師やピアノ演奏家として既に活動されている方々が、さらなる高みを目指して来られるのです。
共通しているのは、ある程度のレベル以上の方々であるということです。他の先生に習っていて仕上げの部分で行き詰まった方や、子どもさんであればある程度まで仕上がった段階で、もう一段上を目指したいという方が私のところに来られます。
また、私が所属する大学への進学希望者や、国際コンクール出場を目指す方、海外留学の道筋をつけたい方など、具体的な目標を持った方々にとっての「次のステップ」をサポートすることが多いですね。
『Japan Liszt Piano Academy』の誕生秘話

ーJapan Liszt Piano Academyは、普通のピアノ教室とは大きく異なる印象を受けますね。
赤松:実は私は、いわゆる一般的なピアノ教室というものを開いていないんです。普通のピアノ教室は、先生が自分の家に看板を掲げて、年間スケジュールを決めて塾のような形でやっていると思うのですが、私は大阪、東京、宇都宮、熊本の4つの大学で専任・客員教授を務めており、また毎月のように海外に出張しています。
そのため教室という形での運営はしていなかったのですが、コロナが始まった2020年に状況が変わりました。当時、いろいろな場所でレッスンができなくなったので、神戸の自宅から対応するようになったんです。もともと自宅はレコーディング用のスタジオとして作った場所なのですが、妻の発案で「自宅に車で来られる人なら、コロナの影響を受けずにレッスンできるのではないか」ということになりました。
SNSで告知したところ、わずか1日で50人近くの登録があったんです。コロナが本格化した2020年4月頃から、関西だけではなく、四国・九州・中部からも皆さんが車で押し寄せるようになりました。東京のポータルでも同様のことが起こり、そちらでは約50人が登録しています。
便宜上、教室に名前をつける必要があったので当初は「赤松林太郎 プロフェッショナルレッスン」としていましたが、現在は『Japan Liszt Piano Academy』という名前で活動しています。これは海外で使用している名前でもあります。
門戸は開かれている – 「渡り鳥」を防ぎながらも才能を育てる工夫

ーどのようにしたらJapan Liszt Piano Academyのレッスンを受けられるのか、簡単に説明していただけますか?
赤松:ホームページに窓口を設けているので、そこからコンタクトを取ることができます。東京と神戸のレッスンは弊アカデミーを運営している株式会社PARADEが窓口になっていますが、地方での指導は楽器店や音楽院が窓口になっている場合もあります。
コースについてはホームページに簡単に書いていますが、30分・45分・60分といった枠で、その方が何の曲をレッスンしたいのか、どのくらいの量なのか、現在のレベルなどをお聞きした上でこちらから提案する形です。
一つだけ大事なことは、「渡り鳥」的な生徒さんへの対応です。時々、他の先生に内緒で来られる方がいらっしゃいますが、これは後々トラブルになることがあります。私がレッスンするのは問題ないのですが、元々指導していた先生との間で問題が生じることが稀にあります。ですから、必ず現在習っている先生の承諾を得てから来ていただくようにお願いしています。お互いが気持ちよく送り出せるような環境を作ることが大切です。
国際舞台への切符を手にする秘訣 – 他にはない強みと特色

ー他のピアノ教室にはない特徴やアピールポイントを教えてください。
赤松:私のところの最大の特徴は、「世界に出る」という道筋が整っていることです。例えば、1月(2025年)には韓国・ソウルでピアノキャンプを行い、現地でレッスンやコンサートを実施しました。2月(2025年)にはハンガリー・ブダペストで、私たちの名前の由来でもあるリスト音楽院の教授たちとマスタークラスを開催しました。これは10年以上続けており、初回はリスト音楽院との共催でした。
他に、毎年8月にはポーランドとイタリアのマスタークラスにお招きいただき、講師を務めたりコンサートに出演したりしています。今年の4月にはハノイで初めて開催される国際コンクールで審査員としてだけではなく、マスタークラスやコンサートも勤めてきます。このように、生徒さんたちが自力では手に入れられない世界へのルートを多彩に持っているんです。
ただし、全員が一律に海外に行けるわけではなく、それぞれの生徒さんのレベルやタイミング、将来性を考慮して提案しています。お金があれば誰でも行けるというわけではなく、その人にとって最適なタイミングを見極めるのが重要です。
「世界に常に窓を開いている」と言い換えても良いと思います。マスタークラスや国際コンクール(私自身が審査員として呼ばれることも多いです)、留学などの機会を提供できることが強みだと思います。
「バッシングしない」指導哲学 – 一人ひとりの特徴に寄り添う赤松メソッド
ー生徒さんを指導する際に特に意識していることや方針を教えてください。
赤松:私がヨーロッパで学んだことでもありますが、まず「バッシングしない」ということを大切にしています。演奏において重要なのは、生徒さん一人ひとりの身体性と向き合うことです。器用な子もいれば不器用な子もいる、経験値が浅い子や癖の強い子もいます。まずは生徒さんがどういう身体性を持っているかをよく見ることが大切です。
野球に例えると、変な癖があってもホームランが打てればいいんです。超がつく長打者もいれば、バント専門の選手もいるように、その子の身体性をよく見極めることから始めます。
次に意識するのは、どのような環境で育ってきたかということです。音楽的環境やご家庭の環境によっても指導法は変わります。他の教室の先生たちは同じ方針で全員を指導することが多いかもしれませんが、私のところには「セカンドオピニオン」として来られる方がほとんどですので、ここは大事にしています。
生徒さんと向き合う際に重要なのは、その子の身体性と音楽的背景をすぐにキャッチすることです。そこから最適なアドバイスが導き出されます。薬と同じで、体質が分からないまま強い薬を出すと副作用が出るようなものです。緊張している中で演奏する最初の数分が、私にとっては非常に重要な時間になります。
指導の際は「良いところ」と「改善すべきところ」を見極め、良いところはそのまま伸ばす方針で指導します。現在師事している先生の指導方法を否定することは絶対にせず、「ここをこういう風に改良するといいですよ」とカスタマイズしていくのです。理由を理解してもらうことも重要で、単に「こうしなさい」という指導ではなく、理解と納得、共感が得られて初めて前進できます。
このように細かい点を一つ一つ積み重ねることで練習へのモチベーションも上がります。私との時間は30分〜1時間程度ですが、自宅での練習時間の方が長いわけですから、その時間をどう「遠隔操作」するかが私たちの仕事だと思っています。
日本とアジア、世界の架け橋に – ピアノ教育の未来への展望と挑戦
ー今後、より強化していきたい取り組みや目標があれば教えてください。
赤松:長くレッスンを続けてきた生徒さんの中から、ヨーロッパのイベントに参加する人、国際コンクールに出場する人、大学に進学する人が増えてきています。例えば、今年(2025年)のショパンコンクールの予備予選に出場する生徒もいます。徐々に裾野が広がってきていると実感しています。また、大学講師になった教え子も出てきています。
私は「派閥」を作るつもりはなく、このスタイルは今後も守っていきますが、世界に出ていける機会をより広げていきたいと考えています。ヨーロッパとアジア、両方の機会を増やして、優秀な学生たちに提供していくつもりです。これは大学生だけでなく、小学生の頃から対象にしています。私が開催するマスタークラスには小学生も参加しています。
日本の音楽教育は今、非常に苦しい局面を迎えていると思います。少子化や大学という組織の古い体質からの脱却の難しさ、人手不足など、様々な課題があります。これらを少しでも打開するためには、若い世代を育て、海外の経験を積ませることが重要だと考えています。
特に「ヨーロッパの伝統」と「アジアの活力」、この2つの視点を持つことが大事だと思っています。ヨーロッパは伝統を継承することに重きを置いていますが、アジアは新しいものを取り入れ、変革していく力があります。例えば、ショパンコンクールの予備予選では、かつては日本が最多だった参加者数も、今では中国が3倍近く(日本の24人に対して67人)になっています。中国の上昇志向やエネルギーは今の日本にはない強さを持っています。こうした状況を踏まえながら、日本の若い音楽家たちが世界で活躍できるよう支援していきたいと思います。
「音楽の駆け込み寺」へようこそ – 型破りなキャリアから生まれた赤松式アドバイス

ーこのインタビュー記事を読んで、Japan Liszt Piano Academyのレッスンを受けたいと思う方々へ、熱いメッセージをお願いします!
赤松:「行き詰まったら、ぜひいらしてください」というのが私からのメッセージです。
私自身、日本でピアノを始めたのは生後8ヶ月の頃。まだ首もしっかり座らない状態からピアノに触れていました。4歳で初めてのコンサート、5歳でテレビ出演、小学6年生で全日本学生コンクールに優勝しました。しかし進学先は音楽大学ではなく神戸大学を選びました。外交官を志していたからです。
大学4年生の時、それまで約20年続けてきたピアノの世界に区切りをつけるつもりで「一度だけ国際コンクールに出て、華々しく散って終わろう」と思っていました。ところが予想に反して3つの予選を勝ち抜きファイナルまで残り、結果的にピアニストの道へと進むことになったのです。その後の道のりは険しく長いものでしたが、時代の流れとともに状況も変化してきました。
36歳で東京の洗足学園音楽大学から客員教授として招かれ、その後は大阪音楽大学の専任教員(准教授)にもなりました。日本の音楽界も徐々に変化してきており、今では私もこの世界にしっかりと根を張っています。
私は既成概念にとらわれない指導を心がけています。音楽大学に進むべきか、留学すべきか、どのように演奏を深めるべきか——こうした悩みを抱える方々の相談に乗り、一人ひとりと真摯に向き合っていきたいと思います。何かの突破口になれれば嬉しいです。ぜひ「駆け込み寺」のような存在として活用していただければと思います。