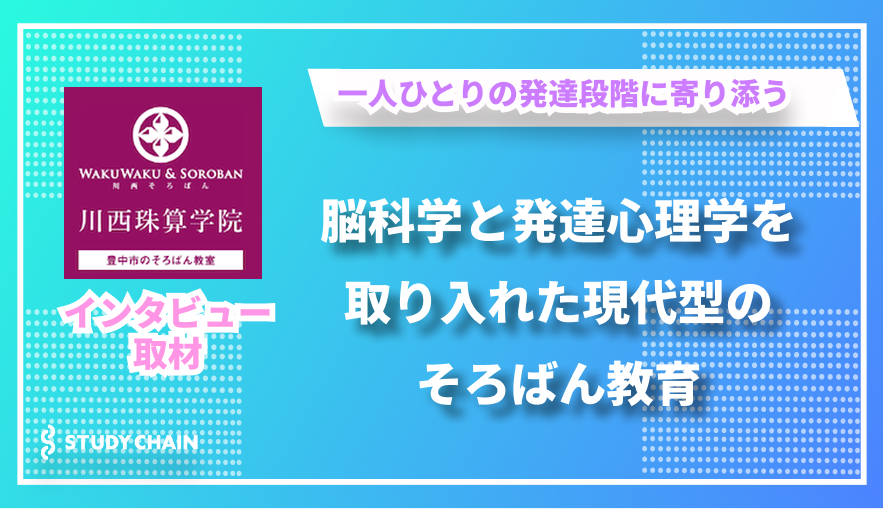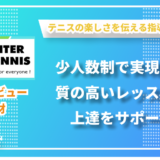大阪府豊中市で3教室を運営する川西珠算学院は、60年の歴史を持つそろばん教室です。AIの時代に必要な能力を育み、子どもたちの自律的な学びを支援する教育方針が特徴です。
代表の川西さんに、教室の特徴や指導方針についてお話を伺いました。
脳科学と発達心理学に基づいた現代型そろばん教育

ー教室の概要についてお伺いさせてください。
川西:大阪府豊中市で3教室を開いており、基本的には5歳から高校生までのお子さんを対象としています。海外事業も展開しており、海外の教育関係者からのお問い合わせやノウハウ提供の依頼も多いです。
通常のそろばん教室は検定試験の合格や技能の上達に重点を置きますが、当学院では子どもたちの総合的な学力向上と、AIの時代に必要な能力を育むことを第一の目的としています。
60年の歴史と新時代の教育ビジョン
ー教室に携わるようになったきっかけや経緯について教えてください。
川西:教室は父の時代から運営しており、約60年の歴史があります。私自身は元々IT業界でシステムエンジニアをしていましたが、父が病気になった際に代行で教室を手伝うことになりました。
当初は教室を継ぐつもりはなかったのですが、教室に通う子どもたちを見ていて考えが変わり、そろばんというコンテンツの持つ力に気づきました。
計算力だけでなく他の能力も身につくことを実感し、昔ながらのそろばん教室の良さを残しつつも、現代の子どもたちに必要な教育を提供していこうと考えました。
独自の指導メソッドと個別アプローチ
ー他のそろばん教室にはない特徴や、一番のアピールポイントを教えてください。
川西:初等教育についての知見が豊富であることが特徴です。「そろばん式脳トレーニング」という商標登録済みのノウハウを持っており、これは脳科学の研究所と連携して開発したものです。
脳科学者の監修のもと、初等教育や発達心理学の研究成果を取り入れたカリキュラムとなっています。
子どもたちの脳や心の発達には個人差があるため、一人ひとりの成長段階を正確に見極め、それに合ったカリキュラムを提供することが重要です。保護者とも連絡を密に取り、子どもの成長段階を共有しながら指導を進めています。
最終的には、子どもたちが自律的に学ぶ力を身につけてほしいと考えています。
自律的に学ぶ力を育てる長期的な視点
ー実際に生徒さんに指導する際に、特に意識していることや方針について教えてください。
川西:一人ひとりの成長段階を見極めることを大切にしています。そろばんや計算力だけを高めるならオンラインでも学べますが、その学習法が子どもの成長段階に合っているかの見極めには経験が必要です。
最適な学習進捗を立てるため、この点に力を入れています。
また、目先の成績向上だけでなく、自律的に動ける子どもを育てたいと考えています。そのため、すぐにアドバイスするのではなく、時には失敗しても見守る姿勢を大切にしています。
最近では、中学2年生まで通ってくれた生徒が、大学受験で難関大学に合格したと連絡をくれました。そろばんの実力は特別高くなかったですが、自律的に考えて動ける人間になれたことを実感しました。
多様なコース設計で子どものライフスタイルに対応
ー教室で提供しているコースやプランについて教えてください。
川西:小学生以上は週2回、週3回、週4回コースを設けています。オンラインコースも提供しており、コロナ禍で蓄積したノウハウを活かした「ハイブリッドコース」も設けています。
特に中学生になると部活動などで忙しくなるため、週1回通塾、週1回オンラインといった柔軟な対応も可能です。幼稚園児に対しては「幼児コース」を設けており、小学生とは異なるカリキュラムと指導方法で対応しています。
AIに負けない国際的な視野をもつ人材を育成
ー今後より強化していきたい部分や、取り組んでいきたいことがあれば教えてください。
川西:AIの時代に対応し、AIに負けない子どもを育てたいと考えています。ルールのあるものはコンピュータに勝てない時代ですが、ルールを生み出すことは人間にしかできません。
そのルールは国や民族、宗教などの価値観によって変わります。子どもたちにはこうした感覚を持ってほしいので、グローバルな視点を身につけられる場を作っていきたいと考えています。
ー最後に、この記事をご覧の方へメッセージをお願いします。
川西:子どもたちの可能性を信じてあげてほしいと思います。老子は「魚を与えるのではなく、魚の釣り方を教えなさい」と言いましたが、私たちは子どもたちが自発的・自律的に学ぶ価値を感じられる教育をしていきたいと考えています。
子どもの可能性を信じて待つことも大切です。当学院では一人ひとりに合わせた指導を行い、一緒に子育てをしていきたいと思います。ぜひ一緒に子どもたちを見守り育てていきましょう。