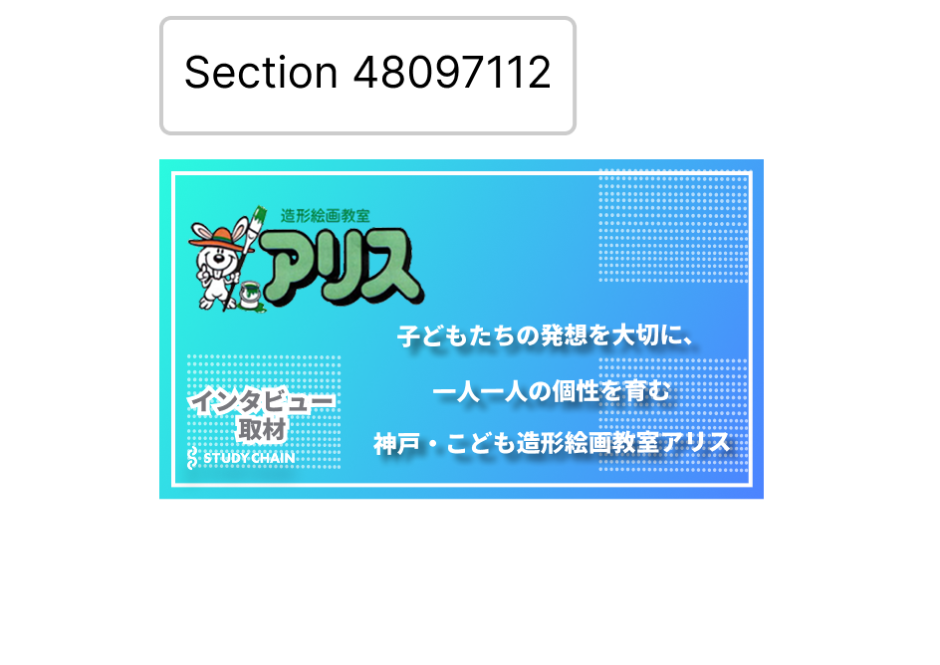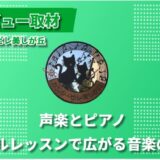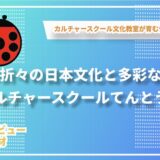神戸市で30年以上の歴史を持つ「こども造形絵画教室アリス」。
3歳から小学生を中心に、美術系進学を目指す中高生まで幅広い年齢層の子どもたちが通う同教室の特徴や指導方針について、マキ先生にお話を伺いました。
教室の概要

ー どういった方を対象にどのようなレッスンをされていけますか?
マキ先生:基本的に3歳から小学6年生までを対象としています。
ただ、美術系の高校や大学への進学を希望する生徒も多いため、中学生以上にもデッサン指導や進路に関わる指導を行っています。
今後は部活動代わりにアートを楽しみたい中高生に向けても門戸を広げ、デッサン指導だけでなくクラフトなども含めたカリキュラムも提供していく予定です。
大人向けの指導とは異なるアプローチで、表面的なテクニックだけでなく創造性やアイディアの芽を育めるよう、子どもらしさを大切にした指導を心がけています。
設立の経緯
ー この教室を始められたきっかけについて聞かせて頂けますか?
マキ先生:この教室は私自身が子どもの頃に通っていた教室なんです。
70年代に恩師が“そらまめの部屋”として開室し、私と同じく学生時代から手伝い始めたエイコ先生との二人が中心になって“アリスグループ”として運営し始めてから、20年以上になります。
現在各教室、主に美術や教育を学ぶ卒業生がアシストしてくれています。
特徴とアピールポイント

ー 他の教室にはない特徴やアピールポイントについて聞かせて頂けますでしょうか?
マキ先生:最も大きな特徴は、異年齢の子どもたちが一緒に作業する環境を大切にしていることです。
小さな子どもの自由な発想に触れることで、年長の子どもたちが固くなりがちな表現を解放できたり、逆に年少の子どもたちが上級生の作品から刺激を受けたりする、そんな相互作用を大切にしています。
また、同じカリキュラムでも年齢によって異なる素材や表現方法を用いることで、同じテーマでも全く違う作品が生まれる面白さがあります。
7-8年と長く通ってくださる方が多いこともあり、同じ内容を繰り返すことなく、平面絵画、粘土、木工、金属工芸、布を使った作品など、様々な素材や技法を取り入れています。
指導方針

ー レッスンされる際に、大切にしていることや特に意識していることはありますか?
マキ先生:私たちは英才教育ではなく、子どもたち一人一人の持つ個性を大切にした指導を心がけています。
教師の色が強く出過ぎないよう注意を払い、指導者というよりも、子どもたちの気持ちやアイディアを形にする支援者としての立場を大切にしています。
キットなどはなるべく使用せず、例えば箱を作る場合にも、展開図から組み立てていくところから始めて、ものづくりの基本を知っていくようにしています。
また、私自身も子どもの頃に元々絵が好きで入会しましたが、だんだんと造形の楽しさにも魅了されていったので、食わず嫌いせず、色々な作業を経験してしていただきたいです。
技術だけでなく、アイディアの生み出し方や物の見方を育むことを重視し、時間をかけて子どもたちの中に創造性が根付いていくことを目指しています。
コースと料金体系
ー 実際に提供をされているクラスについて教えてください。
マキ先生:レッスン時間は1時間半前後を基本としています。
3-4歳の小さなお子さんは1時間程度ですが、年齢や個人差に応じて柔軟に対応しています。
曜日によって月の回数に違いはありますが、じっくりと制作し技術や考え方を身に付けていただきたいので、どの教室も継続しての参加をお願いしております。
今後のビジョン
ー 今後、新たに取り組んでみたいことや、強化したい点はありますでしょうか?
マキ先生:AIの進化により、想像力やアイディアを生み出す力、工夫する力がますます重要になってくると考えています。
近道をして、上手いけど既視感のあるような作品づくりをするのではなく、深く自身と向き合う時間を大切にして自分らしい表現を見つけてもらえるよう、今後もサポートしていきたいと思っています。
メッセージ

ー 最後に入会を考えてらっしゃる方にメッセージをお願いできますでしょうか?
マキ先生:絵が上手くなるというアプリがあったり、画面の中のモチーフを見ながら描くことも多い時代ですが、実際の素材に触れ、迷いながら創作する体験は大きく異なります。
立体作品を作ることで平面作品への理解も深まり、お友達との交流から新しいアイディアが生まれることもあります。
年下だった生徒さんが成長して、自身がお兄さん・お姉さんにしてもらったように小さい子達のお世話をしたことであったり、遠足や夏祭りなどのイベントや共同作業を含めた様々な経験が心に残り、絵画や彫刻等の作家やデザイナーなどだけでなく、美術を含めた教育や保育の道に進まれる方も多いです。
集中力も付くのか分かりませんが研究者を目指したり、はたまたバンドで世界的にも有名になっていたりと、各々が好きなことを見つけて生きていて、ジュニアを連れて来てくれる卒業生も増えている現状は嬉しい限りです。
ぜひ一度体験していただいて、楽しい雰囲気を感じてくだされば幸いです。