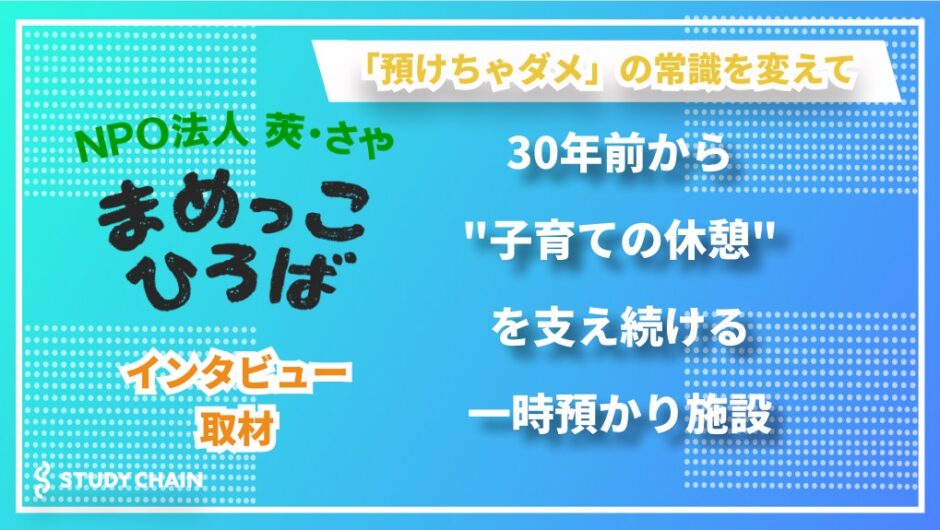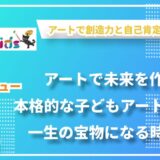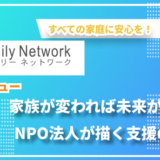子育て支援の現場では、働く母親のための保育所整備は進んでいるものの、専業主婦やパートタイム勤務の母親への支援は、まだまだ十分とは言えない状況が続いています。特に「リフレッシュ」や「自分の時間が欲しい」といった理由での一時預かりに対しては、今でも理解が得られない場合があります。
そんな中、横浜市で30年以上にわたって一時預かり事業を運営してきた『NPO法人 莢(さや)・さや』の「まめっこひろば」は、‟子育ての休憩”を提供する施設として、多くの親子に支持されています。利用理由を問わない受け入れ体制や、元利用者がスタッフとして活躍するという特徴的な運営形態は、子育て支援の新しいモデルケースとしても注目を集めています。
今回は、設立代表者・施設長の押山 道代(おしやま みちよ)様に、設立の経緯から現在の取り組み、そして今後の展望まで、詳しくお話を伺いました。
「子育ての休憩」を提供する一時預かり施設『NPO法人 莢(さや)・さや』

ー押山さま、本日はどうぞよろしくお願いいたします!まずは『NPO法人 莢・さや』が運営する「まめっこひろば」の概要について、教えていただけますか?
押山道代 施設長(以下敬称略):私たち『NPO法人 莢・さや』は、横浜市の乳幼児一時預かり事業として「まめっこひろば」を運営しています。生後57日目から未就学児までの単発利用・一時預かりを行っており、朝7時半から夕方6時半までの間で、30分刻みで必要な時間帯に預けることができます。
毎日通う保育園とは異なり、利用者も時間も日によって様々です。その日その日でお預かりするお子さんたちが違い、来る時間も帰る時間もみんな異なる、という特徴的な保育形態となっています。
元々は私が自宅で始めた小さな活動でした。その後、行政がこういった活動への支援を始めると聞き、プレゼンテーションを行って助成金を獲得し、現在の形になるまでに約30年の歳月がかかっています。当時は「一時預かり」という言葉すら一般的ではない時代でした。
「自分の時間」を持てない母親たちへの想いから始まった
ー押山さまが「まめっこひろば」を作られた経緯について、詳しくお聞かせください。
押山:きっかけは、第一子が生まれた時の経験でした。当時は1歳までは行政による身長・体重測定をしてくれる‟赤ちゃん会”といった支援がありましたが、1歳を過ぎると行政の支援がほとんどなくなってしまう状況でした。そこで、近所の方3人で親子サークルを立ち上げ、月に2回ほど地区センターを借りて活動を始めました。
数年経つと、第2子、第3子が生まれ、3歳児と2ヶ月の赤ちゃんが同じ場所で活動することの難しさを感じるようになりました。私は元々保育士だったこともあり、3歳児の子どもたちと「幼稚園ごっこ」のような遊びをする一方で、小さな子どもたちは親子で楽しめる遊びを提供するという形に発展していきました。
その後、自身の3番目の子どもが幼稚園に入る前の1年間、自宅で友達の子どもと「幼稚園ごっこ」として週に1回2時間ほど遊ぶ機会を設けたところ、口コミで広がり、最終的には20人ほどの利用者が集まりました。4畳半と6畳の部屋を仕切りを外して活用し、家具をシーツで隠すなど工夫しながら、5-6人ずつ別の曜日に分けて預かっていました。
当時、鶴見区や横浜市の行政には「仕事をしていない母親が子どもを預けるなんて、前例がない」と言われ、理解を得ることが難しい状況でした。「ママ友ができれば子育ての悩みは全て解決する」といった旧態依然とした考え方も根強く、苦労した記憶があります。
しかし、私自身3人の子育てをしている経験から、待望の子どもを授かったのに、育児に追われて優しくできない自分を責めてしまう気持ちがよく分かりました。大きな贅沢ではなく、ほんの2、3時間でも自分の時間を持つことができれば、より良い子育てができるのではないか。そんな思いで活動を始め、現在に至ります。
「ここで助けてもらったから、今度は私が」― 元利用者ママたちが紡ぐ支援の輪

ー他の施設との違いや、特徴的な点を教えてください。
押山:大きな特徴として、利用理由による受け入れ制限を設けていないことが挙げられます。また、私自身や副理事長が障がい者施設での勤務経験があることから、医療的ケアが必要な場合を除き、発達障害や自閉症の子どもたちも積極的に受け入れています。生後57日目という早い段階からお預かりできるため、発達障害などの診断がまだついていない時期の子どもたちも多く利用されます。
特筆すべきは、現在22人いるスタッフのうち、4分の3以上が元利用者のママたちだということです。施設を利用していた母親たちが「お世話になったので、今度は私も何か手伝えることはないですか」と声をかけてくれ、最初はボランティアや短時間勤務から始めて、徐々にスタッフとして活躍してくれるようになりました。
実は、大々的にスタッフ募集をかけたことは、一度もありません。元利用者のママたちが自然と加わってくれているのです。彼女たちは利用者の気持ちを痛いほど理解しているため、泣いている子どもを預ける母親の気持ちに寄り添うことができます。
一方で、通常の保育園での経験がある保育士さんは、この一時預かりの特殊性に戸惑うことも多いようです。毎日の流れが決まっている通常の保育園とは異なり、その日その日で異なる子どもたちを預かり、慣らし保育もない中で、いきなり長時間の預かりが必要になることもあります。そのため、その子の気持ちを読み取り、心地よく過ごしてもらうための工夫が特に重要になってきます。
子どもだけでなく、親の気持ちにも寄り添う

ーお子さんを預かる際に、特に意識していることはありますか?
押山:子どもの気持ちを読み取り、心地よく過ごしてもらうことはもちろんですが、親の気持ちにも寄り添うことを大切にしています。例えば、「お友達作りのため」と言って預ける母親が、実は「自分の時間が欲しかった」と半年後に打ち明けてくれることもあります。そういった言葉にできない思いも含めて、受け止めることを心がけています。
児童相談所からの依頼や緊急の受け入れ、突然のピンポン訪問など、様々なケースがありますが、どのような状況でも、親子それぞれの気持ちに寄り添うことを大切にしています。実際に、最初は子どもを預けることに強い抵抗があった母親が、その後さらに3人の子どもを産み、全員を「まめっこひろば」に預けてくれるようになったケースもありました。
オンラインで繋がる、子育て支援
ー「まめっこひろば」の具体的な利用方法について教えていただけますか?施設を利用する際の流れを詳しく知りたいです。
押山:利用にあたっては必ず事前面談を行っています。以前は対面での説明会や個別面談のみでしたが、コロナ禍を契機にZoomでの面談も取り入れました。これが予想以上に好評で、現在は対面とオンラインを併用しています。
実は、このオンライン面談の導入が、私たちの支援の可能性を大きく広げることになりました。例えば先日は、海外在住の日本人家族とZoomで面談を行い、一時帰国時の利用について相談を受けました。海外在住の日本人家族にとって、帰国後の子育て環境の確保は大きな不安要素。事前にオンラインで施設の様子を知り、顔見知りのスタッフがいる状態で利用を始められることは、大きな安心感につながっているようです。
また、国内でも、遠方からの転入を予定している家族との面談にも活用しています。知り合いが誰もいない土地での子育ては不安も多いものです。引っ越し前からオンラインで繋がることで、転入直後から支援を開始できる体制を整えています。
さらに3年前(現在2025年)からは、横浜市の乳幼児一時預かり事業のウェブ予約システムが導入され、面談済の方は24時間いつでもオンラインで予約が可能になりました。深夜2時、3時に予約が入ることも珍しくありません。「今日、急に預けたい」という切実なニーズに、システムが応えてくれています。
このように、テクノロジーの活用は、物理的な距離や時間の制約を超えて、より多くの方に子育て支援を届けることを可能にしました。ただし、私たちが大切にしているのは、あくまでも人と人との繋がり。オンラインは、その繋がりを作るための入り口として活用しているんです。
「顔の見える関係作り」は変わらず大切にしながら、テクノロジーの力も借りて、支援の輪を広げていきたいと考えています。
「学校に行けない」そんな日は、幼い頃の思い出の場所へ

ー今後の新しい取り組みや、目指されている方向性などをお聞かせください。
押山:最近特に力を入れているのが、かつて利用していた子どもたちの「その後」のケアです。特に気になるのが、小学生になって‟行き渋り”になるケースです。幼稚園や保育園では大きな問題がなかった子どもたちが、小学校という新しい環境で困難に直面することが少なくありません。
学校では20人以上のクラスの中の1人。先生との1対1の関わりも限られます。確かに学校にはカウンセラーがいますが、「学校に行きたくない」と感じている子どもにとって、学校の中にあるカウンセリングルームは、必ずしも心を開ける場所ではないかもしれません。
そんな中、嬉しいことに「まめっこひろば」に自然と足を運んでくれる子どもたちがいます。弟や妹の送り迎えのついでに立ち寄ったり、学校を休んだ日にふらっと来てくれたり。幼い頃から知っている私たちだからこそ、「今日は学校、行けなかったの?」と特別視せずに受け入れることができます。
この状況を見て、もっと積極的にサポートできないかと考え、月に1回、小学生向けの居場所づくりを始めました。特別なプログラムは用意していません。工作をしたり、おしゃべりをしたり、ただそこにいられる場所を作ることを大切にしています。
今後は、乳幼児の一時預かりという原点は大切にしながら、その経験とネットワークを活かして、子どもたちの成長に寄り添える場所を増やしていきたいと考えています。例えば、不登校の子どもたちの居場所づくりや、発達障害を持つ子どもたちへの支援など、既存の制度ではカバーしきれていない部分にも、少しずつ取り組んでいきたいと思っています。
さらに、子育て中のママたちの心と体のリフレッシュタイムを大切にしたいという想いから、お子さまをお預かりしている間に【ママの身体メンテナンス】や【初めての子育てママの会】、【お裁縫をしながらのおしゃべり】など、ホッと一息つける新しい試みも企画中です。
一時預かりの利用者だった子どもが成長し、今度は自分の子どもを連れて来てくれる―。そんな循環が生まれ始めています。この30年間で築いてきた信頼関係を基盤に、子どもたちの「その後」まで見据えた支援の形を作っていきたいですね。それが、次の30年に向けた私たちの挑戦です。
罪悪感を持たずに、気軽に利用を

ー最後に、『NPO法人 莢・さや』の利用を考えている方へメッセージをお願いします!
押山:子どもを預けることに罪悪感を持つ方が多いのですが、決してそうではありません。お子さんにとっても世界が広がるチャンスですし、その間にママやパパが充実した時間を過ごすことで、より良い子育てにつながると信じています。
最近は、心療内科に通うほど育児に疲れ切ってしまう方は減ってきましたが、それでも子育てに真摯に向き合えば向き合うほど、しんどくなってしまうのが現実です。ネイルに行きたい、Netflixを見たいといった些細な理由でも、リフレッシュできる時間を持つことは大切だと考えています。
子どもの幸せは、親が心身ともに健康で元気であることが大切です。私たちはそのサポートをすることで、子どもたちの幸せにも貢献できると考えています。ホームページには利用者の方々の声も掲載していますので、ぜひ参考にしていただき、気軽に利用してみてください。