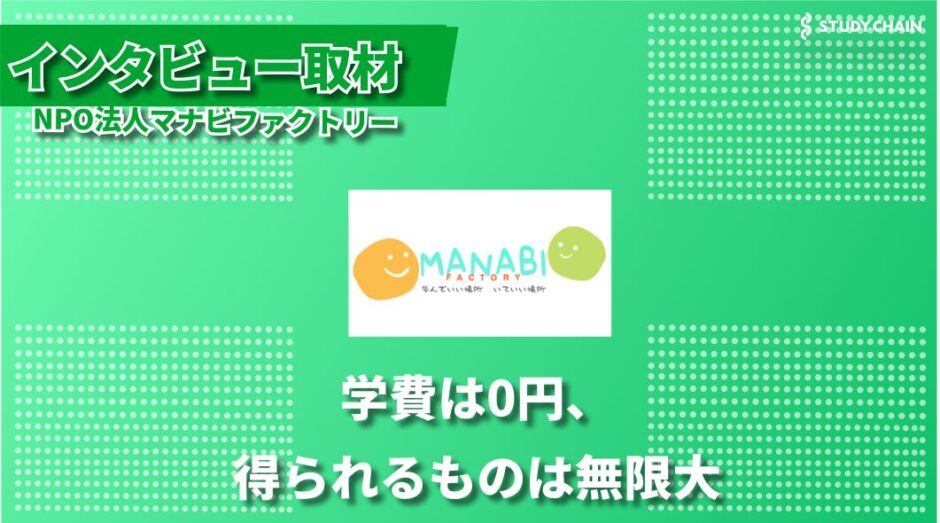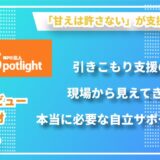“お金の有無で教育機会に差をつけたくない”。そんな思いから2021年に誕生したマナビファクトリーは、生活困窮世帯の子どもたちに無料で学習支援を提供しています。学びの場であり、居場所でもある教室の取り組みについて、石井さんにお話を伺いました。

生活困窮世帯の子どもたちに無料の学習支援を提供
ーマナビファクトリーさんの事業概要について教えてください。
石井さん:私たちマナビファクトリーは、生活に困窮している世帯の小中高校生を対象に学習支援を提供している団体です。活動日は週6日で、月水金は午後5時から9時まで自主学習スペースとして開放し、生徒たちが自由に出入りできる環境を整えています。また、火曜日と水曜日は午後6時半から8時半まで、土曜日は午後2時から4時半、5時から7時、5時半から7時半の3つの時間帯でクラスを設けています。
学習内容については、生徒一人ひとりの希望や進度に合わせた柔軟な対応を心がけています。基本的に生徒たちは自分の学習したいものを教室に持ち込むことができ、学校の宿題に取り組む生徒もいれば、市販の教材を持参して学習する生徒もいます。また、一部のクラスでは「みんなの学習クラブ」という、小中学校の主要教科をカバーするプリント教材も用意しています。このプリント教材は生徒の希望に応じて必要な単元を提供でき、特に学び直しを必要とする生徒たちに重宝されています。
複数の教室で多くの生徒をサポート
ー各クラスの生徒数について教えてください。
石井さん:現在、渋谷区と品川区に複数の教室を展開しています。火曜日の代々木教室では約15人、水曜日の西品川教室では約20人の生徒が通っています。土曜日は3つの時間帯で授業を行っており、西品川教室(午後2時から4時半)には約25人、大井町教室(午後5時から7時)と代々木教室(午後5時半から7時半)にはそれぞれ約15人の生徒が通っています。各教室では、生徒数に応じて適切な数のスタッフを配置し、きめ細やかな指導を心がけています。
設立の経緯と無料塾へのこだわり
ーマナビファクトリーを立ち上げた経緯を教えてください。
石井さん:私は元々高校教師として教育現場に携わっていました。その後、大田区のNPO法人で学習支援の仕事に就き、そこで多くの仲間と出会いました。しかし、雇用される立場では実現できることに限界があり、「もっと自分たちの思い描いた形で学習支援をしたい」という思いが仲間たちの間で強くなっていきました。そうして2021年、新たな一歩を踏み出す決意をしたのです。
全国的に見ると、学習支援を行うNPO法人の中には月謝制やワンコインでの受講料を設定しているところも多く、それぞれの運営方針があると理解しています。しかし、私たちは生活に困窮している子どもたちから一切料金を受け取らないというポリシーを掲げています。将来、成長して社会人となった後に還元してくれることがあれば嬉しいですが、現在困難な状況にある方々からは決してお金を頂かない、という強い信念を持っています。
設立当初は私たち自身に大きな資産があったわけではなく、かなりの決意を持っての挑戦でした。しかし、様々な助成金や温かい寄付のおかげで、現在も継続的な運営ができています。この支援の輪を大切にしながら、今後も活動を続けていきたいと考えています。
学習支援にとどまらない総合的なサポート
ーマナビファクトリーの特徴的な点を教えてください。
石井さん:私たちの大きな特徴は、学習支援だけでなく、居場所支援や食事支援も含めた総合的なサポートを提供している点です。月に1回程度、様々なイベントを開催しており、中でも人気なのが「子どもテーブル」です。これは、子どもたちのリクエストに応じた料理を皆で作って一緒に食べるイベントで、コミュニケーションを深める貴重な機会となっています。また、昨年からは合宿も実施しており、バーベキューやキャンプファイアーなどを通じて、普段の教室では味わえない体験を提供しています。
特に代々木教室では、学習時間の合間に晩ご飯を一緒に食べる時間を設けており、これは、ボランティアの方々や飲食企業からの支援、そしてスタッフによる調理で実現しています。生徒たちは無料で温かい食事を楽しむことができ、スタッフと一緒に食卓を囲むことで家庭的な雰囲気も味わえます。
このような取り組みの背景には、家庭や学校に居場所を感じられない子どもたちが多いという現状があります。学びの場であると同時に、心が安らげる居場所としての機能も大切にしています。
子どもたちの自己肯定感を育む
ー居場所のない子どもたちへの接し方で意識していることはありますか?
石井さん:学校教育では往々にして「できる・できない」「やる・やらない」という評価軸が重視されがちです。もちろん、社会に出れば評価を避けて通ることはできませんが、発達段階にある子どもたちにとって、まず必要なのは無条件の受容と励ましだと考えています。
本来であれば、家庭という安全な環境の中で、様々なことにチャレンジしながら成長していくのが望ましい姿です。しかし、私たちの教室に通う生徒の多くは、自己肯定感が低く、学校生活での困難な経験を適切にフォローしてもらえないまま成長してきています。その結果、「自分にはできることが少ないから価値がない」という考えに陥り、新しいことへのチャレンジを避けるようになってしまうのです。
そのため、私たちは常にポジティブな言葉がけを心がけており、スタッフ研修でもこの点を特に重視しています。また、子どもたち自身が自己否定的な言葉を使ったり、他者を傷つけるような言葉を使ったりした際は、その場で優しく諭すようにしています。時には厳しく指導することもありますが、それは相手を否定するためではなく、お互いを大切にし合える関係性を築くためです。
このように、一人ひとりの存在そのものを大切に思える思考を育めるよう、日々の活動の中で場の雰囲気づくりに注力しています。
今後の展望
ー今後のビジョンについて教えてください。
石井さん:私たちは、団体の規模を急激に拡大することは考えていません。その代わりに、現在活動している渋谷区と品川区での地域密着型の支援をより充実させていきたいと考えています。両区での活動は偶然のご縁から始まりましたが、今ではこの地域とのつながりが私たちの大きな強みとなっています。
今後は、より多くの子どもたちにこの教室の存在を知ってもらい、支援を必要とする子どもたちが確実に私たちの支援に繋がれるようなシステムを構築していきたいですね。同時に、単なる学習支援の場としてだけでなく、子どもたちの確かな成長を支える居場所として、さらなる進化を目指していきます。
メッセージ:共に学び、成長する場所として
ー最後に、入塾検討者や支援者へのメッセージをお願いします。
石井さん:「学び」という言葉には、深い意味が込められています。もちろん、子どもたちにとって学びは将来への大切な投資ですが、それは支援する大人たちにとっても同じです。私たち支援者は子どもたちから多くのことを学び、この活動を通じて共に成長させていただいています。
私たちは、「教える側」と「教わる側」という一方的な関係ではなく、互いに学び合い、成長し合える関係性を大切にしています。そして、その中で生まれる「安心できる場所」という雰囲気が、私たちの教室の最大の特徴だと自負しています。支援を必要とする子どもたちはもちろん、その支援に携わりたいと考えてくださる方々にも、ぜひ私たちの活動に関わっていただければ幸いです。